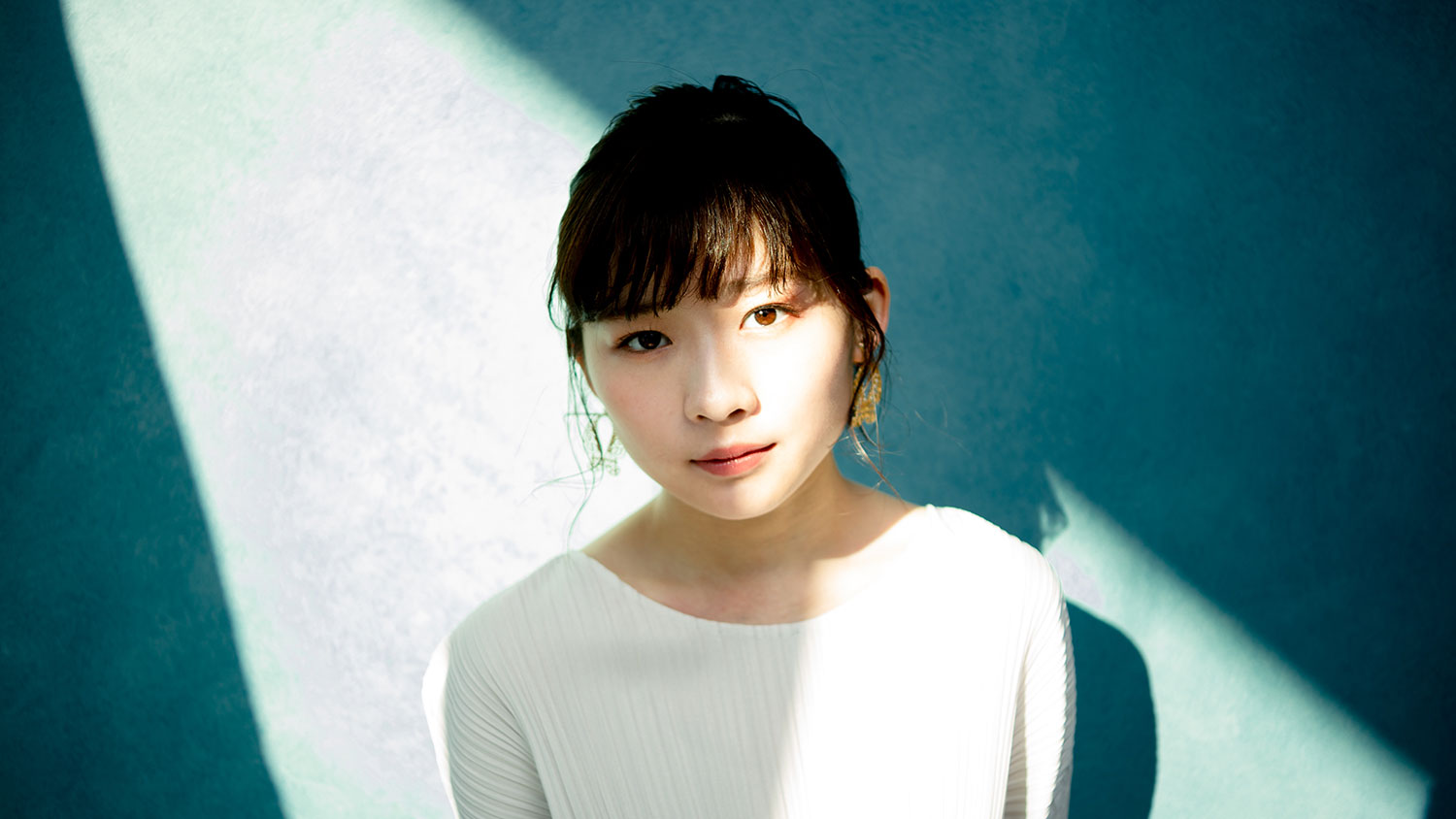目次

“本当”に捕われず、実在する人を“生きる”。
― 今年は主演作が『ニワトリ★スター』(2018年3月)、『返還交渉人 いつか、沖縄を取り戻す』(18年6月公開)、『止められるか、俺たちを』(18年秋公開)と続けて公開されますね。テレビドラマにも出演され、日本の伝統文化を広める活動もされています。さぞかし目まぐるしい日々を送られていることかと。
井浦 : ありがたいことです。でも、『返還交渉人』は2017年8月に放送されたドラマが映画化されたので、撮影はだいぶ前になるんです。この作品は当初、映画化は予定されていなかったのですが、担当された柳川監督の情熱によって異例に映画化が実現したようです。
― 柳川監督と井浦さんが組むのは、今回で3度目ということ。本作で井浦さんが演じられた外交官・千葉一夫は、沖縄返還で外交交渉の最前線にいた実在の人物です。アメリカの外交官の間で語り継がれるほど、激しい外交交渉を重ね、何度も沖縄に足を運び現地の人の声に耳を傾けたという、情熱と義侠心の固まりのような人であるとお伺いしました。柳川監督はキャスティングする当初から、井浦さんの心性にぴったりだと思っていたそうですね。劇中で度々登場する、千葉が対“人”、対“状況”などに憤慨するシーンは印象的でした。
井浦 : あれでも、怒るシーンは少なくしたんですよ。千葉さんは、いわゆる昭和の豪傑なので、やることなすこと情熱的。千葉さんのご子息が一足先に映画を観てくださったのですが、「父はもっと怒っていました」と笑いながら仰っていたぐらいです(笑)。一方で、当時の千葉さんを知る方々は「仕事のことならば声を荒げて怒り散らすこともあったが、豪快に酒を呑んで楽しく酔っ払うユーモアも持ち合わせた人だった」と。
― たしかに、怒っている千葉さんだけでなく、家族と笑いながら過ごしている姿も同じく印象に残っています。
井浦 : 千葉さんが怒っているシーンすべてを、「怒り」という感情だけで表現するのはどうかなと思ったんです。人間ってもっと豊かでいろんな感情を持っていますよね。映画は限られた短い時間で、人となりを見せなければならない。忠実さよりも、彼のモチベーションである「怒り」を自分の腹に貯め込みつつ、それを色々な形で表現しました。

― 怒りはベースにありつつも、人となりの深みもきちんとみせようと。
井浦 : 本や映像で本人を知ることは大きな手がかりにはなりますが、人間なので一辺倒ではないでしょうし、どんなに努力しても僕がその人そのものにはなれないと思います。僕はこれまで三島由紀夫や連合赤軍の坂口弘など、実在する人物をたびたび演じてきましたが、大事にしているのは忠実性ではありません。それよりも、その人がどんな思いを持って生きてきたのかを考えること。「何のために一人の役者が実在する人物を演じるのか」を考えたとき、肝はそこにあると思うのです。
― モノマネはしない、ということですか。
井浦 : モノマネ、つまり“本当”に捕われすぎると、人となりの純粋な芯の部分がなくなってしまうように思います。だから、実際の出来事を血肉にしながらも、「こんな側面もあったのではないか」という個人的な思いも演技にのせています。それは、自分が感じたことを素直に演じることが大事だと考えているからです。つまり、自分というフィルターを通しながらも、実在する人を“生きる”ということです。そういう役者同士でぶつかり合って演じたときに出てくる感情を、現在の人が観てどう感じるかが重要なんです。

手がかりを見つけたら、血肉にする。最後は「帰ってこられなくてもいい」と思うほど役にのめり込む
― 今作のクランクイン前に、井浦さんは映画の舞台である沖縄を訪れたそうですね。
井浦 : クランクイン前に、千葉さんが現地で暮らす人の声を聞くために何度も訪れた沖縄のアメリカ軍基地を一人で巡りました。それは役づくりのためというよりは、昔から今に続く“空気”を感じるため、というんですね。物語の舞台である60-70年代の沖縄を体験することは難しくても、千葉さんが見て感じた景色は何だったのかを僕も感じて、身体にいれなければいけないと思うんです。基地の雰囲気、戦闘機の爆音、沖縄県民の人柄、それらを自分の目で見て肌で感じて、心の底まで響かせてから撮影現場に向かいました。
― 役を演じた後にも沖縄に行かれたようですが、感じるものが違いましたか?
井浦 : 違いましたね。元々沖縄が好きで、いち観光客としてグスクなど古い歴史や文化、自然が残る場所によく行っていました。ですが、千葉さんが訪れていたのは僕が行っていた場所とは違う、戦後の歴史が残る那覇や嘉手納。彼を演じたことで、観光的だけにしか捉えられなかった沖縄の戦争の跡をもっと切実に感じるようになりました。
自然が豊かで、暖かくハッピーになれる場所という側面はもちろんありますが、別の側面もある。人も街もどんなこともそうですが、ある側面と違う側面が見つかると、愛の深みが増すんだと実感しました。沖縄がもっと大切な場所になりました。

― 調べようと思えばいくらでも調べられてしまう時代なので、「忠実に再現する」ことよりも「自分の考えを役にのせる」ことの方が難しいように思います。それは、俳優業に限らず表現するすべての事柄に対してですが。
井浦 : 少しでも手がかりがあれば見つけて自分の血肉にした上で、できる限り決め込まないフラットな状態で現場に臨み、その人を演じることで追体験することが僕にとって幸せなんです。でも、だからこそ実在する人物を演じるときは、その人の地位や名誉に関係なく、本人とその家族に敬意をはらうことは忘れないようにしています。敬意を持って実在する人物を生き、周囲からおかしいと思われるほど、その人物と向き合ってのめりこむ。「帰ってこられなくてもいい」と思うくらいに入り込まないといけないんです。
― そこまでご自身を追い込むんですね。
井浦 : キツイですし、失敗もたくさんしますけど、本人やその家族に対して絶対に失礼のないように演り尽くしたいと思っています。今回も、“怒る”千葉さんに似せるのではなくて、「ノー」をはっきりと言えるその背中や、豪傑がたまに笑う目元など、役と向き合ったからこそ無意識に滲み出る、そういう芝居ではないものを表せるようになりたい。僕は演じる責任を負っているので、微力ながらも43年間生きて感じたことを、その自分の小さな経験を膨らませて、足したり引いたりすることでリアルにみせることができると思う。できることはなんでもするつもりで役に臨んでいるんです。