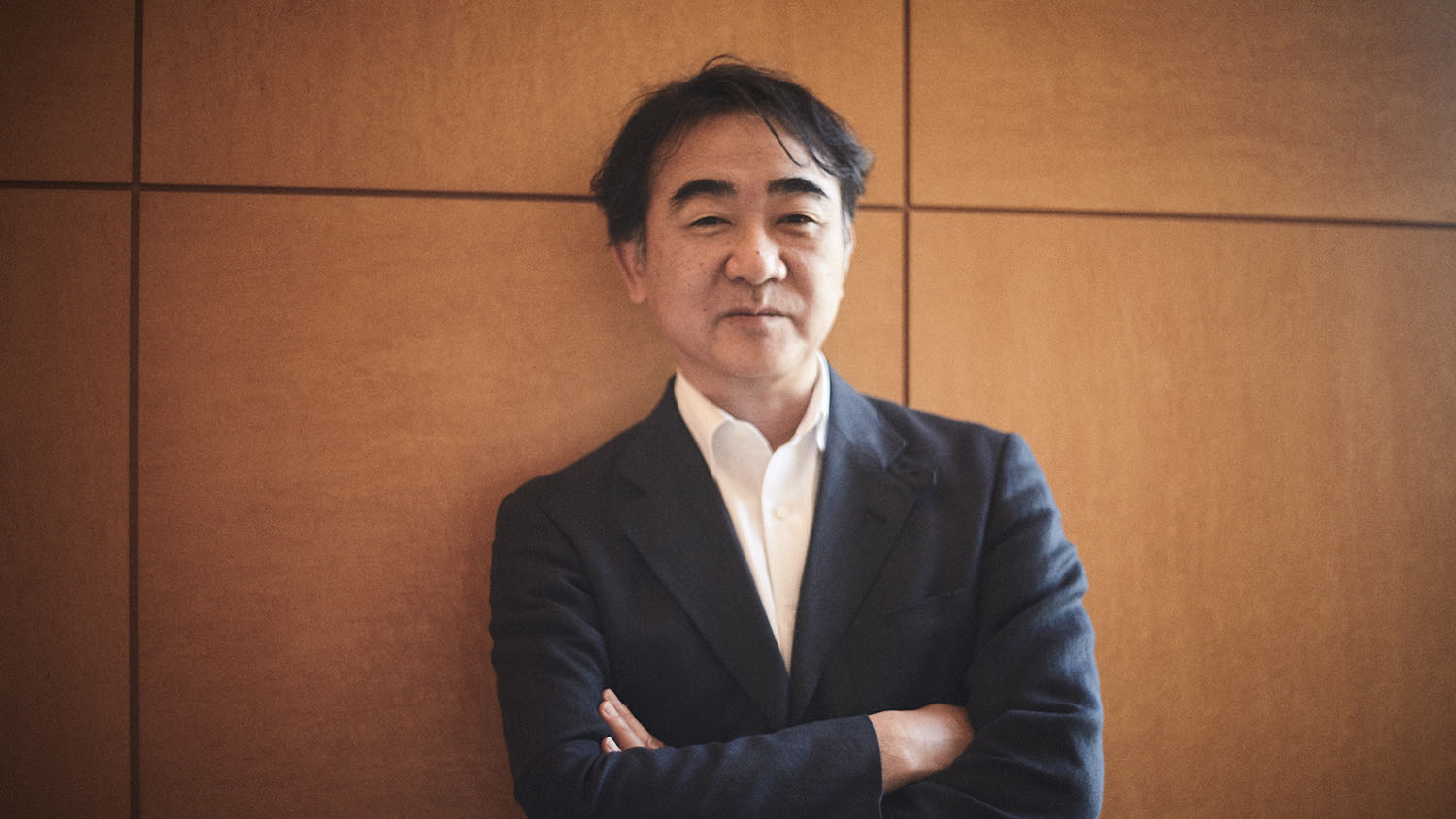目次
会社や組織といった社会の構造の中でもがく人々の姿を丹念に描いたその作品は、老若男女を問わず多くの読者からの支持を受けています。

数十人もの人生を描き切ること
― 事故か。それとも事件か。大型トレーラーからのタイヤ脱輪による重大事故が発生し、整備不良を指摘された中小運送業者・赤松運送が危機に立たされるところから始まる『空飛ぶタイヤ』は、大手自動車メーカー・ホープ自動車のリコール隠し疑惑へと発展。双方の関係者たちが自らの尊厳をかけて立ち上がる姿を描いた、硬派な社会派群像劇です。
池井戸 : これを書いていた2005年頃は、ちょうどコンプライアンス(法令遵守)が世の中で叫ばれ始めた頃。大企業であれば何をやっても許されるのか? ということに、個人的にも疑問を感じていました。そういう意味では、僕の小説の中では比較的、テーマ性の強い作品と言えるかもしれません。

― 先ごろ発売された新版単行本(実業之日本社刊)の帯には、《ぼくはこの小説から、「ひとを書く」という小説の根幹を学んだ》とのコメントが記されています。
池井戸 : デビュー当時、銀行を舞台にしたミステリー小説を書いていたこともあって、書店で作品が企業小説の棚に置かれることが多かったんです。ひと昔前の企業小説には、『小説・○○○○(実在の企業名)』というような、実際にあった事件や出来事をベースに書かれたものがたくさんあって、それらと混同されることも多かった。
自分の書いているものはあくまでもエンタテインメントで、企業小説じゃないのに、書いても書いてもその棚に置かれる。それで開き直って、「そこまで言われるのなら、企業小説らしいものをやってみるか」ということで書いたのが、この作品。いわば、開き直りの産物です(笑)。そうしたら、直木賞の候補に挙げられたりして、意外と文芸作品としての評価を得ることになりました。
― 「開き直り」で、新たな道が開けたんですね。
池井戸 : ええ。『空飛ぶタイヤ』には、正確には数えていませんが、たぶん70人くらいの登場人物が登場する。70人分の人生が、物語の期間で輪切りにされている、そういう認識で書いた作品です。だから、書いているときには、顔写真付きの登場人物一覧表を作りました。そんなことをしたのは、この作品が最初で、たぶん最後でしょうね。
― 70人分! 顔や特徴、キャリアを、ですか。

池井戸 : そうです。でも、大事なのは外見じゃない。小説で外見について細かく書いても、あんまり意味がなくて、大事なのはやっぱり会話です。たとえば、ある人物の言葉を読んだときに、「ああ、この人は大企業の偉い人だけど、あんまりいい人じゃないんだな」とか、ちゃんと思わせなくてはいけない。
で、そうしたキャラクターたちの人生が、きちんと無理なく積み重なっていないと、小説はあっという間に破綻してしまいます。小説にとって最大の瑕疵になるのは、登場人物が途中でブレてしまうこと。プロット(筋立て)を優先すると、必ずそういうことが起こるんです。
― ストーリーを作るのではなく、人をきちんと描くことが大事だと。
池井戸 : 『空飛ぶタイヤ』とほぼ同時期に書いた、『シャイロックの子供たち』(06年刊・文春文庫)という、銀行を舞台に書いた連作短編集がありますが、この2作が、僕の小説の書き方の転換期になった作品だと思います。

小説も映像も、評価はきちんと受け止める
― そうして生まれた重厚な長編作品。これまで、作品の映像化はおもにテレビの連続ドラマが多かったですが、2時間という尺にまとめられた映画『空飛ぶタイヤ』(18年)を、どうご覧になられましたか。
池井戸 : 原作のエッセンスを上手に抽出しているな、という印象でしたね。その上で本木(克英)監督なりの映像作品に組み立ててあって、なかなか上手に作られていると思いました。
たとえば、主人公・赤松徳郎の家族が事件と同時期に向き合うことになる、息子の学校のPTAでのトラブルは、原作ではかなりのページ数が割かれているエピソードですが、映画では削られています。でも、削ったことで、物語の骨格がうまく浮き彫りになったと感じました。
― 人を描く、という点では、長瀬智也さんが演じる主人公・赤松と、彼と対立するホープ自動車のエリート課長・沢田悠太のふたりが、映画ではよりクローズアップされていますね。赤松は円満な家庭人ですが、ディーン・フジオカさん扮する沢田はバツイチで孤独な男と、原作にはない対照的な肉付けがなされています。
池井戸 : 原作の沢田は妻帯者で、妻から有益なアドバイスをもらう場面があったりもするんですが、映画のような描き方もありだと思いますね。赤松と沢田の、ベッタリくっついたりしないけれども、徐々にお互いの存在や考え方を認め合い、わかり合っていく描写も繊細で、好ましかったです。

― 長瀬さんとディーンさんは、お二人とも、池井戸さんの映像作品には初出演でしたが、印象はいかがでしたか。
池井戸 : ディーンさんはクールで、小説の沢田のイメージにぴったり。長瀬さんは、運送会社の社長にしては本当は格好よすぎるんだけど(笑)、でも、すごく熱演してくださった。長瀬さんなりの赤松を研究して演じておられたように思いました。
ホープ自動車と同グループの銀行で、融資をするか否かの決断を迫られる担当者を演じた高橋一生さんは、僕の原作の他のドラマ『民王』(15−16年・テレビ朝日)、『鉄の骨』(10年・NHK)にも出演していただきましたが、今回もいいお芝居をしてくださいました。これだけのキャストが揃っているわけですから、万が一、映画が興行的に失敗したら、「原作が悪かったから」と僕が責められるんじゃないかと、いまはちょっと不安に思っています(笑)。
― 作品への評価は、やっぱり気になりますか。
池井戸 : もちろん。小説を発表したり、ドラマが放送されたりすると、SNSなどで読者や視聴者がどんなふうに受け取ってくれたかは、ちゃんとチェックしています。作家にとって、小説は商品だし、映像は僕が直接撮っているわけではありませんが、言ってみれば自分のコンテンツ。だから、商品が市場に、消費者に届いたときに、どんな反応が起こっているかというのは、確認するのが当たり前だと思います。
ただ、大切なのは、評価の上と下、つまり褒めすぎとけなしすぎその両端は外して見ること。極端な評価をする人たちでなく、中間層の意見を総括して、たとえば小説の、Amazonの星の数でいえば、4と残りの星半分くらいがついていれば今回は合格、という具合です。
― かなりシビアに分析されているんですね。
池井戸 : もし調査会社に依頼したら、大変な費用がかかるでしょうから、タダで見られるSNSはありがたいですよ。作家の作品づくりは、基本、プロダクトアウト(作り手がいいと思ったものを提供する)の世界で、提案型のエンタテインメントなわけですが、読者の反応を見て世に出すのとそうでないのとでは、結果がぜんぜん違うのではないかと。人に読んでもらいたい、楽しんでもらいたいと思って世に出しているわけですから、必ず反応を見て、次に生かすんです。

人を描き、人を楽しませる、エンタテインメントの第一人者ならではの仕事術。後編では、そんな池井戸さんと映画との関わりを、さらに掘り下げます。