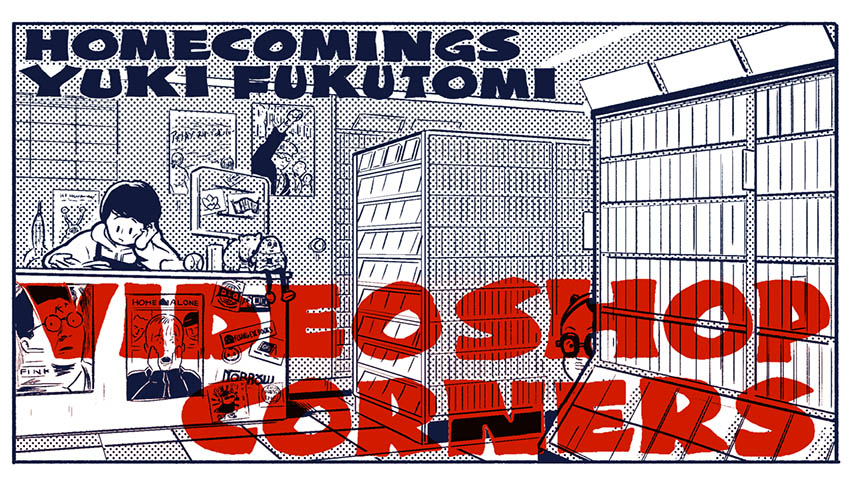今、私が朝起きて一番最初にすること。それは踊ることだ。
まず目が覚めたら、布団をあげ、床をさっと拭いて、器に白湯か温かい飲み物を用意する。それからノートパソコンで音楽をかけ、習い覚えた日本舞踊を踊る。多い時は五曲くらい、時間のない時は一曲だけ。扇子を持って踊ったり、番傘の代わりにビニール傘や箒を持って踊ったりする。旅先のビジネスホテルの部屋の中でも、まだ人気のない朝の川原でも、とにかく扇子一本あれば踊れるのだ。気づけば、この朝のモーニング・プラクティスをもう何年も続けている。
「真歩は小さい頃から踊りが好きだったのよ」と母はよく私に言った。兄と一緒に通っていたピアノ教室で、先生のピアノの伴奏に合わせてソルフェージュを歌う兄の後ろで、あなたはいつも踊り回っていたのだ、と。小学生の頃は近所のバレエ教室と新体操教室にずっと通っていたし、大人になってからも、なぜか踊っている時が一番安心できた。役者になったばかりの頃、オーディションの前に緊張して身体がカチコチになってしまい、トイレに籠って汗だくになるまで踊ったり、あれこれ思い悩んで行き詰まった時にも「DON’T THINK! DANCE!!」と好きな音楽をかけてハチャメチャに身体を動かすことでいろいろな窮地を乗り越えてきたように思う。
こんなふうに「踊り」は私にとっていつも身近な存在だったけれど、日本に昔から伝わる舞踊を習ってみようとは一度も思わなかった。それらはなんとなく古臭く、自分とは関係のない過去のものという感じがしていたのかもしれない。
私が最初に日本舞踊に興味が湧いたのは、役者を志して会社を退職した二十代後半の頃。いざ無職になったはいいけれど、周りにプロの役者の知り合いがいるわけでもなく、毎日具体的に何をしたらいいのか見当もつかなかった。たとえばバレリーナだったら、日々血の滲むようなバーレッスンをするかもしれない。たとえば画家だったら、世の中のありとあらゆるものをスケッチブックに写生していくかもしれない。じゃあ、役者は? 演じる役が来るまでじっと家で待つだけ?
そんなことを思いあぐねながら、することもなく漠然と映画を観ていたある日、確か『お遊さま』という古い日本映画の冒頭で、着物を着た女性が庭園を歩くというシーンがあった。映画の内容は忘れてしまったけれど、その人の歩く姿だけは強烈に覚えている。「何なんだ、この歩き方は?」と思ったのだ。ゆっくりと地面すれすれを撫でるように歩いているその姿は、まったく重力を感じない。いつか宇宙飛行士が月面を歩く映像を見たことがあるけれど、それに近いものがあった。私はそんなふうに人が歩く姿をこれまで見たことがなかったので、一瞬にして釘付けになってしまった。そして、彼女が動くたびに周りに柔らかいそよ風が広がっていくようで、とろけるような気持ちになった。「わあ、なんて美しいんだろう」と私は見とれた。映画が終って名前を見ると、田中絹代さんという女優だった。
その魔法のような歩き方を目にしてからというもの、私はこれまで観て来なかった日本の古い作品を探して観始めた。映画館の特集上映で観た『西鶴一代女』の冒頭シーンも忘れられない。とぼとぼと歩いていく着物の女性の後ろ姿がずっと映し出されるのだけど、その後ろ姿だけで、彼女が長いこと歩き疲れ、人生に疲れ、身寄りのない寂しい身であることが胸に刺さるように伝わって来た。その人も田中絹代さんだった。映画の中で彼女は、高貴な女性が愛する人を奪われ、我が子を奪われ、長い年月をかけて最後は身を売る夜鷹にまで没落していく様を演じていた。一人の役者がこんなふうに様々な境遇や心を豊かに表現することができるのかと驚いた。
そして他の日本映画も観ていくうちに、田中絹代さんだけでなく、「こんなふうになりたいな」と思う役者たちと沢山出会うことができた。彼らは年齢や性別を問わず、美しかった。顔そのものが美しいというよりは、その人の生み出す仕草や佇まいがなんとも素敵で、静かな色気が漂っているのだ。そしてだんだん気がついたのは、私が「素敵だな」と思う人たちに共通しているのは、日本の伝統芸能に触れているということだった。
その頃からだと思う。自分がまだ生まれる前の祖父や祖母たちの時代のこと、さらに昔の日本のことをもっと知りたいと思うようになったのは。
私が生まれたのは昭和五十六年で、高度経済成長を終えてバブル期に入ってく頃だった。当然のことながら世の中の人々はもうすでに洋服で生活をしていたし、子供の頃一家に一台あったダイヤル式の黒電話は姿を消して、一人ひとりが携帯電話を持つようになり、テレビもどんどん薄くなっていった頃だった。音楽といえばJ-POPや洋楽が主流で、周りで三味線なんかの伝統音楽を聴いている友達なんて一人もいなかった。日本人なのに日本の昔のことをよく知らずに育った私が、大人になって初めて目にした白黒の日本映画から聴こえて来る三味線や琴の音色、着物を生き生きと着こなす女性たちを目にした時の驚きといったら……。なんだろうこの美しいものたちは、と思ったのだ。
田中絹代さんの歩き方を目にしてから、私の中で何かが変わった。若い頃は、毎日着物を着てお茶の先生をしていた祖母に「茶道を教えてあげる」と言われても、正坐でじっとしているのが退屈で逃げてしまったし、祖父が詩吟の先生だったことすら知らなかった。彼らが差し出してくれていた両手の中のものを、私はそっぽを向いて受け取らなかったのだ。いまや、祖父母の手の中のものは空中に消えてなくなり、着方のわからない何枚もの着物と、使い方のわからない年季の入ったお茶道具だけが沢山後に残った。なんて勿体ないことをしたのだろう、なんでちゃんと話を聞いておかなかったんだろうと悔やまれた。
「とにかく、彼らが学んでいたことを私も学ばなくちゃ」と焦るような気持ちで、都内の日本舞踊の教室を調べて電話をかけてみた。そして最初に電話に出てくださったのが、今も踊りを習っているA先生だった。「日本舞踊を習いたいのですが……」と私が緊張しながら言うと、「どうぞ、いつでも見学にいらしてください」と優しく仰ってくださった。
私はさっそくリサイクルショップで浴衣を買い、いそいそとお稽古場に出かけた。二階が檜舞台になっている日本家屋で、A先生はお弟子さんに一対一で稽古をつけていた。私は隅っこの方に正座してその稽古の様子を見つめながら、「うわー、宝の山だ!」と興奮した。目に見えないはずの心の動きや周囲に広がる風景が、言葉ではなく、ふとした仕草や振りで現されていて、それが一つの美しい踊りになっていた。昔の人たちが “心” を伝えるために時間をかけて磨いてきたこの踊りを、私も習ってみたいと強く思った。
こうして、気持ちばかりが先走った最初のお稽古は、浴衣の着方もめちゃくちゃで、扇子の開け方もわからず始まった。私にとって日本舞踊は “NIPPON-BUYO” だった。まるで日本好きの外国人のように、日本の昔のことを学び始めたのだ。
よく「習い事を始めるのは六歳の六月六日がいい」なんて言うけど、そんな時期はもうとっくに過ぎていた。その時、すでに二十八歳。無職になり、お金はないけれど時間ならたっぷりあった。「人生で学ぶことに遅過ぎるということはないさ」と自分を励ましながら、A先生のお稽古場へ通う日々が始まったのだった。
(つづく)

- 「手を振りたい風景」をめぐって
- 「人間らしさ」をめぐって
- 「言葉にならないこと」をめぐって
- 「ありのままの風景」をめぐって
- 年末年始におすすめの映画(後篇)
- 年末年始におすすめの映画(前篇)
- 初のホラー体験記
- 足下を流れる見えない水
- 緑はよみがえる
- 「のぐそ部」のころ
- 午後の光のようなもの
- 袋の男とボナセーラ
- 空洞に満ちたもの
- 「わからない」という魅力
- 猫と留守番しながら思ったこと
- いつでも口ずさむ歌があれば
- 白い、白い日々
- 続・私の日本舞踊ビギニングス 「男のいない女たち」
- 私の日本舞踊ビギニングス 「なんなんだ、この歩き方は」
- ゆっくり歩くと見えてくるもの
- 猫と留守番しながら考えたこと
- となりの山田くん、出番です
- ミジャさんからの手紙
- トラ(寅)ベラ・ノー・リターン 旅人帰らず
- 季節外れの腹巻き
- 未来よ こんにちは
- 子どもはどうでもいいことばかり覚えている
- 恋文、または命がけのジャンプ
- 私の出会ったワンダーランド
- 「ありがとう、トニ・エルドマン」たち