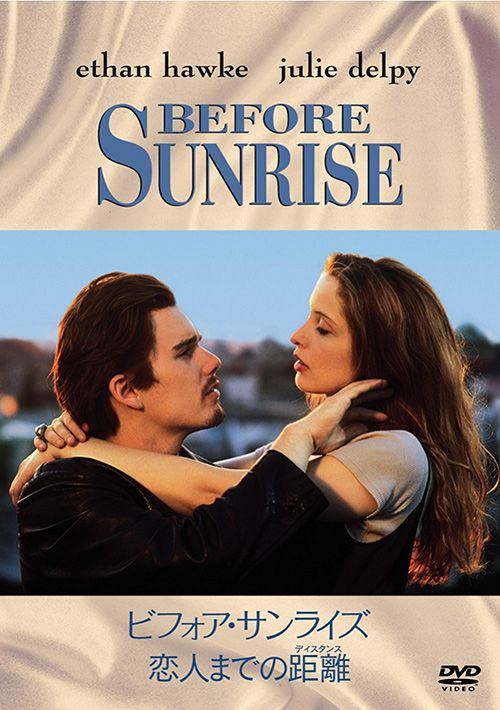目次

人生の先生は
いつも映画の中にいた
絵の具やスケッチブックと一緒に仕事机に置かれたパキラの鉢、本棚に沿うように伸びるポトスの葉、ベランダや窓際にはトックリランやワイヤープランツ。ここがマンションの一室であるということを忘れてしまうほど、たくさんの観葉植物に囲まれ、窓からの風が気持ちよく吹き抜けるこの部屋は、今回DVD棚をご紹介していただく漫画家・山田玲司さんの仕事場です。
「マンションに住んでいると、植物みたいに地面に根ざしたものが近くにないと落ち着かないんですよね。それに、植物があると、葉の様子から自分の精神状態や健康面にも気づくことができるんです。忙しすぎるとつい水やりを忘れて葉が元気なくなっちゃうから」
『週刊ヤングサンデー』で連載されていた人気作『Bバージン』や、各界の偉人にインタビューする『絶望に効く薬』、宮藤官九郎さんと手がけた漫画版『ゼブラーマン』など、これまで多様なスタイルで漫画をつくってきた山田さん。その他にも、“ごきげんに生きる方法”をテーマに恋愛や映画、漫画などを多彩なゲストと語り尽くす「山田玲司のヤングサンデー」(ニコニコ動画)など配信コンテンツでの発信も行っています。

壁一面を埋めるほど大きな本棚には、ご自身の著作を含めた漫画や小説、画集などがぎっしりと並び、上には絵の具などの画材で描かれた山田さんの絵が飾られています。その間を沿うように茂る植物を眺めていると、棚の一部に映画のDVDが数十枚並んでいるのが見えました。
「映像や技術に凝ったスペクタクル巨編よりも、作り手の美学や哲学が見えるような、知的な映画が好きなんです。かといって、教養をひけらかすような感性のものは嫌いで、そこの線引きが僕の中では大事。知識を自慢するようなオタクじゃなくて、ちゃんと物事を考えている大人が手がけた作品が好きなんです。例えば、この棚の中だと、『アメリカン・ビューティー』(2000)のサム・メンデス監督や、『ソーシャル・ネットワーク』(2010)のデヴィッド・フィンチャー監督は、哲学的な台詞まわしも多くて好きな作り手です」

人生について語られる、哲学的な問いを含んだ台詞。それが嫌味なく映画に溶け込み、観客側に投げかけてくる作品を、山田さんは繰り返し観ることが多いと言います。なかでも特に好きな作品として棚から出してくれたのは、リチャード・リンクレイター監督の『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離』(1995)でした。ハンガリーからパリへ向かう列車で偶然乗り合わせた男女が、途中下車したウィーンの町を歩くというストーリーを、ドラマチックな展開ではなく、哲学的な会話で見せていく作品です。
「自分がラブストーリーを描いているというのもありますが、恋愛映画を観ていると“観客の喜びそうな演出しよう”という作り手の意図が透けて見えてしまうことがあるんです。でもいい恋愛映画って、実は恋愛以外の要素で決まると思います。『ビフォア・サンライズ』は、アメリカ人とフランス人の男女が人生について語ることで、文化圏の違いも見えてくるし、その二人が旅先のウィーンを歩くことで、その“違いの層”がより複雑な色合いを持ってくる。エンディングの後に、二人のいない“二人が歩いた場所”が映し出されるんですけど、『人生ってなんだろう、時間ってなんだろう』という哲学的な問いを、そのシーンがこちら側に投げかけてくるんです。“こうすれば喜ぶだろう”ではなくて“どう思う?”と。観ている方も映画に参加させてもらっている感覚になりますよね」
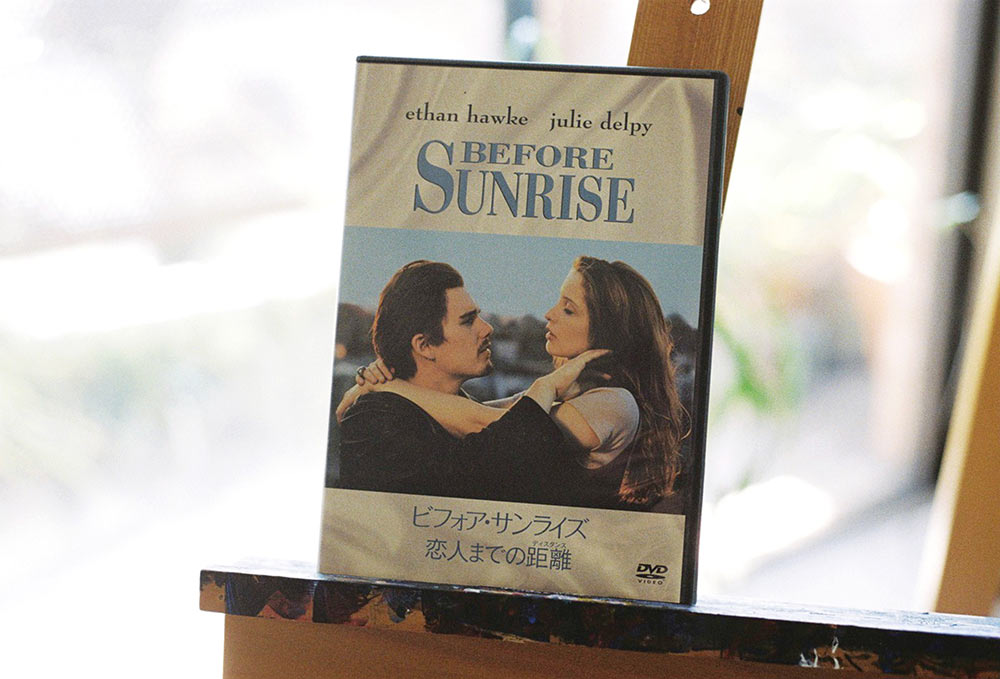
棚にはあまり並んでいない日本映画ですが、山田さんが昔から憧れているという日本映画の登場人物がいます。『男はつらいよ』シリーズの主人公、寅さんこと車寅次郎です。
「母親が下町、父親が山の手出身なので、僕は子どもの頃から寅さんの映画に出てくるような世界の中で育ってきたんです。寅さんの甥っ子、満男みたいな感じ(笑)。だから、ああいう大人たちにも馴染みがあるし、憧れでもあるんです。寅さんって“俺はいいからよ”とか“じゃあ、まあこのへんで”って、ふっといなくなるじゃないですか。そういう格好の付け方もいい。あれは逃げてるわけじゃなくて、寅さんの美学なんですよね。山田洋次監督、倉本聰さん、市川崑監督あたりの日本映画には、頑固で融通がきかないけど、可愛げと優しさがある、こういう男の美学が貫かれていた気がするんです。」
山田さんは、寅さんを監督自身の哲学や美学が体現された存在として、憧れていると言います。と同じく黒澤明監督の映画に出てくる男たちが今でもかっこよく見えるのも、監督の血肉が通った美学が感じられるからだと。

学校や職場では出会うことのできないキャラクターや、自分では経験することのできない数々の人生。そうした出会いを通して、「物事をよく知り理解したい」という知的好奇心を満たしてくれたのが映画だったと、山田さんは語ります。
「人って、知的好奇心が満たされた経験があれば、自分から物事を考えるようになるし、面白いものを自ら探しに行くようになるんです。そうすると人生の選択肢も増えるし、世の中に面白い人が増えると僕は思っていて。その知的好奇心を最も、かつ確実に満たしてくれるのが、僕の場合は映画だった。好きな監督や作品を通して、いろんな文化圏のことを知るようになったし、考えるようになりました。そんなふうに、より多くの人にいい作品を観て、人生の楽しみ方を映画の中から見つけてほしい。そういう思いから、映画について紹介する配信コンテンツを放送してるんです」

映画からもらう「初期衝動」と「嫉妬」が、
創作に向き合う力になる
自身がチャンネルを持つ動画配信コンテンツを通して、映画を多くの人と共有したいという山田さんですが、数名のアシスタントと一緒にこの仕事場で漫画の作業を行う時も、机の上の大きな液晶モニターで、映画を流して観ているのだそうです。作業中に、ラジオや音楽ではなく映画を流すのはどうしてなのでしょうか?
「漫画のストーリーを考える時は頭を使うので流しませんけど、みんなでペン入れをしている段階の時はもう“作業”になるので、映画を観ます。というのも、ここで働いている人たちは、この先プロの漫画家になりたいという思いで集まっているので、映画を観ることも学びに繋がるんですよね。この台詞が後の演出で効いてくるとか、ここの演出がいいねとか、みんなで話していて。そういうインプットと、ペン入れ作業というアウトプットを、同時にしている時間なんです。僕も昔は、映画を観る時に、気になったところは一時停止して、スケッチブックに好きなシーンの構図を描いたり、カメラワークの勉強をしたりしていました。でも漫画家としての経験も重ねてきたので、今はスケッチしなくても構図を頭の中に留められるようになっています。ミュージシャンが音楽を聴く時に、無意識にベースの音を聞き分けたりするのと同じかもしれないですね」

ストーリーやキャラクターの奥に、どんな哲学や美学が潜んでいるのか。構図やカメラワークが演出の中でどう効果的に使われているのか。ひとりの観客であると同時に、漫画家という表現者としても映画を観ているという山田さんですが、映画からインプットしているものは、技術的な視点だけではありませんでした。
「個人のアイデアだけじゃなくて、ビジネスが介入してくる業界に身をおいていると、本当に魂が失われていくんです。『最近はこういう漫画が売れてるからこういう方向性で』と、安易に世の中の流行りに乗っかるとか。でも関わっている人たちも悪気はなくて、作品が多くの人に届いてみんなが幸せになるためにそうしているんだけど、結果的にそういうものを作ると“魂のない空っぽなもの”を描いているような、虚しい気持ちになってくるんです。そういう時、漫画家としての初期衝動や自分の魂を蘇らせるために必要なのは、好きな映画を観ること」
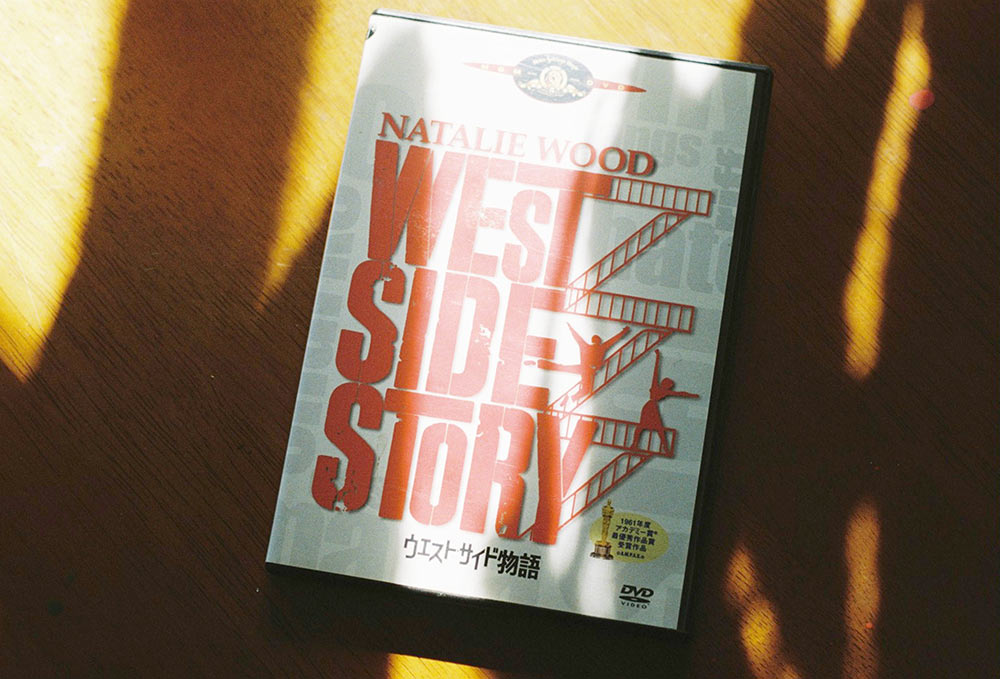
そうして、棚の中から出してくれたのは、ブロードウェイのミュージカルを映画化した『ウエスト・サイド物語』(1961)です。「持っているDVDの中でも、一番繰り返し観ているかもしれない」という今作は、『ロミオとジュリエット』を基にした王道ラブストーリー。現代にも通じるフラストレーションを抱えたニューヨークを舞台に描かれた、永久の名作です。イギリスのシェイクスピア文学とロシアのバレエの融合、そして移民問題や多様性への問いかけなど、多くの要素がこの作品に詰まっています。
「第一次世界大戦の終結後のパリは、世界各地から芸術家が集まって“狂騒の20年代”と呼ばれた時代がありましたよね。あれと通じるのかもしれませんが、あらゆる文化圏の芸術が出会って充実しているという時代感が、この映画の時間に閉じ込められていて、すごくエモーショナルに感じるんです。“人間はここまでやれるんだな”ということを思い出す。自分の中の初期衝動に火が灯るんです」

「それから最近は『ミステリアス・ピカソ 天才の秘密』(1956)というドキュメンタリー映画を見つけて、それもよく観ています。画面に真っ白なキャンバスが映されて、そこにピカソが筆を入れながら絵を完成させていく様子が、何の説明もストーリーもなしに、ひたすら繰り返される映像です。当時のピカソは75歳ですけど、どんなに繊細に描いた絵でも、躊躇なく大胆に塗りつぶすこともあって、とにかく筆が止まらない。創作や表現の根源みたいなものに触れることができるんです。今年に入ってから毎日のように観ていて、仕事部屋にも、こうしてピカソの絵を飾っています」
自分の中の初期衝動を蘇らせてくれる、いくつかの映画の存在。同時に、それを観た時に生まれる、もうひとつの感情があるのだそうです。それは、山田さんも表現する側だからこそ湧き出てくる「悔しい」という気持ち。
「いい作品に出会うと、観客として幸せな気持ちになるのと同時に、いつも“悔しい”と思うんです。自分もこういうふうに表現したい、こういう作品が作りたいと。それは映画だけじゃなくて、本業である漫画でもそうだけど。嫉妬しないのは、音楽くらいかな。だから、本屋とか映画館に行っても辛いんですよ(笑)。でも、そういう体験を求めているんだと思います。自分が“これ面白くないじゃん”と思うものが売れてると、情けない気持ちになる。実は、それが一番辛いですよ。だったら、いい作品に出会って嫉妬する方が幸せなことだし、自分のモチベーションにもなる。だから、悔しいけど、“ありがとう”という気持ちです」
大きな本棚の中に並ぶ十数冊のDVDは、どれも背表紙が日に焼け、これまで長い時間棚に置かれ、繰り返し再生されてきた時間の積み重ねを感じました。人生を楽しむための知的好奇心や、漫画家としての初期衝動や魂を何度も蘇らせてきたその映画は、これからも色褪せることなく山田さんのそばに置かれているのでしょう。

- 映画に込められた愛情と熱量が 自分の「好き」を貫く力になる
- 「好き」が詰まった部屋はアイディアの引出し
- 映画を作るように、料理を作りたい。働き方の理想は、いつも映画の中に
- 最新技術と共に歩んできた映画の歴史から、“前例のない表現”に挑む勇気をもらう
- 映画は仕事への熱量を高めてくれる存在。写真家のそばにあるDVD棚
- “これまでにない”へ挑みつづける!劇団ヨーロッパ企画・上田誠が勇気と覚悟をもらう映画
- “好き”が深いからこそ見える世界がある!鉄道ファンの漫画家が楽しむ映画とは?
- 一人で完結せず、仲間と楽しむ映画のススメ
- おうち時間は、アジア映画で異国情緒に浸る
- 漫画家・山田玲司の表現者としての炎に、火をくべる映画たち
- 時代の感覚を、いつでも取り出せるように。僕が仕事場にDVDを置く理由
- 「この時代に生まれたかった!」 平成生まれの役者がのめりこむ、昭和の映画たち
- 好きな映画から広がる想像力が 「既視感がバグる」表現のヒントになる
- 好きな映画の話を相手にすると 深いところで一気につながる感覚がある
- 勉強ができなくても、図書館や映画館に通っていれば一人前になれる。
- ナンセンスな発想を現実に! 明和電機とSF映画の共通点とは?
- 22歳にして大病で死にかけた僕。「支えは映画だった」 絵本作家の仕事部屋にあるDVD棚
- 映画は家族を知るための扉。 保育園を営む夫婦のDVD棚
- 「映画を観続けてきた自分の人生を、誰かに見せたい」 映画ファンが集う空間をつくった、飲食店オーナーのDVD棚
- “すべての人を肯定する服作り”をするファッションデザイナーのDVD棚
- 「データは信用していない」映像制作プロデューサーが、映画を集める理由
- 写真家としてテーマを明確にした映画。自分の歩む道を決めてきた、過去が並ぶDVD棚。
- DVD棚は“卒アル”。 わたしの辿ってきた道筋だから、ちょっと恥ずかしい
- 映画を通して「念い(おもい)を刻む」方法を知る
- 家にいながらにして、多くの人生に出会える映画は、私の大切なインスピレーション源。
- オフィスのミーティングスペースにDVD棚を。発想の種が、そこから生まれる
- 映画の閃きを“少女”の版画に閉じ込める
- 映画の中に、いつでも音楽を探している
- 映画から、もうひとつの物語が生まれる
- 探求精神があふれる、宝の山へようこそ。
- 無限の会話が生まれる場所。 ここから、創作の閃きが生まれる。
- 夢をスタートさせる場所。 このDVD棚が初めの一歩となる。
- 本や映画という存在を側に置いて、想像を絶やさないようにしたい。