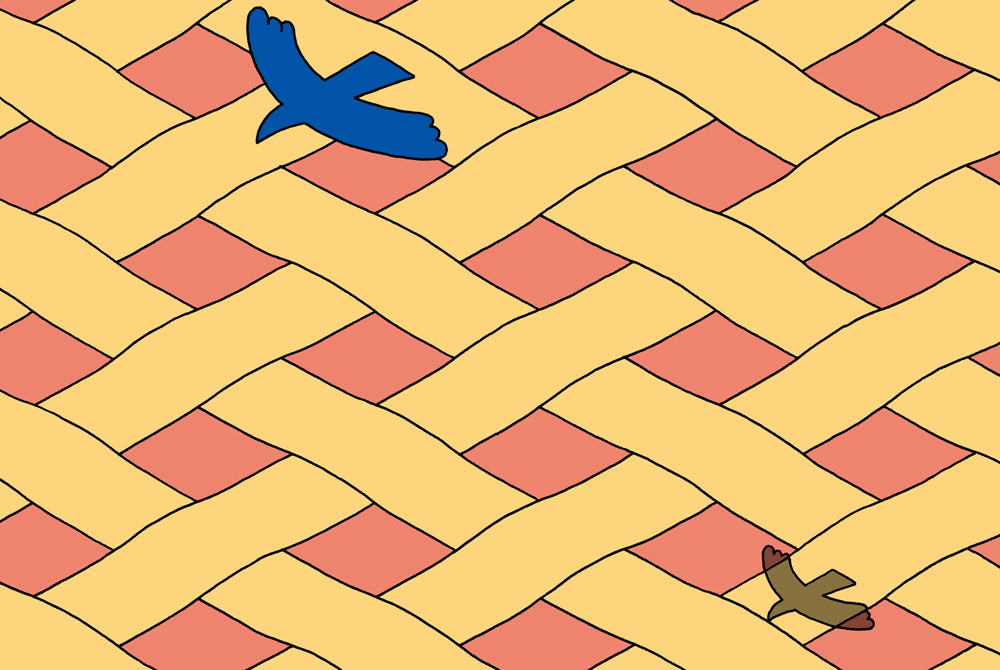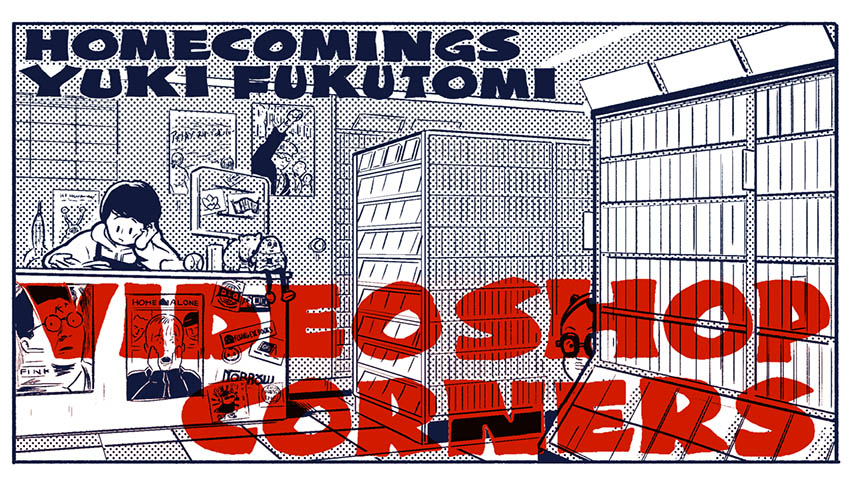
大学時代の僕にとって映画というのは、大学の情報館という施設にある大量のVHSやDVDのことだった。たまに、情報館で借りられないものでどうしても観たい映画があると、バイト先のピザ屋さんがあった町のレンタルビデオショップまで借りにいった。そのレンタルショップは、芸大が近くにあることも手伝い、なんだか特別な場所のような雰囲気をもっている店だった。
当時まだVHSの貸し出しもやっていたそのビデオショップは、24時間営業のため、いつ行っても、気怠そうで、それでいてヘラヘラしている大学生ぐらいのアルバイトの店員さんがいる、ドラマや漫画に出てくるようなお店だった。それはあのアラスカの匂いとちょっと似ていて、小綺麗なチェーン店よりもなんだか居心地がよかった。ごちゃごちゃした店内の棚に並べられた映画はざっくりとジャンルで分けられてるだけなので、目当ての映画を探すのにいつも苦労した。けれど、一番上から下へ左から右へと人差し指でなぞっていくその時間が僕はとても好きだった。大抵それは、バイトが終わったあとの夜の遅い時間帯で、ピザ屋のバイトで体についてしまった油の匂いと疲れた体と、ちょっとした開放感がちょうど合わさって妙にぬるい気持ちよさがあった。
そのときにはもうHomecomingsの活動も少し軌道に乗り始めていて、フジロックのルーキーステージに出たり、月に1、2回のペースで東京に行ってライブをしたりと忙しくはなってきていたけれど、まだ自分がこれからどんなふうになっていくかは全然掴めていなくて、そんな不安な気持ちとも絶妙にリンクしていたのだと思う。
借りるのはいつも決まって旧作の映画だったから(旧作は2週間で100円ととても安かったのだ)、すぐに返却しなくてはいけない新作や準新作のコーナーはちらっと眺めるぐらいで、ほとんど借りたことがなかった。そんなこともあって、ちょうどこの頃の、2011年から2013年ぐらいまでに公開となった映画が、僕からすっぽりと抜けている。情報館に新しい映画が入ることもそんなにはなかったし、とにかく僕にとっての観たい映画なら、もう数え切れないぐらいそこにあったのだ。
そんな頃、映画館で観たほとんど唯一といってもいい映画が、ウェス・アンダーソン監督の『ムーンライズ・キングダム』だ。
ウェス・アンダーソン監督の映画はそれまで、情報館にあった初期のいくつかの作品しか観ていなかったけれど、レコード屋さんでなんとなく見かけたポスターがとても可愛いくて、さらに僕の大好きなビル・マーレイ(まだウェス・アンダーソンの映画のほとんどに彼が出ていることも知らなかった)が出演しているということもあり、ある日、電車に乗って街まで観に行ったのだ。多分そのときもう『ムーンライズ・キングダム』は新作映画というタイミングでもなくて公開から半年ぐらい過ぎたあとだったと思う。お昼の1回の上映。はじめて京都シネマで映画を観た。それまで行ったことのある映画館のなかで一番小さな映画館だったし、平日のお昼ということもあってお客さんもまばらだったけれど、そのことが余計に「スクリーンの前に座っている人たちはみんな、本当にこの映画を楽しみにしているんだろうな」と感じさせた。
場内が暗くなる前、スタッフの人が出てきて館内での注意事項を、大きくもなく小さくもないちょうど真ん中の音量で伝えていた。僕はなんだか少し緊張して、席に座り直し背筋を伸ばした。今まで行ったどんな映画館でもこんなふうにスタッフの人が出てきて話すのを見たことがなかったからだ。そんなことはそこにいた僕以外の人にとっては当たり前のことだったのだろう。とくに誰も気に留めていないようだった。でも無視するというわけではなく、なんとなくの敬意のようなものが感じられたのを覚えている。照明が落ちて予告編がはじまっても、僕はなかなか背筋をもとにもどせなかった。
はじめて映画館のスクリーンで観るウェス・アンダーソンの映画は登場人物の衣装に着いている小さなワッペンから何気ない子供部屋の置物まで、画面の端から端まで、文字通りなにからなにまで魔法がかかっているかのように魅力的だった。
『ムーンライズ・キングダム』は、ウェス・アンダーソン監督の7作目の長編で、小さくて静かな島が舞台だ。身寄りのないボーイスカウトの少年はまわりからは少し浮いていて、そして同じようにまわりとは少し違う大人びた女の子と出会い、小さくて壮大な駆け落ちを計画する、という映画。小さな恋人たちの冒険の物語でもあるし、少年が家族を獲得する物語でもある。僕は、彼の映画の見た目や世界観の可愛さ、美しさはもちろんのこと、それ以上にその物語の力強さに心を掴まれた。それはこのあと観ていくことになる過去の作品や、あとに公開された新作にも共通して、様々な形をした「家族」というものを通し、やさしさの大事さを描きながらも、決して暴力や死から目を背けないその強さがあった。それこそ、一番の魅力なんじゃないかと思う。
新作の上映ではなかったからパンフレットも置いてなかったので、チラシだけをきれいに折り目がつかないように畳んでもって帰った。ウェス・アンダーソン、という名前はここに来る前とそのあとでは、まるっきり価値や意味が違ったように思えた。それはちょうど大学を卒業する春休みのことだった。
そのすぐあと、僕は大きなチェーンのCD屋さんで働き始めた。CD屋さんの店員になることは、小さな頃からずっと憧れていたことで、小さな夢が一つ叶ったような気すらしていた。そのCD屋さんでは、少しだけだけど社員割引があって、働きはじめてすぐに僕はウェス・アンダーソンのDVDとサントラのCDを片っ端から買った。廃盤になっていた『天才マックスの世界』のDVDは「100000tアローントコ」という中古レコード屋さんで見つけた。今でも僕の宝物のひとつだ。
大学のあった京都の北の端の静かで寂しい町から、市街地のすぐそばの街へと引っ越した部屋で、僕は毎晩のように彼の映画を繰り返し観た。彼の映画はどれも何回観てもそのたびに小さな発見があった。セットの細かい遊びや、セリフ、そして画面のなかにはまだ僕が見つけられていない仕掛けがあるような気がした。
劇中で流れる音楽にもとても影響をうけた。エミット・ローズ、ニック・ドレイク、キャット・スティーヴンス、フェイセズ、ゾンビーズ、セウ・ジョルジが歌うデビッド・ボウイ、ニコの「These Days」。物語のなかで流れる音楽を好きになる楽しさも、ずっと大好きだった曲がシーンを彩ることの嬉しさも、そのどちらもが彼の映画のなかにはある。
そしてなんといっても、DEVOのメンバーでもあるマーク・マザーズボーが手がけるスコアだ。僕が初期から中期にかけての作品が大好きな理由のひとつが彼のスコアの魅力であることは間違いない。
学生という縁取られたモラトリアムの期間を過ぎても、まだ漠然と将来の不安を抱え、アルバイトをしながら音楽を続ける、という青春期の延長線にふらっと足を踏み入れていた自分にとって、彼の映画のなかの登場人物たちの抱えるやりきれなさ、とりわけ、もたざるものではない者たちが抱える寂しさや、どこか足りない、欠けてしまっている感覚のようなものが胸の奥の方まで深く刺さっていくような気持ちになった。
ウェス・アンダーソンの映画は初期のアメリカ小説のような物語から、作品を重ねるごとにだんだんと視点が広くなっていく。インドを舞台にしたかと思えばストップモーション・アニメーションを手がけたり、ヨーロッパで撮影をしたりもする。どんどんと物語のスケールが変化していっても、魅力が失われないのは、彼自身が大切にしているものを離さず掴み続けているからだろう。規模や種類は違えど、ものを作ることを続けると決めた僕にとって彼の世界のすべてに憧れると同時に勇気をもらった。
小学生の頃、週末のテレビやレンタルショップ・アラスカで出会った『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『E.T.』、そして『ゴーストバスターズ』のビル・マーレイに憧れたり夢を抱いたりしたのと同じように、22才の僕はウェス・アンダーソンに夢を与えられたのだ。
毎朝起きて、支度をして自転車に乗って音楽が溢れている場所で働く、週末には遠い街で演奏して、たくさんの人に会う。そんな日々のなかで、僕の生活のなかにはずっと彼の映画がそばにいてくれていたように思う。そして今も、Homecomingsのライブは照明が落ち、ニコの「These Days」が流れることから全てがはじまる。そして、それは今も。
その頃住んでいた街からは遠く離れた街に住んでいる。あれから何年か経ち、音楽や物語を作ることは僕の仕事になった。それでも、まだなにかが僕を不安にさせる。なにげない瞬間にふと寂しくなることもある。自分のことが嫌になったり、自分が作るものにすら自信をなくしてしまいそうになったりすることもある。そんなときに、僕が憧れ、夢を見続ける彼の映画の世界は、いつまでもそっと背中を押してくれる。世界や周りに背を向けて自分の大事なものを守り続け、自分であり続けるキャラクターたちや、頭の中に描いたものを長方形の中でどこまでも追い求める、彼のものづくりに対する情熱は、僕にとって、どんな悩みも打ち明けあえる大事な友だちなのだ。
歩いていたんだろう? 僕も同じさ 不思議な気分 会ったこともないのに 全部分かられているみたい
秘密を少し分けよう 君がしてくれたみたいに 不思議な気分 会ったこともないのに ずっと前から分かっていたみたい
月明かりの下にだけ 僕たちの居場所があるのだ 踊るように夢を見て 今もまださめない
近頃は また物事がきっと良くなっていくような そんな気分さ 近頃は 君がそばにいないと思うことも少なくなってきたのさ