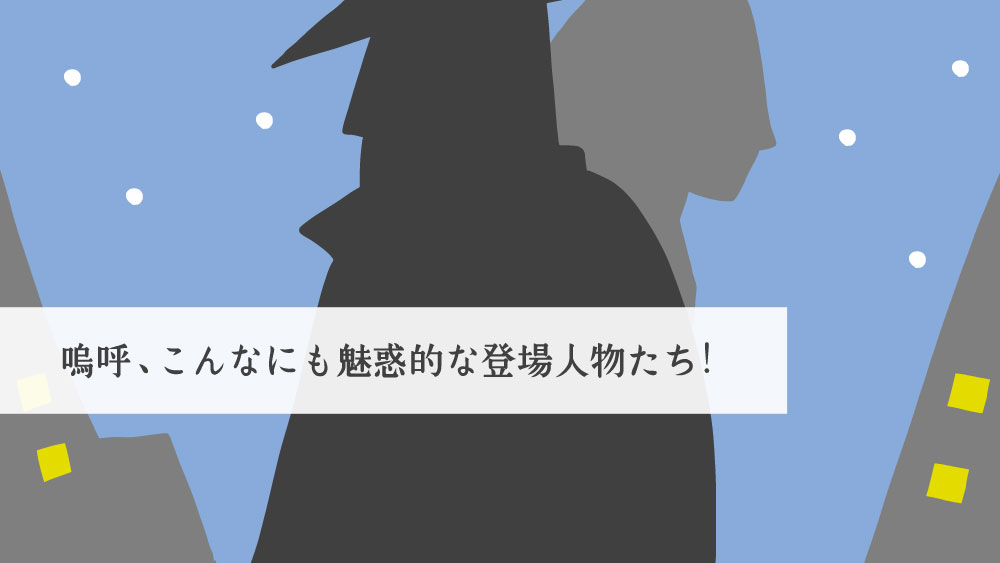目次

コントロールできないからこそ魅力的
― ポスターにある「共感度0.1%」というコピーどおり、観ている側が主人公になかなか共感できない、その“共感のできなさ”が大変印象に残りました。その主人公・辻一路を森崎さんが演じたわけですが、「同じ職場の女性に二股」「どこかいつも冷めていて受け身」という“曖昧と無難”を繰り返してきたようなこの役柄は、俳優として歌手として世界へ挑戦する森崎さんのイメージとはかけ離れているように感じたのですが…?
深田 : そうですか? 「当て書き」みたいなものでは?
森崎 : 何を言ってるんですか! 原作があるじゃないですか!!
一同 : (笑)
― …当て書き…!?
森崎 : もしそうだったとしても、「そうです」とは言いません!(笑)
― (笑)。本作は、深田監督が初めてマンガの映像化に挑んだ作品でもあります。原作は、星里もちるの異色作と呼ばれる『本気のしるし』。描いたご自身も「それまでコメディオンリーだった私が、負のパワーを総動員し自分のドロドロした内面ととことん向き合い、本気で描き上げた野心作」とおっしゃる恋愛サスペンスです。

森崎 : 僕が演じた辻くんの行動は、ところどころ共感できる部分もあったんですけど…やっぱり最初に台本を読んだ時は、「ぇえ!? なんで?」と感じてしまうところは多かったです。と同時に、人って理屈で説明できるような行動ばかりをとっているわけではないよなと、理解することもできたんです。
― 辻は、「なぜその選択を!?」という行動を、葉山浮世(土村芳)という女性に出会ってから、次々と取るようになります。浮世と関わった登場人物が「こいつといると、とんでもない目にあわされる」「一度でも抱いたら地獄を見ますよ」と言うように、“関わらない方が絶対いい!”という予感しかない彼女へ自ら近づいて行きますね。
森崎 : でも、理由は説明できないけど、衝動的に体が動いてしまうことってありますよね? だから、今回は撮影現場でも、その場にいて生まれるものを信じて、それは深田監督を信じて染まりにいくと言ってもいいかもしれないですが、反応することを心がけていました。

― 2019年にメ〜テレ(名古屋テレビ)でのドラマ化が発端となった今作は、その反響の後押しにより、劇場用のディレクターズカット版として公開が決定しました。ドラマでは年月をかけて変化する二人の関係が全10話を通して描かれています。長い時間の中で微細に変わっていく辻の心情を、現場で生まれるものを大切にしながら表現するのは難しかったのではないでしょうか。
森崎 : はい、あの…難しかったです。でも、それが後半になってくると…深田監督が描くそういう世界のことを、僕は勝手に「深田ワールド」って呼んでるんですけど、やっと少しずつ理解できるようになってくるんですよね。「あ、キタ! 深田ワールド!」っていう瞬間があって。
深田 : (笑)。そんなにはっきり、わかったりするの?
森崎 : はい、はっきりと。
― はっきりと!
森崎 : 僕の中でつかめる瞬間があったんです。例えば、辻が自宅に帰ってきたら、細川先輩と浮世がそこにいた、というシーン。

― 細川先輩は辻が長年曖昧な関係を続けている職場の先輩で、一緒に暮らしているわけではないけれど、自宅で一緒に過ごすことも多い。彼女と、知らず知らずのうちに気になる存在になっている浮世が、自分の部屋ではち合わせしたシーンですね。
森崎 : このシーン、台本で読んだだけでもゾクっとするんですが、実際の現場も、本当にその場に居たくなくなるような空気があって。だから、僕はその空気をそのまま感じて表現しました。心情の変化を「こう表そう」とプランを立てて演じたわけではなく、そこにあるものをリアルに感じていたというわけです。
― 心身ともにリアルな反応が呼び起こされるのが「深田ワールド」だと。
森崎 : 深田監督の現場にいると、ふと「明日何が起きるかわからないしな…」とか、思ってしまうんですよ。そんな僕や撮影現場を、深田監督は俯瞰で見てるのかな…とも思ったり…。謎が多すぎます!…でも、面白いんですよ…本当に。

― 「深田マジック」とも言えますね。深田監督の作品づくりは、謎が多くて、面白いということですが、ご自身はそれを聞いていかがですか?
深田 : 僕を信じて撮影に臨んでくれたというのは、とても嬉しいし、ありがたいことです。僕も、「この役はあなたにお任せします」という思いがあってお願いしているので、キャスティングの段階から信用しています。キャスティングは僕からお願いしたり、オーディションで決めたりと、自分できちんと決定に携われていることもあり、監督として俳優の演出の6、7割はそこで成し遂げられていると言ってもいいと思いますね。
― 反応が起こるように、調合するのがキャスティングということでしょうか?
深田 : うまく化学反応を起こすよう、集めていくという感じです。これは監督によって違うと思うんですが、僕の場合、俳優が役に無理矢理合わせるのではなく、その人自身と役柄が混ざり合ってキャラクターが出来上がっていけばいいなという思いがあります。
― 以前、深田監督の前作『よこがお』(2019) に出演した市川実日子さんにインタビューした際も、「(深田監督は)私のリズムに委ねてくださっている感じがありました」とおっしゃっていました。森崎さんは「深田ワールド」と表していましたが、市川さんは「(撮影現場で)“映画の粒子”というか“空気の粒”のようなものを感じた」とおっしゃっていましたね。

深田 : 俳優によって、それぞれの時間やリズム、例えば撮影に向けて気持ちを高めていくための時間、それを僕は「アイドリング状態」と呼んでいるのですが、それが違います。役を演じている時間だけでなく、そこも含めた時間を抱える存在として、それぞれへ依頼しているんです。
― その人が役に向き合う時間含めて、その役者のことを捉えていると。
深田 : 自分が俳優をコントロールするのではなく、まず俳優から自然と出てくるものを見たい。例えば、流れていく水や木から落ちていく葉っぱの動きは、予測できないからこそカメラに映した際、魅力的に映る部分があると思います。俳優も実は、本質的にそれと変わらないと思っていて。「カメラの前で起きる豊かな偶然」であってほしい。

深田 : 「監督にもコントロールし得ない何かである俳優」「それぞれの人生や生活を背負っている一人の人間としての俳優」と一緒に作品をつくる方が、絶対その作品は豊かになる。そう思っています。魅力的な偶然を引き起こしてくれると感じた俳優に、役をお願いしているとも言えますね。
― 市川さんは、深田監督の撮影現場で「本来の自分のリズムでいることができた」とおっしゃっていましたが、森崎さんは撮影を通して何か変化はありましたか?
森崎 : もちろん変化は確実にあったと思うんですが…でも確かにあったからこそ、時間をかけて僕の中で熟成させたいと思ってるんです。それは何年か後、自然と表に出てくるのではないかと。だから、今すぐに言葉で説明できるようなものではないですね。そういうことを理解できるようになったことが、1番の変化かもしれないです。

思えば、人生は“思いがけない”ことの連続だ
― 自分や他人の感情であれ行動であれ、「コントロールできない」ことを肯定するというのは、頭ではわかっていても、なかなか難しいことであると思います。深田監督は、どのようにその考えを培っていったのですか?
深田 : これは色んなところで公言していることなんですが、僕の好きな監督にフランスのエリック・ロメールという人がいまして。彼の作品はどれをとっても見事に「エリック・ロメールの世界」になっているんだけれど、そこには偶然が満ち満ちているんです。例えば、『友だちの恋人』(1987)では、主演のエマニュエル・ショーレとロメールが2年の間、定期的に会ってただ雑談をするというのを重ねたそうなんですね。で、できた脚本をエマニュエルが見てみると、自分が何気なく話したことがセリフなっていたと。
森崎 : ほー。なるほど。

深田 : 例えば俳優が自分の芸術に対する考えを語るようなセリフがあって、それはその俳優本人がロメールに話していた内容だったりして。ロメールにとってそれは、自分の考えとは違ったそうなんですが、「その俳優にとっての真実だから構わないんだ」と、脚本に取り込んでいるんです。そういったことが、ロメールの作品の豊かさを生み出しているのではないかと。
森崎 : 「深田ワールド」はそこからきてるんですね。
― 今作でも、辻と曖昧な関係にあった細川先輩が、辻が浮世と関係することで、自分が「こうありたい」という方向とは真逆の、思わぬ人生を歩んでしまいますが、結果、自身でそれを肯定するというシーンが印象的でした。

森崎 : 考えてみれば、そういった思いがけない事って日々起きてますよね。僕にとって、今所属している事務所にスカウトされたこともそのひとつだと思います。当時は芸能界に入るつもりは全然無かったんですけど、週1回行われるレッスンに母親から「タダだし、行ってみれば?」って言われて、通うようになったんです(笑)。
深田 : 何歳の時?
森崎 : 中学校2年生の14歳の時ですね。
深田 : おー。14の時なんて、人生どう転がるかまだ何にも考えていない頃ですよね。何でもチャレンジできるその時に、たまたま芸能界への道を選んで、そして今があると。自分も、13、14歳ぐらいの時に、映画を意識的に観るようになったんです。父親の集めた映画のVHSが大量にある家で。5、600本ぐらいあったかな。
森崎 : 5、600本もですか!?
深田 : 『悪魔のいけにえ』(1974)とか『悪魔の毒々ハイスクール』(1986)とか、ホラー映画がほとんどでしたが、たまにジャン=リュック・ゴダール監督の作品があったり。当時はお小遣いが少なかったから、映画館に行けるのは年に1、2回だったんで、ひたすら家で朝から晩まで映画を観る毎日を送っていました。
それは、今こうやって映画監督をやってるからもっともらしく話せるエピソードのように見えますけど、当時は成績がどんどん落ちていくし、家族には白い目で見られるしで。
― 自身にも家族にも深刻な話だったんですね。

深田 : 私立大学附属の中高一貫校に通っていたので、そのまま行けばエスカレーター式に大学にあげてもらえるはずが、成績が悪すぎて乗車拒否されたんです。「映画をたくさん観ていたから」という言い訳で説明していますが、そうでなくても落ちていたかもしれません(笑)。
― その頃から、映画監督を目指されていたんですか?
深田 : 自分が映画をつくるなんて全く思っていませんでした。人付き合いも得意じゃなかったから、集団で創作する映画をつくろうという選択肢はなくて。絵を描きたいとか小説を書きたいとかは思っていました。でも、それもだんだん才能がないことがわかってきて、本当に暗い高校生活を送っていたんです。そこは結構、どん底だったかも。
でも、その中で唯一自分にあった「映画を観る」ということが、大学時代、たまたま映画館で見かけた映画学校(映画美学校)のチラシから、「映画をつくる」ということにつながって、それが今に続いているという…。

― お二人とも、14歳当時の自分では予期できなかった場所に今いるということですね。確かに、人生はそういうことの連続なのかもしれません…。
深田 : …この流れは、最後の質問ってことじゃないですか? 最後の質問ってことでしょう(ニヤリ)。
森崎 : (深田監督を見て)…好きだなー!こういうエンタテイナーな深田さんが、僕は大好きなんです!!
― ど、どういうことでしょう…?
森崎 : インタビューの冒頭もそうでしたが、深田監督は場を盛り上げるエンタテイナーじゃないですか!? 撮影現場でもすごくエンタテイナーで!

深田 : 撮影現場でも、でしたか!?(笑)
森崎 : 正直ご一緒するまで、作品の印象もあって「気難しい人なんじゃないかな」と勝手に思っていたんです。実際は、すごくおもしろい方で、周りを楽しませるエンタテイナーの面があり、それは僕が『レディ・プレイヤー1』(2018)で感じたスティーヴン・スピルバーグ監督の印象と同じなんです!
― 森崎さんは、大ヒット小説『ゲームウォーズ』を実写映画化したスピルバーグ監督の『レディ・プレイヤー1』に、主人公のウェイド・ワッツらと“トップ5”のメンバーとして出演しハリウッドデビューされました。
森崎 : スピルバーグ監督も、舞台挨拶などの時は「It’s Showtime!」ではないですが、エンタテイナーとして周りを楽しませる。深田監督も、ご自身で周りを楽しませることもしっかり考えていらっしゃる。その幅の広さというか、多面性がすごいなと尊敬しています。
深田 : いやいや、カッコつけられないだけで、笑わせてなんぼ…という(笑)。

森崎ウィンと深田晃司監督の「心の一本の映画」
― では、深田監督の予測どおり、最後の質問として「心の一本の映画」を伺ってもよろしいでしょうか?
森崎 : 僕は『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』(2014)です。緊急事態宣言が出されたステイホーム期間中に観た作品なんですが、初めて映画をつくりたいって思いました。
深田 : おお! 監督をするっていうこと?
森崎 : 監督です! そしてちょっと出演もしたいです(笑)。
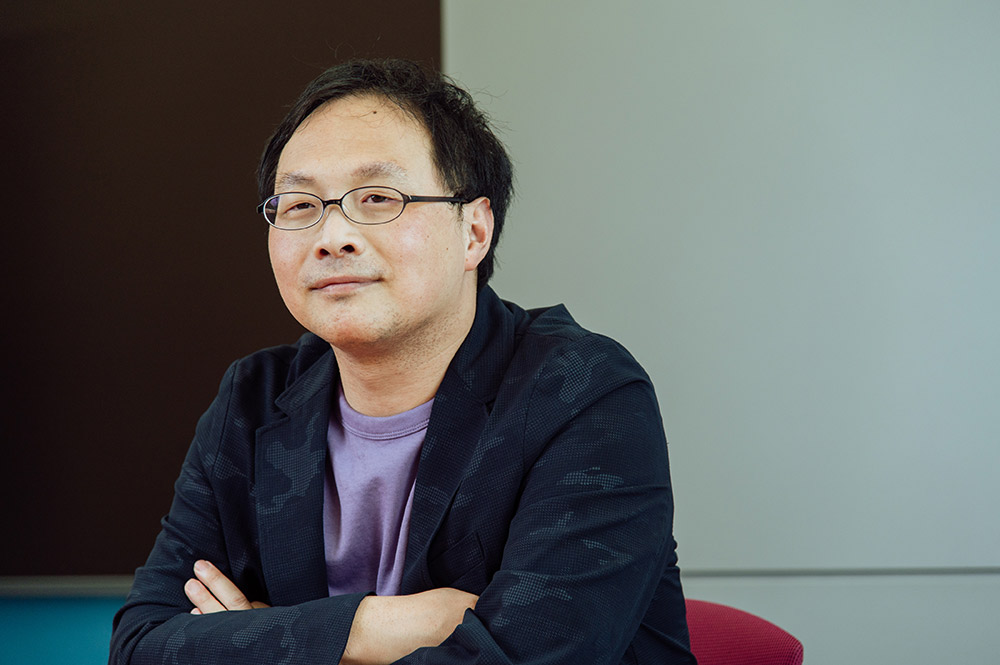
― 『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』は、『アイアンマン』(2008)、『アイアンマン2』(2010)の監督を務めたジョン・ファヴローが監督・脚本・製作、そして主演を務めたコメディドラマです。今まで自身が映画監督として経験してきた事を、劇中のシェフという役柄に投影させた作品と言われていますね。
森崎 : 自分の経験してきた、良いことも悪いことも含めた人生の記録を、表現として、しかもエンタテインメントとして多くの人に伝えられるって、なんて素敵なんだろうと。それを実現できる環境に僕もいきたい、っていう憧れが生まれた瞬間だったんです。そういう視点で映画を観たのは初めてでした。だから僕もいずれ、40、50歳とか、40じゃまだ早いか。50代後半とか…。
深田 : いやいや、いいんじゃないの?
森崎 : その時は絶対深田監督に…。
深田 : エキストラで出演させてもらおうかな。
森崎 : いや、まずは「監督とは」を勉強させてください。「助監督やらせてください!」ってお願いしに行きます。
深田 : 『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』観てみますね。僕が影響を受けた映画は、沢山あるんですけど…今回1本挙げるとしたら、ロバート・アルトマン監督の『ロング・グッドバイ』(1973)です。ロバート・アルトマン監督の作品が好きだっていうのもあるんですけど、その中でも特に好きな1本で、今作をつくるにあたって意識した作品です。撮影に入る前、撮影監督や森崎さんなどとみんなで観ました。
― 『ロング・グッドバイ』は、アメリカの小説家 レイモンド・チャンドラーの代表作を映画化した作品ですね。主人公・私立探偵フィリップ・マーロウをエリオット・グールドが演じています。

深田 : どうやったらこんなカット割りを思いつくんだ! というカットの連続で、最初はその撮り方を取り入れたいと思って観直したんです。そしたら、主人公の私立探偵フィリップ・マーロウの姿が、今作の主人公・辻と重なる部分があって。
マーロウは、依頼者の女性の願いを叶えるために奔走するんですけど、どんどん色んな事件に巻き込まれていくんです。女性の依頼のためにヤクザの事務所に乗り込むシーンは、辻が同じ行動をとる場面の参考にしましたね。辻が飼っているザリガニの名前を、“フィリップ・マーロウ”から取って「マーロウ」にしたんですよ。この作品を初めて観たのは、高校か大学ぐらいの時だったんじゃないかな。
― まさか「自分で映画をつくる」と思っていなかった頃に、深田監督が観た作品のひとつということですね。
深田 : 60、70年代の海外の作品や、日本だったら小津安二郎監督や溝口健二監督、成瀬巳喜男監督の作品ばっかり観ていた頃に出会った作品です。石井聰亙監督や塚本晋也監督などの、いわゆるインディペンデントな作品を観ていたら、自分でも映画をつくろうって思ったかもしれないんですけど、古典作品ばっかり観ていたので、ますます自分がつくる方にまわれるとは思わなかったんですよね。
中学生・高校生の時には年間で150本ぐらい観て、全部メモして感想書いて。当時の自分にとっては、それが自信というか自意識の塊だったんです。大学に入ってからはさらに増えましたし。でも、沢山観てるからって、いい映画を撮れるわけじゃないってことを映画学校で学んで、一度挫折を味わってはいるのですが、でもやはり、今まで自分が観てきた映画から、映画を一番学んでいる気がしています。演技や音楽なども含めて表現をすることって、どこかで学ぶというよりは、日々の中で自然と学んでいたっていう方が大きいと思うんです。
森崎 : そうですね。音楽とか特にそうですけど、小さい時に何気なく聞いていた曲が、自分の表現のルーツになっていることもあるので。芝居も多分そうだと思うんですよね。…監督と話すのは本当に面白いな…。いいなー、いい時間だったなー…。