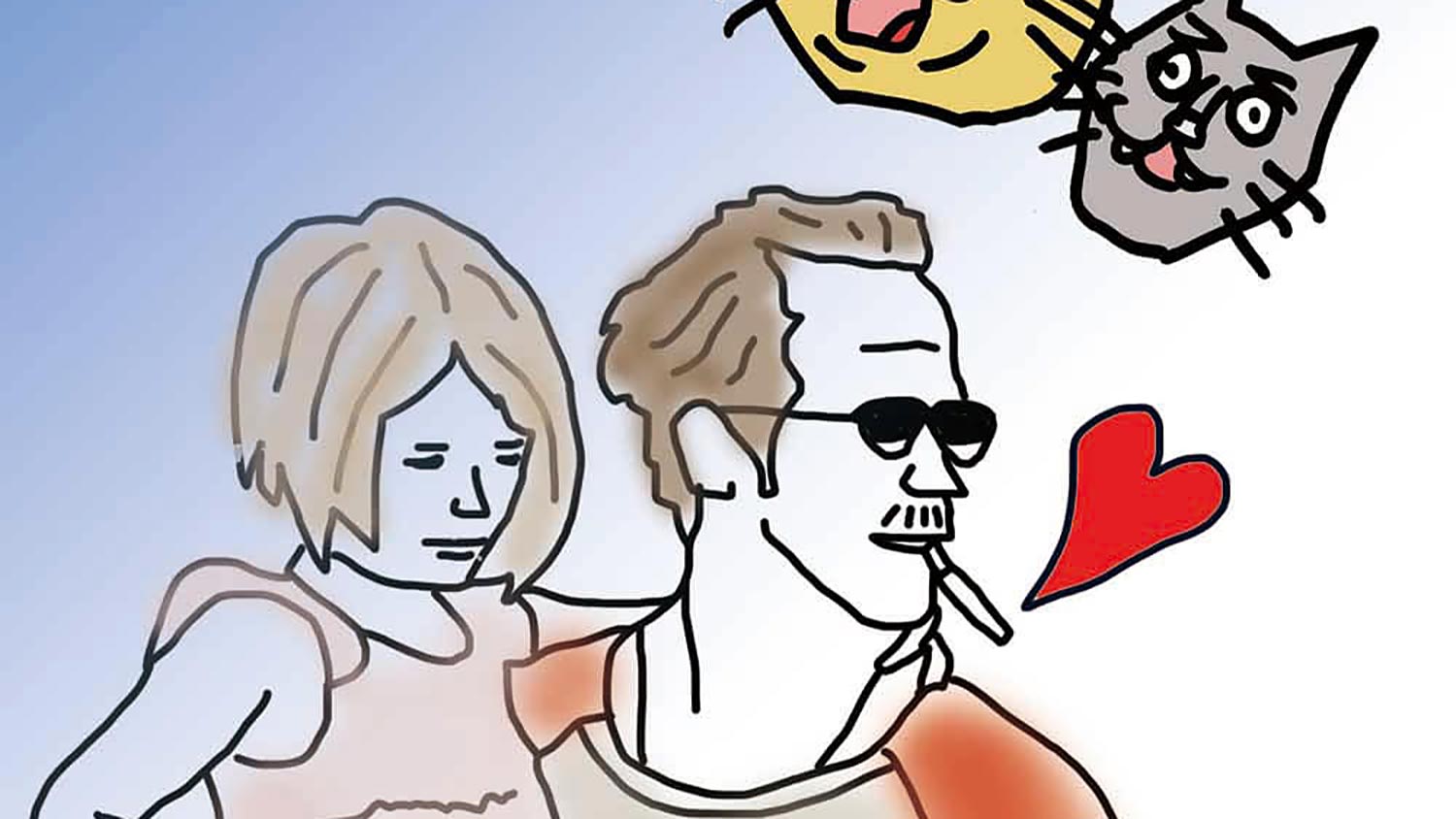目次

一番共感できるのは、
ややこしい大人の感情
― 配信ドラマとして異例の大ヒットを記録した「ポルノグラファー」は、主人公2人の心理描写が繊細に描かれ、“大人の恋愛作品”として大反響を呼びました。その最終章となる本作も、木島と春彦という大人2人の恋愛が描かれるわけですが、木島は「こじらせ官能小説家」という紹介どおり、「誰かと関係性を築くことにむいていない」と春彦と向き合うことに臆病です。竹財さんご自身は、そんな木島に共感するところはありましたか?
竹財 : 木島先生にですか? 全くですね!
― 全くですか(笑)。木島は作中、「僕なんか」「僕みたいな」と自分を卑下する言葉を口にすることも多く、その自信の無さから、大切に思っているはずの春彦を傷つけてしまいます。
竹財 : 「自分の気持ちは素直に言っちゃえばいいのに」「言うの遅いよ」と思っていました、これ言っちゃうと元も子もないですけど。

― 2人が仲違いしたあとに書いた手紙も、せっかく素直な気持ちを綴っていたのに、破り捨ててしまうシーンがありましたね。
竹財 : パートナーを大切にするには、お互いの歩み寄りが必要だと僕は思います。でも木島と春彦の関係性は、春彦のほうからグイグイきてくれて、木島はそれにかまけて甘えているというもので。そのバランスがドラマでは3対7ぐらいだったんですけど、映画ではさらに甘えて1対9ぐらいになってしまったので、一旦壊れたのかなと思いますね。
― 物語の中盤、2人はあることをきっかけにすれ違い、春彦は木島の元から離れてしまいます。春彦を追いかけることができない木島に、居候先のスナックのママである春子(松本若菜)がかけた「タフになるの、大切な人がいるなら」という言葉がとても印象的でした。
竹財 : 木島が変わることができたのは、やっぱり周りの人に助けられたり、春子に背中を押してもらったりしたことが大きいですよね。自分の気持ちを言う勇気を、みんなからもらったんだと思います。
― 木島と対照的に春彦は、相手への思いを常に言葉や態度で示しています。感情の表現の仕方もストレートで、2人の大切な思い出だと信じていた「口述筆記」を木島が静雄(奥野壮)に手伝わせていたシーンでは、それに対する悲しみや怒りの感情を爆発させます。猪塚さんは、木島にまっすぐ向かっていく春彦の姿に、ご自身と重ねられるところはありますか。

猪塚 : 僕自身と重ねると…全然一緒ではないですね。あそこまでまっすぐな愛を相手に向けられるのって、僕にとってはある意味うらやましいというか。僕は「人を大切にするために必要なもの」っていうのは、「見返りを求めないこと」だと思っていて。自分がなにかをするときに相手に期待をしてしまうと、うまくいかなくなってしまうと思うんです。
― 恋愛の関係だと、より求めてしまいがちですよね。
猪塚 : そうですよね。僕は、心に余裕があるときは、それがうまくできるんですけど、余裕が無くなってくるとすぐに見返りを求め始めてしまうんです。でも春彦は、どんなときも自分の気持ちに正直で、真っすぐに気持ちを伝えていますよね。「好き好き」って。あの真っすぐな気持ちっていうのは僕にないので、うらやましいなと思いますね。
― 三木監督は、木島と春彦のコミュニケーションの取り方について、どう感じられますか?
三木 : 僕、基本的に木島の考え方はすごくよくわかるんですよね(笑)。

竹財 : わかりますよね(笑)。
三木 : 僕は高校生が主人公の映画も何本かやっているんですけど、高校生がやったらこれ、「好き」「嫌い」って言って、話5分で終わるんですよ(笑)。
― 三木監督は『弱虫ペダル』(2020)や『覆面系ノイズ』(2017)など、高校生が主人公の作品も多く手掛けていらっしゃいます。
三木 : でもこの映画は、“大人の醜い話”だと思っていて。大人の余計な考えというか。
― “大人の余計で醜いところ”ですか。
三木 : 誰にでも、それまで生きてきたなかで身に着けてきた「余計な部分」みたいなものがあって、「物語」ってそこを描き出すとややこしくなって辛いだけなんですけど、今作では多分それを描いているんですよね。

― 木島は自分に自信がないから、2人の将来に対して不安をこぼし、それをフォローする春彦の言葉も信じることができない。相手の気持ちよりも「ダメな自分」を信じてしまう姿が映し出されていました。
三木 : でもその“大人のややこしさ”って、生きていくうえですごく大事な部分だったりするじゃないですか。過去の生きてきた自分をいまさら曲げることができない。そういう大人のろくでもない感情を、じゃあどうやって変えていくのか。どういう人との関わり合いでそれがプラスになったりマイナスになったりするのか。この映画ではそういうものを描いていて。
― たしかに今作は、木島と春彦の恋愛を描いていますが、それは同時に木島が自分を知っていく過程でもあるということも描かれています。
三木 : だから今回の2人の関係には、まるきり答えがないですね(笑)。

― 弱い、醜い自分を知る…。それが、大人の恋愛の醍醐味、みたいなものなのでしょうか。
三木 : “年を重ねることで身に着けるややこしさ”って、そこが実は本人にとって大事なところでもあって。若いうちは「好き」「嫌い」で終わってしまうところが、そうじゃない。じゃあそれってダメなのかって言われたら、そうではなくて。そういうものがあるから次に進めたりする。たぶん2人の関係は、大人でややこしいが故に、今後もダメなまま続いていくんでしょうね。
― 嫉妬を隠すために「どこで、誰と何をしていてもいい」なんてセリフを相手に吐いてしまうような、こじらせてしまっている木島も、あれはあれで良いんだと。
三木 : まあ、でも気持ちがわかるというか…ああなりますよね。僕も結構なるから。
竹財 : 監督も意外とこじらせてる(笑)。

三木 : 意外とね(笑)。だって相手のこと好きになっちゃったら、思わない?「俺のこと一番好きでいろよ!」って。それで、思ってもないこと言っちゃったりするでしょ? でもそういう人の姿って一番共感できる。
― そうやって過去の経験から、こじらせて身動きがとれなくなってしまう大人が、大切な人と向き合っていくために、何を大事にしていますか。
三木 : なんでしょうね。チューすることかな(笑)。
猪塚 : めちゃくちゃシンプル(笑)。
三木 : 自分の考えとか、よくわかんなくなってきちゃうじゃん。
― 「伝える」というのは、言葉だけではないっていうことですかね。
三木 : そうですね。喋っても伝わらないとき、たくさんありますから。
竹財 : スキンシップは本当に大事ですよね。

竹財輝之助、猪塚健太、三木康一郎の
「心の一本」の映画
― 劇中、「寂しさのない人生なんてあるのかい」という印象的なセリフがありますが、みなさんの寂しいときや心細いときに寄り添ってくれた映画について教えていただけますか。
三木 : 難しいなぁ。寂しいときだらけだからなぁ(笑)。
竹財 : えー!?(笑)。
猪塚 : 「心の一本」ってことですよね。僕は『マイ・フレンド・フォーエバー』(1995)を観ると本当に人恋しくなるし、「人として優しくあろう」って思います。
― 『マイ・フレンド・フォーエバー』は2人の少年の友情を描いた物語です。当時、VHS化にあたっては主人公2人の吹き替え声優を滝沢秀明さんと今井翼さんが務めたことでも話題になりました。この作品の、どういうところにそう思われるのですか。

猪塚 : HIVに感染しているデクスターと孤独なエリックという2人の少年が仲良くなって、2人はデクスターの治療薬を探す旅に出るんです。もちろん、薬はみつからない。そんななかある晩、泣きながら眠るデクスターに、エリックは寂しさが紛れるようにと自分の靴を抱かせるんです。物語の最後にデクスターは亡くなってしまうんですけど、エリックはそこで、棺の中で眠るデクスターに自分の汚いスニーカーを抱かせるんですよ。
― 大好きなデクスターが亡くなったあとも、寂しくないようにと考えたんですね。
猪塚 : 彼らの精一杯の優しさに本当にグッときて…。人に優しくするってこういうことなんだって思います。そういう気持ちを教えてくれる映画ですね。
竹財 : 僕は悲しいときには映画を観ないんですけど、観るとしたら『ハングオーバー!』とかですかね(笑)。
― 『ハングオーバー! 消えた花ムコと史上最悪の二日酔い』(2009)は、独身最後のパーティーに参加した男たちのぶっ飛んだ2日間を描いたコメディ映画ですね。3作公開されたシリーズはいずれも大ヒットを記録しました。監督のトッド・フィッリップスは、日本でも2019年に公開され話題となった、ホアキン・フェニックス主演の『ジョーカー』の監督・脚本も務めています。
竹財 : 単純に何も考えずに観ていて楽しいし、大人になってもあんな風に悪ふざけできたらいいなと思います(笑)。

― 楽しい気持ちになりますよね。
竹財 : そうですね。悲しいものを観てさらに同化するよりは、何も考えずに観られる面白い、バカになれる映画とかがいいかな。
三木 : 僕は最近観たなかでいうと『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』(2020)かな(笑)。初日に2回観て…。
一同 : (笑)。
猪塚 : めちゃくちゃ行ってる(笑)。
三木 : とにかく『鬼滅の刃』にハマっちゃって(笑)。知ってます?

― はい(笑)。週刊少年ジャンプで連載されていた漫画作品で、2019年にアニメ化されるとすぐに話題となり、昨年10月に公開された映画は歴代興行収入ランキング1位となりました。
三木 : 炭治郎くんっていう主人公がめちゃくちゃ強くて、もうダメだと思うようなときにも頑張るんですよ。高い壁も超えていくの。そんな姿を見ると、50歳を過ぎたおじさんも「この子も頑張っているんだから、それくらい(辛いことも)乗り越えなくちゃな」って思うんですよ。
― 劇場で泣く人も多いって聞きますけど、三木監督はいかがでしたか。
三木 : 後半はちょっとヤバかったですね。どれだけ強い敵が出てきても頑張る、あの姿勢にね。「負けちゃだめだ!」って気持ちになりましたね。