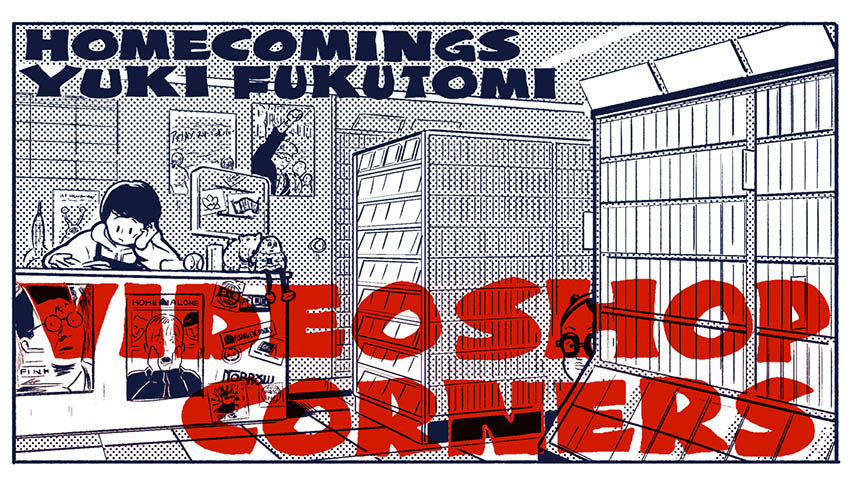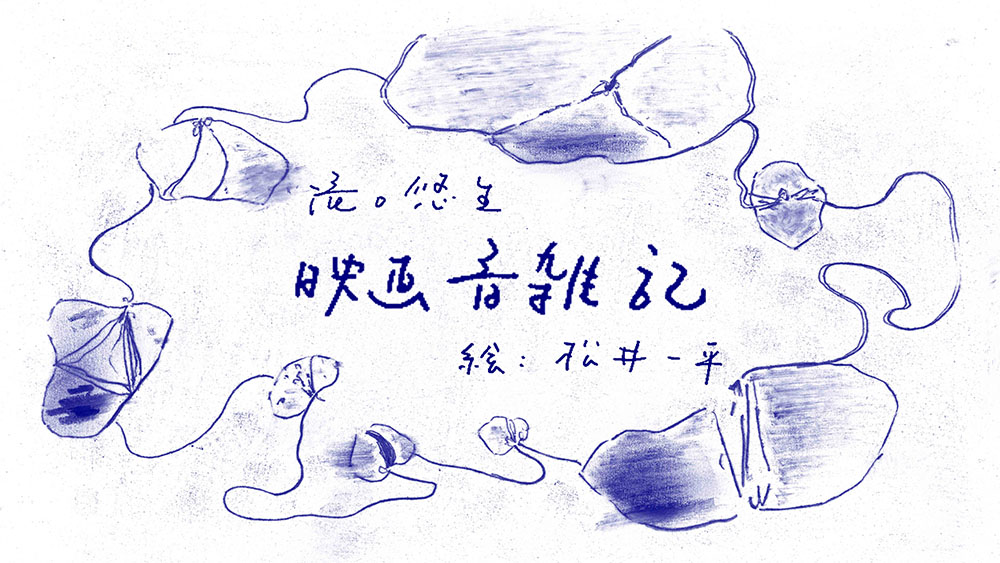
仕事は何か、と訊かれて、フィリップは、”Sound.” と応える。”Make sound.”
彼は録音技師である。ヘッドフォンをしたフィリップは、旗を掲げるみたいに、長いマイクを宙に差し出しながら街を歩く。マイクは鳥の羽音を、バスの走行音を、人の声を、街のすべての音を拾う。
私はかつて、録音技師みたいな生活をしていた。映画制作にかかわっていたわけではないし、なにか特別な技能があるわけでもない。ただ毎日テープレコーダーを持ち歩き、街なかや、駅や、店で、やたらめったら録音していた。そんな時期は五年ほども続いたろうか。
暇だったと言えばそれまでなのだが、ちゃんと小説を書きはじめたのもその頃だったし、私のなかではそれも小説を書くのと同じようなことだったのかもしれない。そうやって書き上げた「楽器」という題名の作品で私は小説家になった。
ほうぼうで鳴って無作為に混ざりあう環境音が、どんな音楽よりもおもしろく、刺激的に思えた。大げさでなく、その頃はただそのへんで鳴っている音が、もっとも豊かに世界を表象するもののように感じられたのだ。テープレコーダーでの録音は、それを確認するための作業のようなもので、実際には録音したテープを聞き返すことはあまりなかった。
『リスボン物語』を観たのもその頃だった。これは、音の映画だ。だから、自分の映画だ、と思った。フィリップが使っているようなあの、先っちょがふさふさで、長い柄のついたマイクが欲しいと思った。けれど、どこにも売っていなかった。
どこか遠くで犬が吠える。その声はここまで届かない。しかしその時その犬が吠えなければ、きっといまここで鳴っている音は、いまここで聞こえるのとはちょっと違う響きのはずだ。そう考えれば、宙に差し出したマイクが拾うことになるのは、その時世界で鳴っていたすべての音の記録、ということになる。と、当時私は思っていたし、いまでもやっぱりそう思う。
そしてそういった考えの反動として、私はあまり音楽を聴かなくなった。家で、CDを選んで、ステレオのスイッチを入れて、音楽が流れてくる、ということにこびりつく自分の様々な作為が、どうにもうっとうしくなってしまったのだ。それもまた、いまなおあまり変わっていない。
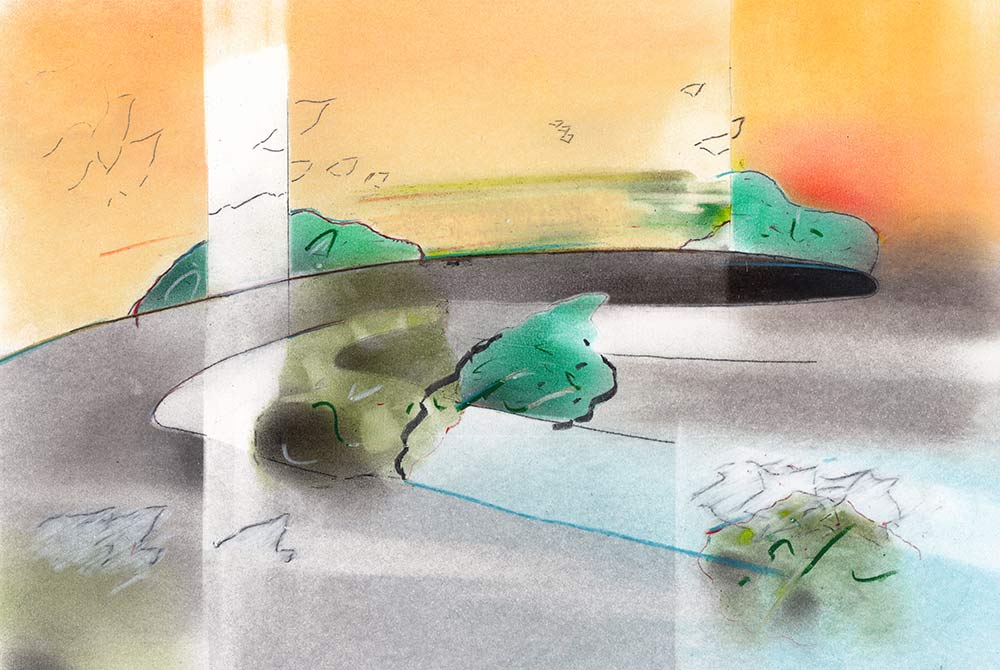
フィリップは友人の映画監督フリードリヒから手紙を受け取って、車に機材と音作りの道具をたくさん詰めて、ドイツからポルトガルの首都リスボンへと向かう。映画はその道中からはじまる。
車を運転しているフィリップの姿はなかなか画面に映らない。車内からフロントガラス越しに捉えたいろんな国の風景が、国境を越えるごとに切り変わっていく。そこにぶつぶつ呟く彼の声と、地域ごとに切り変わるラジオ放送の音が聞こえる。それがこの映画の最初の音だ。フィリップはまだ録音を開始していないが、冒頭部分の最後で、彼は、テスト、テスト、とレコーダーのスイッチを入れ、通り過ぎてきた国々の印象をひとりで語り出す。そして、どの国も”My home country”に思える、と呟き、録音を切る。注意して聞くと、その時に、ふっ、というノイズが聞こえるはずだ。それがこの映画の、最初の音が終わる音。もちろん映画はそのあとも無音になることなく続いていく。
音を録音していると気がつくのは、記録のはじまりが、同時に、記録されなかった音の終わりである、ということだ。そして同様に、記録の終わりは、記録されない音のはじまりである。
テープレコーダーを持ち歩くようになった最初の頃は、周囲の音が、自分の耳で聞くのとは違って記録されることをおもしろいと思っていた。意思の介在しないマイクによって、自分の耳に聞こえていたのとは違ったものとして自分のまわりの音が聞こえるようになる。
けれども私はだんだんと、音の切れ目に興味をもつようになった。録音ボタンが押されて音がはじまる時の、わずかな引き攣れ。そして、停止ボタンが押されて、やはりわずかに歪んで途絶える音と、その直後に生じるあの、ふっ、という小さなノイズ。音が完全に途切れたあとに、おそらく磁気テープとレコーダーの間のなんらかの干渉によって生じる、何の音でもない、幽霊のような音。

終わりのそのあとに一瞬鳴る音に私はとても惹かれた。これはもちろんデジタルのレコーダーには起こらない。はじまりと終わりに現れるわずかな、けれどもたしかな、物理的な歪みと、何かの痕跡。音と音楽の境目。音楽でなかった音が音楽になる瞬間、あるいは音楽が音楽でなくなる瞬間の音。
録音技師が主人公というだけで、『リスボン物語』はじゅうぶん、私の映画だ、と思わせるに足るものだったけれど、はじまって早々にこの、ふっ、というノイズが聞こえたことで、その思いはいっそう強く、確信に変わるのだ。