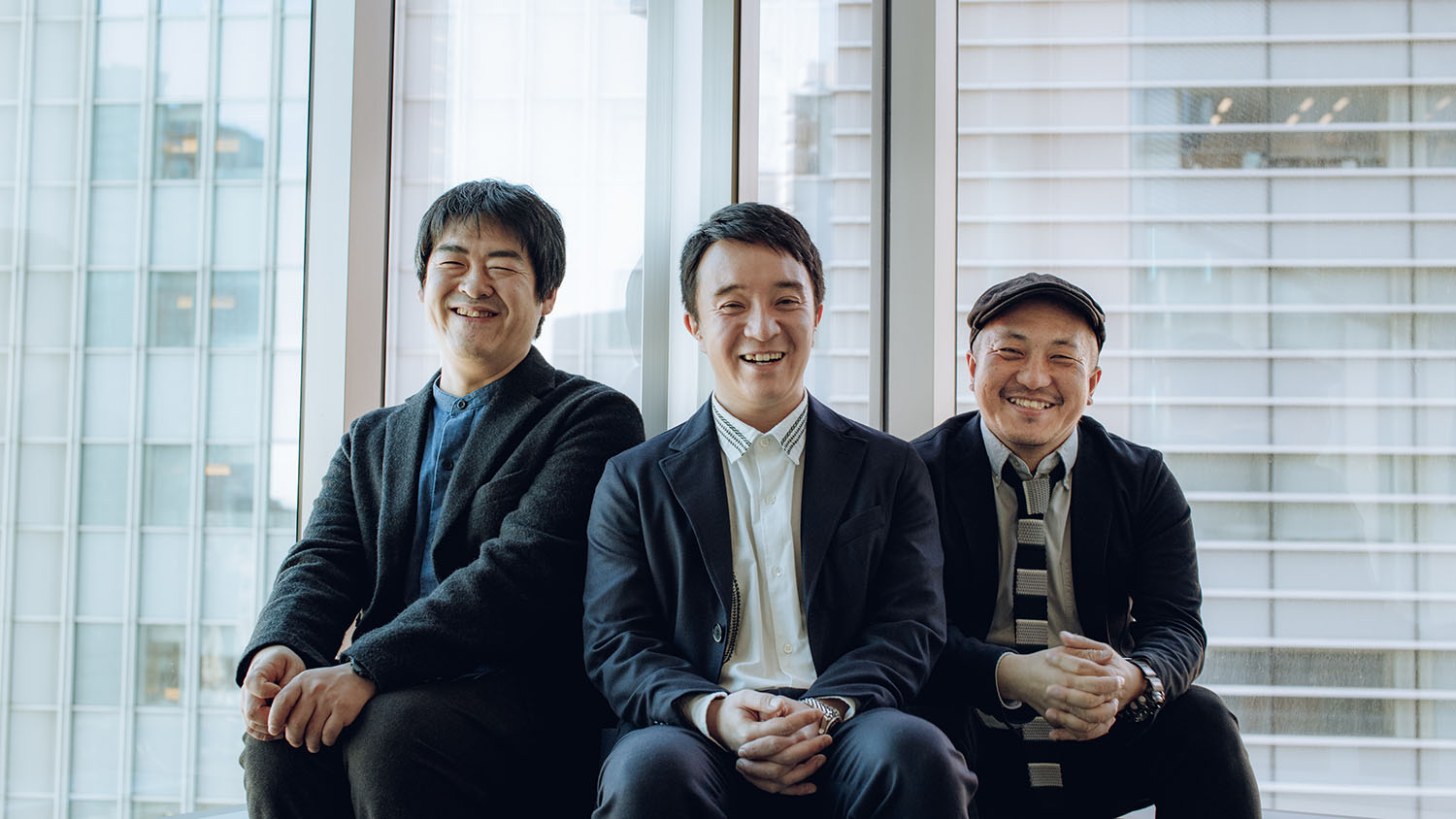目次
人は人を救えないのかもしれない。
それでもその先に続く道を、光で照らしたい。
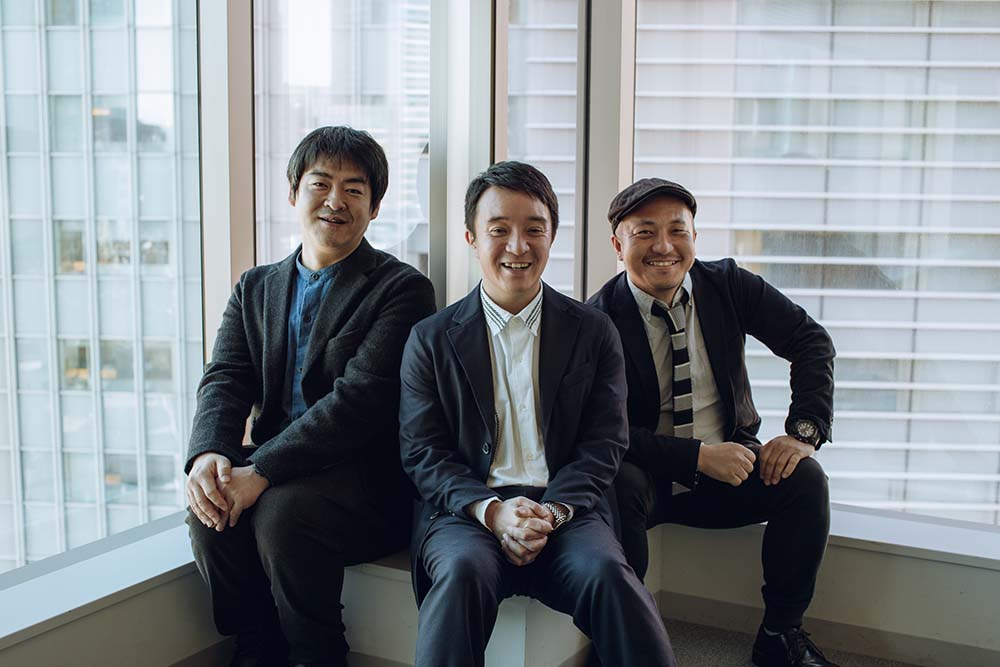
悲劇と喜劇は、表裏一体
― 白石監督と沖田監督。一見まったく違う作風の映画をつくられているお二人が、今回、連続ドラマ『フルーツ宅配便』を撮られると伺いました。このドラマに沖田監督を誘ったのは、白石監督だそうですね。
白石 : 僕、沖田監督のファンなんです(笑)。僕は、沖田監督がつくる作品は“懐が広い”と思っているんですね。その“懐の広さ”が、このドラマには合うと思ったのでお誘いさせて頂きました。もちろん僕が沖田監督を好きなのは、大前提として「作家として尊敬している」というのが根源にあるからです。
あと、主演の濱田さんは、沖田監督と絶対相性がいいに決まっていると感じて。むしろ、なんで今まで一緒にやっていなかったのか不思議に思うぐらい(笑)
(濱田さんと沖田監督が照れて、同じタイミングで水を口に運ぶ)
沖田 : そして同時に水を飲むという…。
白石 : 水がこぼれてる!こぼれてる!(笑)

― (笑)。沖田監督と濱田さんは「相性がいい」と言うことですが、お二人は「人生に起こる“悲喜こもごも”の面白さ」を、日常の中に表現し続けていらっしゃいますよね。『フルーツ宅配便』原作者の鈴木良雄さんは、濱田さんについて「シリアスもコミカルも自然に演じられる数少ない俳優さんであると思います。」とおっしゃっています。
白石 : 悲劇と喜劇って表裏一体なところがあるじゃないですか。沖田監督も俳優としての濱田さんもギャグで笑わせているわけではなく、「一生懸命だからこそ笑えてくる、滑稽に見える」ということを表現されていますよね。わかりにくいけれど、僕も実はそう。
― そうなんですね。白石監督の作品は暴力を扱うシーンが多いため、「普通の日常」を描いた沖田監督の作品とは一見対極にあるように感じてしまいます。

白石 : 僕は恐怖の中にある“滑稽さ”をいかにして表現するか、を考えながら作品をつくっています。「恐怖」は、笑えるラインで止まることもあるし、それが転じて「恐怖」に行き着くこともある。
濱田さんと沖田監督のお二人と、僕の作風は見え方が全く違うように感じるかもしれないけれど、人間を見つめる眼差しは三人ともそんなに違わないのかなと思っているんです。
沖田 : (白石監督と目が合い)……僕もそう思いますよ(笑)。
濱田 : 無理矢理…?(笑)
沖田 : いやいや、白石監督はただの凶悪な監督ではないなって思ってます(笑)。
一同 : (笑)

― 濱田さんから見て、現場でのお二人は、どうでしたか?
濱田 : 二人とも、現場ですごく楽しそうなんですよ。モニター見ながら、異常に楽しそうにしている(笑)。現場にいる人全員が、「本当に撮影が好きなんだなー」って感じていると思う。
白石 : 僕が一生懸命撮影した後に、沖田監督の演出をコーヒーを飲みながら見ることができるのは至福でしたね。
沖田 : 撮影中、振り返ると白石監督が僕を見てるんですよ。で、写真撮ってる(笑)。今回、僕は現場でゲラゲラ笑いながら撮影していたんですが、白石監督も同じでした。僕だけじゃないんだなと(笑)。

名もなき人の人生を
愛して、描きたい
― 沖田監督は、「No暴力、Noセックス」で今まで作品をつくられていますよね。今回の作品には、直接的な性表現はないにしろ、舞台がデリバリー・ヘルスということや、夫にDVを受けた女性なども登場しますが、どのように作品に向き合われたんでしょうか?
沖田 : 登場人物がやはり、どこか滑稽なんです。作品には、老齢にして「フルーツ宅配便」にハマってしまう人や、人とのコミュニケーションがうまくとれず「フルーツ宅配便」で働く女性などが登場するのですが、彼らの日常を描くと“生きることに一生懸命”だからこそ、笑える部分が出てくるんですね。
― 先ほど、白石監督も「悲劇と喜劇は表裏一体」とおっしゃっていましたね。
沖田 : なんだか笑える、だからこそ、より悲しく感じるということがあると思います。「性的なことを描く」ということでいえば新しい挑戦なんだけれど、「一生懸命に生きている人」を細かく見つめて、面白がったり悲しがったりするというのは変わらないのかなと。この作品は、生きていくのに不器用な人たちを、色んな角度から切り取った作品だと思います。そして、僕もその一人だと思っている…。

沖田 : でも、みんな、どっかに何かしら足りない部分を持っていて、それがそれぞれに違う形で表出しているだけだと思うんです。
― 「一生懸命に生きる人たちを見つめる」という点では変わらないと。
沖田 : 「面白がったり悲しがったり」というのは、決してバカにしているわけではありません。その人を好きになるということなんです。例えば、登場人物は架空の人ですが、「この人は、こういうときに、こういうことをしているんじゃないか」とか、現場にいる人たちでよく話します。そうやって、その登場人物に「生」を吹き込んでいくのです。
濱田 : 僕も、沖田監督や白石監督と同じで、だんだん登場人物を好きになって、応援する気持ちになりましたね。俳優仲間で集まると、どうしても「次はどんな役を演じるの?」という話になるんですよ。今回僕は「フルーツ宅配便」で働く店長を演じるので、「岳は?」って聞かれたら「デリヘルの店長役」って答えるんです。そしたら、みんな「あっ…ああ〜…」みたいな反応で(笑)。そういうとき、「くそ〜見とけよ、うちの店で働いている人はみんなすごいからな!」って。
― 役とシンクロした気持ちになっているんですね(笑)。
濱田 : 自然と僕が演じた咲田という役とシンクロしていましたね。濱田岳としても「俺が背負うから、みんな好きにやれ!」という気持ちが出てきて(笑)。
一同 : (笑)
― 濱田さんはドラマ出演にあたって、「生きていくということ」がこの作品の大事なテーマのひとつとおっしゃっていました。

濱田 : ドラマに登場する女性たちは、みんな一生懸命生きていますよね。ただただ一生懸命にいきている。…振り返れば、他のいろんな選択肢が人生にあったかもしれないけれど…。正直言うと最初は、「フルーツ宅配便」で働く女性の人生に降りかかった辛い話を聞く度に、どう受け止めて表現していいのかわからなかったんです。
― 彼女たちの人生に対しての向き合い方が、つかめなかったんですね。
濱田 : そういう時に、立川談志師匠の「落語とは、人間の業の肯定である」という言葉を思い出したんです。僕たちが今表現しているのも、日本人が古から表現してきた「人間の業」なんだろうなと。落語の面白さも、一生懸命やっている人の滑稽さを笑うというか。与太郎(落語に登場する架空の人物の名称)も一生懸命だから笑える。
だから、僕も「一生懸命やるしかないな」と。そして、もしかしたら「その先がどこかに繋がっているかもしれない」。そういう気持ちで、それぞれの人生や作品を受け止めていましたね。
白石 : 『フルーツ宅配便』には、希望溢れる未来がすぐには訪れないであろう人がたくさん登場します。でも、救いがないわけではない。直接誰かが誰かを救うわけではないんだけれど、「みんなで頑張って生きていこう」という感じは、作品内に必ずありましたね。

― 白石監督は、原作となったマンガ『フルーツ宅配便』を読んだことで、「まだまだ描かなければいけない人生が世の中にはたくさんあると痛感させられた」とおっしゃっていましたが、白石監督にとっての“描かなければいけない人生”とは、どういう人生なのでしょうか?
白石 : このドラマのプロデューサーである濱谷晃一さんは、この原作を「ドラマ化したい」と局に提案したところ、「何考えてるんだよ、できるわけないだろう」と言われたそうなんです。つまり、僕が描きたいのは、そういうことだと思うんです。
― と、言いますと?
白石 : 僕が観たいのは、誰もが「やりたい!」と飛びつく話ではないんです。誰もが「あまり見つめようとしない」ことを、どんな眼差しで見つめられるかなんじゃないかなと。そこにこそ、伝えられることがあると思います。

― 前回のインタビューで白石監督は、「人間って愚かさとは切っても切れない関係で、愚かであればあるほど、どうしようもなく愛しさを感じてしまう」とおっしゃっていました。そして、「愛しさが大きくなるほど映画にしたい」と。
白石 : 僕は“名もなき人たちの話”が好きです。この作品がまさにそうですよね。ドラマに登場する「フルーツ宅配便」で働く女性は、みんな本名ではなく「ゆず」「みかん」といった源氏名でしか作品内で特定されません。それは、逆に言うと、いつ誰しもがその役と同じ状況になってもおかしくないと言う話の羅列でもあるということです。
そして、そういう“名もなき人たちへの応援歌”に作品がなればいいなと、その思いは常にありますね。

一生懸命に生きている。
だからこそ滑稽な“生”
― 今回、濱田さんが演じられる咲田は、東京で勤めていた会社が倒産し、社宅も追い出されて、仕方なく地方都市にある故郷に戻ってきた男性です。濱田さん自身の人生で、咲田のように「今までの普通が突然なくなってしまった」経験ってありますか?
濱田 : 咲田は、失業したことで日常が突然奪われてしまうけれど、僕は俳優なので、言ってみると就職と失業をずっと繰り返しているんですね。だから、それが普通の日常というか、それに慣れてしまっているから、もし何ヶ月もお仕事がなくても焦らないと思うんです。「得るとき」と「失うとき」が、人生の流れの中で波のようにおとずれているというか。
― 失っている期間は、怖さや不安などはありますか?
濱田 : 怖さは当然ありますね。ただ、俳優という仕事は自分の努力だけではどうにもならない部分もあります。監督や演出家、プロデューサーの方の構想に入っていなければ、その現場に入ることはできません。だから、焦っても仕方がない。仕事を与えられた先で、ただ一生懸命やるしかない。それが何かに繋がっていくかもしれないという気持ちで。

濱田 : そういう部分では、この作品に登場する「フルーツ宅配便」で働く女性たちと同じだと思います。
沖田 : 映画監督も、作品をつくっている時と、そうでない時の差が凄くあって。作品に携わっていなきときは、無職だし。でも、気がついたら「監督」って呼ばれていて、現場に立っていて。気がついたら、こうやって取材を受けている。「いつから、こうなったんだろうか…」「なんで今自分の話をしているんだろう」って思うこともあります。
― 確かに、俳優という仕事も、監督という仕事も、“常がない”という側面がありますよね。
沖田 : だから久しぶりに撮影現場に行くと、「監督って、どうやるんだっけ?」って思うことがある。撮り方とか忘れちゃうんですよ(笑)。でも、それはそれでいいのかもしれないとも思っていて。僕は、“続けていることで、だんだん失われていく新鮮さ”みたいなものもあるような気がするから。表現を続けていると、自分でも気づかないうちに、僕から色んなことが剥がれ落ちているんだろうなと感じています。
― 何かを失っている感覚があるということでしょうか。
沖田 : 最近、何が面白いのか、だんだんわからなくなってきて。20代の頃は、僕が中高生の頃に面白いなと感じていたことを踏襲したいと思って、作品をつくっていたんだけれど、その「面白い」が何かわからない(笑)。「俺、どんなことに影響を受けてたんだろう?」って。続けていくことって、そういうことなのかもしれないなと思います。
でも、過去の感覚に戻りたいわけではなくて、変わっちゃえばいいやとも思っています。ずっと同じではいられませんよね。

― 変化する過程で失うものもあるけれど、生まれるものもある。それが、濱田さんのいう「ただ一生懸命に生きていると、その先がどこかに繋がっているかもしれない」ということなのかもしれませんね。
白石 : 映画監督は、ひとつの作品が終わったら、すぐに次の作品に携わることにはならないので、確かに沖田監督のような感覚になるかもしれませんね。
沖田 : 白石監督は間髪入れずにじゃないですか(笑)
白石 : 今、話を聞いていて、「俺撮りすぎだな」って思いました(笑)。でも僕も、今自分が映画を撮れていることは常だと思ってなくて。
僕は助監督として映画界に入ったんですが、もちろん監督を目指していて、そのタイミングをはかっていました。でも、最初に立ち上がった監督の話が、2年ぐらい準備した末に、立ち消えてしまったんです。そのタイミングで子供も生まれたので、この業界で働き続けられないかもしれないと思ったことはありますね。
― そのとき、どうされたんですか?
白石 : 履歴書をとりあえず買ってきて、書きました。で、近所のスーパーの肉の販売員の面接に行きました。
一同 : へー!

白石 : 面接を受けたんですが、「また電話するよ」って言われて。でも、数日立っても連絡がこない。そしたら、ちょうど小さいドラマのお仕事をもらえたんです。人生不思議なもので、その撮影中に知らない電話番号から電話がかかってきて、出たら「白石くん、明日からスーパー来れる?」って(笑)。
一同 : (笑)
白石 : 当日に採用されていたら、今頃どうなっていたかわからないですよね。
濱田 : 残酷に肉をさばいていたのかもしれませんね(笑)
― (笑)。その頃のことを思い出すことはありますか?
白石 : …ふと思い出しますね。今、監督として仕事ができているのも運命…とまでは言いませんが、それぞれのタイミングが少しずれれば、監督という仕事はしてなかったかもしれないわけじゃないですか。同じ頃に助監督としてカチンコ持って現場を走り回っていた人も、今は辞めている人もいる。どちらの人生が成功ということではなくて、僕もタイミングが少しずれていれば、違う人生を歩んでいたかもしれない。

白石 : だから、例えば、映画業界を離れていった人も、どこかで僕が携わった作品のニュースだったり、このドラマだったりを観てくれて、ちょっとでも「頑張ろう」と思ってもらえるようになればいいなと思っているところはあります。
― そういう気持ちが、観ている人の“光”や“応援歌”になれば、という想いに繋がっていると。
白石 : 沖田監督の担当話で、最後光が射して「道が拓けた」みたいに終わるシーンがあるんだけれど、内容的には「なぜ、そこで光が?」というのがあって(笑)。
沖田 : 後ろの方で、咲田が「これで…いいの?」という表情をしているんですよね。
濱田 : そのシーン、どう受け止めていいか、本当によくわからなくて(笑)
沖田 : この作品に携わっていると「何が正しいか」わからなくなる感覚はありますよね。「正しさ」の価値観が揺らぐというか。
白石 : 映画やドラマを観るとき、「楽しみたい」という気持ちはあっても、最初から「何かを得たい」と思って観るわけではない。結果何かをもらうものであって。でも、作り手としては「何かを持ち帰ってもらいたい」、という気持ちは、やはりありますよね。
濱田 : この作品が描く“女性が「生きていく」”という本質的なことを、女性はどう感じるのかなと思います。

濱田岳と白石和彌と沖田修一の「心の一本」の映画
― 最後に、お三方にとって「救いになった映画」「人生の光となった映画」があれば、教えてください。
濱田 : 僕は困ったときは『ブルース・ブラザーズ』(1980)ですね。
→→『ブルース・ブラザース』をU-NEXTで観る【31日間無料】
― どういう時に観ているんですか?
濱田 : はっきりした理由があるわけではないけれど、シュンって気分が落ち込む時ってあるじゃないですか。そういう時、この二人に頼ります。「これでいいのだ!」ではないですが、あの二人を観ると「よし。がんばろ!」って気持ちが切り替わります。
沖田 : 僕は、映画ではなくてドラマなんですが、荒川良々さんから教えて頂いた『さば』(2008)ですね。荒川さんが出演している作品を観たくて、ご本人に聞いたんですよ。それで初めて観たんですが、めちゃくちゃ面白くて。荒川さん主演の映画『全然大丈夫』(2007)も好きで、同じ藤田容介監督の作品です。クランクアップ後に観たんですが、この作品を観たことで、今希望に燃えたぎっているんです(笑)。
一同 : (笑)。
沖田 : きたろうさん演じる老女が、定食屋でさばに醤油とソースを間違えてかけるんです。それを主演の荒川さん演じる青年が自分のものと交換してあげるシーンからドラマは始まります(笑)。話の筋もあってないようなものなんですが、すごく面白くて救われましたね。
白石 : 僕は、このドラマがクランクインする前に観た『ひばり・チエミの弥次喜多道中』(1962)です。京都ヒストリカル映画祭に別の作品のトークゲストとして招かれたんですが、その作品の後に上映された映画がこの作品で。
美空ひばりさんと江利チエミさんが出演している時代劇、なんですが現代語で会話が展開するミュージカルなんですよ。日本最古のガーリームービーですね。二人は芝居小屋の下足番を演じていて、その少女二人が世の中をぶっ壊していく映画です。
― どんなところに救われたんですか?
白石 : 社会で弱い立場である少女が、世の中をぶっ壊していくということを意図的に描いているのがわかるんです。「弱者である少女が世界を壊す」というその構図と、あと、話の筋はあるものの、常にめちゃくちゃなアイデアが優先されているところも。そういう、ものづくりへのパッションだったり、美空ひばりさんと江利チエミさんという“超絶天才アイドル”がミュージカルを歌っている自由な感じだったりに、久々に心洗われたんですよ。
最近は、なかなか映画を観て、心新たにすることってそんなにないんですけど、昔の偉大な先輩からメッセージもらっちゃいましたね。「なんか映画って進化してるのかな、本当に」と思うと同時に「まだまだやれることあるな」って思いました。そういう意味でいうと、今回の作品も女性に焦点をあてた作品なので、色んな意味で自由にできたら良いなと思いながらつくりました。クランクイン前に出会えて、本当によかったですね。
※2021年3月11日時点のVOD配信情報です。