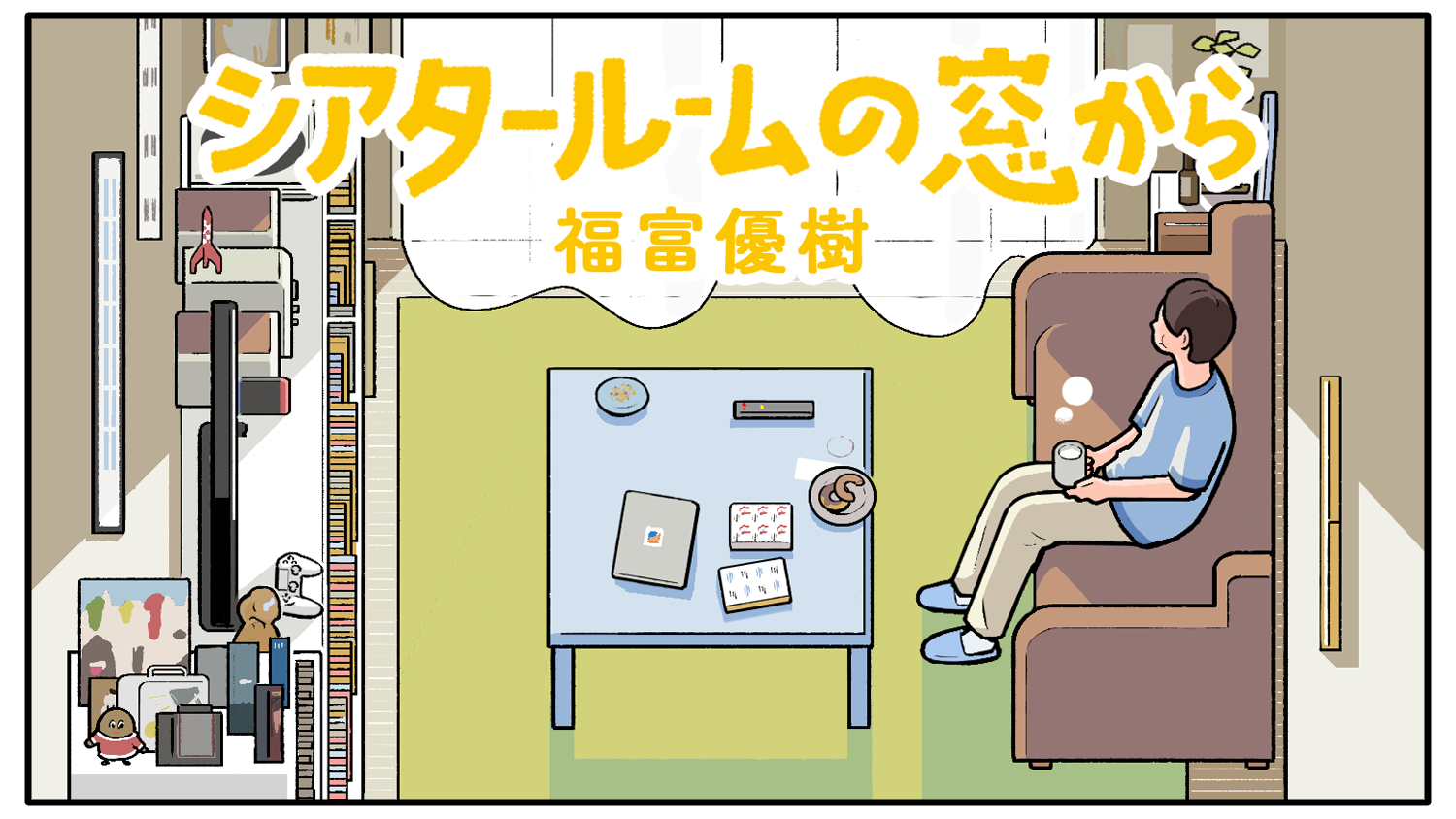
気軽に外に買い物に行けなくなったここ1年半の間に、通販で買い物をすることが多くなった。
どこへでも自転車で行けた京都の街から、東京の郊外に引っ越してきたことも、理由のひとつかもしれない。東京にはなんでも揃っているけれど、それはひとつの街に全部がある、ということではなくて、あっちこっちに広がる電車に乗って街から街へと移動する必要がある。
本屋さんでもレコード屋さんでも、そのお店へ行くのにかかる電車賃とそのお店の通販でかかる送料を比べてみると、通販のほうが安かった、なんてこともしょっちゅうある。
そんなこともあって、去年くらいから、ほとんど毎日のように部屋になにかが届くようになった。
せっかくならと、京都で暮らしていた頃に通っていた大好きな本屋さんから、通販で本やzineを買ったりもする。レコードもできる限り個人でやっているような小さなお店で買いたいのだけれど、ポイントや送料無料のサービスにつられて中古のもの以外の新譜はほとんどチェーン店のオンラインサイトで買ってしまう。
本やレコード以外にも、ちょっとした生活用品も通販サイトで買うようになった。特に去年の春や今年の夏のように感染者が増えている期間は、歯磨き粉やテープ、洗剤や電池のような、いつもだったらどこかに出掛けたついでに薬局やスーパーで買うようなものも通販で買うくらい、ほとんど外に出ない日々が続いていた。それくらい通販サイトが安くて速くて便利だということでもあった。
配達のベルで目覚めることもあるし、荷物を受け取っている間にまた新しい配達員がやってくることもある。家族で住んでいる部屋が多いこのマンションでは廊下にずらっと置き配のダンボールが並んでいることもある。
ダンボールが並ぶ廊下の風景は、誰もいなくなった渋谷や新宿の街角の映像と同じように、このパンデミックの波のなかの生活を切り取る一枚の絵となるかもしれない。そして、人が行き来しなくなった街の上をだれかの荷物を抱えて走る人たちがいる。
コロナウィルスが浮き彫りにしたのは、僕たちの生活がたくさんの人の仕事に支えられているという当たり前すぎて忘れられていた事実だ。
エッセンシャルワーカーということばが注目され、様々な職業の価値や問題が語られるようになったけれど、それでもまだ目をあまり向けられていない仕事はたくさんある。暮らしに近いにも関わらず、見えにくくなってしまうのは、生活のなかでそれに気がつくための想像力を働かせる必要があるからだ。
パンデミックを経て今や当たり前の存在になった自転車やバイクで食事を配達する人たちも同じように保障されない労働者ともいえる。夏の終りに起こった大規模なハリケーンによる豪雨で水上都市のようになったニューヨークの街をじゃぶじゃぶと雨をかけ分けて進む配達員の映像は衝撃的だった。
僕たちがウィルスを避けて、安全な部屋のなかで暮らしていたあの期間に、外では物や食事を運んでいる人がいたことを僕たちや社会は顧みていただろうか。選択肢が増えたというだけのことだと、自分で選んだことなのだから、とないがしろにされてはいなかったか。
彼や彼女たちは本来ケアワーカーとは呼ばれないかもしれないけれど、このパンデミックのなか、入院することもできずに自宅療養となった人たちとってはケアを担う存在になっていたのではないかと思う。
便利になることは、必ずしも余裕ができるということではないかもしれない。 過剰な便利さのなかでそれを担う誰かの顔はどんどんとぼやけていく。
僕たちは、自分や親しい人が肌で触れたもの以外へ想像をはせるため、映画や小説に触れるのかもしれない。想像することは優しくなることのはじまりの一歩でもある。
近所にある小さな本屋さんで、何気なく手にとった『ケア宣言 相互依存の政治へ』という本を読んで、すぐに思い出した2本の映画がある。
ケン・ローチ監督が引退を撤回してまで撮った『わたしは、ダニエル・ブレイク』そして『家族を想うとき』だ。
世界中で際限なく拡がり続ける格差や貧困の問題に対して、できることが、表現しなくてはならないことがあるという想いで作られたこの2本の映画には、僕たちが生きている世界の今のリアルが描かれている。
『家族を想うとき』の主役として登場する家族は母親がケアワーカーとして、そして父親がゼロ時間契約労働の配送ドライバーとして働いている。
ケアワークの仕事は人手不足や決して良いとはいえない環境という問題を抱えている。訪問介護士としての働く母親は時間で細かく区切られたタイムスケジュールのなかで、精一杯の仕事をするが、時間を超過した分の給与はルールの外のものとされ支払われることがない。
ゼロ時間契約労働のドライバーは個人事業主としてみなされるけれども、配送会社からは厳しいノルマや規則を守ることを求められる。その反面、保証のようなものはなにもない。日本でいうところの非正規雇用に近く、政府による公共政策を縮小し自由競争を重んじる「新自由主義」が行き着く先の未来を表すような新しい仕事の形だ。
すべてが自己責任の世界で、出口がそこにあるにもかかわらずなにかによって塞がれているような暮らしのなかで、そこから漏れる光だけをたよりに懸命に生きている家族の物語は、そのままこの国を舞台とした物語ともなりえるだろう。
非情で冷たい社会を描きながらもケン・ローチ監督の目線には温かさと優しさがあり、それが様々な場面で感じられるからこそ、胸を打つ痛みにも手に取るような実感がある。
『家族を想うとき』の原題でもある「Sorry We Missed You」という文言は、不在により荷物を届けられなかったことを配達員が不在票に綴る伝言でもあり、家族への、そして社会から制度から目を逸らされてしまう人々へのメッセージのようでもある。
僕たちはケアというものをもう一度見つめ直さなくてはいけない。オリンピックなどの大規模なイベントも行われていたこの夏、繰り返し発令されるたびにどんどんその効力を落としていった緊急事態宣言の連続のなか、ケアワーカーやエッセンシャルワーカーに対するケアもだんだんと遠ざかっていっていたのではないかと思う。
さらに、様々なかたちのジェンダー、新しい働き方、メンタルヘルスにおける問題、介護、教育の場など、以前からあった問題へのケアの必要性がこのコロナ禍によってより、浮き彫りになってきている。
社会全体がケアをないがしろにする方向へと突き進んでいくことに対して、ケン・ローチ監督はひたすらに現実を物語に投影することでNOを突きつけていく。
前作『わたしは、ダニエル・ブレイク』で描かれているのはケアの問題だ。行政が取り仕切る、形式ルールに基づいたケアが取りこぼしてしまう、大勢の人たちの生活と、それを補う隣人へのケア、つまり「Neighborhoodのケア」。
世界が抱える格差問題は日に日に膨れ上がっていき、フードバンク(※)などのネイバーフッドによるケアには限界がある。誰もこぼれ落ちないようにするには、政府や自治体によるケアが必要不可欠だ。
矛盾と現実に向き合わされた末に、主人公のダニエルが職業安定所の壁に叫びを表現した行動と、そのあと警察に連行されるときの落ち着きをはらった表情に、勇気を讃えると同時に、彼の絶望にも似た思いが生み出す衝動が、もしも誰かを直接的に傷つけるような行為のトリガーとなってしまったら、と先日また新たに起きた電車での事件のことが頭によぎってしまうのだった。
こぼれ落ちてしまった先では、音楽も映画もそこからだれかを救い出すには力が足りないのかもしれない。実際に僕らは手をとることはできないし、温かい場所を用意することもできない。そうならないように、そうなってしまうまえに、誰も取りこぼさないケアやセーフティーネットが必要だ。
僕たちにできるのは寄り添うこと、そしてその現実や問題を音楽や物語を通じて知らせることだ。ケン・ローチ監督は現実の、すぐそばにあるのに見えにくくなってしまっている問題を作品にして世界に差し出す。それは想像してみることを世界に求めるということだ。想像力のある社会をつまり、誰にとっても優しい社会を。そんな世界を作るのは私たちであると。

※フードバンク…品質に問題がなくても、包装の傷みなど様々な理由により流通に出されない食品を、福祉施設等へ無料で提供する団体・活動。
- two sea, your color 物語の終わりはハッピーエンドがいい
- moon shaped river life
- 『ゴーストワールド』にまつわる3篇
- won’t you be my neighbor? 『幸せへのまわり道』
- 自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に 『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』
- “君”のように遠くて近い友達 『ウォールフラワー』
- あの街のレコード店がなくなった日 『アザー・ミュージック』
- 君の手がきらめく 『コーダ あいのうた』
- Sorry We Missed You 『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』
- 変化し続ける煙をつかまえて 『スモーク』
- 僕や君が世界とつながるのは、いつか、今なのかもしれない。『チョコレートドーナツ』と『Herge』
- この世界は“カラフル”だ。緑のネイルと『ブックスマート』
- 僕だけの明るい場所 『最高に素晴らしいこと』
- 僕たちはいつだって世界を旅することができる。タンタンと僕と『タンタンと私』
- 川むかいにある部屋の窓から 君に手紙を投げるように




