目次

私たちの「日常」を覗き見すると、見えてくるもの
― 映画で描かれるのは、かつての自分にも思い当たるような、一見すると「何気ない大学生の日常風景」です。しかし、観終わったあと、「おもしろかった」で済ましていいのか迷ってしまいました。
藤原 : その感想、めちゃくちゃわかります。体感としては、109分が一瞬で過ぎ去っちゃうくらいおもしろいんですが、おもしろいでは片付けられないというか。「この作品をおもしろいって言ってるやつ、大丈夫?」ってなりますよね(笑)。だけどやっぱり、おもしろいっていう感想になってしまうんですけど…。
覗き見するように人間を客観視してみると、行動とか言葉とか突っかかるし、納得できないところがこんなにあるんだなって。その不思議さなんですかね。「恋愛も人間もおもしろいな」と思いました。
木竜 : 人がいて、生活があって、映画の中の出来事を見つめられる映画ですよね。私は、自分が出ているのに、他人を見ているような感覚になったんです。これまで、そんなことはほとんどなかったので、驚きました。

― 撮影中はどんなお話をされていたんですか? 繊細なやりとりが交わされるシーンが多かったので、監督と話し合うことも多かったのでしょうか。
藤原 : くだらない話ばかりしてました。
加藤 : ここで思い出せないくらい、どうでもいい話しかしてないです。
木竜 : 個々に「ここは話しておきたい」という場面はあったと思うんですけど、3人揃って真面目に話す、ということはなかったですね。
藤原 : 核心には触れられないですよね。核心に触れちゃうと、「これです」って決まっちゃうじゃないですか。かっこいいこと言っちゃったな(笑)。

加藤 : わかんないけど僕が「このシーンは、こう」って外側のことを言い切ってしまうと、僕の代わりを演じることになってしまうじゃないですか。僕の役割は、あくまで役者が考えたり行動したりするきっかけを演出すること。
ある花を咲かせたいと思っていたとして、どれだけ水をあげて、太陽に当てて、どんな肥料を与えるかっていうことはするけれど、結果花の咲き方みたいなものは俳優次第。
藤原 : そうですね。一緒に中華料理食べに行ったりしたけど、会話の内容は一つも覚えてない。
木竜 : 私もまったく覚えてないです。
加藤 : 僕が、頼んだメニューの3/4くらい残したんですよ。それを、季節が全部食べてくれて。
木竜 : そうそう、加藤さんが全然食べきれなくて。

藤原 : 僕は、加藤さんが残したものを食べることがよくあります。加藤さんが脚本・演出を務める「劇団た組」の公演には何度か出させてもらっているので、ご飯に行くことも多いんですけど、よく残すんですよ。そういう話を延々してました。
加藤 : 木竜さんは、撮影中にどんどん痩せていきましたね。
木竜 : 意識的にというより無意識に、どんどん役に入り込んでしまったんですよね。
― 大学生の優美は直哉と半同棲状態になるものの、突然別れを告げられるなど関係性は不明瞭なまま。そんな中で予期せぬ妊娠がわかり、優美はどんどん体調を崩していきます。その過程で、痩せてしまったんですね。
木竜 : ふたりは「食べな!」と言ってくれてたんですけど、お弁当も2、3口とかしか食べられなくて。これまでの現場で、一番痩せてしまいました。

加藤 : 似顔絵を台本に描たりしました。10日目くらいかな、砂時計みたいな女の子を描きました。
木竜 : ふたりはよく一緒に作品を作っているから、やり方もわかっているし、本番に入っていくスイッチングもほぼ同時なんですよ。
― 藤原さんは、加藤監督主宰「劇団た組」の舞台『まゆをひそめて、僕を笑って』(17)『貴方なら生き残れるわ』(18)『誰にも知られず死ぬ朝』(20)『ぽに』(21)に出演されていて、加藤監督も「僕の現場や作品におけるトーン&マナーみたいなことを十分理解してくれている」とコメントされていました。
木竜 : ふたりは控え室でたくさん盛り上がっていたのに、急に本番モードになる。それを1週間毎日やられると情緒がおかしくなりそうで、ほんとにやめてほしくて。初めて監督という存在に言いました、「バーカ!」って(笑)。
でも、そういうことを正直に言えるくらい信頼していました。藤原さんも知っていたので、ふたりを信頼して、身を委ねて現場に立てたのは大きかったと思います。

正常と異常は両極端ではない。
重なり合ったり、近くに存在したり。
― 映画では何度もふたりでコミュニケーションを図るシーンが描かれているのに、演じているふたりもボロボロになるぐらい、ふたりの関係性が破綻していきます。おふたりは「わかりあうこと」について、どう思われますか? 役を演じる中で、考えられたことはありますか。
藤原 : 映画の中のふたりは、自分たちでは「理解し合っている」と思っているんですよ。第三者的に見ている僕たちからしたら「全然、わかりあえていないな」って思うけれど。だけど、優実と直哉にもわかりあえないことも愛しい、もしかしたらわかりあえていたかもしれない幸せな時間があった、というのが大事なことなんだと思います。
わかりあえない方ばかりに目が行きがちですけど、ふたりがわかりあえない互いを理解して、心を通わせていた時間もたしかにあったので。幸せな時間も忘れちゃいけないなって思います。
木竜 : そうですね。それはきっと、いろんな人間関係があるからで。優実にも恋人以外に、友人、家族といった人間関係が描かれて、それぞれ気持ちや立ち振る舞いが違う。だけど、時々別のグループに別の私を持ち込んでしまうから、理解できないことが生まれるのかもしれないですよね。
藤原 : つまり、「わかりあうこと」について考えるきっかけになるということ?
木竜 : 「わかりあえないこと」についても考えられる。両方の側面があるかな。
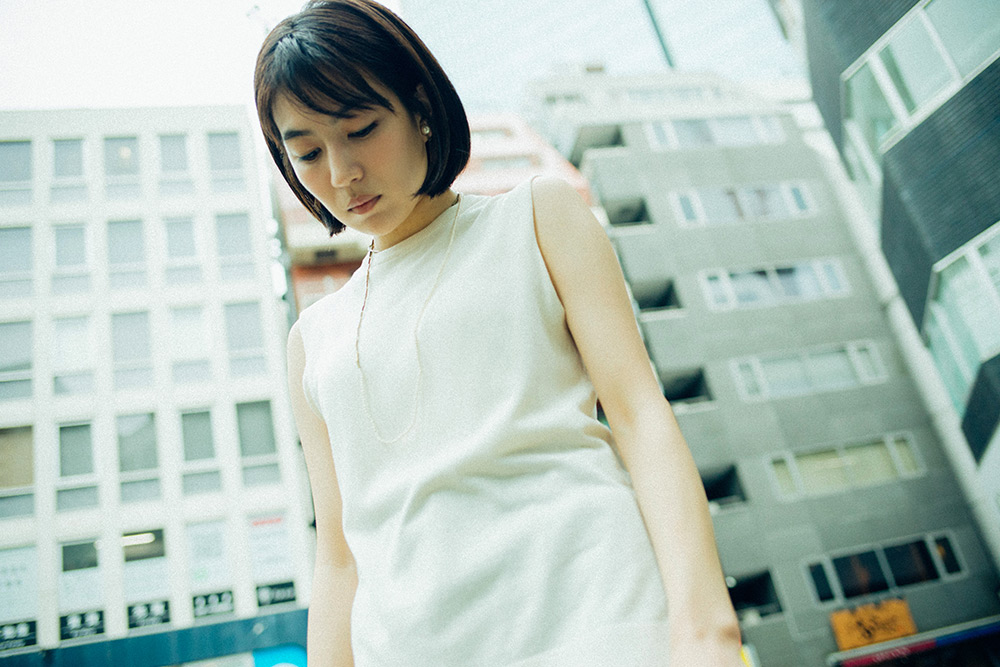
藤原 : 監督はどうですか?
木竜 : どうですか?
加藤 : いや、「わかりあう/わかりあえない」ということではなくて大前提、他人のことは絶対にわからないですよね。その「わからない」ということを、理解しているかどうかが大事なのではないかと思います。
藤原 : 他人のことはわからなくて、当然?
加藤 : わからないでしょう。
木竜 : たしかにこの映画は、「“理解し合えないまま生きていること”は大前提としてある」を考えるきっかけになりますよね。

― お互いに本音をずっと言わないから、理解し合えないのではないかと考えていました。
木竜 : 優実はあけすけに本音を話すような子ではなかったと思います。話す相手がどんな人で、どんな状態か、他人を探る女の子だと思いました。ただ、どんな人も、今話したことが「ほんとの本音か」わからないと思うので、優実みたいな人はいっぱいいますよね。
藤原 : 直哉も、本音はほぼ話さない。自分が悪者にならないように、計算し尽くした本音を相手にぶつけるんです。一度相手の意見に同意して、それから自分の意見を言う。
木竜 : 肯定しているようで、してないんだよね。
藤原 : そうそう。「仮にそうだったとして、でも〜」って、自分の意見をうまく通そうとするんですよ。
― 監督の作品のベースには「伝えたいことと言っていることとやっていることは違う」という考えがあると拝見しました。今作のように日常生活を覗き見すると、日常にあるズレが浮かび上がり、こんなにも「異常」があることを感じました。

藤原 : 僕も加藤さんの作品を観ていると、普通の延長に異常があるなっていうのは思います。この前まで上演されていた舞台『もはやしずか』でも、成人男性が包丁を振り回すシーンがあったんですけど、明日は我が身だと思わされるような場面で。
そこだけ切り取れば異常なんだけど、普通の延長に異常とされる行動があるんだと思いました。あと、普段から僕自身が「行動が異常」って言われます。
加藤 : 水を飲んでいたら、急に吐き出したりするんですよ。
藤原 : みんなが笑うから、楽しくて(笑)。木竜さんは言われますか?
木竜 : 私は「異常」と言われたことはないですけど、正常と異常が両極端に位置しているわけじゃなくて、実は重なり合ったりものすごく近くに存在していたりするんだなってことは思います。監督の舞台を観ても、そう思いました。
加藤 : 僕は異常だとも、普通だとも思ってないです。普通だとか異常だとかカテゴライズはしてないし、そう思うことはあまりないです。
― 今回の映画は、恋愛で、しかも望まない妊娠をした女性とその恋人という何度も描かれてきたテーマでした。そうしたものを書くときに、加藤監督として決めていたことはありますか?
加藤 : ラブストーリーという主題は依頼としてあったので、そこから僕が思う「ラブストーリー」を書いた感じです。決めていたことを聞かれると難しいですね。
藤原 : 何度も描かれてきたテーマですけど、描かれているものは極めて個人的な気がします。正常も異常も、人によって価値観や視点が全然違いますから。
その違いを真摯に見つめて、一人の人間を描いた結果、他人から見ると異常に見えるのかもしれない。人によっては、普通に見えるかもしれない。普通に見える女子大生のお腹には子どもが宿っていて、そこに正常や異常では片付けられない感情があるってことですよね。

木竜麻生、藤原季節、加藤拓也監督の「心の一本」の映画
― 最後に、みなさんの「心の一本」の映画を教えていただけますでしょうか。
藤原 : 初めて聞きますよ、監督の「心の一本」。カルチャーに影響を受けたりするんですか?
加藤 : 見聞きしたもの全てに影響受けてるよ。でも、なんだろう……小説でもいいですか? 小川洋子さんの『博士の愛した数式』という作品がすごく好きで、何度も読み返しています。
― 80分しか記憶のもたない64歳の数学者を中心に、家政婦、10歳の息子の3人の日常風景を描いた物語ですね。2005年には映画化もされました。
加藤 : 小川さんの言葉がすごく美しい。とても綺麗なのに、奥底にほんの少しぬるい毒のようなものが仕込まれている感じが心地よくて。それは、小川さんの作品全般に感じる魅力ですけど、その中でも特にこの作品が好きです。
木竜 : 私は、ヤスミン・アフマド監督の『タレンタイム~優しい歌』(2009)ですかね。新文芸坐で再上映すると聞いて、映画館にも行きました。
― 2009年に51歳の若さで亡くなったマレーシアの女性ヤスミン・アフマド監督の遺作となった作品ですね。劇中の音楽も大変素晴らしく、多くのファンを生み出しました。
木竜 : 「優しさ」を言葉にするのは難しいけれど、私にとっての「優しさ」が描かれているように感じましたし、カメラと映される人たちとの距離感が心地よくて、すごく好きな作品です。
― 藤原さんは前回のインタビューで『スタンド・バイ・ミー』(1986)を答えてくださいました。
藤原 : 最近観た映画で心に残っているのは、廣木隆一監督の『夕方のおともだち』(2020)ですかね。
― 漫画家・山本直樹さんの同名漫画を映画化した、SMの女王様・ミホ(菜葉菜)とドM男・ヨシダヨシオ(村上淳)の不思議な恋愛模様を描いたヒューマンラブストーリーです。
藤原 : 廣木監督の作品は絶対に映画館で観たいと思っていて、まさにそういう映画でした。引き画が多用されてるんですけど、見るのに集中力が必要。音も画も、大きなスクリーンで観るための温度感があって、物語もすごくよかったです。
― 何度も、繰り返し観ていらっしゃる映画が『ノルウェイの森』(2010)、『マトリックス』(1999)でしたよね。
藤原 : そうですね。何度も観返している映画とか、あります?
木竜 : 私が、何度も観返しているのはジブリ作品の『もののけ姫』(1997)です。あとは、『GO』(2001)。お父さんの影響で『グーニーズ』(1985)と『ブルース・ブラザーズ』(1980)も何回も観ましたね。部屋の中でいつも流れていたので、曲を聴くと懐かしい気持ちになります。











