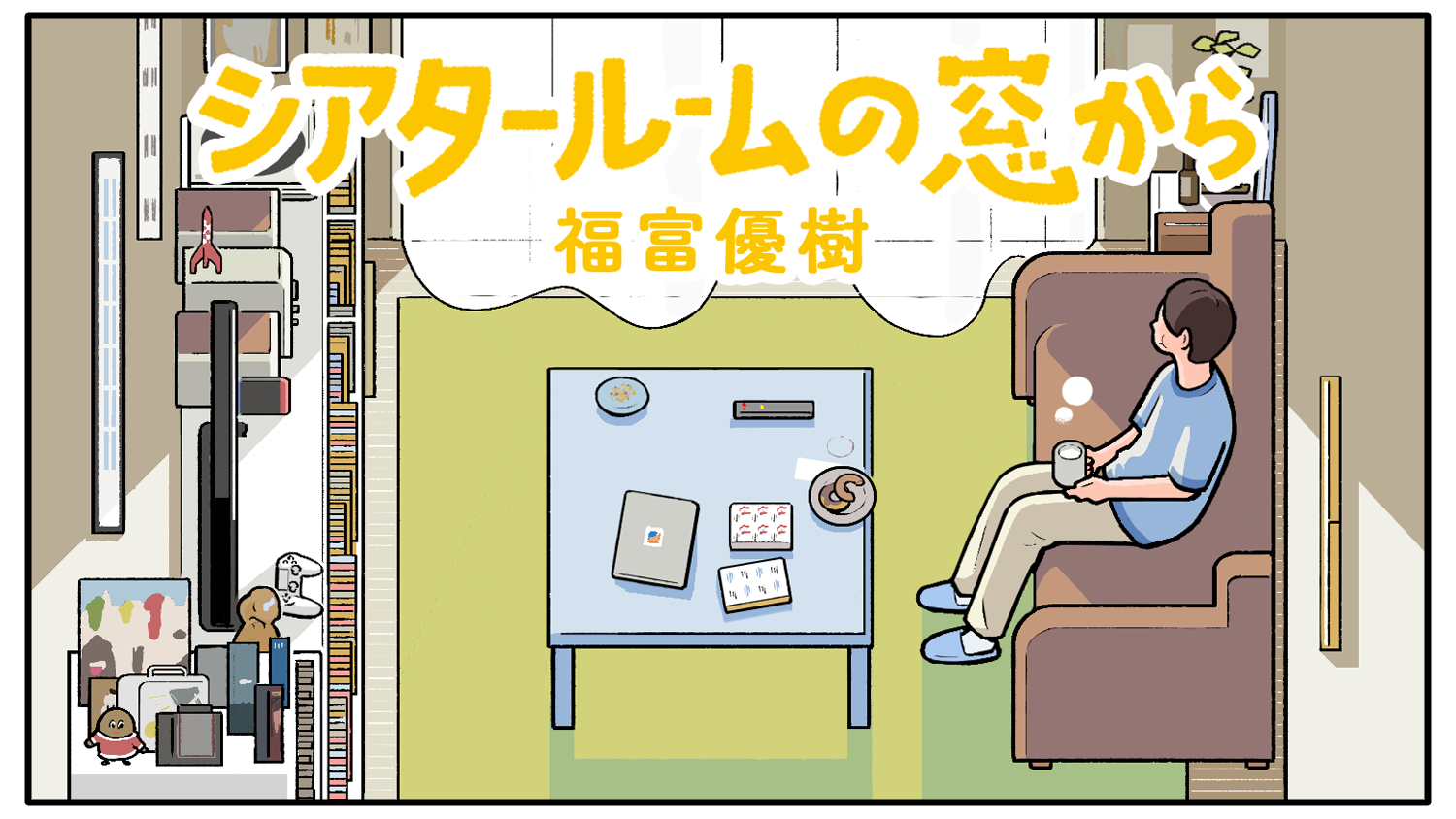
朝10時。タイムカードを押し、ロッカーにかばんを放り入れる代わりにエプロンを取り出す。パネルや試聴機に電源を入れて回る日もあれば、モップを片手に簡単に床を掃除する日もある。朝礼があって、それまで3分の2くらいの明るさだった店内の照明がぱっとつき、開店時間になるとBGMが鳴る。僕はバックルームで、大小いろんな大きさのダンボールを片っ端からカッターで開いていき、中身をスキャンしてジャンルごとに仕分ける。レジからベルが鳴るとフロアに出て、並んでいるお客さんのお会計をしたり、予約や問い合わせを受けたりする。裏方だから電話には積極的に出る。キーボードをかたかたと叩き、納品書の束を片手に棚から棚へと移動する。
15時になったら作業台を片付け、引き継ぎの簡単なメモを夕方に来る同僚のロッカーに貼り付けて、タイムカードを押す。エプロンをはずし、挨拶も兼ねて小さな会話をあちらこちらでしながらフロアを適当に散歩する。ほしいレコードが入荷しているときは、先輩に声をかけて精算をしてもらう。下に持っていく荷物があるときは小脇にそれを抱えて従業員用のエレベーターに乗り、集荷に出し、最後に退館表に名前を書いて館内を出る。
四条の街は西陽に黄昏れていて、オレンジ色に染まっている。ちょっとした疲労感と開放感でちくちくする胸を遊ばせながらそこから僕の一日の後半がはじまる。ミスタードーナツで歌詞や原稿を書いたり、誠光社で本を買ったり、レーベルの事務所兼お店になっている場所へ行って誰かをつかまえて無駄話をしたり、京都シネマで気になっている映画がやってないか覗いたりする。それがあの頃の僕の毎日の暮らしだった。はちみつのようにとろんとした黄金色の甘い日々。
『アザー・ミュージック』を観ながら、僕はそんな全てが洪水のように溢れてくるなかにいた。大学を卒業して、京都の中心部にある黄色の看板のレコード・チェーンのお店で働きはじめたころのことだ。
『アザー・ミュージック』は2016年に惜しまれつつも閉店した、ニューヨークにあったその名も「アザー・ミュージック」というレコード店のドキュメンタリー映画で、今年の9月に日本で公開になる。監督自身もアザー・ミュージックで働いていた経験があり、どのシーンもその場所への愛に満ちた、とても近いまなざしを通して切り取られてる。

アザー・ミュージックは1995年にオープンし、21年もの間インディー・ミュージックの発展に一番貢献するレコード店のひとつであり続けた。インディー・ロック、サイケ、電子音楽から、ジャンルでは区切ることのできないまさしく「アザー」な音楽まで、ジャンルを横断したその品揃えと音楽愛に溢れすぎたスタッフたちとそのファンともいえるお客たち。映画のなかではアニマル・コレクティヴやヴァンパイア・ウィークエンドといったブルックリンのシーンやポスト9.11のニューヨークのカルチャーについても触れられていて、ニューヨークという場所にとってアザー・ミュージックがいかに重要な場所であったかも語られている。ミュージシャンにとってもレコードを買いに訪れる人にとっても、そしてそこで働く人たちにとっても、アザー・ミュージックはただ単に買い物をするための場所ではなかった。音楽というものを通じて、様々な人やものが集まりなにかへと繋がっていく、その交差点として街にあったのだ。
アザー・ミュージックの向かいには、僕が働いていたレコード・チェーンの大きな店舗があった。そのお店はその大本の企業ごと、アザー・ミュージックよりも早く市場から姿を消してしまうことになるのだけど、アザー・ミュージックで働くスタッフたちはそれを喜ぶことはない。街からまたひとつ場所がなくなってしまったことを悲しむだけだ。そして街から次々とレコード店や書店が消えていき、代わりにコーヒー・チェーンと24時間明かりが灯り続けるフィットネスクラブが街にやってくる。彼や彼女は分かっている。街というものの大切さも、はかなさも。これはある意味で、マンハッタンのイーストヴィレッジという街の映画でもあるのだ。
最後の営業が終わりレコードの棚が空っぽになった店内を、スタッフたちが解体していくと、なにもなくなった場所に思わぬところから「時間」が浮かび上がるシーンがいつまでも僕の胸に残った。
場所には時間が染み込んでいる。時間は思わぬかたちで目にすることができる。それはこれまでになくなってしまった、たくさんの好きな場所にも最後にはこんな時間が待っていたのだろうな、というシーンだ。育った町の「アラスカ」や京都の堀川二条にあった「WAVE」のようなレンタルビデオショップ。大学生のときにアルバイトしていた夜遅くまで開いていた一乗寺の古本屋。本当に大好きだった小さな洋食屋さん。いつものように衣装のシャツをもっていくと、なんの知らせもなく急に閉店してしまっていた近所のクリーニング屋さん。色んな場所が頭に浮かび、同時に、今はまだなくなっていない場所のことも考えたりした。いつかあのお店も閉店してしまうのだろうか、と思うと胸がつまるような場所が僕にはたくさんある。
僕があのレコード・チェーンのお店で働きはじめた頃には、もうHomecomingsでフジロックに出演したりレコードを何枚かリリースしたりしていて、バンドを辞めるとか、就職しながら活動するという考えには全くならなかった。そこはインディー・ロックが好きなスタッフが多いお店だった。それを反映するようにインディー・ロック、特に日本のインディーの売上が他のお店よりも良い店舗だ。Homecomingsの商品もよく売れていて。自分のCDやレコードが目の前で売れていくのを見るたびにとてもうれしくなったし、いつまでのそのよろこびは薄くなることはなかった。
シャムキャッツやミツメや森は生きているのライブを観に行くと、だいたい同僚の誰かに会ったし、僕たちのライブにもよく遊びに来てくれた。「職場の人」と「友だち」が混ざったようなその関係性がなんだかとても居心地がよかった。なにかにつけてよく鴨川でお酒を飲んだ。今でも続く大切な出会いがいくつもあった。なにより音楽がある場所で働けていることがとにかくうれしかった。
週末にはライブで京都を離れ、月曜日からはレコード屋さんに行く、という慌ただしい暮らしは2018年にバンドが本格的に忙しくなるまで続いたけど、僕にとってレコード屋さんで働いていることは、音楽をやっていることと切り離せないくらい大事なことだった。日々新しい音楽と出会える環境は自分が音楽を作る上でとても大きな影響があったし、僕がラジオで紹介したレコードをお店に買いに来てくれる人もいたりして、生活のなかの点と点がしっかりと結びつくことがとてもうれしかったし、ある意味ではそれが僕にとっては誇りのようなものでもあった。どれだけバンドの活動が忙しくなっても、新譜商品の入荷日である火曜日には出勤を続けていた。そんなふうに働くことを許してくれたお店のみんなには頭があがらなかった。東京に引っ越すことになって、お店を辞めることになった。それは住み慣れた街から離れることと同じくらい寂しいことだった。
エプロンのポケットにはタンタンのイラストが入ったメモとボールペンとカッター。心の片隅にはどこかモラトリアムな、とろんとした居心地のよさと、これがいつまで続くのだろうというざらついた不安が同時にある日々だった。それはずっと昔の思い出というよりかは、今でもすぐに取り出せるまだ温かさが残る感触だ。

Happynessの『Weird Little Birthday』、Alex Gの『DSU』、Andy Shaufの『The Magician』、そしてシャムキャッツのいくつかのレコード。あの頃、レコード店のバックヤードでみんなが夢中だったインディー・ロックのレコードは、今も僕の部屋でくるくると回り続けている。でも、僕がこれまで数え切れないほどの時間を過ごしてきたあの空間は、いつまでもずっとあるようなものではないのかもしれない。あの本屋もレンタルショップもレコードショップも。僕が大好きでずっと抱えていたいのは、そこで出会ったものだけじゃなくて、場所そのものでもあるのだ。
その場所がなくなったとき、僕たちはそれを守ることができなかったことを悲しく思うかもしれない。便利さに誘惑され、ネットの通販で本やレコードを買ったことを思い出して後悔するかもしれない。時代の流れはいつでも、僕たちが暮らしのなかで打つ小さな点が集まってできている。それでも、どうしようもないことがたくさんあるだろう。
全部を守ることはできないし、小さな点の抵抗は数にはかなわない。きっと、なくなってしまってから気がついたり思い出したりする場所やものもあるだろう。そんなとき、僕たちにできるのはその場所のことを、その場所であったことを残しておくことなのかもしれない。思いがけずそのバトンが次の世代に渡り、新しい場所ができるきっかけになるかもしれないし、なくなってしまったものが再び姿を取り戻すきっかけになるかもしれない。
映画のなかで、Vashti Bunyanの「Diamond Day」という曲が流れる印象的なシーンがある。レコード店の先輩に教えてもらったアルバムの一曲目に入っていた曲だ。その場所がなくなっても、その場所で過ごした日々が遠くなっても、その場所での時間はいつまでも砕けることなく、心の中に、そしてこんな風にして映画のなかで輝き続けることができるのだった。
Vashti Bunyan「Diamond Day」収録アルバム
- moon shaped river life
- 『ゴーストワールド』にまつわる3篇
- won’t you be my neighbor? 『幸せへのまわり道』
- 自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に 『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』
- “君”のように遠くて近い友達 『ウォールフラワー』
- あの街のレコード店がなくなった日 『アザー・ミュージック』
- 君の手がきらめく 『コーダ あいのうた』
- Sorry We Missed You 『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』
- 変化し続ける煙をつかまえて 『スモーク』
- 僕や君が世界とつながるのは、いつか、今なのかもしれない。『チョコレートドーナツ』と『Herge』
- この世界は“カラフル”だ。緑のネイルと『ブックスマート』
- 僕だけの明るい場所 『最高に素晴らしいこと』
- 僕たちはいつだって世界を旅することができる。タンタンと僕と『タンタンと私』
- 川むかいにある部屋の窓から 君に手紙を投げるように



