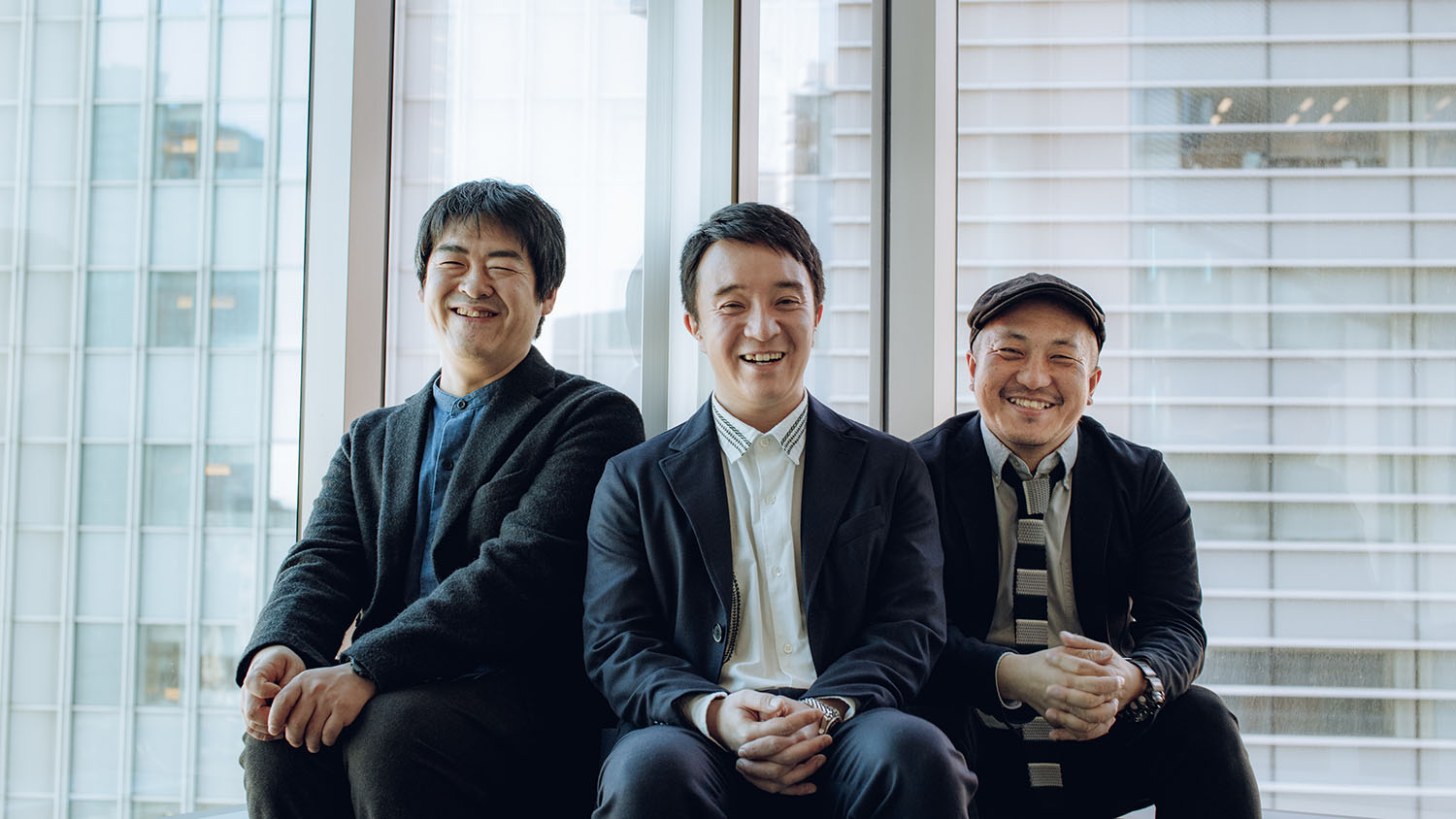目次

どんなシーンも楽しく撮る、
それがいいアイデアを生み出す
― これまで白石監督作品に出演された役者さん何名かにインタビューをしたことがあるのですが、みなさん口をそろえて「白石組の現場は楽しい」とおっしゃるんです。白石監督の作品は暴力が描かれたり流血するシーンが多かったりと「重め暗め」のイメージが強かったので、「楽しい」という現場からのコメントは意外で驚きました。
白石 : 僕の作品のイメージから僕自身も怖い人だと思われがちですけど、僕はできるだけ人を怒ったり、大声をあげたりしないようにしています。助監督時代は若松監督に怒られてばかりでしたけど(笑)、それは愛のあることでした。暴力が現場にあるとどうしても殺伐としてしまいますし、得することはあまりないと思うので、僕の組では暴力一切禁止。「やったら出てってもらうんで」とスタッフに宣言しますよ。
― 現場では、どういったムードを大切にされているんですか?
白石 : みんなが意見を言いやすいような空気をつくろうとは意識していますね。先日、今度リリースされるBlu-rayとDVDに収録するため、『彼女がその名を知らない鳥たち』のオーディオコメンタリーを蒼井優さんと阿部サダヲさんと録りました。それで思い出したんですけど、クランクインしてから陣治は痛風持ちという設定を追加したんです。そうしたら美術スタッフがおもしろがって「じゃあ、グリーンラベルだね」と、ビールを呑むシーンでは必ずプリン体の少ないグリーンラベルを用意してくれて。ですが、十和子と陣治が最後の晩餐をするシーンで美術スタッフから「このシーンだけは、普通のビールでいいですか?」と提案がありました。僕もそれを聞いて「最後の晩餐くらい、そうだよね」と。そういうアイデアって、スタッフみんなが撮影を楽しんでくれて、自分の意見を言える雰囲気がないと出てこないと思うんです。
僕が演出部出身だから思うのかもしれませんが、スタッフには僕と二人三脚で頑張ってもらいたいと思うんですよね。撮影が始まる前には核となる人たちと呑みに行きますし、どんなシーンも楽しく撮りたいと思っています。
― 監督ご自身が現場では猫をかぶってしまう、ということはありますか?
白石 : それはないですね、なるべく自然体でいるようにしています。ただ、役者には身体をはってもらわないといけないシーンもあるので、そういうときは楽しさよりも安全を一番大事にします。そういうときは、怪我をさせないように、あえて緊張感を出すことはあります。

「権力側からものを描くな」師匠の言葉が映画づくりの基盤にある
― 助監督を経て、様々な役者さん、スタッフさんと関わられていますが、これまでの仕事で忘れられない言葉はありますでしょうか?
白石 : 僕にとって、やっぱり若松孝二監督と行定勲監督の存在は大きいです。今どき珍しく「弟子入り」のようなかたちで現場に入らせてもらったので、二人の映画づくりを通してそれぞれに違うことを教わりましたね。若松監督からは「世の中のものの見方や人間の葛藤」というパッションの部分を多く学びました。対して行定監督からは「映画づくりの実践」をリアルにひとつひとつ学ばせてもらいました。
その中でも特に覚えている言葉は、若松監督に言われた「権力側からものを描くな」ということ。この言葉は何度も言われましたし、僕にとって腑に落ちた言葉でもあるんですよね。なので、弱い人間たちの視点から物語を描く、ということが僕の映画づくりの基盤にあります。
― 弱い人間の目線に寄り添う、ということは理解がないと横柄になったり、価値観が違っていたり、実は難しいことのように思います。
白石 : たしかにそうですね。そういう意味では、僕の家は貧しくて、幸せの多い家庭ではなかったので、スッと理解できたんだと思います。人間にはヒエラルキーがあると感じていたし、その底辺にいる人たちの視点は大事だと思っていました。
― 弱さを描くことは、怖くはないでしょうか?
白石 : 怖くはないですが、僕が弱い人間たちと同じ目線で居続けることを大事にしています。それは作家として物語をつくるときの視点もそうだし、撮影するときのカメラの視点も。なるべくカメラが主人公の目線よりも上に入らないようにしているんです。本当は、上から俯瞰して撮ったり何人も画角に入れて撮ったりした方が、映像的なおもしろさが出るので楽だったりするんですけどね……目線はすごく大事なんですよ。

― 目線、ですか。
白石 : 1カット程度なら気にならなくても、何カットも積み重なると、目線より上にある画角には違和感を感じてしまうんです。なんというか、カメラも主人公や登場人物たちと同じ目線に立ち、ともに寄り添って生きていくという感覚。もう、生理として染み付いてしまっていますね。だからどうしても僕自身の気持ちが作品にかなり乗っかってしまうし、客観的な映画は僕には撮れないなと思います。
― 弱い人間に寄り添う、というのは監督の作品に一貫していえることだと思いました。最後に監督の思い入れのある映画作品をおうかがいしたいのですが、「弱さ」というキーワードで思い返される映画はありますか?
白石 : 映画の世界に入りたいと思うようになってからは、僕自身に関していうと弱さは出さないように頑張っていました。監督になれると思っていなかったので、弱さを出してしまうと自分の脆さが顕になってしまって、映画の世界に居られなくなってしまう恐怖があったからです。映画を辞めるにも勇気が入りますし、居心地も良くて映画界にずっと居たかったんでしょうね。
なので、自分の弱さと戦ったという意味では、処女作の『ロストパラダイス・イン・トーキョー』(2010年)を思い出しますね。それは、監督を一度もせずして田舎には帰りたくないと思って、この作品の後に仕事が続かなかったら辞めようと考えていたからです。収入がない中で子どもが生まれて、「いつになったら稼いできてくれるの?」なんて妻から言われて、しゅんとして(笑)。撮り終えたときの手応えもなかったですし、出来上がってからも大丈夫かなとずっと心配していました。でも、この作品を観て一緒にやりたいと言ってくださった方がいたおかげで今があるので、思い入れがありますね。

― お好きな映画の中でも、特に繰り返し観られる映画はありますか?
白石 : いろいろありますが、パッと思い浮かぶのは高橋伴明監督作、鈴木砂羽さん主演の『愛の新世界』(1994年)です。18歳くらいに劇場で観て、衝撃を受けました。最近HDリマスター版が発売されて、すぐに観返しましたね。作劇も上手なのですが、女の子たちの気分を丁寧に描いていて空気感の切り取り方がいいなと思っています。
あとはフルーツ・チャン監督の『ハリウッド★ホンコン』(2001年)。レンタルビデオ屋で3回に一回は借りていて、買えばいいのにと思うほど好きでした。香港の貧民街を舞台に、取り壊しでなくなってしまう街で暮らす人たちが主人公です。彼らの街から見上げた場所に高層マンションが建っているんですよね。富裕層を見上げながら暮らす底辺の人間たちの葛藤を描くということは、まさに弱い人間に寄り添うということ。フルーツ・チャン監督の2作目で初の日本公開作『メイド・イン・ホンコン』(1997年)も好きです。時代が移り変わっていく中でそこに生きるひとりひとりの物語を描くこの映画を観ると、今の僕の作家性とは違いますけど、若い頃はこういう作品を撮りたかったんだなと思い出します。
― ひとつひとつの作品が積み重なって白石監督の現在があると、お話しを聞いていて思いました。娘さんが成長して、白石監督の作品を観るときが楽しみですね。
白石 : 僕が怖い映画を撮っている、ということしか知りませんからね(笑)。そのときは、僕がいない間にこっそり観てくれるのかもしれません。全然想像できませんけど。…何て言うのかな。