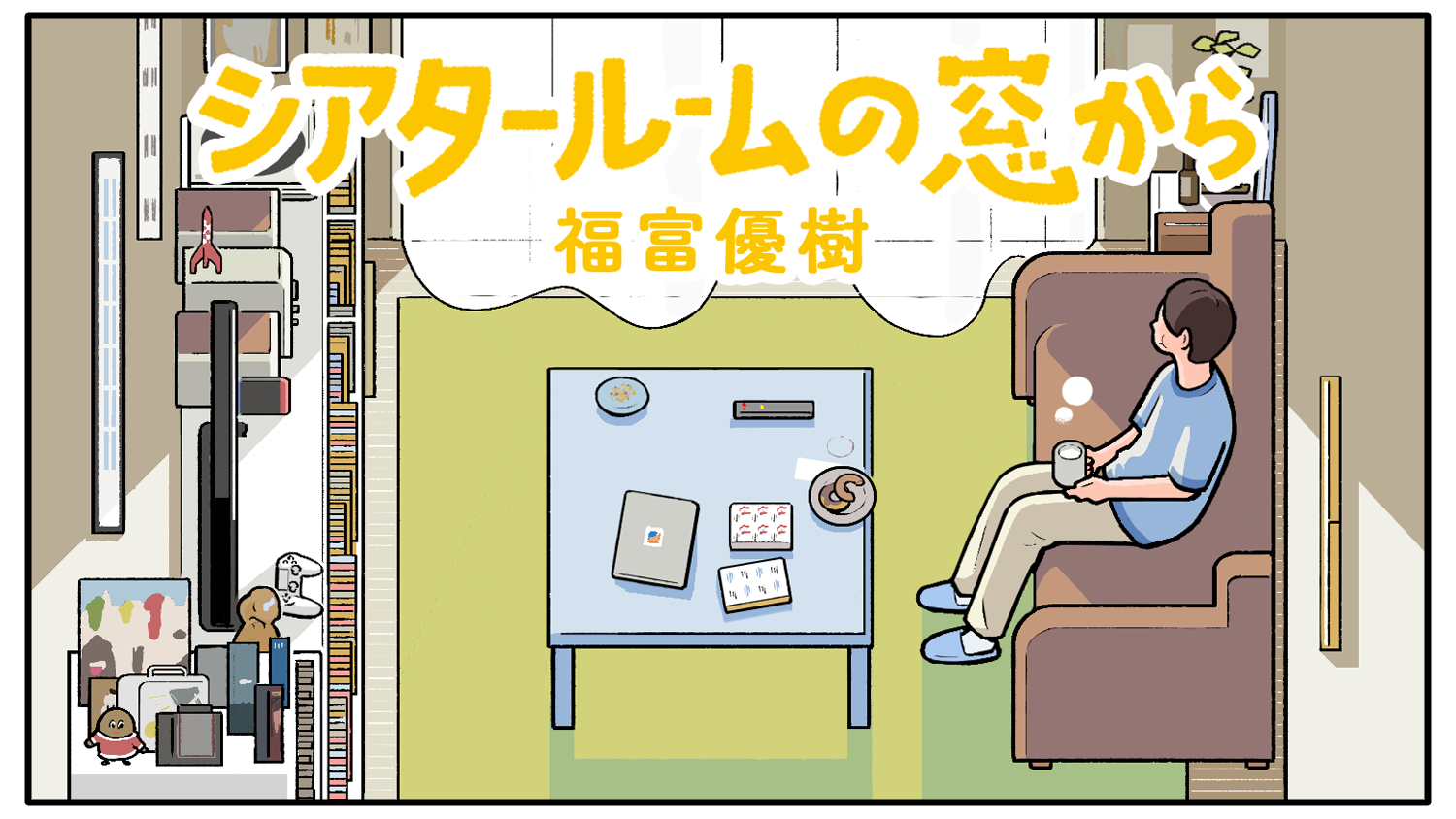
京都駅からまっすぐ北に上がると京都御所があり、地図上で見るとわかりやすく縦長の長方形になっているその周りをぐるっと囲ったエリアは東西南北でざっくりとエリア分けがされていて、それぞれ「御所南(ごしょみなみ)」や「御所西(ごしょにし)」のような呼ばれかたをする。御所北の西寄りには同志社大学の大きなキャンパスがあって、そこからほど近い御所西のエリアには僕が長年暮らしていた小さなアパートがある。
朝は御所に沿うように南に下り、そのままL字を書くように御所南エリアを通過し、さらに少し下がって職場であるCDショップまで自転車で向かう。夕方前に退勤するとそのまま北上して御所東の南にある誠光社という大好きな書店に寄る。そのあとはまた北に上がって出町柳のミスタードーナツに入り、買ったばかりの本を読んだり、歌詞を書いたりする。オールドスタイルで古ぼけたそのミスタードーナツは妙に居心地がよくて、夜になるとオレンジ色のライトがぼんやりときれいで、なんだか映画に出てくるアメリカの街角のコーヒーショップのようだった。
お腹がすくか、作業や読書が一段落するまでその場所で過ごしたあと、御所北エリアを西に向かって通過して、大学の近くの松乃家というお蕎麦屋さんで晩御飯を食べる。「かけそば」を頼むと4回に1回くらいの確率で「やきそば」が出てくることがあって、僕はそれを「当たり」と心のなかでだけ呼ぶ。薄口ソースっぽいいたって普通なやきそばなのだけど、なぜかやたらと美味しい。やたらと美味しいけど、はじめから注文したことはない。「当たり」だからいいのだ。
気分によっては出町柳商店街の王将に寄ることもある。どこの王将でも自分にとってちょうどいい内容のセットはなかなか見つからないので、大抵は餃子と炒飯を単品で頼む。京都の街にはあちらこちらに王将があって餃子はどのお店でも大きな違いはないけれど、麻婆豆腐や炒飯や付け合せのスープはお店ごとにかなり違う。帰り道には今出川駅前のフレスコに寄って明日のパンを買ったり、ペットボトルの緑茶を買ったりする。
これが僕の京都で過ごすだいたいの毎日だった。時計がぐるっとひと回りするようにぐるっと御所を一周りすると、一日が過ぎていく。御所のなかには数えるくらいしか入ったことがないし、特別思い入れがあるわけではないけれど、その周縁の街とそこでの暮らしには自分でもびっくりするくらいの思い入れがある。大学を卒業してから東京に来るまでの5年間、それはあるひとつの季節のようだった。モラトリアムと不安と期待の季節。果物のように甘くて渋くて酸味が走るような時間。

この春公開になった金子由里奈監督の『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』は、京都のなかでもまさにそのエリアを舞台にした小説を映画化した作品だ。鴨川と賀茂川、うすみどりのバスの影、ひとけのない夜の商店街、同じようにひとけのない夕方の境内、どこまでもまっすぐ伸びていく通り、ミスタードーナツの窓から眺める夜の出町柳、レンガ造りの中立売通り、堀川、なくなってしまったレンタルビデオショップ、いつもシェイクの機械が故障中のマクドナルド。スクリーンに映し出される街と思い出のなかの街が混ざっていくような感覚。自分がそこにいた、とはっきりと思える映画体験はどこまでも個人的なものだけど、今まで感じたことのないような親密な切なさや懐かしさで胸がいっぱいになってしまった。けれども、この映画はそんな感傷だけで終わるようなものではない。
「恋愛」というものや「男らしさ」「女らしさ」といったものに居心地の悪さを感じている七森は、進学先の大学で、偶然出会って心を通わせた麦戸と共にぬいぐるみとしゃべるサークル、「ぬいサー」に入部する。小さな部室には所狭しとぬいぐるみが置かれていて、そのどれもがきちんと手入れされている。ぬいサーのみんなは好きなときにそこに来ては、ぬいぐるみとしゃべる。他の誰かが話している内容を聞いてしまわないように、部室の中では基本的にはヘッドフォンやイヤフォンをつける。外から見ると変てこなそんな光景には、吐き出されることが必要な想いで溢れている。こんがらがっているのは「世界」か「ぬいサーのみんな」なのか。社会の一歩手前にある大学という場所にはほとんど社会とそっくりな世界があって、セクシュアリティや凝り固まったジェンダーバイアスによる視線がどろどろと存在している。七森と麦戸の2人も、いつのまにかそんな悪意のない悪意に押し流されてしまう。
正しくありたいし、やさしくありたいけれど、だからこそ自分のことも世界のことも嫌いになってしまうときがある。誰も傷つけないなんて絶対に無理なのかもしれない。どれだけ気をつけながら話していても、無意識のうちにだれかを傷つけ、なにかを勝手に決めつけたり、わかりやすい記号として扱ってしまったりしてるかもしれない。想いを尽くした言葉はどこかで絡まって、思ってもみないかたちで誰かに怒りや悲しみを与えるかもしれない。この文章だってそんな可能性がどこかしらに縫い合わされている。部屋を締め切ってスマートフォンを投げつけても、世界のあちらこちらにこびりつく悪意と欲望と加害性をすり抜け続けることはできないだろう。
やがて七森は、そして僕たちも自分のなかにもその加害性の影を見ることになる。男性性はぬぐってもぬぐってもじんわりと浮かび上がってくる。それでもやさしくなること、やさしくなりたい、と願い、そうあろうとすること。自分の影を見つめながらも、やさしくなろうと祈ること。もしかするとそんな強い意思こそが大事なのかもしれない。つよくしなやかであること、そんなに簡単でもなく、遠くむずかしくもない理想を心のどこかに持つこと。そんな意思が世界を少しずつやさしくする。
「誰かに/なにかにしゃべること」と同時に、この映画には大切な対話がたくさん描かれている。話すことと聞くことの交差する合間。そんないくつもの忘れられないシーンがある。時折やってくる、日常にいながら現実からふんわりと5センチほど浮かぶような演出や「ぬいサー」の部室の暖かな西日のような明かり、そしてまるでことばを語るようなひとつひとつの雑音の息遣いもとても印象的だった。古い扉の開く音やぬいぐるみの肌が擦れる音がどれもとても近くで、その場所がすぐそばにあるようだった。
この映画を観た日の夜、色とりどりの自分の部屋のぬいぐるみたちのなかから、『かいじゅうたちのいるところ』のマックスのぬいぐるみを手にとり、ゆっくりとはなしかけてみた。恥ずかしさのせいなのか、小さくてか細い声が出て、そのまぬけさに思わず笑ってしまう。モンスターや動物がモチーフのキャラクターではなく、人であるマックスのぬいぐるみを手にとったのも、照れや気恥ずかしさのせいかもしれない。映画の真似をしてイヤフォンを耳に挿してぬいぐるみに話しかけてみる。不思議とさっきより恥ずかしさが薄まって、ぽつりぽつりと僕はしゃべりだす。誰かの会話を聞いてしまわないように、というやさしさは、自分がしゃべりやすいようになるというやさしさでもあることに、はっとする。ぬいサーのみんなのようによどみなく、まるで友達に電話をかけるようにしゃべりかけられるようになるにはもう少し時間がかかるかもしれないけれど、少しずつでも僕はやさしくなりたいと思うのだ。
あのオレンジ色の明かりのミスタードーナツは改装してきれいになって、よく行っていたパン屋さんや出町柳の王将も閉店してしまった。遠くで変わっていく街のことを想うと少し胸の奥が動く。けれど、誰かが出ていった部屋には誰かがあたらしく暮らしはじめる。ぬいサーには今年も新しく誰かが入部するだろう。街も暮らしも社会も、僕たち自身も変わっていく。止まっているように見える川も動き続けている。『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』はそんな時間の流れのなかで変わりながら、同時に変わらずにあり続ける「安心の場所」だと思う。多分この先も全然大丈夫じゃない世界にはこんな場所が必要なはずなのだ。

- moon shaped river life
- 『ゴーストワールド』にまつわる3篇
- won’t you be my neighbor? 『幸せへのまわり道』
- 自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に 『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』
- “君”のように遠くて近い友達 『ウォールフラワー』
- あの街のレコード店がなくなった日 『アザー・ミュージック』
- 君の手がきらめく 『コーダ あいのうた』
- Sorry We Missed You 『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』
- 変化し続ける煙をつかまえて 『スモーク』
- 僕や君が世界とつながるのは、いつか、今なのかもしれない。『チョコレートドーナツ』と『Herge』
- この世界は“カラフル”だ。緑のネイルと『ブックスマート』
- 僕だけの明るい場所 『最高に素晴らしいこと』
- 僕たちはいつだって世界を旅することができる。タンタンと僕と『タンタンと私』
- 川むかいにある部屋の窓から 君に手紙を投げるように


