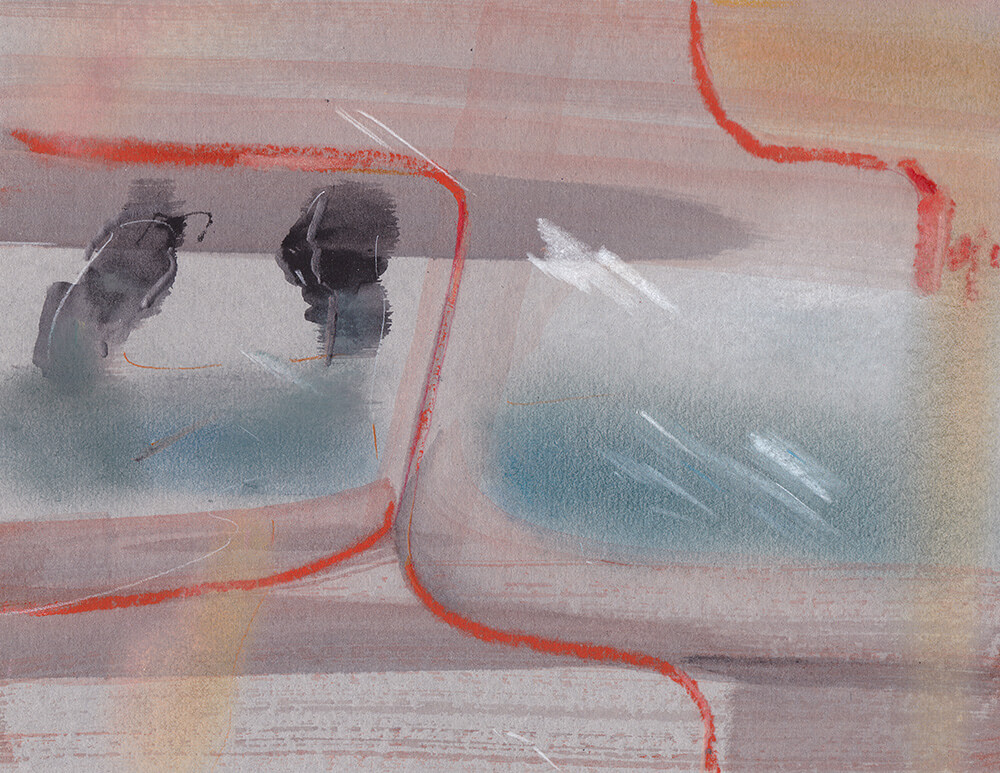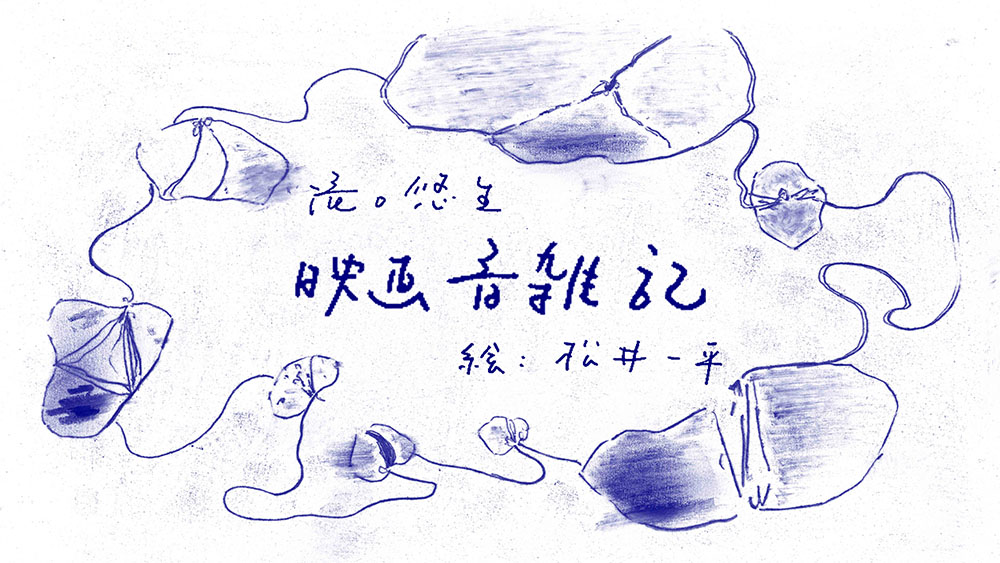
子どものころの記憶のなかで、いま小説を書いていることに深く関係すると思えるものがある。何歳くらいだったかはっきりわからないが、朝の布団のなかで台所から聞こえてきた大人たちの話し声だ。
おそらくそれは祖父の家で、夏に親戚たちがみんなで泊まりに来て、おじやおば、いとこたちと広間に布団を並べて眠った。朝になって、まだ子どもたちは寝ているなか、自分ひとりが目を覚ました。障子を隔て、廊下の奥の台所では大人たちがなにかしゃべっている。内容は聞きとれないが、そこには大人たちが大人たちだけで会話するトーンがある。なにがどう違うのかはわからないけれど、もし子どもの自分がその場にいたなら大人たちはあんな声では話さないのだ、ということはわかる。
その記憶を忘れずにいるのは、この世界についての認識がはじめて揺らいだ瞬間だったからではないかと思う。それまでは、自分の見えるものや聞こえるもの、自分のいる場所だけがこの世界だったけれど、大人たちはまだ寝ているはずの自分をよそに、自分とは関係のない会話をしている。大人たちの声で。たぶんこのときに、私はもし自分がこの世界にいなかったら、という可能性をぼんやりと考えたのではないかと思う。
この不在の感覚が、小説に通じる。
小説は人間がさまざまな不在について想像するためのひとつの方法だ。言葉を用いることは、どんな形であれ、自分のいない場所の、自分ではない誰かに向けて、なにかを届けようとする意志から切り離せない。
小説を読んでいると、この、子どものころに布団のなかで誰かの話し声を聞いている、という場面にときどき出会う。そのたびに自分の記憶も呼び起こされるのだけれど、もしかしたら多くのひとが子どもの頃に同じような瞬間を経験し、その後も記憶にとどめているのかもしれない。

『ムーンライト』の第一部は、主人公のシャロンが「リトル」と呼ばれていた子ども時代の話だ。薬物中毒の母とマイアミの貧困地区で暮らすシャロンは、あだ名の通り小さな体で同級生たちからいじめられている。いじめっ子から身を隠していた廃屋で、シャロンはフアンに出会う。ドラッグの売人であるフアンは、シャロンを危険地区から家に送り届けようとするが、シャロンはなにを訊かれても黙っている。母のいる家に帰りたくないのだ。仕方なく車に乗せて自分の家までシャロンを連れてきたフアンは、待ってろ、とシャロンに言い置き、恋人のテレサを呼びに行く。
玄関から出てきたテレサとフアンが、車の外で話している。その声がドアの閉まった車内にもほんの少し届く。自分の処遇について話す知らない大人ふたりを、シャロンは不安そうにうかがっている。自分の理解の及ばない事情について言葉が交わされているが、彼が聞いているのはその言葉ではなく、大人同士の会話のトーンだ。
フアンとテレサは、黙り続けるシャロンに無理に話すことを求めず、ひと晩家に泊めてやった。彼らは、彼のその後の人生に大きな影響を与えることになる。不安と混乱のなかにあった幼いシャロンにとって、沈黙を許されることは、彼の声に耳を傾けてくれることときっと同じだった。
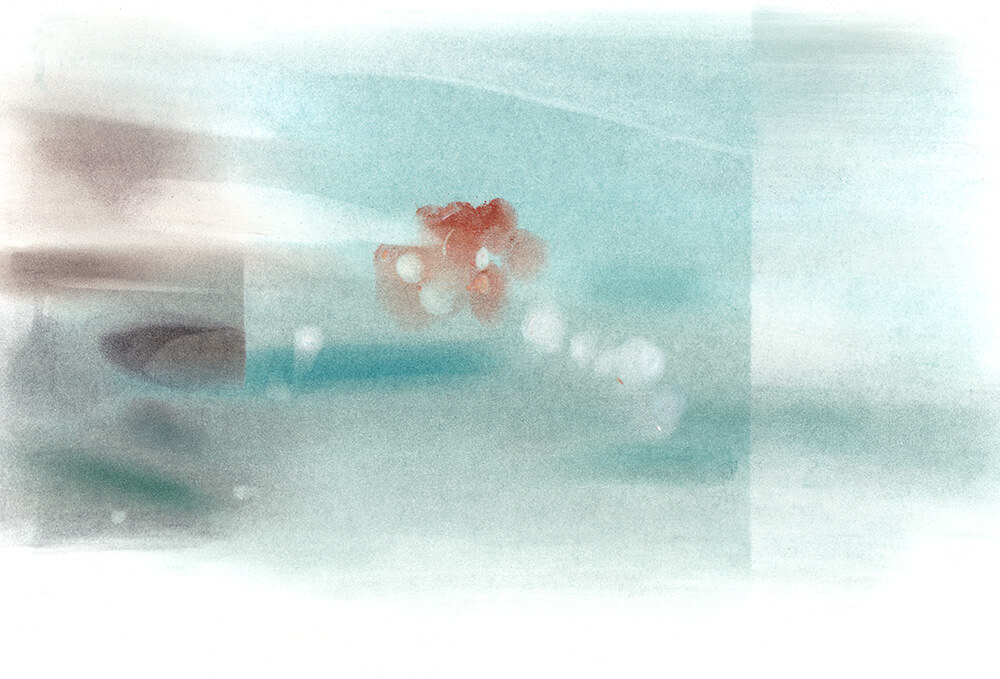
子どもの頃には未知のものだった大人たちの会話は、当然ながら成長するにつれてだんだんと理解が及ぶようになる。そして自分もいつの間にか、大人の話し方をするようになっていく。複雑な文脈を言葉に織り込み、大人同士のやりとりにおけるマナーとトーンを自然と使いこなすようになる。
そんな自分の声を、どこかで子どもの自分が聞いているような感覚におそわれることがある。そのとき、自分の声は、目の前の話し相手だけでなく、いまはもういない、かつての自分にも向けられる。
第二部、第三部と映画が進むにつれ、長じたシャロンを捉えたいくつかの場面では、彼の発する、あるいは彼の聞く声が映像とずれて、フラッシュバックのような印象を観る者に与える。まるで別の時間から届いたみたいな、突然思い出されたみたいな声。
自分の過去もまた、自分の言葉の宛先となる大切な不在のひとつなのだ。