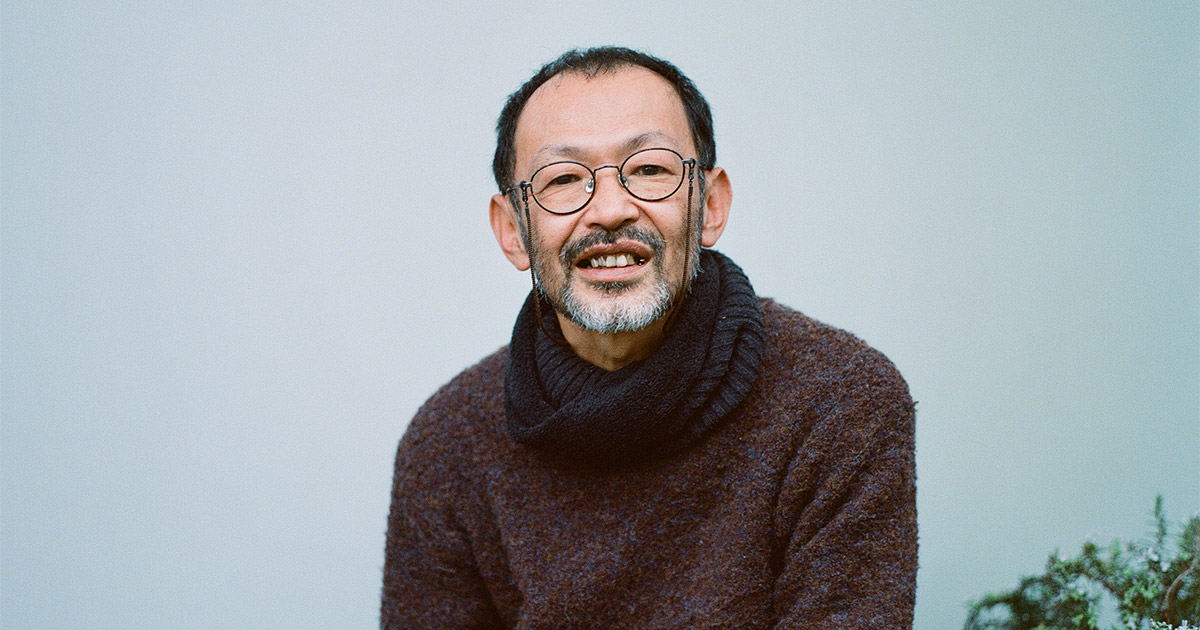目次
「大作映画の縮小版」ではない
インディーズ映画をどう撮るか?
― 「誰のものでもなく、誰のものでもある傷をつくっている」ということでしたが、越川監督にとって12本目となる長編監督作である『水いらずの星』を撮り終え、「映画づくり」についてどんなことを感じていますか?
越川 : 映画は自意識なんかじゃつくれないのではないかと思います。芝居も自意識なんかじゃできない。自意識なんかいらないんです。僕自身の自意識も、正直言って邪魔だと思います。
― なるほど。脚本だとどうですか?
越川 : やっぱり、いらないと思います。それこそ若い頃に自意識で書いていた頃は、もう自分の書いた字を見るのすら嫌でした。字には、自分の体の歪みが直接的に現れていて、自家撞着を起こしていたから。原稿用紙に1行書いてはそれを破って。
最後はゲーゲー吐いて、体がクタクタになってはじめて、自意識から離れ、ようやく諦めて2行目が書ける。それがわりと書けるようになったのは、ワープロを導入してからです。文字がどんどん物質化して、自分から離れていくからですが。

越川 : 言葉は自分じゃないんですよ。私は言葉ではできていない。言葉には言葉としての在り方があって、書いた瞬間、僕から離れていく。僕じゃないものになっていく。ワープロやパソコンのおかげでやっと、自分の「内面」と「書くもの」の自家撞着から少しは離れられたと思います。
― フォントの文字によって自意識から救われたと。面白いですね。
越川 : 最近、石川淳(※小説家、文芸評論家、翻訳家)をよく読んでいるんです。彼によると、何が小説を書かせているのかといったら、「ペン先」だと。これはアラン(※フランスの哲学者)の言葉だそうですが、書くっていうのは、ペン先と一緒に考えることだと。要するに、こういうふうなことを表現しようって、あらかじめ作家の頭の中で完璧にできあがっているんであれば、書く必要ないって言うんです。
もし「私が書いてる」って言うのなら、それは自意識なんだと思います。でも別に、私なんかどうでもいいと思うんです。「私が書いてる」とか「私が演じてる」って思う時点でまだダメなんじゃないかと思ってしまいます。そうではなく。ペンとともに考える、というところが大事なのではないかと。
だから、それがいいかどうかはわかりませんけど、僕は演出するとき、自分のコントロールが効かなくなるように演出をしています。コントロールできなくなるようにコントールする、というのか……。

― コントロールが効かないように?
越川 : 上手く言えませんが、自分が次どうなるのかわからなくなったらOKというようなことです。あえて俳優も自分も、どこに向かっているのかわからなくなるようにコントロールする。
― 「私が監督してる」っていう表現も、越川監督にとっては成り立たないってことですね。
越川 : そうです。10人から10人、40人なら40人のクルーが集まり一緒に仕事をすることで、映画がある方向に伸びていこうとするわけです。僕はこれをまるで植物が育っていくみたいに、とにかくどこまでも伸ばしていったらどうなるんだろうと、いつも考えています。
設計はします。しかし、現場はもっと有機的に動いていきます。それが、人が集まって一緒に仕事をするということの意味だと思います。自分が机上で考えた青写真に合わせてつくるのではなく、作品自身が伸びたい方向にどこまでも伸ばしていく。それは、「自分がつくっている」ということではないと思います。つくりながら、絶えず発見していく。そういうスリリングな現場をつくりたいと思っています。
― 監督として、あるいはプロデューサーとして、どうやって現場をモチベートしていますか?

越川 : いや、そんな難しいこと考えてないです(笑)。基本は、みんなが楽しかったらいいと思ってる。つくっている人間が楽しくなかったら、観る人も楽しくないはず。たとえば料理店だって、「まずいな」と思ってつくったものを出すわけにいかないでしょう。それと同じです。
そのためには、映画的な課題、あるいは演劇的な課題が必要だと思います。意欲的な課題を設定できれば、現場は楽しいと思うんです。「つくるのが面白いな」っていう課題をつくりだす。こういうつくり方をして、つくりながら、みんなで発見し続けていければいいと思っています。つくりながら発見するって楽しくないですか?(笑)
― 人と人の間に入ることもやっぱりありますか。
越川 : というか、仕事ってそれしかないですよね(笑)。
― 越川監督はプロデューサーとして、青山真治監督の『路地へ 中上健次の残したフィルム』(2001)、足立正生監督の『テロリスト 幽閉者』(2007)、タナダユキ監督の『赤い文化住宅の初子』(2007)、ヤン・ヨンヒ監督の『かぞくのくに』(2012)などに参加してきました。ご自身の監督作も含め、日本でインディーズ映画をつくることについて、思いを教えてください。
越川 : もちろんすべての現場を知っているわけじゃないのですが、基本的に、日本にはインディーズ映画をつくる基盤というものがない。だから、自分もそうですが、どうしても「大きい映画の縮小版」になるという発想しかできないと考えています。
― 越川監督自身にもそういうジレンマがありますか?
越川 : あります、あります。それは、僕ら日本人はネオレアリズモもヌーヴェル・ヴァーグも経験していないってことなのかもしれない。要するに、低予算で撮るノウハウや発想が乏しいのではないでしょうか。
エリック・ロメールのように、たとえば5人のクルーしかいなかったとして、僕らにあんな映画が撮れるかといったら、NOだと思うんです。あるいはフレデリック・ワイズマンみたいな映画のつくり方ができるのかといったら、それもNOだと思う。
― それは基盤がないから。
越川 : もちろん、誰もがそうだというふうに言うつもりはないんです。でも、「大きな映画の現場ごっこ」になりがちだなと思う。撮影所でやっているようなやり方を踏襲しようとしたら、絶対に人数がいなきゃ無理なんです。
だからプロデューサーをやっていても結局、「もっと人数が要るんじゃない?」という話になりがちです。本当は予算の少なさを、表現として逆手をとって豊かなことができればいいんですが……。
やっぱり、5人のクルーと40人のクルーでは、映画のつくり方も表現自体も自ずと違うものになると思うんですよね。それを考えないといけないんじゃないかな。これは別にどっちがいいとか悪いとかっていう話では全然ありません。エリック・ロメールの最小人数のクルーで撮った映画と、ハリウッドの超大作をその物量で比べたってほぼ意味がない。3ピースバンドとビッグバンドを比べたって意味がないのと同じです。ハリウッドのやり方で低予算の作品を考えても、「それはできないし、予算が足りないよね」って話です。予算の大きな映画を撮ることは目標ではないのだと思います。

― そうしたいと考えてしまう人が少なくないってことですね。
越川 : 僕自身も含めてですけど、どうしたってそう考えてしまう部分はあると思います。ただそうなると、いつでも人は足りないし、いつでもお金は足りないし、いつでも日数は足らない。
― どういうふうにそこを乗り越えていますか?
越川 : まずは台本をそうつくるってことだと思います。あとはなんでもないところに美しさを見出せるかどうか、でしょうか……。たとえば、今僕らがいるこの部屋の隅とかでいいと思うんです。それを「こういうところじゃなきゃダメだ!」って言ったら、「そりゃ予算が足りないね」ってなりがちです。諦めろっていうんじゃなくて、それをとことん追求できるかどうか、ということだと思います。
― たとえば黒澤明監督が『どですかでん』(1970)で、家の影を墨で地面に書いたみたいなことになりかねない(笑)。
越川 : たとえばホン・サンス監督って、そこがうまいんじゃないでしょうか? ホン・サンス監督のミソは、ありふれた街角を美しく撮れるということでもあると思います。そして、美しいものは壊れるというプロセスをあらゆるレベルで映し続けるところです。どこで撮っていても、最初に綺麗な構図があって、カメラが動くことによって壊れる。内容的には「誰かを愛していた」という美しい理想が崩れ、誰かが泣く。そういうことを劇中、いろんなレベルで何度も繰り返すところが、彼の映画のすごさだと思います。

越川道夫監督の「心の一本の映画」
― 最後に監督の「心の一本の映画」を聞きたいです。それこそ、「映画というより傷をつくっている」と思える作品を教えてほしいのですが。
越川 : 映画を撮る前に必ず観る作品があって、フィリップ・ガレル監督の『孤高』(1974)なんです。
越川 : 僕が1997年にスローラーナーという映画会社を立ち上げたときに、ガレルさんの作品をどれか一本を配給しようという話になり、ご本人から「お前はどれがいいと思うんだ?」って聞かれて。「『孤高』じゃないか」と言ったら、「俺もそう思う」と。
― 『孤高』は音のないスクリーンの中で、フィリップ・ガレル監督自身が愛した二人のミューズ、ジーン・セバーグとニコを映し出す、実験色の強い一作です。越川監督にとって、思い入れが強い作品なんですね。
越川 : ガレルさんの映画はよく観ます。彼はいつも「傷」に向き合っていて、それが映画を超えしまう。それに、彼は撮っている対象が大好きなんだと思います。だから、『孤高』を観ているといつも(意識が)飛ぶんです(笑)。誰が観ているのかわからなくなるんです。ガレルさんが自分でカメラを回し、ジーン・セバーグやニコを見つめていて。最後にジーンの唇が「フィリップ」って動いているのも見える。
見つめ続け、画面の向こう側から見つめられ続け、最後にはこれを僕が見ているのか、ガレルさんが見ているのかわからなくなる。さらに、僕が誰を見ているのかもわからなくなる。僕が彼女たちを愛していたのでないかと。監督として、そんなふうに撮影対象を見ることができなければダメだとも思うんです

― 自分の恋人たちを映していながら、自己表現とは違う領域に行ってしまう。すさまじいですね。
越川 : ガレルさんは自分の恋人とか、元恋人とか、家族とか、すごく近しい人をキャスティングする。でもたしかに、自己表現とは違うところに彼の作品がある。なんか突き抜けいる気がするんです。
あと近年観た中では、『アネット』(2021)でしょうか。
― 『アネット』はレオス・カラックス監督の最新作。スタンダップコメディアンのヘンリーと、オペラ歌手のアンの間に、非凡な才能をもった娘アネットが生まれたことで巻き起こるカオスを描いた、奇想天外なミュージカル映画です。
越川 : レオス・カラックスって初期はあれだけ美学的だった人だけど、どんどん映画が下手になっていくというか。なんでしょう……、彼自身の切実さが、映画を食い破ってしまった気がします。切実っていうのは、「人生に関わる」と言い換えられるかもしれない。
大変な正直者だと思うんですよ。だって、最初に自分と自分の実の娘の姿を映して、「さあ始めるよ(So May We Start)」と言って映画を始め、最後に、娘のアネットに父親のことを断罪させて終わるって……、恐ろしいことだよね。
『ポーラX』(1999)も好きなんですが、物語上でいろいろ起きてぶっ壊れちゃうというのではなく、彼の切実さが内側から映画を食い破ってしまっている感じがして。

― 映画を食い破る感じは劇中においてメタなレベルで起きているけど、その出発点はカラックス監督自身の生活実感から来ているんじゃないかと考えているんですね。
越川 : そうですね。レオスさんにとって生きることと、映画をつくることが不可分になってきているんじゃないかと思うんです。もともとそういう人だとは思うんですよ。だけど昔みたいに、美的に均整が取れたところでは、もうできない。(撮影監督のジャン=イヴ・)エスコフィエが亡くなってしまったこともあるのかもしれない。今は、なんか「下手くそ」な映画になってると思うんです。だから、とてもいい。単に下手くそなわけじゃなくて、そこに生きることに対する切実さみたいなものを感じます。
― 映画と人生が不可分なのは、ガレル監督も同じですよね。
越川 : フィリップ・ガレル監督は「心臓の代わりにカメラを持っている」と言われた人です。別に、私小説とかそういうことではないと思います。ホン・サンス監督もですけど。
僕はやっぱり配給の人間としては、ガレルさんの映画が好きで上映したくて独立したようなものだから…。シネマ・キャッツ時代に、『愛の誕生』(1993)を観てしまって、これをどうにか劇場でかけたいと思ったけど実現できず、ビターズ・エンドにやっと、なんとか3本買ってもらえた。そのあとが『孤高』。
― ある意味での正直さに惹かれるんですね。
越川 : そうですね。それ以外にもジャック・リヴェット監督の作品だったり、もちろん好きな監督はいっぱいいますが、自分自身に関連する映画となると、『孤高』と『アネット』、この2作を挙げたいです。