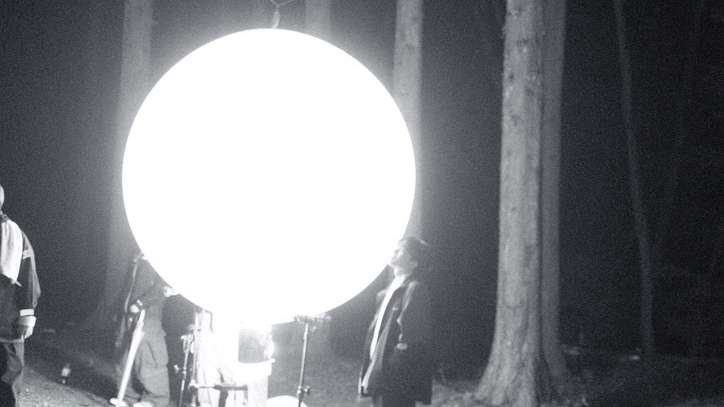目次
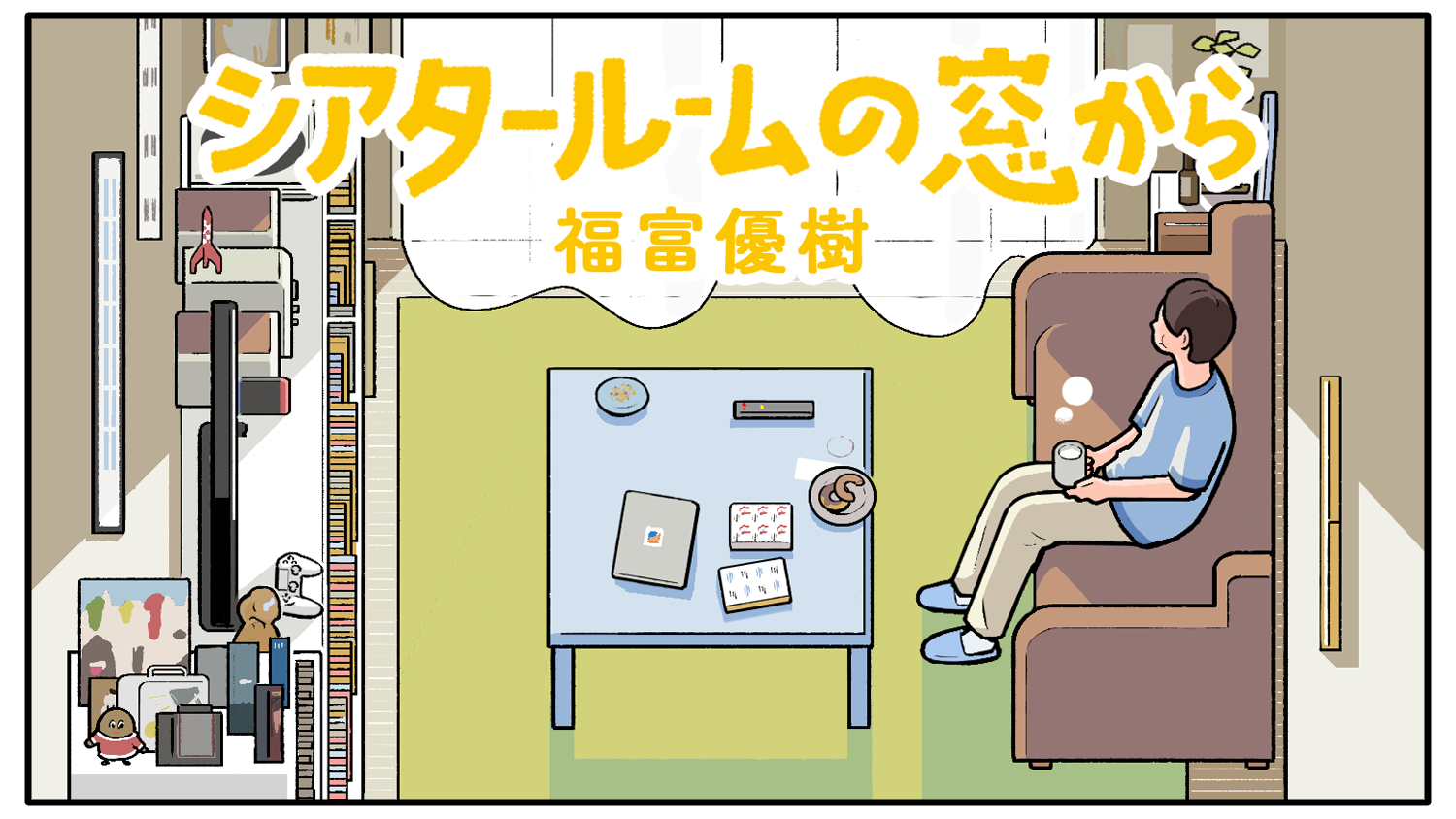
♯1
待ち合わせ場所に少し遅れてやってきた友達の着ている真っ青なパーカーがやけにかわいかった。2012年のちょうど今くらいの時期だったと思う。「ゴーストワールドっていう映画をモチーフにしたイラストなんですよ。」と彼は教えてくれた。それが『ゴーストワールド』という映画を僕が意識した最初の瞬間だった。
Hi, how are you?という名前で音楽をやっているハラダくんとは、その年の夏の終わりにイベントで共演して仲良くなった。ハラダくんには、観てきたテレビや聴いてきた音楽が近い人に感じる少し特別な親密さがあった。そしてそれと同じくらい、自分が知らないものをたくさん教えてくれるワクワクする魅力をもった友達でもあった。同じ京都市内ではあっても通っている大学のエリアが全然違ったので、お互いがお気に入りのブックオフやレコード屋さんやごはん屋さんを紹介しあうのがとてもたのしかった。僕は「グリル宝」という、名物のチキンコルドンブルが美味しすぎる洋食屋さんに連れていき、ハラダくんは「キッチンパパ」という、お米屋さんを奥に入っていくと、なかがレストランになっているというなんとも珍しい洋食屋を教えてくれた。ふたりともぼろぼろの自転車で、京都の街を上がったり下がったりした。ふたりともレンタルビデオ屋さんがとても好きだった。
「トランスポップギャラリー」に連れて行ってくれたのもハラダくんだった。出町柳駅から百万遍の交差点へと向かう、何度も何度も通った道にひっそりとたたずむギャラリースペースと併設のショップは、僕がそれまでに触れたことがなかったけれどずっと探していたような眩しいくらいに最高な場所だった。スパイダーマンやX-MENといったいわゆるアメコミとは違うオルタナティブとしてのコミック。その頃の僕は「グラフィックノベル」という言葉も知らなかったけれど、ここにあるのは自分が探していたものだ、と鼻の奥が暑くなるくらいに興奮した。カラフルで雑多な棚の中に、EelsやYo La Tengoといった大好きな海外のバンドのアートワークで知っていたエイドリアン・トミネのグラフックノベルが並んでいるのを見つけた瞬間、何かの答え合わせができたような気がした。トランスポップギャラリーは、『ゴーストワールド』をはじめとしたダニエル・クロウズの作品やエイドリアン・トミネ、クリス・ウェアといったアーティストのグラフィックノベルの日本語版を出版しているプレスポップが運営しているギャラリー兼ショップのスペースで、ここで出会ったものたちがこの少しあとに僕を先へ先へと導いてくれることになるのだった。その日はたしか『ゴーストワールド』の原作とイーニドとレベッカがプリントされた缶バッチセットを買ったはずだ。そのあと予定があるというハラダくんと解散した僕は、全速力で川端通を駆け上がって部屋に帰って、一気に最後まで読み切ったのだった。薄いブルーと黒で描かれた、不安とあてどない期待と生の物語。小綺麗なモールやチェーンのコーヒーショップのなか、人たちはどこかうつろな表情を浮かべて、それでも生きている。
ある日、ハラダくんは「高校のときにつくったうたがあるんすよ」といって「ゴーストワールド」という曲を歌ってくれた。夕方、フライヤーや雑誌やレコードで溢れたハラダくんの部屋でぼろぼろのアコースティックギターとちょうど部屋で友達に聞かせるときの音量の歌。やけに感動してしまった僕はHomecomingsも『ゴーストワールド』の曲を作ることを約束した。いつのまにかぼくたちのなかで『ゴーストワールド』というものは共通のキーワードのようになっていたのだった。
映画版の『ゴーストワールド』を観たのは、そのすぐあとだったと思う。廃盤でその頃の僕ではなかなか手が出ないくらいのプレミア価格(といっても5000円くらいだったと思う)で見つけた中古DVDを思い切って買ったのだった。あの頃のブックオフ三条駅ビル店はDVDもCDも本もとにかく品揃えが充実していて、僕たちのなかでは聖地のようなお店だった。受験のために初めてひとりで京都に来たときに、食事代として両親から持たされていたお金を使って『ヴァージン・スーサイズ』のDVDを買ったこともあるその魔法のようなブックオフで、『ゴーストワールド』のDVDを買った。原作では重たい影がよぎっていたラストが少し違ってみえるような表現になっていて、そのラストカットが胸にいつまでも張りついて離れなかった。市営地下鉄の終点、京都タワーと同じ標高だという、京都のはずれの方の小さな町での暮らし。大学の卒業が近づいてきたことの焦りと音楽を続けていけるかもしれないという不安定でも少しだけ光が視える未来。ひとりぼっちでごちゃまぜになっていたあの部屋で僕は、これは今、出会うべくして出会った映画なのかもしれないと思った。
しばらくして僕たちは「Ghost World」という曲を作った。一度だけライブで演奏しただけでボツになったバージョンのものを経て、曲として完成したものが収録された『Somehow Somewhere』というアルバムは2014年の12月24日にリリースされた。同じ日、Hi, how are you?は「ゴーストワールド」が入った『にこいち白書』というアルバムを出した。あの日の何気ない約束は少し時間をかけたぶん、ひとまわり大きくなって叶うことになった。
♯2
サヌキナオヤさんのイラストにはじめて出会ったのは、たまたまレコード屋さんで手に取った『ジオラマ』という自主制作の漫画誌でのことだった。そこに収録されていた、サヌキさんによる「明日、居なくなる」という短編がとにかく素晴らしくて、本当に何度も何度も読み返した(今でもときどき本棚から取り出して読むことがある)。日常のなかの別れのシーンを、そのなにげなさもかけがえのなさも同時に捉えるその温度感にたまらなく感動してしまった。その出会いからほどなくして、大好きなシャムキャッツというバンドのシングルジャケットをサヌキさんが手掛けることになった。早朝の空とトラックだけのごくごくシンプルなそのイラストにはトランスポップギャラリーに並ぶあのグラフィックノベルの作品たちの匂いがあって、感動と同時に自分がやりたかったことを先に実現されてしまったような少し悔しい気持ちにすらなった。それくらい素晴らしいイラストだったのだ。間髪入れずにリリースされた『AFTER HOURS』というアルバム(このアルバムのサヌキさんのアートワークも本当に素晴らしかった)に伴ったツアーに僕たちも参加したことをきっかけに、少しずつ外堀を埋めるようにHomecomimgsとサヌキさんの距離は近づいていき、僕たちのはじめてのバンドロゴを依頼したことで、現在まで続く関係がはじまった。
はじめてサヌキさんと打ち合わせをしたのは新宿のロッテリアだった。2階の角の決して広くはないテーブルの上には、サヌキさんが家から持ってきてくれたグラフィックノベルの本が海のように広がっていた。ゆっくり話をするのがはじめてだった僕とサヌキさんはものすごい勢いでいろんなことを喋った。音楽のことや映画のこと、グラフィックノベルのことや京都のこと。サヌキさんも学生時代を京都で過ごしていて、僕と同じようにトランスポップギャラリーの扉を開いたことでなにかがはじまったひとりだった。そして、やっぱりここでも『ゴーストワールド』がキーワードになるのだった。それから僕たちは何枚ものアルバムやポスターを一緒に作った。サヌキさんの作業部屋はトランスポップがまるごとやってきたような部屋で、東京でライブがあると、よく泊まりにいっては朝までいろんなアイデアを試してはなにかを作り出した。そのときそのときでふたりが興奮したいろんなカルチャーをヒントにして、自分たちにしかできない、自分たちが大好きなものを織っていく。それはときに音楽だったり映画だったりNetflixのドラマだったり、たまたまそのとき食べていたカップのアイスクリームだったりした。そしてどんなものを作るときにも、ふたりとも、あのトランスポップギャラリーのカラフルな棚に戻る瞬間が、あの棚を目指す瞬間があるのだ。
Homecomingsとサヌキさんとで共催している映画と音楽とzineのイベント『New Neighbors』 の、現時点で唯一の東京での開催回と、閉館してしまった京都みなみ会館での最後の回では、『ゴーストワールド』を上映した。グッチーズ・フリースクールをはじめとした様々な人に助けてもらいながら、版権を取り、字幕をつけるところから準備をしていった。僕たちにとって特別な映画だから、という理由が物事を進めていったように思う。それはどこか、使命感のような“落とし前”のようなもの にも近かった。
サヌキさんが引っ越し祝いでプレゼントしてくれた、クリス・ウェアがプレスポップに描き下ろしたポスターは今もこの部屋のリビングのど真ん中、シアタールームの特等席に飾られている。ソファにだらんと横たわりながらサヌキさんと深夜の長電話をする、そんな大切な時間を見守るように。
♯3
小さな頃から、「いつかこの町を出ていく」ことばかり考えていた。ミュージシャンになるか、小説家になるか、お笑い芸人になるか。小学生から中学、高校と進むにつれて、それがレコード会社のスタッフになったり、書店員になったり、編集者になったり映画のPRの仕事になったりと現実の色が混ざったパレットに変わっていったのだけど、それでも、どんなパターンの夢を空想しているときも、僕はあの町を出ることばかりを考えていた。お母さんが折に触れて「せっかくやりたいことがたくさんあるんやから、絶対この町から出たほうがいいよ」と言ってくれていたことも影響していると思う。思えば音楽も小説も好きになるきっかけはいつもお母さんからもらっていた。
放課後の海を眺めているときや、あたり一面を田んぼで囲まれた細い道を自転車で漕いでいるとき、ときたま僕はひどい閉塞感で胸が不安になった。大きな図書館とTSUTAYAは音楽や映画や小説を通して僕に「どこか」を見せてくれた。「どこか」を見れば見るほど、知れば知るほど、僕もそこに近づいていっているように感じた。高校に入って彩加さんと出会ってからはその「どこか」で自分がなにになりたいか、が明確になっていった。彩加さんの歌には、はじめからそう思わせる魔法があった。イーニドとレベッカは同じバスに乗ることになった。
『ゴーストワールド』を上映した渋谷のTOEIと京都みなみ会館はどちらも、今はもうない映画館になってしまったし、あの町のTSUTAYAもいつのまにか閉店してしまっていた。あの頃のようにブックオフで何時間も過ごすようなことはなくなってしまった。思えば、『ゴーストワールド』を上映する際のばたばたの中で、資料として使っていた僕のDVDがどこかへ行方不明になっていたのだけど、なんとなくそのまま放ったままになっている。つまり少なくとも4年間は一度も観直すことがなかったということだ。
「ここじゃないどこか」だった京都の街を出て、今は東京で暮らしている。京都を出る最後の日、イーニドの気持ちになってみたくて、昼行チケットをとってバスで街を出ることにした。大型バスのりばの八条口から京都南インターまでの間の景色は特に思い入れもなくて、センチメンタルになるようなこともなくあっというまに窓の外は高速道路のスピードで流れるように後ろへと流れていった。案外イーニドもそんなふうだったのかもしれない。
僕らはいくつかの季節や何度かの引っ越しを経て、いつのまにか大人になった。久しぶりに『ゴーストワールド』を観て、イーニドやレベッカが離れていくことはないけれど、シーモアの気持ちに寄り添いながら観ている自分がいることに気がつく。「なんとなく分かる」からもう少し肌で彼の寂しさを感じるようになった。シーモアはレコードに囲まれて暮らしながら、いつまでも新しい自分のお目当てのレコードを探すことに夢中になっている。「探しているレコード」という存在を探している、というような感覚はわかってしまう自分がいる。この1枚さえ手に入れば、どんなに幸せだろう、と甘く夢見るレコード。それを、どれほどの幸運で手に入れたとしても、シーモアや僕たちの日々は大した変化もなく続いていくだろう。そんなことはもう百も承知なのだ。ここがゴーストワールドだということも。誰もが“ここじゃないどこか”へ行けるわけではないということも。
ハラダくんは地元にもどって音楽を続けている。Homecomingsは10年目を迎えた。今でもギターのストラップには『ゴーストワールド』の缶バッジがついたままだ。今でもふとしたときに「ここじゃないどこか」のことを考えるときがある。それはきっと変わらない町の生活に飽きるとかそんなことではなく、自分の変化によるものが大きいのだろう。僕にとって『ゴーストワールド』というのは海のそばのあの町のことだったり、京都の街のことだったり、大きな川沿いのこの部屋のことであり、そして自分のなかの世界のことだったりする。イーニドはバスの窓からどんな景色を観たのだろうか。

- two sea, your color 物語の終わりはハッピーエンドがいい
- moon shaped river life
- 『ゴーストワールド』にまつわる3篇
- won’t you be my neighbor? 『幸せへのまわり道』
- 自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に 『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』
- “君”のように遠くて近い友達 『ウォールフラワー』
- あの街のレコード店がなくなった日 『アザー・ミュージック』
- 君の手がきらめく 『コーダ あいのうた』
- Sorry We Missed You 『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』
- 変化し続ける煙をつかまえて 『スモーク』
- 僕や君が世界とつながるのは、いつか、今なのかもしれない。『チョコレートドーナツ』と『Herge』
- この世界は“カラフル”だ。緑のネイルと『ブックスマート』
- 僕だけの明るい場所 『最高に素晴らしいこと』
- 僕たちはいつだって世界を旅することができる。タンタンと僕と『タンタンと私』
- 川むかいにある部屋の窓から 君に手紙を投げるように