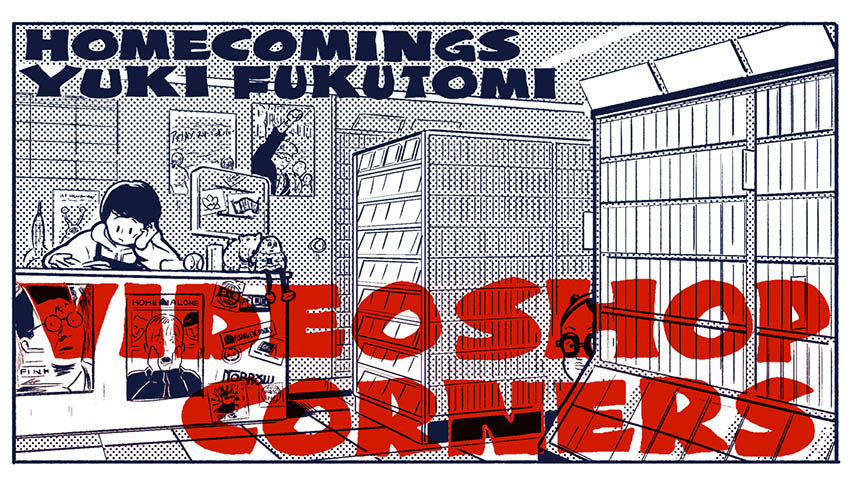目次

欠けているところを認めあう
― 本作は倉科さんの地元・熊本が舞台で、劇中では路面電車が走る熊本市内や深緑の阿蘇など、熊本の美しい風景がたくさん映っていました。個人的にも熊本に憧れがあって、勝手に「No.1オシャレ地方都市」だと思っています。
倉科 : そうなんですよ! わかっていらっしゃる!
安達 : 実際に熊本で撮影したのは私だけだったんですけど、とても良いところでした。
― 撮影は、暖かい時期だったんですか?
渡邊 : 8月くらいでしたよね。
安達 : そうですね、結構暑くて。でもすごく素敵で、暑さが吹き飛びました。阿蘇山近くの、扉を開けると草原が広がる美術館(※)で撮影したんですけど、この世のものとは思えない景色で。
※…葉祥明阿蘇美術館(旧称:葉祥明阿蘇高原絵本美術館)。熊本で生まれた画家・詩人・絵本作家の葉祥明氏が、心の故郷“南阿蘇村河陽”の丘に建てた絵本美術館。絵だけでなく、草原の散歩コースなども楽しめる。
安達 : めちゃくちゃ気持ちよくて。撮影自体はバタバタしていたんですけど、私的にはゆったりした気持ちで過ごせたんですよね。本当に景色が美しかったです。
倉科 : 熊本は緑が豊かなんです。特に夏は青々としていて、本当に綺麗なんですよ。
― 出来上がった作品をご覧になって、帰りたくなられたんじゃないですか。
倉科 : 今も帰りたいです!
安達 : いつでも帰りたいもんね(笑)。

― 本作では、40代の書店員の灯、30代精神科医師の鹿乃子、そして20代のアパレルショップ店員の仁という、年齢や職業、セクシャリティの異なる3人が、愛猫と共に支え合って暮らしながら、自分たちらしい生き方を模索する様子が描かれています。3人の関係性を、みなさんは演じながらどのように感じていらっしゃいましたか。
渡邊 : じゃあ、僕から。
安達 : もう話す順番は決まっているんです(笑)。
渡邊 : 僕は最初からあまり違和感なく、共同生活がスタートできたんじゃないかなと思います。それは僕が演じた仁君の明るい性格もあるんじゃないかな。

― 彼自身は、自分のことを「何の才能もない」と言っていましたが、いつもほかの2人のことを良く見ていて、ムードメーカーみたいな存在でしたよね。
渡邊 : そうですね。ただ明るいだけじゃなくて、ちゃんと空気を読むみたいなところが、彼の良いところだと思います。
倉科 : 次は私の順番で(笑)。私は素敵だと思いました。3人は家族ではないけれど、それぞれにお互いが大切だと思える存在なんですよね。程よい距離感があるからこそ成り立つ、新しい形の暮らしだなと。
― 3人は熊本地震をきっかけに偶然出会い、「猫好き」の共通点を発見し、一緒に暮らし始めますね。
倉科 : 自分の気持ちのまま、一緒にいたい人と一緒にいるのは、すごく自由だなと思います。そうやって大切だと思える、心の支えになれるような人と出会えることもまた貴重なことですよね。そんな関係を育んでいけるのは羨ましいと思いました。

― 倉科さんが演じた鹿乃子は、灯に彼氏ができ、3人の生活が解消される可能性が出てきた際には、その寂しさを2人に言えずに押し殺してしまうなど、なかなか思っていることを話せなかったり、共同生活ではストレスがたまりやすいタイプなのかなと思いました。
倉科 : いや、鹿乃子さんは、ほかの二人に助けられているところが大きいと私は思います。彼女は精神科医で、仕事以外の面でも完璧な人に見えるけど、本当は激情型というか、激しいものを持っていて、でもそれを理性で抑え込んでいるところがあるのかなと、演じていて感じました。この激しさをぶつけてしまったらどうしようと思っていたりするような、意外と臆病なところがあるんですよね。
そうやって自分自身「ちょっと欠けているな」と思っているところがあるからこそ、二人が一緒にいてくれることで満たされる、自身が満ちていく感覚があるのかもしれません。
― 2人がいるから一人前になれる、みたいなところがあるんですね。
倉科 : ありますね。不器用だからこそ、2人との生活がすごく支えになっている。

― 40代で独身の自分自身について「ずっと誰にも認められていない感じがある。欠けたまんま、オトナになりきれていない」と言う、灯を演じた安達さんはいかがですか?
安達 : 現実的には難しいですよね、他人である3人が一緒に暮らすのは。でもこの作品のなかの3人は、認め合って埋め合うことで成立する関係だったんだと思います、奇跡的に。
― なるほど。
安達 : それぞれが欠けているところを持っていて、その欠けているところやまっとうじゃないと自分で思ってしまっているところ、そういうものを背負いながら生きている。
でも一緒に暮らしていると、部分は違えどもみんな欠けていて、「みんなそうなんだな」と思って安心できるし、その相手の欠けている部分が自分にとってはすごく愛おしくて愛せるし、相手が大切にしていることを、認めてあげられる。それぞれが欠けているんだけど、それでもいいよねって認め合える。そんな3人だったと思います。
― 「欠けているところを認めあう」というのは、難しい部分でもありますよね。相手の不足を責めたくなったりしてしまうこともあります。
安達 : 「もっとこうやってよ」みたいなね。

― この3人がそれを認め合えるのは、どうしてなのでしょうか。家族ではない、ほどよい距離があるのが良いんですかね。
倉科 : 尊重、じゃないですかね?
安達 : ね。血縁関係でも恋愛関係でもないけど、お互いを尊重しているからこそうまくいっている3人なのかなと思いますね。

不調はそのまま受け入れる
― 本作の主人公である灯は、年齢や未婚であることなど、まわりと違う自分に引け目を感じつつも、料理やネコとの時間、大好きな本など、「自分らしくいられる時間」も大切にしている人でした。

― そうやって「ご機嫌な自分」を大切に日々を積み重ねることで、人生の岐路に立った際も自分らしい決断をすることができるようになるのだなと灯を見て思いました。みなさんにも伺いたいのですが、普段自分らしくいられるために大切にされていることや時間はありますか。
渡邊 : そうですねー…。
倉科 : かっこつけてる(笑)。
渡邊 : (笑)。なんですかね。僕自身、っていうことですよね?
― そうです。
渡邊 : 僕はそこまでモチベーションが下がったり、調子が悪くなることはあんまりないかもしれないです。
安達 : そっかあ(笑)。
倉科 : 若いなあ(笑)。
渡邊 : そうですか?(笑)「やりたいことやっている」って気持ちが強いのかもしれません。
― いつも、自分がやりたいと思うことを迷いなく選んでいる自覚があるんですね。
渡邊 : そうですね、楽しいことが好きなんで、仕事も私生活も、楽しむことを目標にしてます。
― そのなかで、もし少し気分が乗らないようなときがあった場合は?
渡邊 : 地元の仙台に帰ります。友達と会って、リフレッシュします。

倉科 : 私は大きなことから小さなことまで、自分の心にちゃんと聞くようにしています。たとえば今日何食べようかと考えたときに、「期間限定だし、これを食べておこうかな」よりも、「今の自分が何を食べたいか」を聞くようにしているんですよ。意外と、自分で縛っていることって多くて。
― わかります…。
倉科 : この映画でも、いろんな場面で「すべき」がたくさん出てくるんですよね。私もいろんなことを「すべき」で考えていたときがあるんですけど、そうしたらいつのまにか、「あれ私、なにがやりたかったんだっけ?」ってわかんなくなっちゃって。だから、小さなことでも、自分にちゃんと聞きます。
あと、自分が不機嫌だったり調子が悪いなってときは「あ、今日調子悪いね」って認めてあげますね。「まあそんな自分もいるよね。でもみんなもたいして気にしていないと思うし、機嫌が良くなるまで自分で何か楽しいことを見つけようよ」と思って、スケジュールを見て未来のことを考えたりして。そうやって自分の心が「何にときめいて」「何に縛られているのか」を、明確にするようにしています。
― 調子が悪いときは、その自分をそのまま認めるんですね。

倉科 : はい。ちょっと意外と、ちゃんと鹿乃子ちゃんっぽいでしょ?(笑)
安達 : うん(笑)。
― 他にもなにかされていることはありますか。
倉科 : 身体を動かしますね。動くと本当に気分もよくなるので、少しでもいいから動くようにして。あと感情も出すようにしています。
― どんな風に?
倉科 : たとえば悲しいことがあったときとか、寂しいときなどはもう、大泣きしますね。映画を観て、「ウワ~ッ」ってわざと泣いたり。床をたたくくらい(笑)。
安達 : それは面白いね!
倉科 : 一人でお酒を飲みながら映画やドラマを観て、「もうヤバいこれ~」って言いながら号泣する(笑)。でもそれってすごく感情を出せるし、「オモシロ」に変わるじゃないですか。「ああいうときもあったな、昨日ちょっとオモロかったな自分」って。

渡邊 : 恋愛もののドラマや映画を観ながら、「なんでお前そっち行くんだよ!」って怒ったりもします?
倉科 : そこまで怒ったりはしないけど、ブーブーは言っている(笑)。「いやいや、絶対こっちやん!」って言ったり。
― 渡邊さんも映画を観ながら「ウワ~ッ」って泣いたり…。
倉科 : する?
渡邊 : いや、全然しないです (笑)。でも今ふいに思い出したんですけど、僕の実家は二世帯住宅で、おじいちゃんとおばあちゃんがいたんですけど、おじいちゃんは野球中継を観ながらめちゃくちゃ喋っていましたね。
倉科 : なに!? 私がお年寄りみたいにテレビに向かってしゃべっているって?(笑)。いいじゃん!
渡邊 : いや、素敵なことだなと (笑)。僕もやろうと思いました。
倉科 : 意外と感情は出す方がリフレッシュになるよ? スッとしているほうがキツい。
安達 : たしかに、そうかもね。

― 安達さんは、なにか大切にされていることはありますか。
安達 : 私は、心がそんなに乱れないんですよ(笑)。
倉科 : すごい!
― それは秘訣があるんですか。たとえば毎朝瞑想などされたり。
安達 : 全くないです(笑)。なんにもしていない。ストレスがたまっているんだろうなって身体の不調は感じるんですけど、気持ち的にはあまりストレスを感じていなくて。だから、身体の調子が悪くなってから「あ、ストレスだったのかな」って思うくらい。
― 心より身体が先に教えてくれるんですね。
安達 : そうですね。子どもがいるからというのもあると思うんですけど。やっぱり一緒にいて安心してもらいたいから、一定でいられる方がいいじゃないですか。無理をすることもなく普通に穏やかにいます。だから、あんまりないかな…。
― 「今日は調子が悪いな」みたいな日もないですか。
安達 : それはあるんですけど、そういうときは、「心の調子」じゃなくて、「体調が悪い」とき (笑)。だから、あんまりイライラもしないです。「今日はちょっと悲しい気分だな」ってときもあるけど、でもまあ、それはそれ、というか。大したことじゃないと思ったりして。
― 「そういうときもあるよね」と受け止められるんですね。その意味では、安達さんと倉科さんは少し似ているかもしれないです。
安達 : そうですね。あと灯のような「人生の岐路に立ったときの、自分らしい決断」に関して言うと、何か決める必要があるときは、たとえ決めたあとで後悔したとしても、「後悔も全部引き受ける」って覚悟すれば、そのことに心を乱されることはないと思いますね。

安達 : 後悔したところで、「だってそれはもうわかってたことだし、全部受け入れようと思って決めたんだから」と思えるから、「うわ~あれやっとけばよかった」とは思わない。「まあ、わかってたじゃん、後悔するって。でもやっちゃったから、いいか!」って思えますね。
― ずっとそんな風に、普段からあまり心が乱れることなく、決断するときも落ち着いていられたんですか?
安達 : あ、昔はすごく「気にしい」でした。「今日あの人とすれ違ったとき、ちゃんと笑顔を作ったかな?」とか考えたり。
― めちゃくちゃ気にしていたんですね。
安達 : そう、いろんなことを気にして生きていたんですけど、30代に入ってたくらいかな、なんにも気にならなくなりました(笑)。
― 年齢を重ねて、自然と変化してきたと。
安達 : 緊張して生きているよりも、自分がリラックスしてオープンマインドで生きた方が、周りの人も楽なんだなってわかってきたから。
仕事でも、キャリアの長さが自然と自分を助けてくれることも増えて、すごく自由に、楽になりましたね。

安達祐実、倉科カナ、渡邊圭祐の「心の一本」の映画
― 最後に、みなさんの「心の一本の映画」について伺えますか。
渡邊 : 僕はこういう質問にいつも『スカーフェイス』(1983)って答えています。
― アル・パチーノ主演の、マフィア映画ですね。
渡邊 : はい。男の格好良さ、みたいなものを学んだんですけど、「心の一本」って言うとちょっと別の作品をあげたいかもなと、いま思い始めています。「ハリーポッター」シリーズもなんども観てるんですが…これはちょっと思いついた方からでお願いできますか?
安達 : そうだね、そうしよう。
渡邊 : 倉科さん、もうあれですか、選択肢が上がっている感じですか。
倉科 : うん。
安達 : すごい!
― では、倉科さんからお願いできますか。
倉科 : 私は『gifted/ギフテッド』(2017)が好きです。天才な女の子と、その子を育てる叔父の話なんですけど、その叔父を『アベンジャーズ』にも出てる俳優さんが演じていて。
渡邊 : 『キャプテン・アメリカ』にも出ている人ですよね?
― 『gifted/ギフテッド』は『(500)日のサマー』や『アメイジング・スパイダーマン』のマーク・ウェブ監督がメガホンをとったファミリードラマで、叔父を演じているのはクリス・エヴァンスですね。
倉科 : そうです! 彼は『キャプテン・アメリカ』の面影が全くなくて。映画のセリフもちょっと哲学的で、全部良いんですよ。子どもに対して言う言葉が一つ一つ良いし、ブラックユーモアも効いていてすごく好きで、何回も観ています。あと、『女神の見えざる手』(2016)も好きですね。
― 『女神の見えざる手』は、ジェシカ・チャスティンが政治を裏で動かすロビイストを演じた社会派サスペンスです。
倉科 : ジェシカ・チャスティンが孤独で、格好いいんですよね。落ち込むことがあったときなど、無性に観たくなるときがあって、何度も観ちゃうんですよ。
安達 : 私がいま思い浮かんだのは『ゆれる』(2006)ですね。
― 『ゆれる』は西川美和監督の長編2作目の作品でもありますね。オダギリジョーさんと香川照之さんが演じられるディスコミュニケーションの兄弟の姿を通して、家族の在り方や絶望からの再生を描いた作品でした。
安達 : ちょっと、「人間の気持ち悪さ」が表現された作品が好きなんですよ。人って多面的で、綺麗ごとだけじゃ語れない、みたいなことがこの作品では描かれていて。表面で見えていることと全く違うことが裏で行われていたことが、あとからわかるシーンがあるんですけど、気持ち悪くていいんです。そこが人間の魅力なのかなと思って。すごく好きですね。
― では満を持して…。
倉科 : トリだ(笑)。
渡邊 : 話に聞き入っちゃって、ちょっと…。
倉科 : 一本出さないと終わらないよ!(笑)
安達 : 舞台挨拶始まっちゃうから!(笑)
渡邊 : そうですね(笑)。では僕は、『ユージュアル・サスペクツ』(1995)を。
― 『ユージュアル・サスペクツ』は、前科をもつ5人による犯罪計画の顛末を描いたクライムサスペンスです。
安達 : ケビン・スペイシーが印象的な役を演じているよね。
渡邊 : そうです。この作品を観てから、ケビン・スペイシーがどの映画に出ていても「この人だろ、黒幕は!」って思っちゃうんですよね。
全員 : (笑)。
渡邊 : 映画ってこんなに面白いんだってことを教えてくれた、それまでとは違う映画の観方を知った作品で、特別な一本ですね。