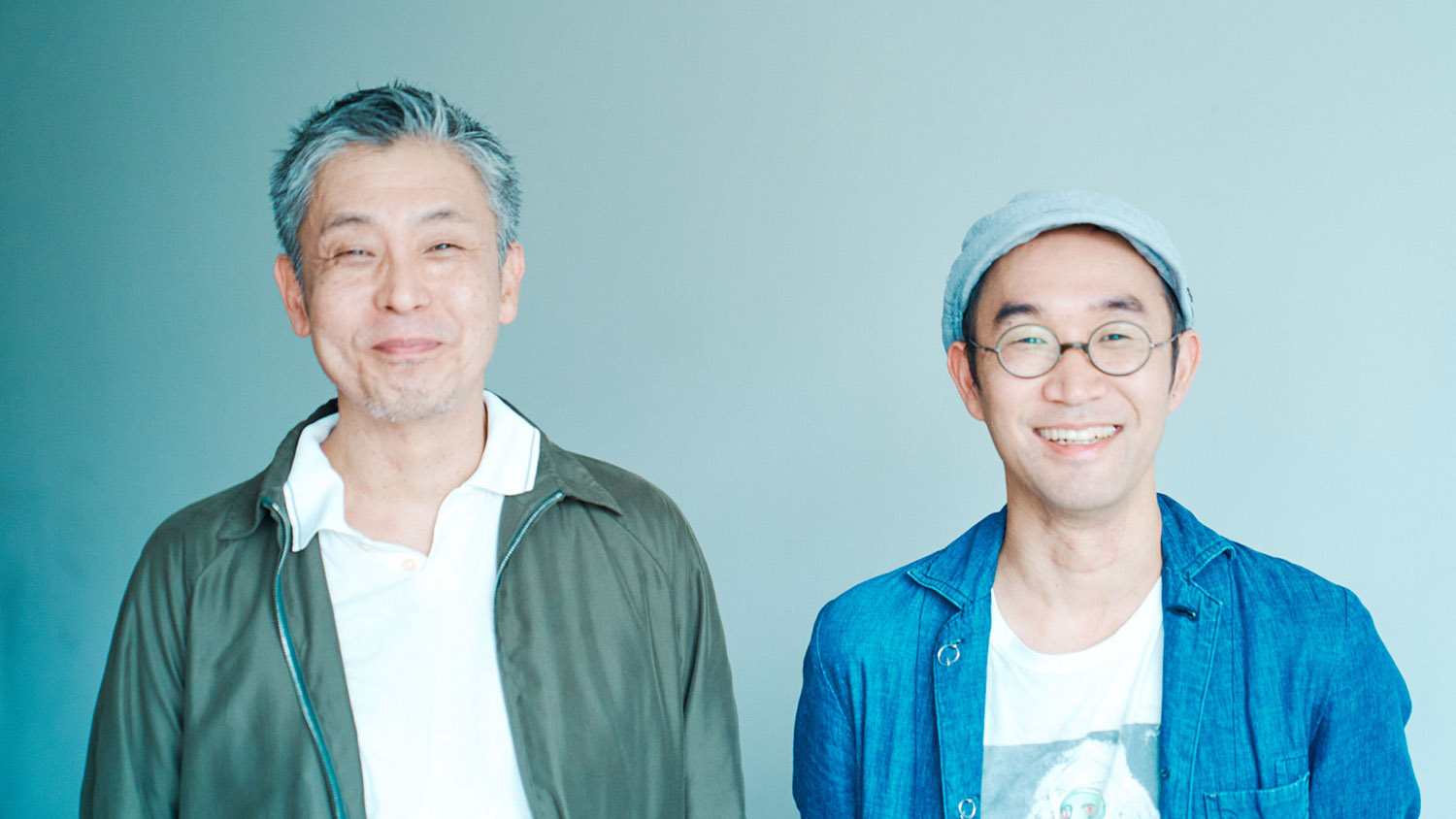目次

病むほど「痛かった」映画体験
橋口 : カンヌから帰ってきたばっかりですか?
奥山 : 先週帰ってきたんですが、時差ぼけが治らないですね。
橋口 : 高揚感がまだ残ってます?
奥山 : 無事終わってよかったと言いますか、やっと落ち着いた感じです。
橋口 : レポート記事を見たら、『ぼくのお日さま』の主役の男の子(タクヤ/越山敬達)は随分身長が伸びてましたね!
― お二人が顔を合わせるのは、今日この場が初めてになるのでしょうか?
橋口 : 初めてですね。
奥山 : 緊張します…。
橋口 : 日本映画界の新星ですから!
奥山 : いえいえ、そんな…(笑)。
― 橋口監督を前に緊張されているということですが、今回の対談は橋口監督の『お母さんが一緒』が7月、奥山監督の『ぼくのお日さま』が9月に劇場公開されるタイミングに加えて、奥山監督はもともと橋口監督作品が大変お好きで、その魅力に惹きつけられている一人と伺い、実現しました。
奥山 : はい。
橋口 : ありがとうございます。
― 奥山監督が、橋口監督の映画に出会ったのはいつ頃だったのでしょうか?

奥山 : 高校生の時に、部活をやめて暇になったので、学校の帰り道にレンタルビデオショップに寄って、新作は高いので旧作をまとめてたくさん借りるようになった時期があったんです。
その時にレンタルDVD特有のスキップできない予告映像で、『ぐるりのこと。』(2008)が流れてきて。
― 『ぐるりのこと』は、一組の夫婦・翔子(木村多江)とカナオ(リリー・フランキー)が、子どもの死や妻のうつ病など、さまざまな困難を前に寄り添い、時にぶつかり合いながら生きていく姿を描いた、橋口監督の長編4作目となる作品ですね。
奥山 : リリー・フランキーさんが出演していて面白そうだなと思ったので、その時借りていたビデオを返却するついでに早速『ぐるりのこと。』を借りて観ました。そうしたら、心にものすごく痛みを感じて。ちょっと病みかけるくらいに。
橋口 : すみません(笑)。
奥山 : しばらく落ち込んでしまうくらい、強烈な映画体験でした。その後、またレンタルビデオショップへ行って、『ぐるりのこと。』を借りたコーナーを見てみると、そこは監督ごとに区切られていて、橋口監督の作品を一気に借りて観たんです。他の監督名で区切られている作品数よりも少なくて、今考えるとすごく失礼ながら、「この数なら全部観れるな」と思って……。
橋口 : 良かった、作品数が少なくて(笑)。
― 『二十才の微熱』(1993)、『渚のシンドバッド』(1995) 、『ハッシュ!』(2001)と、橋口監督作品を高校生の時に浴びるように鑑賞されたと。
奥山 : 「映画っていいな」と思えた経験でもありましたね。
橋口 : でも、もともと映画は好きだったんでしょ?
奥山 : そうですね。映画館に行くのは好きでした。でも、橋口さんの作品を一気にみた経験を境にして、是枝裕和監督や岩井俊二監督など、監督で作品を観るようになっていくことでさらにのめり込んで、というような。
それで、ちょうど大学生になった時に、橋口さんの新作『恋人たち』(2015)が公開されるんです。
― 『恋人たち』は、心に傷を負う三人の男女の絶望と再生を描いた作品で、『ぐるりのこと。』から7年ぶりとなる橋口監督の長編5作目です。“作家主義”ד俳優発掘”を理念とした松竹ブロードキャスティングによるオリジナル映画製作プロジェクトから生まれ、2015年の日本映画を代表する作品のひとつとして、数々の映画賞を受賞しました。
奥山 : 初日にテアトル新宿へ観に行ったことを覚えてます。その後、少しずつ影響を受けながら『僕はイエス様が嫌い』(2019)を撮りました。
橋口 : 大学生の時に撮ったんですよね。
奥山 : はい。大学の卒業制作として撮りました。あまり指摘されたことはありませんが、細かいところで橋口さんの影響を受けている作品なんです。学校で先生が「起立」と言って生徒が立ち上がった瞬間に、別のシーンに切り替わるとか、逃げたニワトリを追いかけるとか、本当に細かい演出の部分で(笑)。
橋口 : そうなんですか! なるほど(笑)。
― 奥山監督の長編デビュー作となる『僕はイエス様が嫌い』は、子どもの視点から捉えた“神様”や死生観、友人との別れを描いています。
― 幼少期から通っていたミッション・スクールのこと、小さい頃に友人を亡くした記憶など、奥山監督の実体験が反映されている作品ですが、“自身の体験を普遍的なテーマとして描く”という点でも、橋口監督の作品と共通していると感じました。
橋口 : 『ぼくのお日さま』でも、篠原篤という縁がありましたね。
― 奥山監督の最新作『ぼくのお日さま』は、フィギュアスケートを題材に、アイスダンスのペアを組むことになる少年と少女、二人を見守るコーチの関係性を描いた作品です。

― 『恋人たち』で橋口監督自らがオーディションで選んだ主演の一人である篠原さんは、『ぼくのお日さま』で主人公が習っているアイスホッケーのコーチとして出演されていますね。
奥山 : 篠原さんは『恋人たち』を観ていたことで、出演をお願いしたいなと思いました。ホッケーの経験があるとおっしゃってましたね。
橋口 : 学生時代にやってたみたいだね。あと、子どもの頃にずっとスケートを習ってたとも言ってました。「滑れるイメージないと思いますが、滑れるんです」って(笑)。
奥山 : 先ほど、“自身の体験を普遍的なテーマとして描く”ことを共通点として挙げてくださいましたが、自分の「好き」とか「こういう体験をしてきた」というものは、2本の映画を撮る過程で早くもやり切ってしまった感覚があって。次は、どうしていこうかなと。
橋口 : やりたいことがいっぱいあると思ってたんで、意外ですね。でも、長編デビュー作の『僕はイエス様が嫌い』は(サンセバスチャン国際映画祭にて)最優秀新人監督賞を受賞されて、2作目がカンヌ国際映画祭(の「ある視点」部門)で上映されて、すごく幸運な映画人生のスタートを切られてるから。これからもいっぱいお話が来るでしょうし。そういうものなんですよ、映画祭というのはね。

橋口 : 僕が『ぼくのお日さま』を観て一番いいなと思ったのは、痛みをちゃんと描けている、それが良かった。池松くんを観て「あ、痛いなー」って、ちゃんと痛い。
― 池松壮亮さん演じるコーチの荒川は同性の恋人(五十嵐/若葉竜也)がいて、そのことで起こる周りとの不和が描かれていますね。
奥山 : 最近のドラマや映画に登場する同性愛の描き方に、僕は疑問を感じることが少なくありません。記号化されたような存在にはしたくないという考えから、最初の企画書にも、同性の恋人が登場するその意図について悩みながら書いていました。

橋口 : 僕が『二十才の微熱』や『渚のシンドバッド』、『ハッシュ!』を撮っていた頃に比べると、今、LGBTQ+というのは余りにも政治的に扱われ過ぎているので、当事者でも慎重にならざるを得ないなと感じていますね。それを打ち破るような、例え主題に同性愛が絡んでもおおらかなコメディにならないかと、『恋人たち』を撮った後に準備していたんですけど、それも難しいということがありまして。
実は、今回の新作『お母さんが一緒』のドラマシリーズの6話目に、アナザーストーリーとしてその話を使っているんですよ。
奥山 : 僕もそのことについて、お伺いしたいと思っていました。

「小骨が刺さった」ように、個人的な体験を感じてもらう
― 前作の『恋人たち』から9年ぶりの最新作となる橋口監督の『お母さんが一緒』は、CS「ホームドラマチャンネル」(松竹ブロードキャスティング)の開局25周年オリジナルドラマとして、劇作家・ペヤンヌマキさんの同名舞台を橋口監督が脚色、あらたに再編集した長編映画です。

― 橋口監督の作品を高校時代から追い続けてきた奥山監督も、ご覧になったということでしたが、いかがでしたか?
奥山 : 僕の中で橋口さんって、映画を作る時に「二人」いるような気がしていて。自主映画時代からの「自分が体験してきたことを自己紹介するかの如く真っ直ぐ表現する」視点と、「ワークショップで出会った役者さんたちをどう輝かせるか」という視点。その両方が混ざり合ったのが前作の『恋人たち』というイメージだったんです。
今回はそれまでの積み重ねもありつつ、3人目の橋口さんを見た気がして、すごくワクワクしました。「また違う橋口さんが見れた!」と。
― ずっと作品を追いかけてきた奥山監督からすると、嬉しいですよね。
奥山 : そうなんです。
橋口 : …恐れ入ります(笑)。
― ドラマシリーズを再編集して長編映画にされることも、原作があることも、橋口監督にとっては初めての挑戦となりましたが、これまでと違うアプローチになったのでしょうか。
橋口 : 自主映画時代からずっと「続編を撮り続けている」という感覚で映画を撮ってきたんです。すべてが繋がっているような。特に『恋人たち』は、自分の全体重が乗っかった作り方だったんですよね。
― 以前、橋口監督にインタビューした際に「“私(わたくし)”の映画」とも表現されていましたよね。
橋口 : でも今回は原作があり、「自分の中のもの」ではない。だから不安でした、果たしてそういう自分の血肉を使わない作品でも自身の力は出るのだろうかと。
ドラマシリーズとして放送する企画でもあったので、気軽に観てもらえる楽しさも出したいし、なおかつ自分らしいテイストも入れつつ、登場人物たちを「生きている人間」としてどう描くか、その幅やバランスについてはいろいろ考えました。
― 『お母さんが一緒』は、親孝行のつもりで母親を温泉に連れてきた三姉妹が、それぞれ抱えていたコンプレックスや不満を次第に爆発させていく、家族ならではの悲喜こもごもを描いた作品です。

― 三姉妹を演じる江口のりこさん、内田慈さん、古川琴音さんの掛け合いが軽快でつい笑ってしまいますが、その感情の揺らぎの中には、人生のもどかしさやほろ苦さも感じられ、「橋口監督の作品を観たな」という後味が残りました。
橋口 : キャラクターの輪郭がはっきりしてる作品ですが、それが記号的ではなく、観ている人が「あれ? 今なんか苦味を感じた」とか「口の中に小骨が刺さったような違和感があるな」とならないと、観ている人の心に引っかからないですよね。
作品というのは、観ている人の上を物語が通り過ぎていくようではだめなんです。「自分たちの中にあるもの」を使う、その「生(なま)」の感じがないといけないんだ、ということは今作では最初に役者のみなさんにお話ししました。

奥山 : 僕もお聞きしたいんですけど、橋口さんはよくエッセイの中でも「生の感情」という言葉を使われていますよね。
橋口 : エッセイも読んでくれてるんですか?(笑)
奥山 : はい。その感情の具体を役者さんたちに、どう伝えているのかを伺いたくて。
橋口 : 僕もそれは今回特に考えました。「生の感情」と言われても、何を出せばいいのかわからない人もいるでしょうし。それで話したのが、自分の体験なんですよ。
「こう演じて欲しい」ではなく、本編とは関係ない、僕自身の体験したことをお話しました。
奥山 : はい。
橋口 : 僕は、17歳の自主映画時代から「伝える」ということを考え、表現し続けてきた人間なんだけれど、『ぐるりのこと。』を撮った後、一度全てのモチベーションを失くした時期があったんです。
その時に、京都の映画館からトークショーの依頼があって、とても人前に立てる状態じゃなかったけど、嬉しい依頼だったのでお引き受けしたんです。

橋口 : 楽しくお話ししてトークショーは無事終えることができたんですが、その後ロビーにいたら、一人の女性のお客様が僕のもとに来て、「本日は京都まで来てくださってありがとうございました」と丁寧に挨拶してくださったんです。
奥山 : はい。
橋口 : そして、『ハッシュ!』の登場人物の朝子について、まるで自分の半生を重ねるように語ってくださったんです。その語り口や一分の隙もない凛とした姿勢から、「誰にも私の人生を踏みつけるようなことはさせない。だから誰よりもきちっとしていよう」という強い意志を感じました。
当時僕は、映画を作ることに対してのモチベーションを失っていたけど、僕の映画の主人公を支えにしてくれてるんだと思ったら、帰りの新幹線で泣けてきたんです。僕もこれでいいと、そう思うことができました。
今作の江口さん演じる「弥生」も、そういうところがある人なんじゃないかなと。映画と全然関係のない、そんなことを役者たちにたくさん話しました。

― 弥生は、妹たちに密かな劣等感を抱きながらも、長女として誰よりもしゃんとしていようとする、生真面目さを感じさせる役でした。
橋口 : 江口さんは、そうした僕の話した時間が、すごくよかったと言ってくれて。あの時間から感じ取ってくれた何らかのことが、やっぱり反映されていたんじゃないかなと思います。
― 奥山監督は、前作『僕はイエス様が嫌い』同様、『ぼくのお日さま』でも、キャストの子どもたちに台本を渡さず、そこで起こる出来事だけを伝えて演技してもらったそうですね。それもやはり、カメラの前で「生の感情」を引き出したいという考えからなのでしょうか?

奥山 : はい。池松さんはじめ、大人の役者さんたちには台本をお渡ししていますが、子どもたち本人には、台本をお渡しせず、事前に読んで練習してくる、というのをやめてもらっていました。その場で初めて体験してもらうことで、実際に感情が動いてくれたらいいなと思って。もちろんリハーサルしたり、テイクは重ねたりしていくので、それは理想論なんですけど。
あの…そうやって何とか「生の感情」を引き出そうとしても、テイクを重ねていくうちに芝居が定型化してしまう時があるんですけど、どうされてますか?
橋口 : 僕の場合ですか?
奥山 : はい。実は今日、橋口さんにお聞きしたいことがたくさんあって、質問リスト作ってきたんです。
橋口 : ほんとだ、すごい書いてきてくれてる!(笑)
奥山 : 橋口さんの作り方の一つに、撮影前にリハーサルを重ねるというのも特徴の一つかと思います。そうすると、カメラを回す時にはお芝居が固くなってしまう人もいそうですけど、どうされてるんですか?
橋口 : 何回繰り返しても崩れない人もいるし、逆にリハーサルそのものを嫌がる人もいるけど、そこは監督のコントロール次第だと思います。
僕の映画も、アドリブに見えるようなところもあるかもしれませんが、全部台本で決まっていて、リハーサルも重ねています。『二十才の微熱』の時からずっとその形です。

橋口 : でも、『ぼくのお日さま』を観て思ったけど、もう自分のスタイルにちゃんと確信があるでしょ?
奥山 : それを確信と呼ぶべきかは分かりませんが、映画における好き嫌いはだいぶ固まってきている気がします…。
橋口 : 全てのショットに確信があって撮ってるなと感じました。一つも無駄なカットがなかったし、ジャストサイズでそこにある。「これを26歳で撮ったの!?」と驚きましたよ。
― 『ぼくのお日さま』では、アイスダンスの練習をするタクヤとさくらが、手を重ねたり、呼吸を合わせたりと、実際に身体の距離が近くなることと連動して物語が展開していたのも印象に残りました。身体を通したコミュニケーションを描くことは意識されていたのでしょうか?
奥山 : 男二人と女一人の三角関係を描きたかったんです。それもまた、橋口さんの作品の影響でもあるんですが…。で、その三角関係のどこが近くなって、遠くなっているのかという距離感は、アイスダンスを通して実際の身体の距離感で見せたいなと思っていました。
あとは、フィギュアスケートというスポーツを題材にしている以上、身体性というものは映画の中に映り込ませたいと考えながら撮っていました。
― 今回奥山監督は、7年間フィギュアスケートを習っていた経験をいかして、スケートリンク上のシーンでは、実際に滑りながら撮影されたんですよね。

奥山 : はい。せっかくだから自分も滑りながら撮ろうと思いました。
橋口 : 今回この映画を観て思い出したけど、『アイス・キャッスル』(1978)って古い映画観たことありますか?
奥山 : 観ました。これを撮る時に、スケートに関する映画を一通り観ようと思って。
― 『アイスキャッスル』は、当時フィギュアスケート界で人気を誇っていた、リン=ホリー・ジョンソン主演のアメリカ映画で、2009年に『アイス・キャッスル 氷上のヒロイン』としてリメイクされていますね。ある日、事故で視力を失ってしまったフィギュアスケーターのレクシーの競技に向ける情熱と、恋人との関係を描いた物語です。
橋口 : クライマックスで、視力を失ってしまったレクシーが選考大会に挑戦するシーンがあるんですけど、オリジナル版では、カメラがリンクの中に入っていて、少しずつ滑り出してだんだんとスピードを増していく彼女の様子を、近い距離で追いながら映していくんです。それが本当に良くて。
でもリメイク版では、全く同じクライマックスのシーンで、カメラはオリンピック中継みたいにリンクの外側にいるんです。
奥山 : はい。
橋口 : 「え!」と思っちゃって。カメラが解説者のバックショットを捉えていたり、観客側にいたりするんです。更に、レクシーが滑っている途中で、彼女が視力を失う前のイメージ映像が挿入されたり、最後にキスシーンが入ったりして台無しなんですよ(笑)。
今回、それをふと思い出して。『ぼくのお日さま』も、リンクの中にカメラが入ってますよね。カメラと役者の、その身体的な距離感というのが良かった。凍った湖の上でのスケートシーンでも、3人がどんどん楽しくなって、近づいていく高揚感がカメラ越しに伝わってきました。こういうスケッチシーンは、監督のセンスが見えますよね。

橋口亮輔監督、奥山大史監督の「心の一本」の映画
― 最後にお二人の「心の一本」の映画を聞かせてください。
奥山 : 僕は、橋口さんの作品から影響を受けただけじゃなくて、橋口さんが影響を受けたと公言されている映画も辿って観ていた時期があります。その時に伊丹十三監督や木下惠介監督の作品が好きになりました。
でも、一番影響を受けてるのは、仏映画でアルベール・ラモリス監督の『赤い風船』(1956)という映画です。
― 『赤い風船』は、パリの街並みを舞台に、少年と赤い風船の交流を、ほとんどセリフを使わず映像を軸に描いた作品ですね。カンヌ国際映画祭の短編パルム・ドールも受賞しています。
奥山 : 橋口さんの自主映画『ヒュルル・・1985』で作品の存在を知って、どんな映画なんだろうと気になって、観てみました。少年と風船の友情を、セリフもなくただ黙々と映していくんですけど、映すところと映さないところに意志が感じられて、そこがすごく好きで。いかに言葉で説明せずに映像で伝えるか、という描き方は『赤い風船』から教えてもらいました。
橋口 : 『ぼくのお日さま』の描き方とも繋がるよね。
奥山 : 嬉しいです。
― 奥山監督の映画づくりのメソッドにも、影響を与えた作品なんですね。
奥山 : 本当にそうなんです。橋口さん経由で好きな映画にたくさん出会えた経験があったので、その後も、好きだと思える作品と出会ったら、その監督の作品を観ていくだけじゃなく、その監督が好きだと公言している作品も観るようになりました。
― 橋口監督は、先ほど『ぼくのお日さま』を観て「痛みを感じた」とおっしゃっていましたが、同じように痛みを感じた作品はありますか?
橋口 : 若い頃にフランソワ・トリュフォーの『大人は判ってくれない』(1959)を観て、それこそ生々しさを感じましたよね、テクニックじゃない。
― 『大人は判ってくれない』は、家庭にも学校にも居場所のない少年の視点から大人の世界を描いた、フランソワ・トリュフォー監督の自伝的映画であり、長編デビュー作ですね。
橋口 : 当時、リアルタイムで観た人たちも衝撃を受けたんだろうけど、年代を経て今観るからこそ感じる少年の痛みもあって。トリュフォー自身が反映されてるんだろうけど、我がことのように感じました。
でも、痛みが自分の精神的支柱になった作品は、『二十四の瞳』(1954)ですかね。
― 『二十四の瞳』は、第二次世界大戦に飲み込まれていく日本で、女性教師と12人の生徒たちの交流を描いた木下惠介監督の代表作ですね。どのような時に支柱になったのでしょうか?
橋口 : 先ほどお話しした、『ぐるりのこと。』を撮った後、全てのモチベーションを失っていた時期に、たまたま松竹さんから木下監督生誕100年のお仕事の関連で、「『二十四の瞳』をBlu-ray化するので、予告映像を作ってください」という依頼をいただいたんです。
橋口 : 僕の学生時代は、木下監督を“お涙頂戴作品を撮る人”という偏見があったんですよ。当時はそれに言い返す言葉を持っていなくて、「そうなのか?」と思っても言い返せずにいました。でも、自分が辛い思いを経験した後に改めて観返したら、お涙頂戴なんてとんでもない「厳しい映画」だったんです。
― 厳しい映画、ですか。
橋口 : 生徒の中に、勉強がよくできたのに進学を諦め、家族のために奉公に行くことを選んだ少女がいるんですけど、最後は肺病で倒れ、家に戻ってくるんですね。
大石先生がその子をお見舞いに尋ねると、彼女は荒家で一人寝ていて、「先生、あたし苦労しました」と。先生はその言葉に「苦労したでしょうね」と返して、二人で泣くんです。

橋口 : そのシーンを観た時に、「人生をこんなに厳しく見つめ抜いた映画はない」と感じました。それは、自分がいろんな経験を超えてきた、ということがあったからそう受け止めたんでしょうね。
その後、僕は自分の個人的な体験を反映した『恋人たち』という映画を撮るんです。『二十四の瞳』が公開された1954年というのは、『七人の侍』や『ゴジラ』も劇場公開された年でもあって。
奥山 : すごい年ですね…。
橋口 : どれもヒットしたんですが、その中でも『二十四の瞳』は大ヒットだったんです。当時はまだ日本が戦争の色を強く残していた時代で、戦争で家族をなくしたり、家を焼かれたり、貧困に喘いでいたりしていた。
では、なぜ人は自分たちの境遇と同じ立場に置かれた人を描いている『二十四の瞳』をわざわざ観に行ったのかと考えると、慰めを得たんだろうと思うんです。痛みが描かれた映画を追体験することで救われる人もいる、ということを僕が信じている、その根拠はこの作品にあると思います。