目次
だからこそ、誰かにそれを打ち明けることは勇気も必要ですが、大切にしているものを分かち合ったり、自分とは違う誰かの「好き」を発見したりすることは、ひとりでは想像もつかなかったような新しい場所へと導いてくれることがあります。

言語化できない感覚こそ大事にする
― 今作の主人公・トツ子は、人の“色”が見えるという特別な感覚を持っている高校生として描かれています。山田監督は、「言語化したものではなく、時間と色と動きのような、感覚的なものを受け取ってもらうフィルムにしたかった」とコメントされていました。

― 『映画 聲の形』(2016)以来、4度目のタッグを組むことになったお二人は、そのような“感覚的なもの”を、制作を進める中でどのように共有しているのかを、まずお伺いできますでしょうか?
牛尾 : 山田さんが僕と組んでくださるのは、多分そこに理由があるのかなと思っています。お互いに言語へ落とし込まず、言語以外のことで共有することができるんです。
― なるほど。
牛尾 : ものづくりをする際、「言葉にする」というのはときに危険だと僕は考えていて、丁寧に扱わないと、表現の範囲をすごく狭めてしまう、「言語化したもの」になってしまうんですよね。
例えば、「白」を表現するときに、白って200色あるらしいんですけど……。
山田 : ちょっと待って(笑)。
牛尾 : ん?
山田 : どこかで聞いたことがあるフレーズが。

― アンミカさんの名言「白って200色あんねん」ですね(笑)。
山田 : 真面目な顔で聞いていていい話ですか?
牛尾 : はい(笑)。自分の表現したいものを他人へ共有するときに、言葉にしたり、「それってこういうことでしょ?」って近い作品を挙げたりすると、「到達できるところ」に行けなくなっちゃう恐れがあるんです。
でも、山田さんとは言葉や意味に限定されないコミュニケーションができるし、ノンバーバルなやりとりで感覚を共有することができるんです。それが大事だとお互いに気づいていることが、創作する上でとても大きな部分ですね。

山田 : 牛尾さんがおっしゃる通りです。映画をつくるときには、たくさんのスタッフが関わるので、言葉にして説明したり、みんなが共通で知っているような参考作品を挙げることを求められたりする場面ももちろん必要なんですけど、私は毎度毎度、そのバランスを大切にしないとと思っていて…。
― 牛尾さんがおっしゃっていたように、そのことで“こぼれ落ちるもの”があると感じられているからですか?
山田 : はい。だから牛尾さんとの制作には、すごく救われています。

― 『映画 聲の形』のときから、お二人は具体的な音楽制作に入る前にコンセプトワークを行うと伺いましたが、「言葉や意味に限定されない、意味に寄らないコミュニケーション」というのは、具体的にどのようなやりとりになるんでしょう?
山田 : グラフを一緒に見たりとか。
牛尾 : 関数とかね。
― グラフと関数!?
牛尾 : 例えば「コサイン4乗則」っていう入射角と照度の関係を示すものがあるんですけど、『映画 聲の形』のときは、そのグラフを見ながら話したりしました。
― そのグラフを見て、何をどういう風に共有していくんですか?
牛尾 : 二人でグラフを見て「なるほど。ということは、モランディじゃない?」となって、そこからジョルジョ・モランディ(※「20世紀最高の静物画家」と称されたイタリアの画家)の画集を開いてみたりと、共通の感覚を広げていくことができるんです。
山田 : うんうん。
― 共通のイメージを連想して広げていく、または解像度を上げていくような方法で、探っていくんですね。『きみの色』では、共通の感覚として持っていたモチーフやテーマなどはありましたか?
牛尾 : 企画の始まりに、「バンド活動を通じて、三人の少年少女が前に進んでいく音楽もの」ということがあって。
― 今作は、どこか自分に自信が持てないトツ子、学校に行かなくなってしまったことを家族に打ち明けられない少女・きみ、実家の病院を継いでほしいという親の期待を感じながらも音楽の道に進みたいと悩む少年・ルイという、それぞれに秘密や葛藤を抱える三人の少年少女が出会い、バンド“しろねこ堂”を始めることで、自分や社会と向き合っていく姿を描いています。
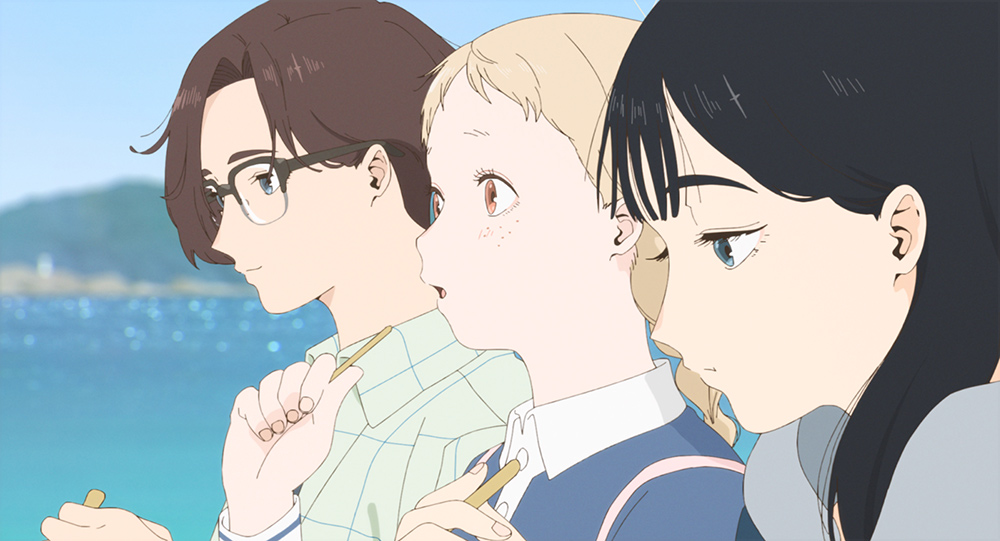
牛尾 : そこで山田さんから発せられたのが、「作用」でした。
“影響を与える”という意味もある言葉だから、三人の関係性を表していると捉えてしまいがちなんですけど、ここで言う「作用」は、物理学における意味に近い、もっと動力学的な性質、「エネルギー量が移る」というようなことなんですよね。そこから紐解いて音楽をつくっていきました。
― 先ほど挙げてくださった『映画 聲の形』の「コサイン4乗則」もそうですが、『リズと青い鳥』でも「素数」について触れられていましたね。そういう数学や物理に関する事象からのインスピレーションでもお二人は共有することができると。
山田 : あと私たちにとって初めてのチャレンジになったのが、劇中のバンド曲をつくったことです。今回はキャッチーなバンド曲を、と考えていました。
多くの人に広く届くものをつくる、ということを意識したものづくりはこれまであまりしてこなかったので…と言うと語弊があるかもしれないですが(笑)。
牛尾 : 僕は普段ポップな曲を書くことはあまりないんですけど、山田さんから出てきた「水金地火木土天アーメン」というワードからインスピレーションを得て、瞬発力ですぐに曲が書くことができたんです。そういうセレンディピティが、今回の音楽制作では起こりましたね。
― トツ子はミッションスクールに通っていますが、そんなトツ子が思いついた曲のフレーズが「水金地火木土天アーメン」でした。
― 今作を観てしばらくの間、主人公たちが演奏していた「水金地火木土天アーメン」が頭から離れなくなりました。
牛尾 : メロディがぱっと思い浮かんだので、「水金地火木…」と歌ってみたんですけど、その打ち合わせに出ていた全員から、最初はポカンという顔をされて。
僕の頭の中ではフルアレンジで鳴っているんだけど、みんなから見たら、「何か急に歌い出したぞ…」だったんでしょうね(笑)。
山田 : 会議室で急に鼻歌を。しかも楽しそうに(笑)。

― 今作は、上海国際映画祭で金爵賞アニメーション最優秀作品賞を受賞しましたが、海外で上映された際の観客席では、バンドの演奏シーンに合わせて身体を揺らしたり手拍子をしたりと、音楽を楽しむ人たちの様子が多く見られたそうですね。劇中には、音楽好きの人が見たら思わず反応してしまうような、細かい演出やこだわりもたくさん込められていました。
牛尾 : 多分、音楽好きの人が観たら、つくっている僕らの年齢がわかりますよね(笑)。
― トツ子ときみが寮でこっそりお泊まり会をするシーンでは、アンダーワールドの「Born Slippy」を連想させるような音楽が流れたり、「水金地火木土天アーメン」できみが演奏するギターを、相対性理論のギタリストなどで知られる永井聖一さんが弾いていたりと、思わず「お!」となるような、嬉しい発見がいくつも隠されていました。
山田 : 私も「牛尾さんがつくったフレーズを永井さんが弾いてる!」となりました。海外で上映させていただいたときは、お泊まり会のシーンで例の音楽が鳴った瞬間、「これは…!」と言う感じでちょっと客席がざわついていました。観客のみなさんが、音楽に合わせて少し揺れているという(笑)。

牛尾 : 僕らと同世代の人たちがね。
山田 : これをきっかけに、アンダーワールドを知る若い人がいるのかも。
牛尾 : そこはいいバトンの渡し方ができたかなと思っていて。例えば、『トレインスポッティング』(1996)でイギー・ポップの音楽を初めて聴いた人もいると思うんですよ。そこから「この曲かっこいいな」と、探して聴いてみた人がいたはずで。
― 1990年代のスコットランドを舞台に、英国の若者たちの実情をリアルに描き大ヒットとなった映画『トレインスポッティング』は、イギー・ポップやアンダーワールド、プライマル・スクリームなど数々のアーティストが楽曲を提供し、サウンドトラックも一大ブームを巻き起こしましたね。
― 私も調べましたもん、イギー・ポップ。
山田 : で、かっこいいと思いましたもんね?
牛尾 : 今回も、「あのシーンで四つ打ちで鳴っていた曲、おじさんたちがはしゃいでいたけど何だろう…」って、辿る人が出てくるかもしれないよね。
山田 : 今改めて聴いても、きっとかっこいいもんね。

好きなものを「好き」と言うのは、怖かった
― 先ほど、「作用」についてのお話がありましたが、「信じる」「規律」「隠しごと」も今作におけるひとつのテーマやモチーフだったとプレス資料に書かれていました。そこから山田監督の場所への関心もあわせて、教会やミッションスクールを設定として考えていた中、候補地に挙がったのが長崎だったそうですね。

― 作品のモデルである長崎県・五島列島は、江戸時代から多くの潜伏キリシタンが移り住んだ場所であり、今も島のあちこちに点在する教会にその歴史が継承されています。
山田 : はい。
― トツ子がミッションスクールに通っていたり、三人が離島の教会に集まって音楽を演奏していたりと、舞台設定とともに描かれる「祈り」がとても印象的でした。
山田 : 信じるものがある、という心の動きや、そこにあるすべてのものの気配と言いますか、「形のないものを捉えていく心」を私自身が学びたいと思ったんです。

山田 : 「信じる」「祈る」という心を持つ、そして心を形にする人たちへの尊敬もありますし、それを描くと何が見えてくるのかに興味がありました。
「自分とは?」を探っている思春期の子どもたちが、その中でどう揺れていくのか、その姿を描きたいと。
― 映画の冒頭、トツ子が聖堂で祈っていた言葉は、神学者であり政治学者でもあるラインホルド・ニーバーの祈りの言葉からの引用ですね。
山田 : あの言葉は、脚本の吉田玲子さんが書いてくださったんです。「なぜこの言葉がここに入っているんだろう」と、最後の最後まで、私もその意味について悩み続けたことを思い出しました。まだ今も悩み続けていますけれど。

― 吉田さんは、『映画 聲の形』やテレビアニメ「平家物語」(2021)など、これまでの山田監督の作品で脚本を担当されていますね。作品の中に、いつもそうしたひとつの問いかけのような言葉を潜ませてくるのでしょうか?
山田 : そうですね。毎回、吉田さんが入れてくださる言葉の欠片について考え続けて、そこから物語やキャラクターの枝葉が生まれていくことが多いです。必ず、何か深く刺すような言葉が入っている感じがします。
― 「祈り」は、音楽にも作用していったのでしょうか?

牛尾 : はい。“しろねこ堂”の三人の総作用的なものにおいて、僕は「場」が必要だと思ったんです。祈るための場、というか。それが、三人の集う離島の教会です。
旧五輪教会堂という、五島市に実際にある教会なんですが、実際に行って、音響的に空間をモデル化し、あの場所で楽器を鳴らしたらこういう響き方をするだろうと、音楽の中で再現できるようにしました。
― 現地を訪れて、音の響きを確認されたと。旧五輪教会堂は、国の重要文化財に指定されている歴史ある建造物でもありますね。映画では、三人が船に乗って離島に建つこの場所に集まり、大切な秘密を共有するように、バンドの練習を行う様子が何度か登場します。
牛尾 : あの場所だけにとどまらず、彼らが祈るようなときに、そのような音が鳴るといいなと思いながら、音楽の残響をつくっています。それは、最初のコンセプトワークのときから導き出されていたものですね。

― 山田監督は、思春期にある子どもたちをアニメーション作品で描き続けています。「思春期の鋭すぎる感受性というのはいつの時代も変わらずですが、少しずつ変化していると感じるのは『社会性』の捉え方かと思います」「『好きなものを好き』といえるつよさを描いていけたら」と今作について書かれていましたが、そこにはどのような思いがあったのでしょうか?
山田 : 他者との距離の取り方や自分を肯定しきれないことに悩み続けるのは、世代にかかわらず誰もが抱えていることでもあると思うんです。でも、見た目とか性格や属性で人をカテゴライズして、言葉の中に押し込められてしまう窮屈さみたいなものが、SNSが普及したことでより強くなっていると感じています。
だから、ずっと“足りない”という感覚を抱えながら生きている子どもたちが多いんじゃないかなと。それがすごく気になって。この作品では、そこからこぼれてしまっている、「もっと大事なこと」に目が向けられたらいいなと思いました。
― そのこぼれ落ちてしまっている大事なことが、「好きなものを好きといえる強さ」でもあるのですね。
山田 : はい。少しでも生きる術というか、生きやすさに繋がったらいいなと。どうしてもね、生きていると悩みは尽きないですよね?
牛尾 : 尽きないです。私は悩みたいです。
山田 : !?
牛尾 : 常日頃、難しく考える方が好きなんです(笑)。でも、僕らの世代もそうだし、僕らより上の世代の人たちも枠の中に押し込められてしまう窮屈さは叫んでいますよね。
僕らの世代には『新世紀エヴァンゲリオン』などがあったので、「自分とは?」とか、やっぱり考えていましたね。

― 思春期というのは自己と向き合う時期でもありますが、同時に、「好き」を通じて他者と繋がることが、とても大きな影響力を持っていたりもしますよね。トツ子たちが、バンドを組んで学園祭のステージに立ったように、ひとりでは辿り着けなかった世界が広がることもあります。お二人にも、思春期に同じような経験はありましたか?
山田 : (隣を見ながら)なさそう…ですね。
牛尾 : なかった結果、ひとりで打ち込みで音楽をつくるようになりました。このモニターだけは俺を裏切らないって(笑)。
山田 : 私も、トツ子のようにお友達ときゃっきゃ言いながら楽しく過ごしていましたけど、自分の本当に好きなものを堂々と言えていたかというと、そうではなかったなと。やっぱり怖かったです。
みんなが好きだと言っているものを「私も好き」ってあわせている方が楽だったし、葛藤はあったけれど、楽な方を選んでしまっていたなと思います。
― 好きなものは、自分の輪郭をつくりあげるコアの部分でもあるので、否定されるのがどうしても怖くなりますよね。
山田 : 怖い。否定されたら立ち直れない! であれば、隠していた方がいいかなと当時は思っていました。
牛尾 : コアの部分を出して、もし否定されて、そこから相手を言い負かしたとしても、自分の大事なものが汚れちゃったみたいな気持ちになるんですよね。そういうことじゃないんだよなーって。
山田 : でも今は、SNSの存在によって窮屈になってしまった側面もある一方で、自分の好きな世界を発信しやすくもなっていますよね。好きなことを堂々と言える人たちの強さにはすごく尊敬があります。
私はそれができなかったからこそ、自分に足りなかった部分を作品に描いて、学んだり、経験し直したりしている気がしますね。

山田尚子監督、牛尾憲輔の「心の一本」の映画
― 普段は、お二人で好きな映画や音楽についてお話しされたりするんですか?
山田 : そうですね、やっぱり音楽はいろいろ教えてもらいました。ふとしたときに、牛尾さんオススメの音楽のYouTubeリンクを送ってきてくださったりするので、そこから曲を聴いてみたり。
牛尾 : 僕は映画にそんなに詳しくないので、山田さんに教えていただいたことで触れた作品がすごく多いです。その中で、人生の一本の映画に出会ったんですよ。
― そうなんですね! ちなみに、そのタイトルは…?
牛尾 : それは、二人の秘密なので。
山田 : (笑)。
牛尾 : グザヴィエ・ドランの映画ですってことだけはお伝えします。
― グザヴィエ・ドランは、19歳で製作した映画『マイ・マザー』(2009)や、カンヌ国際映画祭でクィア・パルムを受賞した『わたしはロランス』(2012)などで知られる映画監督ですね。
山田 : 牛尾さん、海外のインタビューを受けるときに、毎回グザヴィエ・ドランの名前を出しているのを知っているんですよ! これは言霊にしようとしているなと(笑)。
牛尾 : 今度から英語で投稿するときに、ハッシュタグつけようかな。ご本人にも届きやすいように。
― 好きなものは好きって言わなきゃ、ですもんね。
山田 : そうそう、言わないと!
― 最後に、お二人にとっての「心の一本」の映画についてもお伺いできたら嬉しいです。
山田 : 私、前にPINTSCOPEのトークイベントに出演したときにも一本発表しちゃったんですよね(笑)。
― 山田監督とHomecomingsの福富優樹さんをゲストに迎えた、PINTSCOPEトークイベント第二弾「Listen to the silence, let it ring on」のときですね! あのときにも、「心の一本」の映画をお聞きしていました。
牛尾 : 俺を呼んでくれなかったときですね(笑)。
― 山田監督と牛尾さんと福富さんは、『リズと青い鳥』でご一緒されていましたもんね。
山田 : 次はぜひ!
牛尾 : そのイベントのときは、なんの映画を挙げたの?
山田 : 『ラ・チャナ』(2016)という映画です。
― 伝説的なフラメンコダンサー、ラ・チャナの波乱に満ちた人生と情熱を描いたドキュメンタリー映画ですね。映画館で観たときの特別な記憶も含めて、お話ししていただきました。
山田 : 牛尾さんの「心の一本」から先に、どうぞ!
牛尾 : 『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(2011)かな。バレリーナの映画です。あの映画の中で、結構刺さっているセリフがあって。10年以上前の記憶だから朧げだけれど、振り付けしたモダンバレエのダンサーたちがステージに向かう場面があるんです。そのときに、ピナ・バウシュ本人が「さぁみんな、私を怖がらせてね」って言って帰っていくんです。
山田 : かっこいいですね。
― 『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』は、2009年に亡くなった振付家のピナ・パウシュのダンス作品とその思想を、ヴィム・ヴェンダース監督が3Dの形式で映像に収めた作品ですね。そのセリフが牛尾さんの心に刺さったのは、なぜでしょうか?
牛尾 : 多分、「怖がらせてね」というのは、キャリア的な意味で私を怖がらせてね、という意味じゃなくて、「私を理解不能に陥らせるべきだ」っていう、彼女のステートメントだと思うんです。
彼女の振り付けはモダンバレエの極致だから、いきなりなんの知識もない人が彼女の踊りを見ても「え?」と感じるかもしれない。だからこそ彼女は、ダンサーたちに、そこから生まれるであろう批評性とか精神性みたいなものではなく、さらに“先”を求めてる。
山田 : うん。
牛尾 : それに応えて、彼女を恐怖させなければいけないダンサーたちのことを想像すると、すごく震えるというか。「俺は大丈夫かな? ピナ・バウシュのことを怖がらせられるだろうか」ってなるんです。

― ご自身のクリエイティブに返ってくる言葉なんですね。
牛尾 : 背筋が伸びるような気がしますね。この映画は観るのに体力がいるので、まだ観返せていないです。
山田 : 「心の一本」…。
牛尾 : 山田さんのエバーグリーンである『ドラえもん』からはどうですか?
― 『ドラえもん』なんですか!
山田 : はい。いつか『ドラえもん』作品に参加したい、と思っていて。でも「心の一本」となるとテレビ放送の作品になるんですよね…。
― 例えば、思春期の頃に観てすごく心に刺さった映画や、友だちと一緒に好きになった映画などは?
山田 : それが、友だちと一緒に盛り上がった映画が、私たぶんひとつもないんです(笑)。人に合わせた方がいいと思っていた時期だったので、自分が好きな映画が伝えられなかったし、勇気を出して言ったときに「よくわからなかった」と言われたりしていたので…。
でも、それが今に繋がっているし、だからこそ好きになれてよかったと思える作品も多いんですけど。あ、それで言うと、『ざくろの色』(1969)。
― 宮廷詩人であるサヤト・ノヴァの生涯を、絵画のように美しく幻想的な色彩で描いた映像詩的な作品ですね。
山田 : 高校生のときにテレビ放送されていて観たんですけど、映像に携わりたいなと思ったきっかけの作品です。
牛尾 : どんな映画なんですか?
山田 : 詩人の一生を描いている作品なんですけど…まずは観てほしいです!(笑)
牛尾 : はい、観ます!














