目次
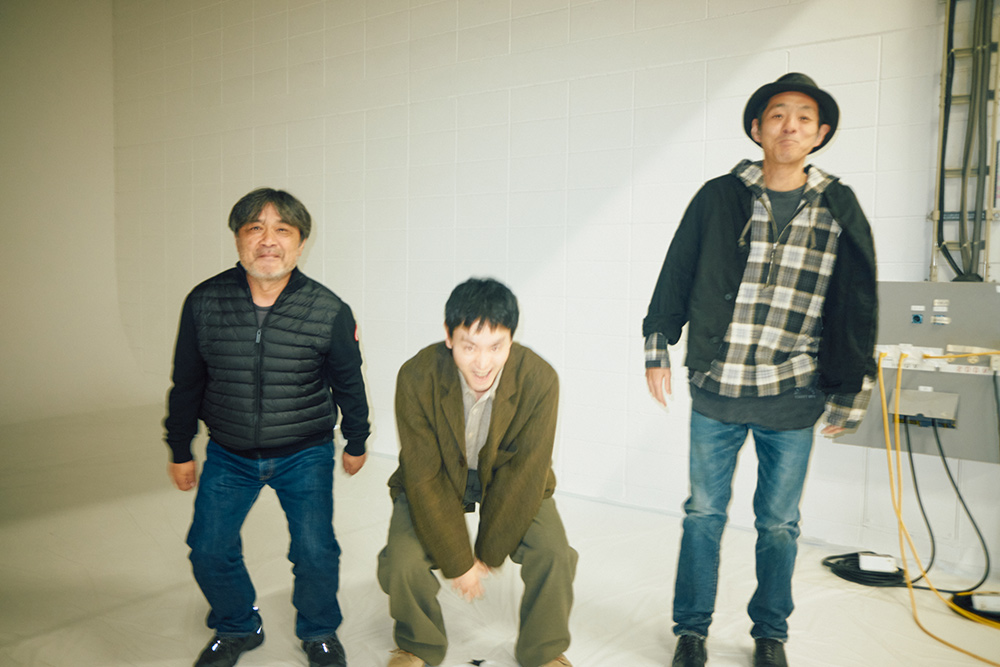
「衝突」から始まるコミュニケーション
― 今作は、南三陸の宇田濱という架空の町が舞台になっていますが、撮影は、気仙沼や大船などに一か月ほど滞在して行われたそうですね。田舎暮らしに憧れ、東京から移住してきた主人公・晋作を演じた菅田さんは、映画の中で釣りをする場面が何度も登場しますが、撮影の合間にも、地元の人と一緒に釣りを体験されたと伺いました。

菅田 : そうですね。釣り船に乗せてもらいました。その船長たちが、撮影の休みの日にバーベキューを開いてくださって。
宮藤 : えー! それは嬉しい。
菅田 : 漁師さんが釣った魚を捌いてくれたり、お肉や貝、ウニ、自家製のめかぶなどをいっぱい出してくださったりして。もう、たまりませんでした。ほんとにこの映画のまんまというか、まさに“もてなしハラスメント”でした(笑)。
― 映画では、宇田濱の居酒屋で、郷土料理をこれでもかと振る舞われる晋作が、「もてなしハラスメントですよ!」と嬉しそうに食べる姿が描かれていましたね。
菅田 : どの料理も最高でした。特に、ホヤは捌く人によって味が違うんです。

宮藤 : あー。それは父親が言ってました。
菅田 : 本当にうまく捌く人のホヤは、フルーツのように甘くて香りも良くて、全然渋くなかったです。
― メカジキの背鰭の付け根を塩焼きにした“ハモニカ焼き”や、タラの芽の天ぷら、ネズミザメの心臓の刺身“モウカノホシ”など、映画には、港町である三陸地方の郷土料理がたくさん登場しますが、どれも本当に美味しそうでした…!
岸 : 現地に一か月滞在していたので、日常的に地元の人が食べる料理をたくさん味わいましたが、居酒屋さんの料理も、お弁当の一品も、どれをとっても美味しいんです。その中でも「これはぜひ多くの人に知ってもらいたい!」と思ったものを、映画にも登場させました。
撮影に協力してくださった、現地の人や漁師さんたちと一緒に時間を過ごしたことで「できあがっていったもの」が、この作品をつくりあげているかなと思います。
― 晋作が宇田濱の人々と出会い、交流していく姿を描いた今作ですが、映画には、晋作を「よそ者」として警戒していた人々が、地元の料理を一緒に食べることで距離を縮めていくなど、食卓を囲むことで動く人間模様が映し出されています。

宮藤 : 実は僕、子どもの時は東北の食の魅力が全然わからなくて。
― 宮藤さんは、宮城県出身ですね。
宮藤 : 親の好みで食べさせられていたという感覚が強くて、正直そんな好きじゃなかったんですよ。“どんこ汁”とか、細かい骨が口の中にいっぱい残るから嫌だなと思ってましたし(笑)。
菅田 : 確かに、子どもだとそう感じるかもしれませんね(笑)。
宮藤 : でも、しばらく地元から離れて、子どもの頃に食べていた味に触れずにいると、思い出すんですよね。各家庭でつくるイカの塩辛のことを“切り込み”って呼んでたんですけど、それも家によって味が違ったんだなとか。
あと、僕が子どもの頃は、物々交換がまだ一般的だったんです。お金じゃなくて、物と物。うちは実家が文房具屋だったので、ノート買ってくれた人が「今お金ないからって、お米で」っていうことがあったり(笑)。
菅田 : ノートとお米! 食物と食物の交換ではなく(笑)。
岸 : あーなるほど。
宮藤 : そうそう。ノート1ダースと米を交換、とか。今思うと「えー!?」って感じなんだけど(笑)、でもそれが「生活」だったんですよね。
― 今作にも、“釣った魚”と“焼酎”を交換するために晋作が居酒屋を訪れるなど、食べ物の交換からコミュニケーションが生まれる様子が描かれていました。
宮藤 : そういう地元での記憶もあったし、僕はこれまで「食を描く」作品をつくってこなかったので、今回は思う存分やろうと思ってました。山菜の天ぷらとか、大人になったらほんと全部美味しいんですよね。

― その中でも作中のハイライトとなるのが、終盤で描かれる「芋煮会」ですね。町に眠るお宝物件“空き家”に目をつけた晋作の会社は、宇田濱での“空き家活用プロジェクト”に乗り出すことになりますが、東京からやってきた会社の人々と、地元住民たちが一堂に会するのが、この「芋煮会」でした。
岸 : 原作である楡周平さんの小説に、宮藤さんがオリジナルで加えたエピソードがいくつかあります。晋作に家を貸し出す百香(井上真央)の幸せを願う男たち4人で結成した“幸せを祈る会”もそうだし、この芋煮会もそうでした。芋煮会は、脚本を読んだ時に、ここがクライマックスだなと感じたんです。
― 岸監督は山形県のご出身、宮藤さんは宮城県のご出身ですが、芋煮会はお二人とも、子どもの頃から親しんできた、東北の風物詩だそうですね。
岸 : はい。まず、宮藤さんと初めてお会いした時に、お互いの地元である東北人の気質についていろいろ盛り上がったんです。相手がいるところでは、はっきりものを言わないけれど、いなくなった後に悪口を言うところがあるとか(笑)。
そういう普段は心の奥にしまっている気持ちを、お酒を飲んで芋煮を食べながら、みんなが吐露するのはどうかと。群像劇のピークを、全部このシーンに持ってこようと思いました。セリフを言ってる人だけじゃなくて、みんなの表情を捉えたかったので、複数のカメラで、長回しで、二日間かけてじっくり撮影しました。

菅田 : 岸組において2カメで撮るなんて…!
宮藤 : これまではあんまりなかったんですか?
菅田 : もうありえないです。テストもあって、2カメなんて。
― 菅田さんと岸監督は、『あゝ、荒野』(2017)で苦楽を共にした間柄でもありますが、今回はそこから7年ぶりのタッグとなりました。菅田さんが驚くぐらい、じっくり撮影したシーンであったと。
岸 : 「破格の撮影」で臨ませていただきました(笑)。都会から来た晋作をきっかけに、みんなが思っていることを一斉にぶちまけ合う。それは衝突でもあるんですけど、コミュニケーションにおいて大切なことでもある。
震災のこと、地元のこと、外から来る人に対しての気持ち、それぞれ抱えていた思いが、宮藤さんのセリフによって全部出てくる場面なので、時間をかけて撮りたいなと思いました。結果、充実したいいシーンになったと思います。
― 『前科者』(2022)や『正欲』(2023)など、これまでも社会が抱える問題や、阻害された人々の生き様にフォーカスしてきた岸監督ですが、東北や地方の町が抱える問題の本質に迫りながらも、ユーモアに溢れた“笑い”の多い作品になっていました。「宮藤さんならではの笑いを損なわずに演出することが自分にとっては大きな課題」とおっしゃっていましたね。
岸 : その時はそう言ってたんですけど、今になって思うのは「コメディ」というジャンルへのこだわりではなくて、例えば撮影する際、僕はいつも「ここは居酒屋さんです」と段取りを説明したら、テストをせずにすぐカメラを回しちゃうんです。
そういう撮り方をしていく中で大切にしているのは、役者さんの芝居をモニターで見ながら、僕自身の身体が震えたり、涙が出たりすることで。

― なるほど、監督自身がカメラの前で行われている現象にどう反応するかを大切にしてきたと。
岸 : この現場では、役者さんの芝居を見ながら、僕はずっと笑っていたんです。編集をする時も、「現場で自分が笑っていたように、笑えること」を基準にしました。
菅田 : それを聞いてふと思ったんですけど、岸監督って前作の現場では、涙は堪えていたんです。悲しいシーン、シビアなシーンで、周りの人が号泣していても、監督はどこか冷静で泣いていなかった。でも今回は逆で、監督が誰よりも先にめっちゃ笑ってるみたいな。それって、何でですかね?
岸 : 解放されたのかも(笑)。
菅田 : 今まで我慢していたものが(笑)。 笑いって、意識でコントロールしづらい感情なのかもしれないですね。面白い。
岸 : それで言うと、脚本をもらった時にまず大笑いしたんですよ。「宮藤さんってすごいな」って思いながら。で、現場で菅田さんたちに演じていただくと、自分のイメージを越えるんです。もう、面白くて面白くてしょうがなくて。それを削ぎ落とさないようすることが、大きな課題でした。
菅田 : 演者からすると、岸監督が楽しそうに笑ってくれていると、現場ですごい安心しました。気持ちがのってくるというか。
岸 : 宮藤さんも見学に来てくださった時、ずっと笑っていましたよね。居酒屋のシーンで、三宅(健)さんがヤンキー的な東北の訛りで熱演されると、その度に宮藤さんが「いるいる、こういう人」って(笑)。

宮藤 : いるんですよ、地元に(笑)。ちょうど染めた髪が伸びて、黒い地毛が出てきている感じもよくて、ちょっと声が甲高いところも。
菅田 : いい声してますよね、三宅さん! わかる〜。実は、三宅さんと共演できることを初めて知った日に、偶然カフェで三宅さんの隣になったんです。
宮藤 : え!?
― 知った日にですか!?
菅田 : そうなんです。この偶然こわ!っと思って(笑)。
岸 : 髪の色も含めて、すごい気合い入れてくれていましたね。現場でも方言指導の人のそばでいろんな言葉を自ら聞きに行ってたし。
宮藤 : 東北弁うまかったですよね。
菅田 : すごく練習されていましたよね。“祈る会”の4人がすごく仲良くて、ロケバスの中でもずっとセリフ合わせされていて。その空気感がシーンにそのまま出ていると思います。

全然主役っぽくない主人公だからこそ
― 宮城県ご出身の宮藤さんはプレス資料の中で、「震災の話になると、僕は疎外感を味わうというか、なんかこう切なくなるんですよね」とコメントされていました。震災以降、ご自身と故郷との距離感というのは、どのように感じてこられたのでしょうか?
宮藤 : そうですね。どう関わるのが正解かわからないと言いますか…、一緒に泣くのもなんか違いますし。震災をテーマにしたドラマの依頼など頂きましたが、当時あの場所にいなかった外側の人間が、勝手に物語にしていいのかと思って、お断りして。それでまた罪悪感を感じて。結局、何もできずにいたんです。
2年経って、NHKの連続テレビ小説『あまちゃん』の脚本に携わり、少し関われた気がしたんですけど、地元の友人からは「なんで岩手なの?」って言われたり(笑)。
菅田 : そうなんですね。
宮藤 : 「今度は宮城でやってね」って言われて。そういう感覚なんだなって。だから今回のお話をいただいた時は「あ、やっと宮城の話だ」とまず思いました。
― これまでも、宮藤さんは『あまちゃん』や『季節のない街』などで、東北や震災に向き合って来られましたが、今回、宮城県について正面から描こうと思えたのは、時間の経過と共にご自身の中で変化してきた思いもあったのでしょうか?
宮藤 : 「今度は宮城でやってね」と言われたこともありますけど、考え続けてきた結果、“これ”という答えはない、というところに行き着いたからかもしれないですね。自分の感じてきた気持ちを、そのまま言葉にできたらいいのかなと。

宮藤 : 「ただ釣りが好きでここに来ただけなのに、なんでこんなに切なくなるんだろう」「この溝はいつまでも埋まらないのかな」っていう、晋作の気持ちやセリフは、僕が感じてきたことでもあって。それをそのまま書くことができました。引き出された感覚はちょっとありました。
― 芋煮会で、竹原ピストルさん演じるケンが晋作に伝える”ある言葉”も、印象に残りました。
宮藤 : あのセリフは、岸監督からのリクエストもあり、もうこれ以上ないだろうというくらい、自分ではわかりやすく書いたつもりでした。あれが全てというか。
― 本作の終盤で、青葉市子さんが歌う曲と重ねて晋作の生活を映していくシーンは、別の場所にいても気持ちが宇田濱に残っているような、晋作の心情が見えてきます。

宮藤 : そこは、岸監督に膨らませてもらったなと思いました。一度田舎に行ってからこれまでの場所に戻ると、今まで当たり前のように暮らしていた場所が違う場所のように映るんだよなって。
例えば、東京に戻ってエレベーター乗っても人が多くて大変だし、釣りしてても隣に誰かいて人を避けて歩く感じとか。東京に戻ってからうまく生活できていない感じというのは、僕もあるので。
岸 : あそこで曲を流すというのは、宮藤さんのアイデアだったんですが、あの曲を持ってきた時点で、もうこの脚本は完成してるなと実は思いました。
この映画では、コロナ禍も震災も描いていますが、どちらも過去のことではあるけど「今も共存しているもの」で。だからこそ、あの歌詞が、僕は全てだと思いましたし、宮藤さんの思いも感じました。
― この映画には、当事者と、そうでない人の間に分断のような距離ができてしまった時、そこにどう向き合うのか、という問いがあったように思います。

― そのコミュニケーションとして、一緒にビジネスを始めるなど、新しい価値観を“共創”していく姿が描かれていたことに新鮮な驚きがあったのですが、演じていた菅田さんはどう捉えていましたか?
菅田 : 僕がこの映画で好きだったのは、みんなが自分の気持ち、我を通したことによって見えてくる形、つまりこの映画の結末でした。
この発想って意外となかったというか。
― “ある過去”を抱えている百香に晋作はある提案をしますが、それに対しての百香の返答には、思わずはっとさせられました。そこから、二人は新しい生き方の形を選択しますね。
菅田 : あそこのシーン面白いですよね。会話をしながら、一度も手を止めず、タイムアタックのように“なめろう”を作り続ける井上さんが見れるシーンでもあって。
岸 : あの包丁さばきのスピード感から、百香の意志がはっきり見えてきますよね。
菅田 : 晋作が百香さんの返答を受けた時、なんかすごい恥ずかしくなったんですよね(笑)。
― ここではネタバレのため詳しくは語れませんが、確かに“あの言葉”は、一瞬にして自分を客観視させられる、ドキッとするセリフです。
菅田 : 晋作と百香、百香の父・章男(中村雅俊)の3人があの形を選択するためには、お互いを思いあっていることを前提に、みんなが自由じゃなきゃいけないんですよね。
既存の価値観にとらわれず、僕はこれがいい、私はこのままがいいと、言えるあの人たちが強いなと思いましたし、そういう人間だから、晋作は宇田濱の人たちに馴染んだんだと思います。

― 晋作は、“空き家活用プロジェクト”にしても、自分から能動的に働きかけるタイプではありませんが、不思議と、周りにいる人たちを変えていく主人公でしたね。
宮藤 : 脚本をつくってる段階で、実は晋作について結構考えたんですよね。主人公として、他の人と何が違うんだろうって、意外とわかりやすく見えてこない人物じゃないですか。
ただ楽しむために移住してきたのに、社長に空き家活用プロジェクトを任されて、言われたからやっているけど…、という。あの微妙な立場は、映画の主人公としては結構新しいですよね。
菅田 : 自分の気持ちも、あんまり吐露しないですもんね。

宮藤 : この人の何が特別なんだろうって考えて…とはいえ、それをしっかり設定しちゃうと「普通の人」じゃなくなってしまうし。でも、現場に行ってわかったのは、ご飯食べて「美味い!美味い!」って言うだけで、スペシャルな存在なんですよ。
何も考えないで「釣れたー!」って帰ってきて、差し入れでもらった刺身やタコを前に「すげー!」って喜んで。そんな姿を見ているだけで嬉しくなるし、それだけで主人公なんですよね。でも、それだけで十分な主人公なんですって説明しても、なかなか理解されないですよね。「ただ、食べてるだけで?」ってなる(笑)。
菅田 : ほんとですね。そう説明されても主人公とは思えない(笑)。

宮藤 : 言葉にすると、全然主人公っぽくないけど、それがいいんですよね。
― 宇田濱を訪れる人に、晋作のような人はいなかったのかもしれませんね。何かをしてあげたい、寄り添って助けてあげたい、というのではなく、ただ純粋に地元の食べ物を美味しいと喜んで、この土地のことを好きだと言ってくれる人が。
菅田 : そうかもしれません。
岸 : 今のお話でいうと、罪のない人なんですよね、晋作って。
菅田 : ほんとそうですね。一歩間違えると、すごく人を傷つけてしまうけど、そうならないのが晋作で。
岸 : 罪のない人が、出会いの中で、罪も背負わなきゃいけないくらいの“決断”を最後に迫られる、という話だと思うんです。それでも、晋作は罪のない生き方を選ぶんですよね。そんな気がしますね。

菅田将暉、宮藤官九郎、岸善幸監督の「心の一本」の映画
― 最後に、みなさんが大切にしている「心の一本」の映画について教えてください。
宮藤 : わー、来た!(笑)
― 前回、『1秒先の彼』(2023)で宮藤さんにインタビューさせていただいた時は、黒澤明監督の『どですかでん』(1970)を選んでくださいました。
宮藤 : そっか、今年公開された映画じゃなくてもいいんだ。でも「心の一本」だから、前と違うの言ったら、嘘つきになっちゃうかな(笑)。
菅田 : 心の中には、何本かあるということで。
― 今作『サンセット・サンライズ』が、他者との関わりや家族の形において“新しい価値観”を映し出していた作品でしたので、新しい景色や価値観を見せてくれた映画、はいかがでしょうか?
岸 : 僕は、宮藤さん脚本、行定勲監督の『GO』(2001)ですね。
宮藤 : えー!
― 『GO』は、在日韓国人の主人公が、恋愛や友情などを通して自身のアイデンティティに目覚めていく姿を、ポップに映し出した青春映画ですね。岸監督にとって、どのようなところが新しかったのでしょうか?
岸 : 今回、宮藤さんの作品をいろいろ観て、どれも面白かったんですけど、この映画の衝撃は大きかったです。本当にいろんな価値観を変えたと思いましたね。まず、社会派なテーマじゃないですか。
菅田 : そうですよね、国籍の問題とか。
岸 : だけど、主人公が笑かせるという。新しい世代という捉え方もありますけど、自分が知らなかった世界を見せてもらえたことが、大きかった。窪塚(洋介)さんも絶品でしたよね。
― 菅田さんはいかがですか?
菅田 : えーどうしようかな、一本…。ちょっと違うかもしれないですけど、一昨年『太陽がいっぱい』(1960)という映画を観たんです。
宮藤 : アラン・ドロンの。
菅田 : はい。面白い映画でした。説明不足感と、あんなに悪人なのに笑えるとか、ドキドキして観ちゃう感じとか。そういえば、アラン・ドロンの作品ってちゃんと観たことなかったなと思って、初めて『太陽がいっぱい』を観たんですけど、結構衝撃的でした。
― 『太陽がいっぱい』は、御曹司の友人とヨットで旅に出た青年が、友人を殺害し、財産と恋人を奪おうとする様子を描いた作品で、主演のアラン・ドロンは、この映画をきっかけに世界的スターへと駆け上がっていきました。これまでご覧になってきた映画と比べて、新しいと感じたのはどんなところでしたか?
菅田 : ラブストーリーでもないですし、何かと戦うかっこいい映画でもないし、サスペンスでもない。なんなら、よくわかんない会話のやりとりも多いのですが、いつのまにかエキサイトして観ている自分がいるんです。エンタメ性というか。
― 魅せられてしまう、という。
菅田 : そうですね。「真面目って面白いな」と思ったんです。
岸 : あぁ。
菅田 : 今作の『サンセット・サンライズ』もそうなんですけど。それだけで魅せることができてしまうというか、まさに「これで映画になるんだ」という気もしました。
― 宮藤さんはいかがですか?
宮藤 : 難しいな、これ(笑)。え、一本ですよね?
― 最近ご覧になった映画で衝撃を受けた作品でも!
宮藤 : 最近…あ、『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』(2024)は衝撃でしたね。
― 『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は、「バッドマン」に登場する悪役・ジョーカーの誕生秘話を描いた『ジョーカー』(2019)の続編で、社会への反逆者、民衆の代弁者として祭り上げられたジョーカーのその後を描いています。
宮藤 : 僕は一作目の『ジョーカー』がすごい好きだったから、あえて過度な期待をして観に行ったんですけど、「え、こういう映画なのか」ってなって。でも「好きな映画の続編だから、好きなはずだ!」と思って、もう一回観に行ったんですけど…うん。
岸 : (笑)。
菅田 : 戦ってる(笑)。
宮藤 : いろんなこと考えました。「あ、これは続編じゃないんだ」とか「続編だからって、〝続き〟を描かなくていいんだ」とか。全力で肯定して。でも…はい、もうこれ以上はやめます(笑)。ホアキン・フェニックスとレディー・ガガの二人は、すごくかっこよかったですね。ミュージカルシーンも最高に良かったです。

- 1.PINTSCOPE公式X @pintscope をフォロー
- 2.下記ポストをリポスト
- ※当選者にはDMにてご連絡いたします。
◤ 映画『#サンセット・サンライズ』
— PINTSCOPE|ピントスコープ (@pintscope) January 17, 2025
サイン入りプレスシート 1名様にプレゼント◢
📝応募方法(2/2〆)
①@pintscope
をフォロー
②このポストをRP
当選はDMで📩#菅田将暉 さん×#宮藤官九郎 さん ×#岸善幸 監督インタビューはこちら▼https://t.co/Tx4ofJ0KjV… pic.twitter.com/2I3ooMse4G
- ・当選は、応募締切後、厳正なる抽選にて決定いたします。
- ・応募締切後1週間以内にPINTSCOPEのXアカウントより、当選者様のXアカウント宛にダイレクトメッセージにてご連絡をさせていただきます。賞品発送のため、お名前、ご住所、お電話番号等をお伺いいたしますので、指定の日時までにフォームへの入力をお願いいたします。
- ・PINTSCOPEのアカウントのフォローを解除されますと、応募が無効となりますのでご注意ください。
- ・PINTSCOPEのXアカウントに既にフォローいただいている方も参加資格がございます。
- ・明らかにプレゼント応募目的で作成されたアカウントからの応募は、抽選時に対象から外れることがありますので、ご注意ください。
- ・以下に当てはまる場合、当選を無効とさせていただきます。
- ①当選者様の都合により、指定の日時までにフォームへの入力ができなかった場合。
- ②住所が不明等の理由により当選者様への賞品がお送りできない、または運送業者により返送された場合。











