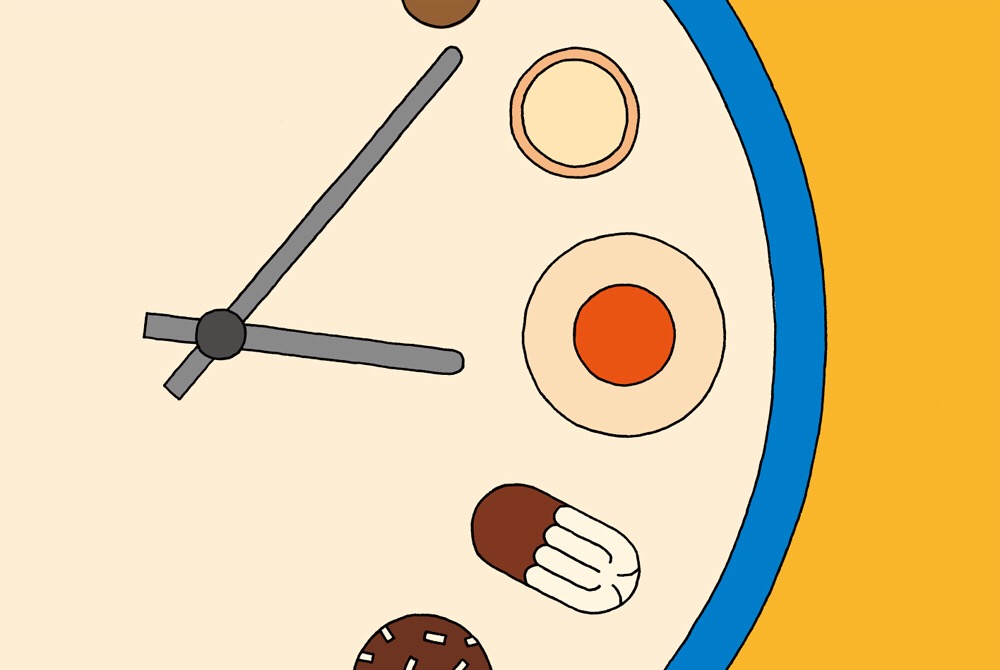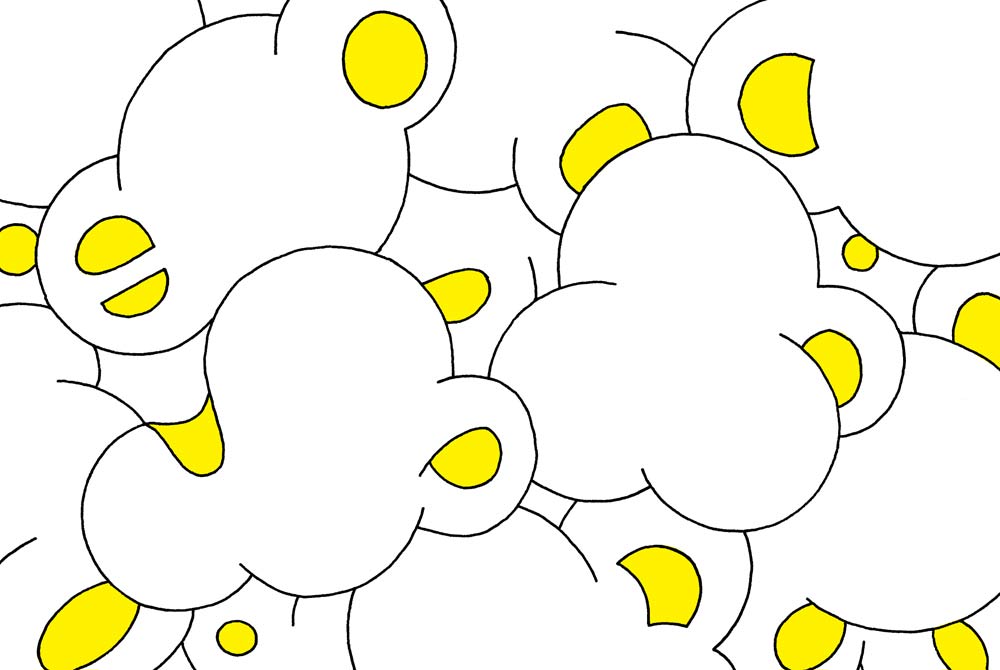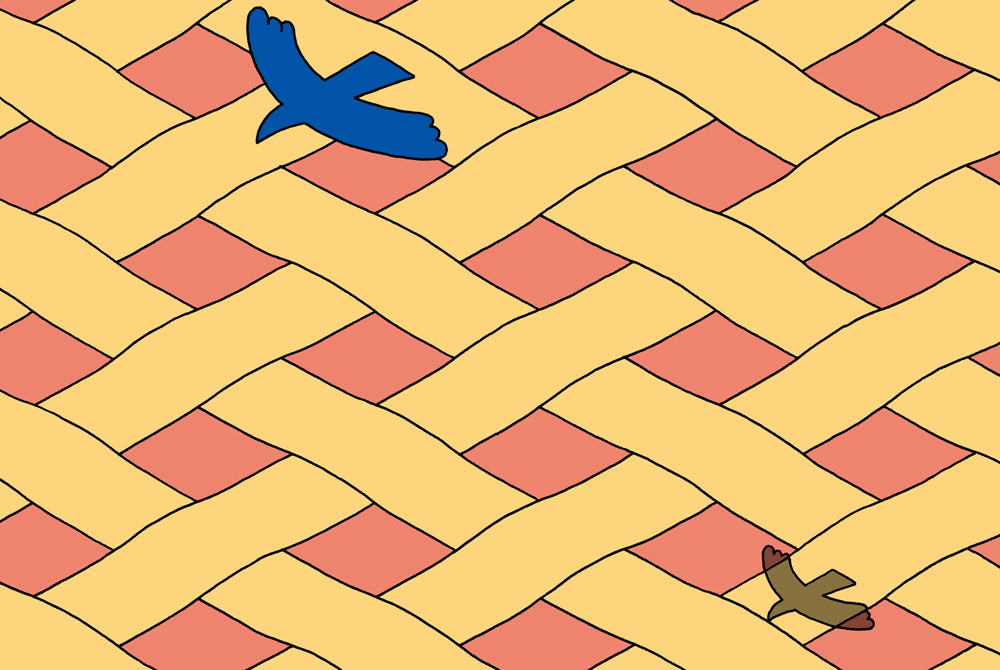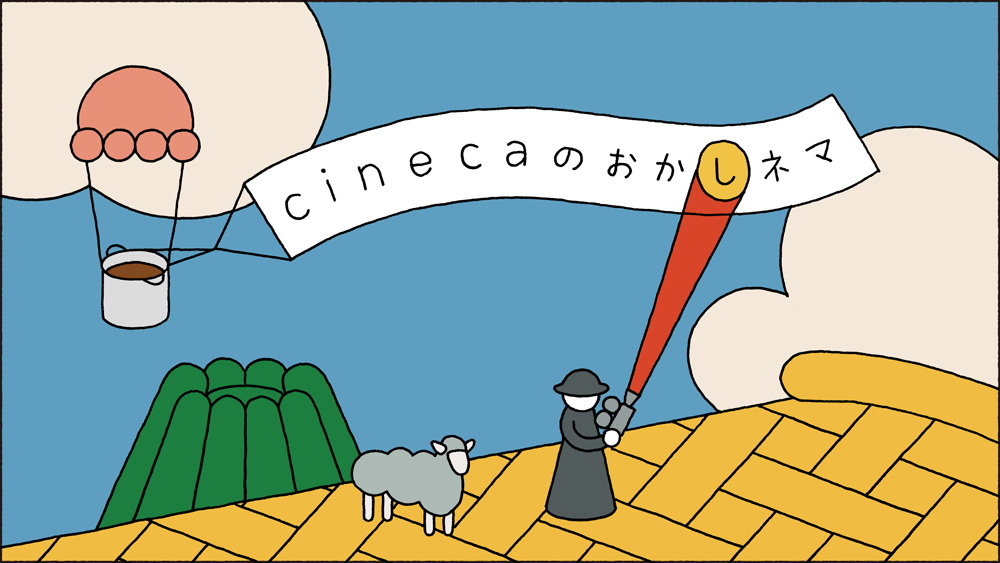
365日クッキーを欠かさない。テーブルのセンターに鎮座させ、電子レンジの中や食器棚の隙間にも、いつもひっそりとクッキーを潜ませている。
それはコンビニに売っているショートニングたっぷりの気楽な100円程度のものだったり、ちょっとしたパティスリーで買い求めた上質でバターたっぷりなもののこともあれば、お菓子の試作の余り生地で作った歪(いびつ)な形のもののことも。家にクッキーがあると思うと、仕事も家事も安心して進むし、映画のお供に困ることもない。私がいつでもどこでもクッキーを買いすぎてしまうのは、ただの心配性によるものなのか。ひとつ明らかなのは、家にストックされたクッキーらが私の守護天使のように“稀に見る安心感”をもたらしているということだ。
はじめましてを解すものとして、お菓子が務める役割があると思う。特にクッキーは、サイズや重さ、素材感がちょうどいいと感じる。切り分ける面倒臭さや温度変化による溶解の心配もなく、簡単に摘める気軽さが、心情や時間や空間のシェアにも結びつくのではないか。大きすぎず、小さすぎず、硬すぎず、柔らかすぎず、口の中でちょうどいい具合に咀嚼を楽しめる。手が汚れすぎないことも相まって、これこそがおやつの成功例です。と胸を張って言いたくもなってくる。
『歓びを歌にのせて』は2005年に日本で公開されたスウェーデンの映画だ。天才指揮者として世界的な成功を手にした男ダニエルが、病を患ったことをきっかけに幼少時代を過ごしたスウェーデン北部の村に帰る。そこで小さな協会のコーラス隊の指導を始めることが物語のはじまり。
問題のない人なんていないと考える私だが、この映画もそんなことを伝えたいのかもしれない。心から音楽と触れることで浮き彫りになっていく人間模様。小さな村に少しずつ変化が起きていくその泥臭いエネルギーから最後まで目が離せない。
ずっとプロフェッショナルの世界で生きてきたダニエルにとって、アマチュアコーラス隊の指導はすぐにうまくいくものではなかった。そんなときに潤滑剤として登場するのが“コーヒータイム”だ。
それは、スウェーデンの言葉でいうと「フィーカ」。コーヒーとお菓子とともに一息つく時間だ。歌の練習場のすぐ目の前のテーブルに(多分コーラス隊の誰かの手作りの)何種類かの焼き菓子が並べられ、音楽の隙間を縫う。「音楽とは聴くことだ」とダニエルは言うが、音楽に留まらず、それがコミュニケーションの正解なのかもしれない。つい話すこと、歌うこと、伝えることに必死になってしまいがちだが、聴くことは自分の声を探す行為にも重なるだろう。
フィーカにはいろんな焼き菓子が並ぶが、そこで欠かせないお菓子の一つがクッキーである。おそらく無意識に求めているのはあの色ではないか? あの焼き色だ。温かみを帯びたたまご色とじんわり焦げ色の間のなんとも形容しがたい安心色。ちょうどよく火が入ることで変化したその「おいしいカラー」にびっくりするほど簡単に魅了されてしまう。
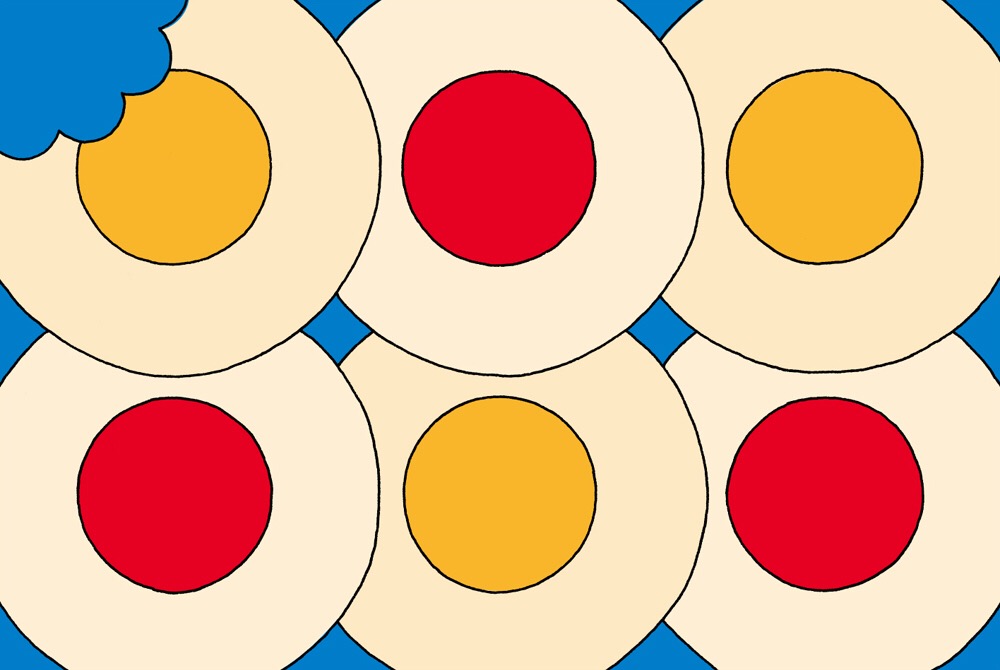
私は、クッキーをつくるたびにクッキーというお菓子のバランスの良さに関心する。材料の親密性、判然たる調法、大概の美味しさ、この黄金の3バランスがとれたお菓子もあまりないだろう。必要なのは、バター、砂糖、たまご、小麦粉という身近な4素材のみ。バターをほぐしたところに砂糖とたまごを入れてよく混ぜ、最後に小麦粉を加えたら軽く練り、好きな形に成形して焼けば完成する。焼き時間も10~15分程度と短くていいし、成形が綺麗に出来なくても大抵はおいしく仕上がる。それに、クッキーのレシピを基本にすれば、様々な焼き菓子への発展性も期待できるのだ。失敗も少ないお菓子なので、はじめてのお菓子作りに悩む人がいたら、まずはクッキーを作ることをオススメしよう。
なんでも最初はバランスをとるところからはじめたい。だいたいのことはとっ散らかった状態で始まるからだ。欠けていたもの失くしてしまったものを補ったりまた捨てたりと、基本のバランスがとれたところでその中の個を探し出し、自分だけの新しいバランスを掴む。その傍らにはいつもクッキーを置き、毎日の、人生の潤滑剤として、呼吸するように口に運びたい。その、あたりまえの「おいしい」がまだ見ぬ新しい「おいしい」に膨らむことに期待して。