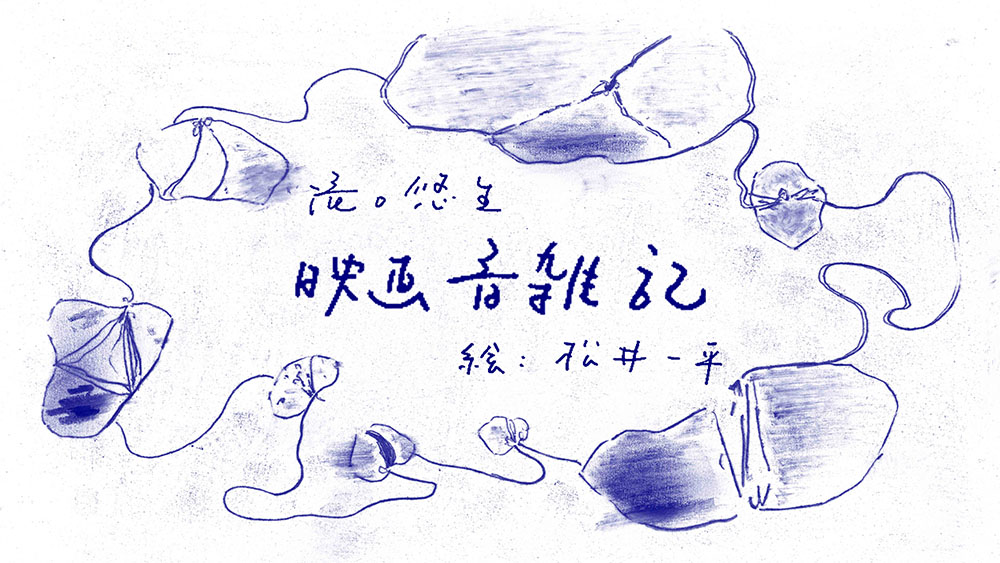
話が暗い方へさしかかると、犬が吠え出す。
自殺を決意した男が、手伝い人を探し自動車で山をうろうろしている。まずは若いクルド人の兵士を、次にやはり若いアフガン人の神学生を車に乗せ、山頂近くまで連れ出す。そして彼は報酬と引き換えに持ちかけた「仕事」の詳細、すなわち自分の自殺幇助について切り出す。
思いもよらぬ依頼に、同乗者たちは戸惑う。兵士の少年は車を降ろしてくれと懇願し、神学生は自殺を思いとどまらせるべく説得する。イスラム教で自殺は禁じられている。
男はしかし頑なである。そして、なぜ自殺を決意したのかについては決して語ろうとしない。その理由は、車に乗った青年たちにも、映画を観ている私たちにも、最後までわからない。男がそう決めるに至ったなにかが、これまでの彼の人生にあったことだけがわかる。

理由も先行きも不明のまま、話の見通しはつかない。のろのろと山道を走る自動車のなかで、死への意志が宙ぶらりんになる。そしてそのたびに、山のどこかで吠える犬の声が聞こえてくる。画面に犬の姿はほとんど映らないが、死の予兆に反応するみたいに、犬たちの声だけが映画のなかに現れる。
この映画には音楽がほぼ使われていない。途中何度か、採掘現場の見張り小屋で流れているラジオかなにかの音楽が聞こえるが、これもあくまで環境音であってBGMではない。自動車の音、通りがかりに近づいてはすぐ遠ざかる沿道の人々の声、工事の音、そして山に響く動物や鳥の声が、この映画の音響だ。
唯一、エンドロールに向かう場面で、ルイ・アームストロングの哀感たっぷりのブルースが流れはじめる。観たことのあるひとならばご存知だろうが、この映画のエンディングは、先に書いた車中劇とは決定的に隔たった場所に行き着く。その最後の場面を見ると、この映画のなかのあらゆる音が、単なる自然音ではなかったことに気づかされる。犬は山のなかでいつでも吠えているが、映画のなかでは吠えるべき時にだけ吠える。それが特別なものとして聞かれ、響く瞬間にだけ吠える。
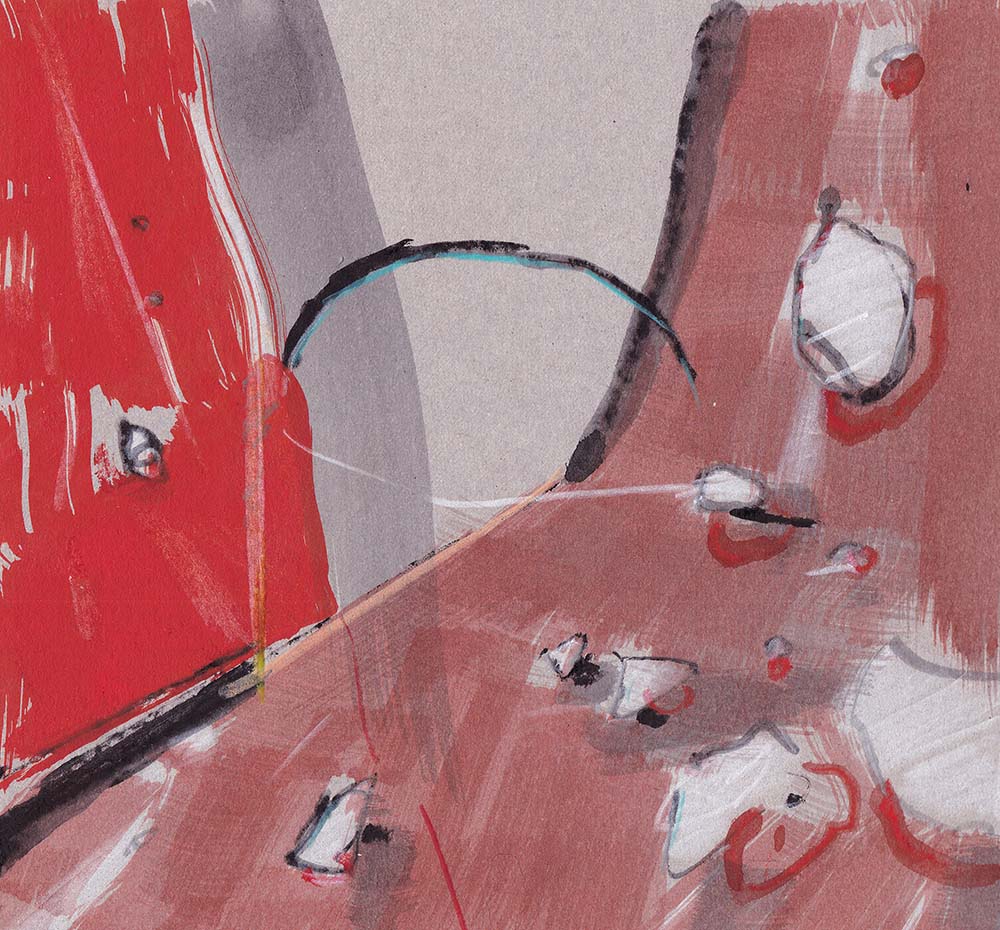
私たちは周囲で鳴っている音のすべてを、たえず聞き続けられるわけではない。音を聞く、という行為は常に意識と無意識とのあいだにある。姿も、出所も見えない、どこか遠くで鳴った音が自分の耳まで届くこと。そのあいだにあるのは、単なる距離だけではない。いま私に聞こえる音は、私の耳とその音の出所とのあいだで、なにか少しでも変化があれば、全然違う音になり、最後に私の耳と意識とがそれを遮らなかった時に、はじめて聞こえる。そうやって聞こえる音はいつだって、いくつもの偶然が重なった、特別で奇跡的な結果だ。
最後の場面を見る限り、男は映画のなかを死なずに生き延びている。もちろん、そこには別の解釈も可能なのだが、少なくとも、頑なだった男の意志が、三人目の同乗者である老人バゲリさんの話を契機に大きく揺らいだことは間違いない。
バゲリさんは、博物館で剥製をつくる仕事をしている。生物の身体を生と死のあいだに留め置くような仕事だ。金に困っているバゲリさんは、男の自殺幇助の依頼を引き受けるが、同時に自分自身がかつて自殺を思いとどまった時の話を男に語って聞かせた。やはりここでも犬が遠くで吠えはじめる。
男にとって特別だったのは、たぶんバゲリさんの話そのものではなく、頑なだった死への意志が揺れ動いた瞬間、その揺れ動きを信じようと思って自動車を引き返した瞬間だ。車を降りて、男は走る。一時間後に、結果がどっちに転んでいるかで、そこから先の自分の人生が大きく変わる。ここが人生の分かれ道だ、と思いながら駆けるほかないから駆けている、みたいな瞬間がたぶん誰にもある。そんな時は、見える景色、聞こえる音のすべてが、特別な意味を持つ。その特別さにはなんの根拠もなく、説明もできないけれど、そういう気持ちがひとの人生を動かす。そのように「いま」の緊張が極度に高まった時に、人生という全貌のつかめない長い時間が私たちの前に現れる。この映画においては、その合図みたいに犬が吠える。
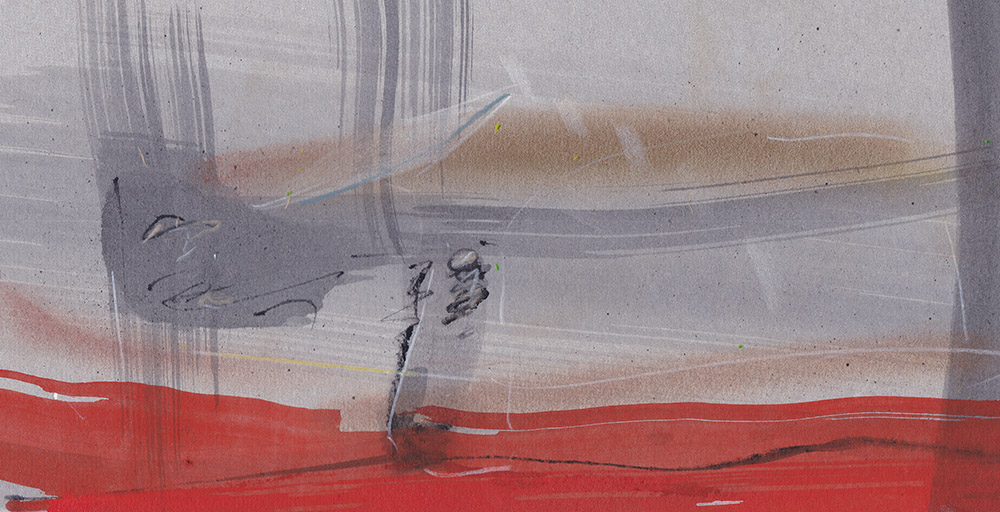
たとえば自分にとって特別な日のことを思い出してみる。受験の合格発表とか、結婚式とか、大切なひとのお葬式の日とか。その日目にした、あるいは耳にした、自分以外にとってはなんでもないような景色や音をひとつふたつ覚えている。前に座っていたひとの着物の色とか、わずかにささくれた畳の目とか、台所から届く声とか、場違いな流行歌とか。特別な瞬間には、そんな景色や音を、まるで深い意味があるみたいに見たり聞いたりしてしまう。その瞬間に感じとった意味は、あとになれば大げさで恥ずかしいように思えるかもしれないけれど、あとから思うことや客観性がいつでも正しいとは限らない。そういう瞬間には「あと」なんかない。



