目次

前回、あれだけ「恋愛映画にハマりそうだ!」「他の恋愛映画も見てみたい!」などと書いた僕ですが、あれ以降実際に恋愛映画を見たのかと言えば全く見ておらず、今現在最も気になっている映画といえば『MEG ザ・モンスター』(2018年9月公開予定)という全長23メートル、体重20トン、歯は25センチの巨大なサメにジェイソン・ステイサムが立ち向かう映画でありまして、いや、だって気になりません? 一人の人間がどうこうできるサイズじゃないでしょ、7階建ての建物ぐらいの大きさのサメですよ? 普通そんなのに立ち向かわないですよね? ジェイソン・ステイサムに普通サイズのサメを当てたところで瞬殺するでしょうから、対抗できるサイズを模索して行った結果23メートルになったのかもしれないですけど、きっとジェイソン・ステイサムは23メートルのサメもやっつけるんだろうし、そうなると「対ジェイソン・ステイサム」要員のスケール感を増大させていくしかなく、最後は「ジェイソン・ステイサムVS太陽」みたいな事になって、最終的には太陽と直接的な殴り合いで決着をつけるのではないかと予想しますが、そうなったらどうしようと勝手な心配が止まらないのです。
つまり、相変わらずジェイソン・ステイサムのせいで恋愛映画どころじゃなかった僕ですが、そうも言ってられないので重い腰を上げて鑑賞した今回の恋愛映画はこちら。
『愛を読むひと』
前回もそうだったんですが、映画の中で繰り広げられる情景や交わされる会話が自分の過去を摘んで引っ張り上げます。
実際に同じような出来事があった訳では無いのですが、自らがしでかした浅はかな出来事や軽薄な会話、その時は「それが全て」だと思っていたからこそ生まれた幼稚な決意など、今思えば赤面するような想い出の数々が掘り起こされ、目の前の映像を観ながら自身の過去と触れ合う時間となりました。
15歳の少年、マイケルは帰宅途中に具合が悪くなり、そこを通りがかった21歳も年上の大人の女性ハンナに介抱され、それがきっかけでベッドを共にするようになります。
マイケルはヤリたい盛り、肉に溺れる少年の心情というものは共感でき、その後、身体を重ねていくに従って「相手は肉ではなく、自分と同じ人である」事に気が付いて「体だけじゃなく心も欲しい」と思っちゃうけど今更それが言えないもどかしさ、分かります、肉体的な満足が得られたから心も潤したいと言う身勝手なセンチメンタルなのかもしれませんが、そこでモジモジするのは分かります。
マイケルがハンナに「出会って四週間、君なしでは生きられない、それを思うだけで苦しい」とか言うんですけど、そう思っちゃう気持ちもわかるんですよね、15歳の戯言といえばそれでお終いなんですけど、それはきっと大人側からの意見であり、僕も初めて付き合った女の子の事が好きで好きで「あの子と今すぐ結婚したい」って姉ちゃんに言ったらゲラゲラ笑われて「最初はみんなそう思っちゃうんだよねえ」みたいな上から目線でたしなめられたので危うく男女間での殴り合いに発展しそうになった事、ありました。
今思えば姉ちゃんの言ってることは「その通り」であったのですが、当時はそんな事に気がつくはずもなく「この決意こそがゆるぎのない真実」だと思って、自らの発言を戯言扱いする全ての人に反抗していたものです。
なので、そんな猪突猛進なマイケルに対してハンナが心揺れながらも距離を置き、たしなめ、例えばマイケルに「怒らせるつもりはなかった」と言われた時に「あなたが私を怒らせる? それほどの相手だと思う?」とか言ってスカすハンナの心情も理解できます。
だって、ねえ、自分は大人だし、相手子供だし、燃え上がってんの今だけだろうし、嬉しいけど、私があなたの全てでは絶対に無いだろうし、今はそうなんだろうけど、絶対そうじゃなくなる時が来るし、あなたの言葉を信じたいけど、信じるほど自分は子供じゃないし、嬉しいけども、嬉しいのだけれども。
かつて僕が手も繋いだことのない相手に対して「お前しかいない、結婚したい」と思った気持ちっていうのは、いま思えば子供の戯言で浅はかだったけれども、だからと言ってそれは嘘ではなく、当時の僕としては「本気の決意」であったわけで、それが分かっているからこそ邪険には出来ないし、でも真っ正面から受け入れる訳にもいかないし、うん、受け入れる訳にはいかないんだけど、あの頃のハンナは日々を生きていくことへの肯定を模索している時であったのかもしれないと思うので、自分を「綺麗だ」と言って来る無邪気な子供の言葉を受け入れたくなる気持ちもわかるんですよね。
この映画は基本的にマイケルの主観で進むので、ハンナが巻き起こす数々の「なんでそれしちゃうの?」っていう行動、例えば「セックスさせる前に本を読ませる」とか「なぜナチスに参加したのか」などの疑問はマイケルの言葉で補完されたり、後々に出てくる証言や事実などでこちら側にも提示されたりするんですが、最後まで「解き明かされない謎」もありまして、
それが
「なぜハンナは何も言わずにマイケルの前から去ったのか」
という事と
「なぜハンナはあの結末を選んだのか」
という事で、マイケルからしたら「きっと」「多分」「そういう事なのだろう」という形で推し量るしかなく、それはモヤモヤするけれど、男女間に於ける「相手の得体の知れなさ」って永遠に付きまとうもので、それがまた自らがかつて経験した「女の子に対する答えのない答え合わせ」をした時間を思い起こさせるのです。
昔、女の子と同棲していた時に、僕がバイト先から自宅に帰ってドアを開けたら、女の子が台所の流し台で包丁を手に下を向いて固まっていたんですよね。
お互い無言で目が合って、とりあえず僕はゆっくりドアを閉めて外に出て
「これは一体何が起こっているのだろう」
と考え込んでみたんですが、考えていても答えが出ないので部屋の中に戻る事にしたんですが、一回自分でドアを閉めちゃったから「今更どういうテンションで戻ったらいいか分からない」感じになってしまい、意を決して「さっき戻ったのは俺ではなく、いま、はじめて帰ってきましたよ感」満載でドアを開けてみたんですが、その時は既に台所に彼女はおらず、ではどこに居たのかといえば居間でテレビ見ながら「おかえり」って言いながら「さっき台所にいたのは私ではなく、いま、はじめてあなたと目が合いましたよ感」満載で迎え入れてくれたので、さっき見た光景は時空のねじれが起こした現象だと思い込む事にしましたが、そう思えるはずもなく、だからと言って話題に出すこともできず、その後もいつも通りの時間が過ぎていったので、勝手に僕の中で「料理の最中、ふと考え事をして電池が切れたように固まってしまったのかもしれない」もしくは「僕が帰ってくる足音が聞こえたので、僕に一瞬自殺のポーズを見せることで僕の何かしらを改めさせようとしたのかもしれない」「どちらにしろ、とりあえず優しくしよう」という答えを導き出したんですけど、そんなものは結局僕が勝手に導き出した「答えのない答え合わせ」でありまして、彼女に対して「何をしていたのか」ということは聞けず終いであったし、その後はそんな類の出来事も起こらず、仲良く数年一緒に暮らして、今は別々で幸せにやっておりますが、何故僕がそれを聞けなかったのかと言えば、それはきっと「本当を知ること」で「自分の愚かさ」を自覚したくなかった自分の醜さであり、「他人に対してのみでなく、自らに対しても曖昧でありたい」という「逃げの姿勢」なのかもしれないですけど、マイケルが獄中にいるハンナと(会おうと思えば会えるのに)会わなかったのは、僕と同じく「ハッキリとした答えを出すことが自分にとっての正解ではない」と思ったからではないでしょうか。
ダサいですよね、ダサいです、だけど、真実にぶち当たって前に進めなくなるより、(僕にとって都合のいい答えを出しつつ)諸々を曖昧にする事で前に進めるなら僕はそっちを選びたいと思っちゃいます。
だって、真実こそが正解だとしたら、笑っていられなくなるでしょう?
話が随分逸れましたが、そういった男女間のすれ違いや相手の「なんでそれしちゃうの」っていう不可解さなどが悲しい事実とともに浮かび上がるこの映画、23メートルのサメをやっつける映画では決して浸れないであろう余韻を感じつつ、23メートルのサメにも負けず劣らずの、あなたがかつて愛した「得体のしれない不可解で愛しいモンスター」に思いを馳せて、決して答えの出ない答え合わせに悶々としてみるのも良いのではないでしょうか。 そういう夜だって、必要だと思いますよ。
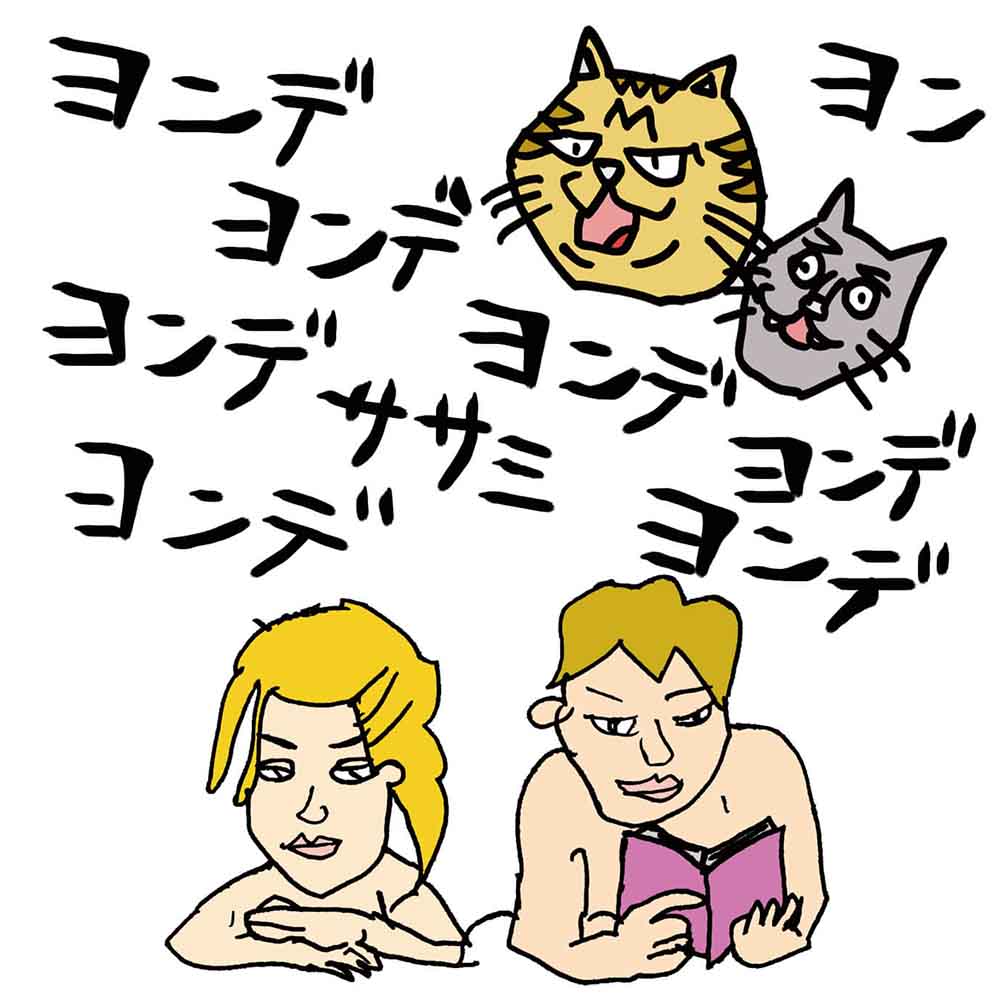
- 世間体なんて気にしない!そんな恋愛は「ワガママ」ですか? 『ノッティングヒルの恋人』
- 思い通りに進まなかった2020年。 世界一頑張って生き抜いたあなたへ休息を『ホリデイ』
- 恋愛映画だけど、恋愛映画じゃない!ドブ・泥に浸かったハミダシ者たちの賛歌『道頓堀川』
- 死にたくなる夜を超えて。 『パーティで女の子に話しかけるには』
- お前を傷つけている記憶が無い事が怖い『50回目のファーストキス』
- メーテルと過ごした、あの頃には戻れない。『あの頃ペニー・レインと』
- 誰もが「隠したい自分」がある。 『パリ、嘘つきな恋』
- モブだって、恋をする。 『サイドウェイ』
- 夫の見えているもの、妻の見えているもの『ブルーバレンタイン』
- 俺はこれを愛と呼べるか? 『彼女がその名を知らない鳥たち』
- あなただけには褒められたいけど、あなたしか褒めてくれないのは不幸だ。『天才作家の妻』
- コンビーフみたいに可愛い君。 『マイ・プレシャス・リスト』
- リリーの幸せは、リリーが決める。 『男はつらいよ 寅次郎相合い傘』
- 夏目雅子だから仕方ない。 『時代屋の女房』
- 答えのない答えあわせ。 『愛を読むひと』
- なんでかわかんないけど、すげぇ好き。『あと1センチの恋』



