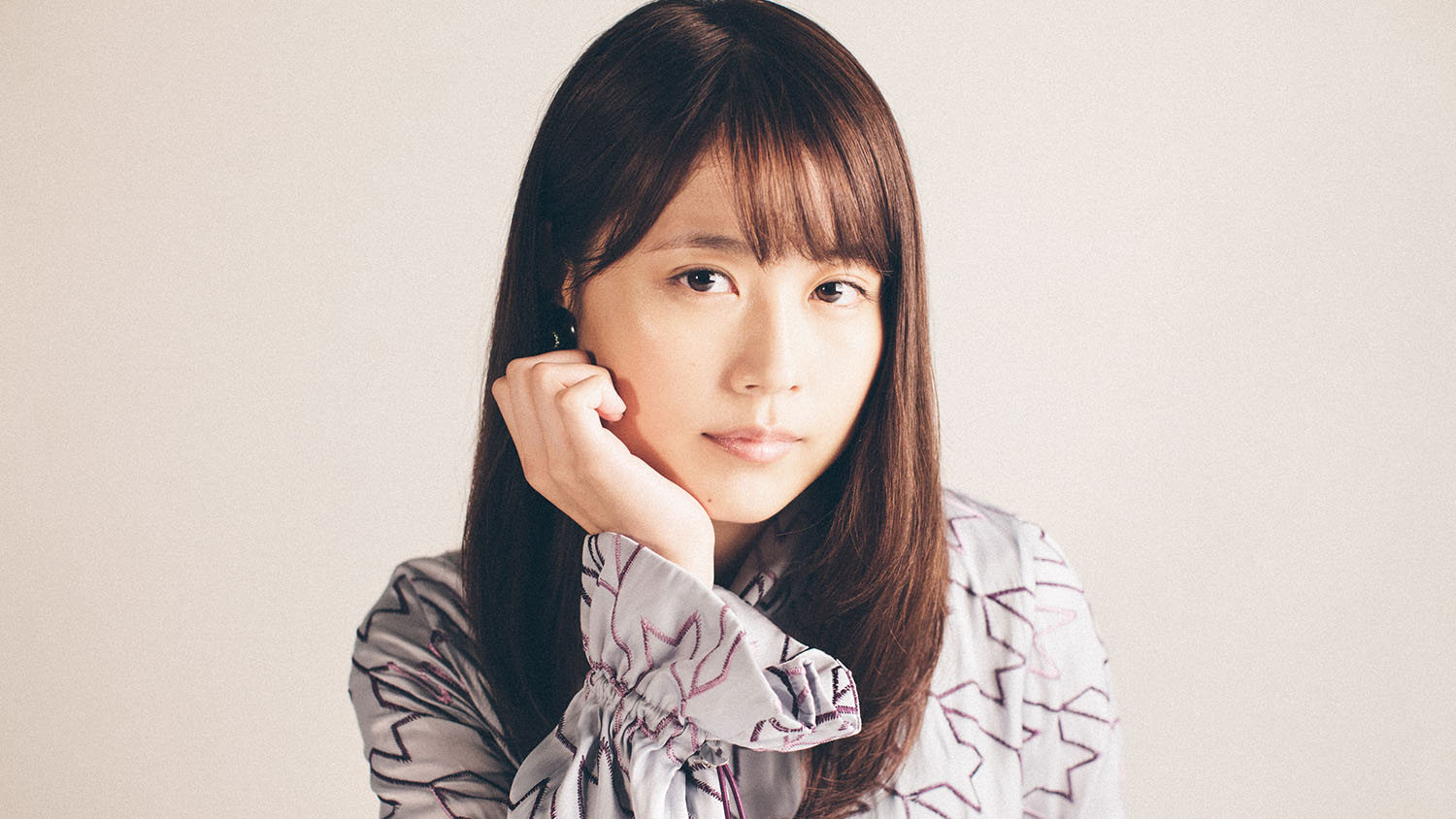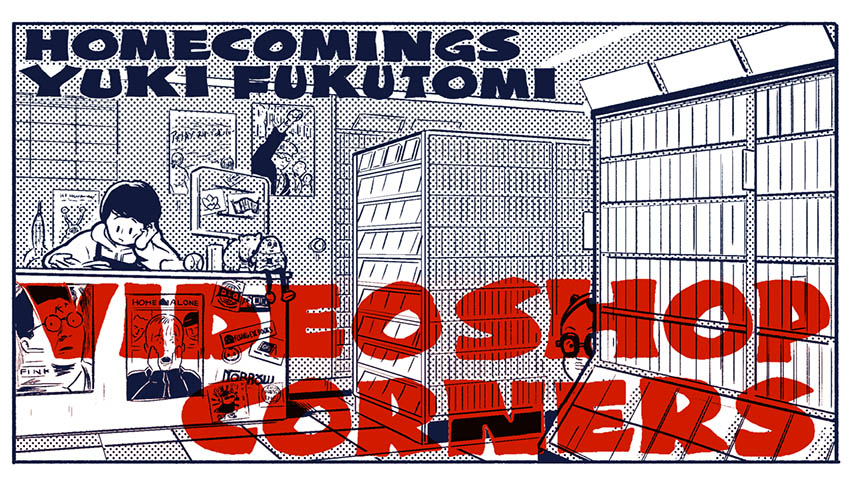
レンタルビデオショップ・アラスカで、新作の映画のビデオをレンタルしたのは後にも先にも、『トイ・ストーリー2』だけだと思う。
新作は子供ながらに手が届かない贅沢品のような気がして、特に誰から言われたわけでもないけれど、そのコーナーの映画はレンタルしないようにしていた。その頃から一度観た映画を何度も何度も繰り返し巻き戻して観るのが好きだったということも、そしてアラスカにビデオを借りに行くのは大抵が夜だったということも、一泊二日で返さなくてはならない新作に惹かれなかった理由のひとつだ。
僕が住んでいた石川県には、その頃映画館が本当に数えるぐらいしかなかったし、お父さんもお母さんも公開中の映画を映画館に観にいくというタイプではなかったので、僕にとっての新しい映画はアラスカの新作コーナーに置かれているものか、店のドアに張ってある新作情報に(映画は赤色の文字で、CDは青色の文字で)書かれているものだった。
『トイ・ストーリー2』は、もう何週間も前から大きなパネルが入り口に飾ってあって、その日付が来るのを僕は今か今かと待ちわびていた。その当時、僕が待ちわびていたものはポケットモンスターの金銀の発売日と自分の誕生日、そしてクリスマスぐらいだった。
パネルにはウッディとバズやスリンキーといった仲間たちと新しいキャラクターのカウボーイの老人とカウガール、西部劇に出てくるような馬のおもちゃが描かれていた。まだインターネットもなかった時代の小学校低学年だった子供には、新作の映画のあらすじがとても遠い情報だったから、僕はそれがどんな物語なのか知るすべもなかった。
初めて借りた一泊二日のシールが張ってあるビデオは、なんだか新しいプラスチックの匂いがした。新作のまっさらなプラスチックの匂いは、旧作のあの独特なほこりっぽい匂いと違って、夏の長くて短いあの一ヶ月のことを思い出させた。
夏休みになると観たくなる映画はたくさんある。例えば『アメリカン・スリープオーバー』や『アドベンチャーランドへようこそ』、『キングス・オブ・サマー』に『レディ・バード』といった映画が観たくなる。それらは夏という季節が、新しい学年へまたは高校から大学へという、大きな節目として描かれている青春映画たち(アメリカの新学期は秋から始まるのです)。期待と不安の入り混じった夏という季節にやってくる、胸の痛みやワクワクしてじっとしていられない不安定な衝動が、物語のそこかしこに漂っているような気がして大好きだ。
アジアのジメッとしていて汗が体にずっとまとわりついてるような、夏の暑さが画面の中にそのまま映し出されているようなエドワード・ヤン監督の映画もいい。『牯嶺街(クーリンチェ)少年殺人事件』には『A Brighter Summer Day』という英題がつけられているし、『ヤンヤン 夏の思い出』も夏の映画だ。『恐怖分子』も夏の暑さと湿気が、登場する人々と物語を不安定な方向へ向かわせているような映画だと思う。
そんな夏の映画たちを差し置いても観たくなるのが、「トイ・ストーリー」シリーズだ。でも、「トイ・ストーリー」は『3』から夏に公開されるようになったので、「夏の映画」になったのは最近だ。
はじめて『トイ・ストーリー』がテレビで放映されたのは、多分僕が小学校三年生の頃の春だ。『トイ・ストーリー2』が日本で公開になったのが、ちょうどその年なのでそれに合わせて金曜ロードショーで放送されたんだと思う。だから、何回も繰り返し観た録画のビデオには、しつこいぐらい『2』の予告や告知の映像が挿まれていて、そのことまでもなんとなく今でも記憶に残っている。ウッディが馬のおもちゃに乗って盛大にひっくり返るシーンは、当時よくテレビCMで使われていた場面だ。
僕がテレビで観た『トイ・ストーリー』は、生まれてはじめてみたピクサーのアニメーションだった。その衝撃も大きかったけれど、なによりも胸に響いたのは『トイ・ストーリー』の「おもちゃたちも生きている」という物語そのものだった。僕にとって、おもちゃたちが繰り広げる冒険は頭の中がひっくり返るぐらいの驚きだった。(ちなみに第一作から主題歌とスコアを手掛けているのは、ランディ・ニューマン。いまでも僕の大好きなアーティストの一人だ。)
その夜、久しぶりに押入れからおもちゃがしまってある箱を取り出したことを覚えている。保育園の頃、周りの友達はヒーローの人形や変身ベルトで遊んでいるなか、僕はひたすらに怪獣や宇宙から侵略にやってきた異星人の人形を集めていた。前にも一度書いたことがあるけど、小さな頃からなぜかやっつけられてしまうかいじゅうたちが切なく感じて仕方がなかった。切ない、という感覚にまだ名前がつく前から、胸がちくちくする痛みを僕は感じていて、そしてなぜかその感覚が好きだった。だから僕のおもちゃ箱には、かいじゅうたちばかりが入っていた。そこは、僕にとって映画やテレビのなかで死んでしまったかいじゅうたちの新しい居場所だった。
多分『トイ・ストーリー』が放送された日の夜、この町や遠くの町の子どもたちはみんな同じように押入れや納戸、物置からおもちゃを取り出し、何年か振りに手にとって眺め、何年か振りに小さな勉強机の隅に置いてみたはずだ。久しぶりに布団のなかに彼や彼女を招き入れたかもしれないし、捨てずにとっておいたはずの大事だったおもちゃがどこにも見当たらないことに悲しくなったかもしれない。あの日は、きっとそんな金曜日だったのだろう。
『トイ・ストーリー3』が公開されたのは僕が大学に入学した年の夏だった。多分僕が京都ではじめて映画館で観た映画だと思う。いまではその半分ぐらいが閉館してしまったけど、僕が住み始めたときの京都には多すぎるぐらい映画館があった。『2』からちょうど10年が経っていた。小学生だった僕は大学生になって町を出た。そしてそれは『トイ・ストーリー』の世界の中でも同じだった。アンディは大学に進学する歳になり、おもちゃたちは箱の中でほこりをかぶっていた。僕はすっかりかいじゅうたちのことを忘れてしまっていたし、それどころかいくつかだけを残して、あとはリサイクルショップに売ってしまっていた。大人になるというのは、なにかとさよならすることなのかもしれない。
今年の7月に公開された『トイ・ストーリー4』には、僕たちがずっと自分の姿を重ねていたアンディはいなかった。でも、だからといってこの作品で語られている物語が、自分たちと違う世界の話だということではない。役目を終えたウッディや自分の声を探すバズ、生まれた時からこわれてしまっていたギャビー・ギャビー、ゴミから生まれたフォーキー、彼や彼女も僕たち自身なのだ。とてもじゃないけど子供だなんて言えない大人になった僕は、やっとこの夏に、僕がこれまでずっと大切にし続けていた『トイ・ストーリー』という作品がなにを描いていたのか、誰の物語だったのかということに気づいた。これはやっぱり僕たちの物語だった。昔からずっとそうだったのだ。
僕は物心ついた頃から、口が上手に回らないこと(それが吃音という症状というのだと知ったのは高校生になってからだった)への悩みや行き場のない悔しさにも似たような想いを、胸の奥にずっと詰まらせてきた。その僕自身の痛みにも、ちゃんと向き合えたような気がした。知ることはやさしくなることへの大事な入り口だ。他人にも自分にも。
そして、この作品は「やさしさ」だけでなく、なにかを「選ぶ」ことの物語でもある。おもちゃたちのやさしさや悲しみ、迷いは全部、今もテレビから流れ続ける世界中のニュースと繋がっているのだろう。隣の国や隣人、世界からはぐれてしまいそうになっている人や弱い人への冷たい目線や悪意がじわじわと暮らしのなかまで近づいてこようとしている時代だからこそ、世界中のレンタルショップで誰かがこの作品に出会い、自分の物語となることを願わずにはいられない。
音もなくなったかいじゅうたちのすみかで ほこりをさけて寝息がうたう 蓋のうえに置かれた箱の重さは 上から眺めることもできない
その夜かれやかのじょの眠りが さえぎられたら それがもし最後の一度だとしても そのあとに続く眠りのなか 何度も夢見ることになるだろう 飛び方を忘れはしないだろう はじめからうまく飛べなかったとしても
次に眠りが途切れたとき そこから出ていくことや どこかを自分で選ぶこと その時はじめて声が跳ね返る やさしさを手放さなければ それを手に取ることができるだろう