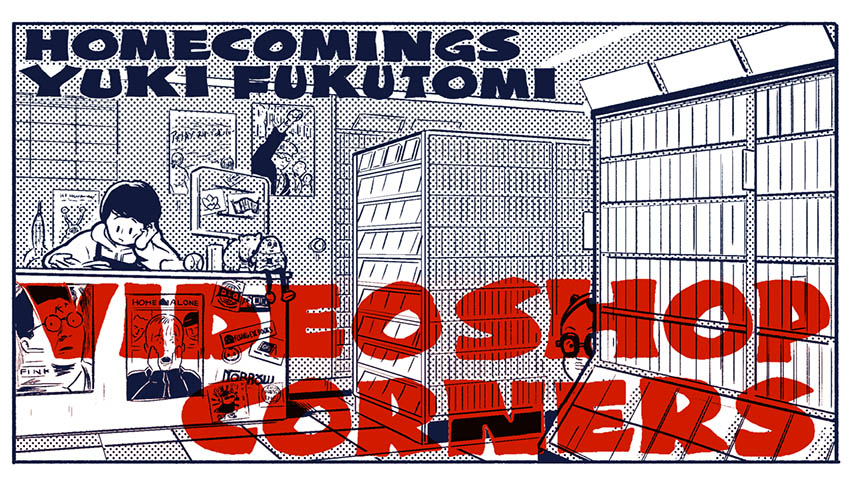
京都に住んでいた頃、僕は誠光社で本を買ったあとや出町座で映画を観たあと、もうそれが当たり前のことのように、決まってミスタードーナツに行った。そのランプ色をした小さなドーナツショップは、いつだってそこが映画や小説の世界の中のように感じさせてくれた。自分の部屋へ戻る前に、そんな世界に少しの間寄り道することが、僕にとって大切なことだった。まだ手の中に物語のかけらや空気をもっていられるような気持ちになれるからだ。そこはもう僕にとって、レコード屋やビデオショップ、お気に入りの本屋さんや映画館と同じぐらい大事な場所のひとつになっていた。ミスタードーナツではたくさんの歌詞や物語、文章も書いた。ミスタードーナツが好きな理由はたくさんあるけれど、ひとつは店内で流れている海外のラジオ番組風のBGMだ。季節ごとに替わるその選曲は妙に心地よくて、イヤホンをせずにずっとそこにいることができる数少ない場所なのだ。特に出町柳店のテカテカしていない、どこか古ぼけたままの店内は本当に居心地がよかった。そういったなにかに出会える場所に囲まれた、自分で物を作る場所。そんな場所になっていたのだった。
去年の年末は、いくつかの「愛」についての映画やドラマを立て続けに観た。そのなかでも、以前から大好きなノア・バームバック監督の『マリッジ・ストーリー』と、『シング・ストリート 未来へのうた』や『ONCE ダブリンの街角で』でおなじみのジョン・カーニー監督による連続ドラマ『モダン・ラブ』の2つがとても良かった。
『マリッジ・ストーリー』はノア・バームバック監督の実体験から着想を得られたという作品で、ある夫婦の離婚の季節を描いた映画だ。どうしてもこの映画を劇場で観たかったのには理由があって、スコアを担当しているのが、昔からずっと大好きなランディ・ニューマンだったからだ。今回のスコアは、ピアノのほかにオーケストラも参加していて、『トイ・ストーリー』シリーズをはじめとしたピクサー作品を思い起こさせた。(2020年のアカデミー賞で、彼は『トイ・ストーリー4』と『マリッジ・ストーリー』で音楽部門の2つの賞にノミネートしている。惜しくも受賞は逃してしまったけれど、アンディの部屋の壁紙を模したセットで行われた彼のパフォーマンスは本当に最高だった)。
『モダン・ラブ』はAmazonが制作したオムニバス形式のドラマで、ニューヨークの街角を舞台にした様々な形の恋愛が描かれている。過去の恋人のことを忘れられないでいる恋愛アプリの開発者、初デートの最中で病院に行く羽目になる一組の恋人、ドアマンとシングルマザー、父親ぐらいの年齢の男性に惹かれる女の子、倦怠期のカップルに、養子を迎えようとする男性同士のカップル。ひとつの街にだって、かぞえきれないぐらいたくさんの形の愛があって、そのどれも間違いなんかじゃない。様々な生き方や愛を描きつつ、そのどれも否定しない、その優しい温かさとカラフルな物語が大好きだった。
LGBTQのことを近い距離で描く、もしくはそこにある当たり前のものとして描く映画や小説がだんだん増えてきている。人種や性別も含めた多様性、という言葉が朝のニュースでも流れてくるのをよく耳にするようになった。世界は少しずつ良い方へ、優しい方へと流れていっていると信じていたい。今はまだ、少し目新しいもののように捉えられているかもしれないけれど、時間をかけてどんどんとそれが当たり前のこととして受け止められていくといいな、と思う。現在のこの世界、そしてその社会の問題や動きが映画や音楽、物語のなかに反射して映ること、映そうとすることはとても自然なことだ。現在のこの世界、そしてその社会の問題や動きが映画や音楽、物語のなかに反射して映ること、映そうとすることはとても自然なことだ。いくら半径5メートルのなかに閉じこもっていたとして、社会の息は生活のなかのいろいろな隙間から入り込んでくる。ドアをしめて鍵をかけても。それは僕が作る音楽もそうだし、こうやってここに書いている文章にだってなにかしらの影響を与えているのだ。
去年、『愛がなんだ』という映画に『Cakes』という曲を書き下ろした。『愛がなんだ』は、角田光代さんの原作を『パンとバスと2度目のハツコイ』や『アイネクライネナハトムジーク』、『his』などを手掛けた今泉力哉監督が映画化したもので、ひたすらに恋すること、好きでいることを描いた物語だ。彼女は彼に、そしてそんな彼はまた違う彼女に、恋をする。恋に「落ちる」、ということについての物語なのだ。 僕はそんな物語のエンドロールに流れる曲として、「恋に落ちる側のもの」でも、「恋に落ちられる側のもの」でもない、そして「男の子のもの」でも、「女の子のもの」でもない、誰もが「自分のもの」だと思えるような歌を書きたいと思った。愛や恋は誰のものでもある。それは同時に誰かと誰かの間にあるものでもある、ということだ。女の子と女の子の、男の子と男の子の恋や愛も、女の子と男の子のそれと同じように描くことができたら、それは物語のなかの世界では描かれてないけれどもそこに確かにある、そんな存在のことも包み込むことができるんじゃないかと思った。もしかしたら物語の世界だけじゃなくて、僕やあなたやまだ会ったこともない人たちが住む、いろいろな街の片隅までも。
『Cakes』の歌詞はその頃住んでいた町にある、古い匂いが残ったミスタードーナツで毎日夜遅くまでコーヒーといくつかのドーナツで粘りながら書いた。冬がとても寒い町だった。お店の前に人が通ったりセンサーの調子が悪いのか、ときには強い風が吹いたりしただけで自動ドアが開いてしまうので、店内はいつでも冷え込んでいた。僕は上着を着込んでそのうえマフラーをぐるぐる巻きにして、何杯も何杯も熱いコーヒーをおかわりした。当時そんなに得意じゃなかったコーヒー(香りだけは昔から好きだった)はあのミスタードーナツのおかげで、今ではよく飲むようになった。23時を過ぎると店内は僕を入れて2、3人のお客さんだけになり、窓の外の町にも人はほとんどいなくなった。ガタガタと小さな音を立ててドアは開くけれど、夜の冷たい空気だけがそっと入り込むその風景は少し不思議で、冬の幽霊がコーヒーを飲みにきたり、ドーナツをテイクアウトにしてきているのを想像したりした。
お店の入り口の側にはバス停があったけど、大きな街のほうに向かう車線のバスは、もうこの時間にはなくなってしまうみたいで、やけに静かになるのだった。まっくらな町のなかでぽつんと、ドーナツ屋さんのオレンジ色の灯りが浮かんでいるので、遠くから見たらランプのように見えるのかもしれない。ふと恋や愛の側、寂しさのなかにふと灯るランプのようなそんな歌のことを思った。できあがった歌詞を読み返してみて、これは僕がはじめて書いたラブソングなんじゃないか、と気づいた。物語の場面や、その中の登場人物の心情、景色とは違うなにかをはじめて形にできたような(というよりは形にした)、そんな気がした。ふたつに分けた、その大きい方をなにげなくあげたくなるようなそんな瞬間の歌。最後の一口分の大きさになったきり、すっかり忘れていたエンゼルクリームのかけらを口に入れた瞬間、『Cakes』というタイトルを思いついた。ドーナツの生地の色とまっ白なクリームはなんだか人の肌の甘い匂いを思いださせた。
『Cakes』を書いてから一年が経った。あの頃から比べて世界がどうなったか、それを正確に測ることは僕には難しいけれど、「優しさ」ということについて考える、考えさせられることは多くなったように思う。悲しいニュースをめくってみると、そこには優しさが足りないことがたくさんあった。もちろん原因になるようなものはそれだけじゃないけれど、もう少しだけ優しい世界だったら起きなかったんじゃないかな、と思うようなこともたくさんあった。差別のことや政治的なことや、社会のことそして戦争のこと、手が届かないように思えてしまうような大きなことも、どれも自分の小さな生活とつながっている。道端に落ちているゴミを拾ってゴミ箱に捨て直すような、電車やバスで席を譲るような、そんな些細な優しさがまわりまわってどこかで誰かを助けるかもしれないし、みんなが息がしやすい世界を作るのかもしれない。
じゃあ自分にはなにができるのだろう。少なくともこの手で物を作りだすことを仕事としている僕にできることのひとつは、優しさや自分の声をその手を伝って物語や音楽に載せることだ。『Cakes』というラブソングは、僕が自分の声に意思を載せることができたはじめての作品だと思うし、そうしよう、と思ったきっかけでもある。ライブでこの曲を演奏する前に「この曲は女の子と女の子の恋愛の歌であるし男の子と男の子の歌でもあるし、男の子と女の子の歌でもあって、誰にとっても自分の曲だと思ってもらえたら、そして僕たちの音楽を聴いてくれた人がそんなふうに色々な形の恋や愛があることに少しでもやさしい気持ちでもって気付けてもらえるような、そんな気持ちで作りました」ということを話すことがある。そんなことを話すのはもしかしたら野暮なことなのかもしれない。だけどこれは僕やHomecomigsにとってとても大事なことだから、だからこそちゃんと言葉にしたいと思うのだ。
夜が終わるベル ドアを見守る誰かと誰か かぞえきれない かたちとかたち 似たものを選んだり 違うものをほしがったり だれかたちの雨の中 ほんとうは傘を持たずに歩けるのに 朝がはじまるベル ドアを開く誰かと誰か
夜や朝、そして昼でさえも はがれた色で探りあう それは形しか掴めない どんな角度から眺めてみても
勝手に名前をつけて 遊ぶ天使たち どうか 守られるものじゃなくなるように
コーヒーの湯気の向こう ドーナツの砂糖 寂しさも美しさも手に取れるけれど この気持はどうだろう








