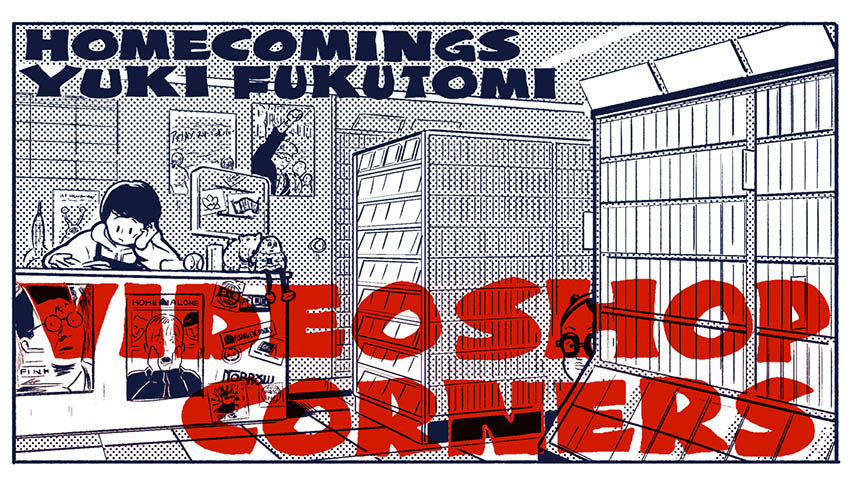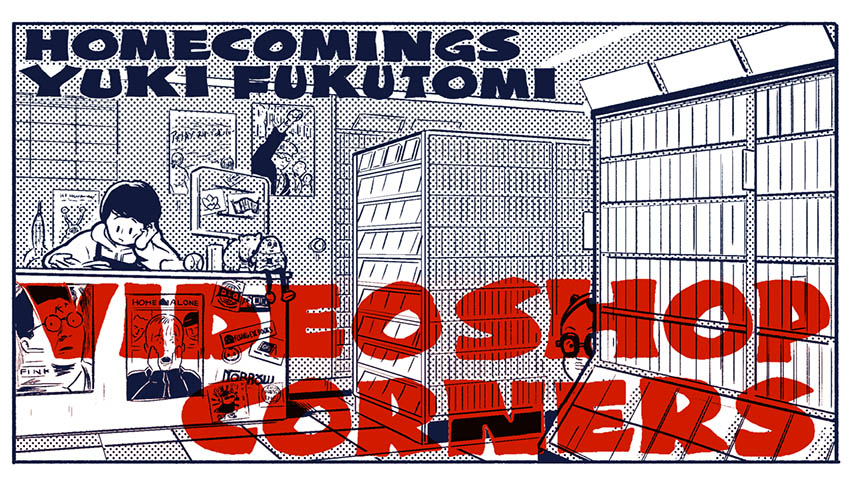
穏やかな坂を登った先に大きな交差点があり、その角には小さなレンタルビデオ屋さんがある。レンタルショップ「アラスカ」、小さな町の小さなお店。
小学5年生ぐらいから中学3年生の夏までの間、それまで僕にとって身近なものだった映画と少しずつ少しずつ距離が離れていった。それまで友達のような存在だった映画の代わりに、僕のそばには音楽と小説があった。
小学5年生のときにはじめてスピッツのテープを聴いたあの日から、僕の世界や未来は音楽で溢れかえるようになった。家で過ごす時間のうち、ご飯を食べているときとお風呂に入るとき以外のほとんどの時間を、誕生日に買ってもらった、MDもカセットもラジオも聴けて、CDがなんと5枚も入るコンポの前で過ごした(今でもこのコンポをつかって音楽を聴いているので、15年以上毎日のように動き続けていることになる)。コンポの前を離れてリビングにいるときも、カセットウォークマンでテープを聴いていた。朝学校に行くときも、お母さんに内緒でポケットのなかにウォークマンを忍ばせて、誰にもばれないように制服の内側にイヤフォンを通してこっそり音楽を通学中も聴いていた。
その通学路の途中には大きくてきれいな図書館があって、部活が早く終る水曜日には暗くなるまでそこで小説を読んでから家に帰っていた。学校やクラスには友達がたくさんいたけど、僕が入っていた陸上部には帰り道が同じ友達がいなかったから、放課後の時間は一人で過ごすことが多かった。それはたまたまそうだっただけなのだけど、そんな些細なことがなければ図書館に通ったり、公園で音楽を聴きながら夕日が落ちるのを待ったりするようなことがなかっただろうし、今の自分とは違った自分になっていただろう。
多分一人で帰るのが寂しかったんだろう。一人でいるのが自由で楽だ、みたいに思うにはまだ僕は子供すぎたし、みんなでわいわい話しながら帰っているであろう野球部やバスケ部の友達のことを羨ましいと思わないわけがなかった。そんな気持ちを紛らわすために、夢中になって本を読んで、音楽を聴いていた。それは僕にとって形のない友達のような存在だった。
この頃観た映画ではっきりと覚えているのは『ジョゼと虎と魚たち』ぐらいで、それを観たのもくるりの「ハイウェイ」が主題歌だったからだ。小さな頃のように週末の夜の映画を楽しみにすることもなくなったけれど、なんとなく僕が好きだった80年代の映画が放送されることがなくなってきていることは感じていた。映画はあまり観なくなったけれど、代わりにCDをレンタルするため「アラスカ」にはよく通っていた。白黒コピーをホッチキスで留めた歌詞カードとケースに入ったディスクは僕にとってまだ触れたことがない音楽が詰まった魔法の円盤だった。
ある日、住んでいた町とアラスカのちょうど間に大きなレンタルショップができた。そのお店は車で20分ぐらいの場所にある大型スーパーのなかにあり、「アラスカ」よりも少しだけ早く新作が入るのとレンタル落ちCDのコーナーがとても充実してるぐらいのイメージだった。そのスーパーのなかにはミスタードーナツがあって、なんとなくオールドファッションの甘い匂いとセットになっていた。
僕の町にできたそのレンタルビデオチェーンはまるでおもちゃ箱のような空間だった。店内にはレンタルコーナーはもちろんのこと、新品のCDやDVDを販売するコーナーがあった。僕にとってそれは大きな事件だった。いつか自転車で行ける距離にCD屋さんができたらな、というのは僕にとってなによりも叶ってほしいと願っていた夢だった。スーパーの端の小さなCD屋さんを覗くためにわざわざお母さんの買い物に着いていかなくてもよくなったし、隣の県にあるタワーレコード(それは僕にとってまるで世界のどんな場所よりもいい匂いのする空間だった)に行くために、お父さんを高速道路に乗ってランチバイキングにいこう、と言い出すように仕向ける必要もなくなったのだ(それでもタワーレコードは僕にとっていつまでも憧れの場所だった)。
なによりも衝撃的だったのはレンタルコーナーにあるCDが全部試聴できるようなっていることだった。その頃はまだYouTubeもなかったし、もちろんサブスクの動画配信サービスなんて『バック・トゥ・ザ・フューチャー2』の世界のなかのもののような、というかもう想像すらしていないようなものだった。お年玉を全部自分のものにできる代わりに月々のお小遣いがない、という世にも珍しい年俸制の子供だった僕にとって、ジャケ買いもジャケ借りもかなりリスキーなことだった。それまで見たことがなかったような種類の音楽雑誌がたくさん並んでいる書籍のコーナーでぺらぺらとページをめくり、気になったバンドをレンタルのコーナーで試聴して、そのCDを買って帰る、なんていう、これまで僕が何週間もかけてやっていたことがたった30分ぐらいでできるようになった。それも自転車ですぐに行ける場所で。僕はますます音楽にのめり込んでいった。
レンタルチェーンができたことで、もうひとつ僕のなかに変化があった。映画をたくさん観るようになったのだ。店内のレンタル棚にあるのは、当たり前のように全部がDVDだった。ジャンルごとに並べられたカラフルな背表紙の壁の間を歩くのは、まるでテーマパークに来たときのようにワクワクした。その頃の「アラスカ」はまだDVDとVHSが半々ぐらいの割合だった。
当時レンタルが開始したばかりだった『リンダ リンダ リンダ』や『スクラップ・ヘブン』、『亀は意外と速く泳ぐ』に『花とアリス』、少し前の『アカルイミライ』、ピカピカのレンタルショップの店内でなんとなく気になって棚から取り出したDVDはたいてい、それまでに僕が夢中になっていた音楽や小説とどこか似たような匂いがするものばかりだった。多分僕が「サブカルチャー」というものの輪郭をなんとなく理解した瞬間だったのかもしれない。それは『ジョゼと虎と魚たち』をはじめて観たときの、まだ触ったことのない感じ方が体のなかにあることに気がついた瞬間とつながって、一気に色んな点が線になったような気がした。
1冊の小説として読んでいた『スワロウテイル』が映画でも体験できることに気づいたり、『リンダ リンダ リンダ』のサントラからジェームス・イハを知り洋楽のイメージが少し変わったり、『青い春』を観たあと原作を読んで、ジャンプやマガジンには載っていないような、ざらざらしたかっこいい漫画がたくさんあることを知った。僕は店内をあっちこっちに飛び回りながら、世界がどこまでも広がっていくのを感じた。音楽も映画も本も僕に同じぐらい大切な友達になった。
少しして、「アラスカ」は閉店してしまった。レンタルチェーンができてからあっという間のことだった。
僕が毎日のようにレンタルチェーンに通っている間も、お父さんは未だに「アラスカ」でビデオを借りていたみたいだった。もしかしたら特別な思い入れがあったのかもしれないし、放っておくとなくなってしまうことに気づいてしたのかもしれない。本当の理由はわからないし、ただ単に新しくカードを作るのがめんどくさかっただけなのかもしてないけれど、こっそりと愛着のようなものを感じていたのだろうな、と思う。「アラスカ」がなくなると分かってからも、僕はとくに様子を見に行ったりもしなかった。まぁそりゃ仕方ないよな、と思っていた。レンタルチェーンになくて「アラスカ」にあるものなんて、棚の下の大きな埃とムキムキのスターの等身大パネルぐらいだった。
「アラスカ」が閉店すると告知をしてから、本当に閉店してしまうまでの間、一度だけお父さんに連れられてビデオを返しに行った。普通なら着いていかなかっただろうけど、なんとなく閉店するお店がどんな様子なのかふと気になったのだ。
この穏やかな坂を登るのも、なんだか久しぶりのような気がした。たしかにそこは町のはずれで、バイパス道路やスーパーや駅からは少し離れた場所だった。僕がその坂を登るのは、陸上部の練習で隣町の競技場に行くときと、「アラスカ」に行くときぐらいだった。どうしてこんなところにあるのだろう、と考えたときに、ふと、もしかしたら僕が引っ越してきたときには当たり前のようにあったバイパス道路(レンタルチェーンはそのバイパス沿いにあった)ができる前から、「アラスカ」はこの場所にあったのかもしれないと気がついた。あの坂の上はバイパスができて、人や車の流れが変わり、勝手に「町のはずれ」にされてしまった場所だったのかもしれなかった。
それでもささやかに町の人に囲まれた営みも、大きなチェーンの前にはどうしようもできなかったのかもしれない。最後だからといってとくに混み合っているわけでもない店内には、あの懐かしい埃っぽい匂いがまだそこにあって、その匂いに包まれながら僕はいろんなことを思い出した。
『タイタニック』の2巻セットにいつもつけられていた「貸し出し中」のタグも、「三倍速!」とでかでかと書かれたダビング用のビデオテープも、もうそこにはなかった。ただ、お客さんに目も向けずガチャガチャと音を立てながらケースを直しているアルバイトのお兄さんも、気の弱そうな店長さんも、そしてそのふたりが思い出したかのように口にする「いらっしゃいませー」の声も、あの頃と全く変わっていないような気がした。この狭い店内のなかにも変化しているものと変わらないものがあって、それはなんだか僕が育ったあの町をそのまま映しているようだった。この人たちはこれからどうするんだろう、と考えると体のなかがぎゅっと押しつぶされそうな気持ちになって、僕はすぐに「アラスカ」から出ていきたくなった。自分のせいだ、自分のせいでこの人たちやDVDやVHSはもうここにはいられなくなってしまったんだ、という思いが何度振り払っても頭のなかにやってきては意地悪く僕を悲しくさせた。でも多分それは本当のことだったのだ。僕のような人がたくさんいて、そのせいで「アラスカ」はなくなってしまうのだった。
その夜、僕はベッドのなかで色んなことを考えた。おじさんやアルバイトのお兄さんが人手不足のレンタルチェーンを助けることになり、また映画に囲まれて嬉しそうに思っているところや、お店を売ったお金でのんびりと優雅な生活をする姿、色んなことを想像したけど、妄想はあまりうまくいかなくて、日に日にお客さんが少なくなっていく店内や、レンタルチェーンの店内をこっそり覗きにきた店長が自分たちには太刀打ちできないことを悟る場面や、お兄さんに店を締めることを話す場面、同じように家族やすっかりおばあちゃんになったお母さんにそのことを打ち合ける場面が、次から次へとまぶたの裏を流れていった。その夜は小さな頃に、正義のヒーローにやっつけられてしまうかいじゅうたちのことを考えながら眠れなくなってしまった夜と似ていた。それは音楽を聴いたり、小説の最後のページを閉じたり、映画のエンドロールを眺めているときの気持ちとも似ていて、それよりももっとほんものだった。
閉店する最後の日も僕は「アラスカ」には行かなかった。店長さんやお兄さんが悲しそうにしている姿を、それがたとえほんの一瞬だとしても、僕は受け止めきれる気がしなかったのだ。
何日かして、あっというまにお店のなかのものや看板はなくなって、真っ白な箱のような建物と駐車場だけが丘の上に残った。その前を通ることはほとんどなかったけれど、その道を通るとき僕はどうしてもその姿をしっかりと見ることができなかった。横目で見るその真っ白な影は、まだなにかを言いたそうにしているような気がした。
そして気づけば、どのジャスコにも入っていた小さなCD屋さんは倒産して、その替わりに別のCDショップができることもなかった。大きなレンタルショップだけが残った。僕が高校を卒業して町を出たあと、ひとつの町ぐらいある大きさのショッピングモールができて、商店街もスーパーもほとんどなくなってしまった。あの小さなCD屋さんが入っていたスーパーのなかには空スペースが目立つようになった。実家に帰るたびにまだ無くならずにそこにあるか、確かめたくなる場所が増えた。そのなかにはあの「レンタルチェーン」も入っている。あのとき、なにもかもが詰まっているように思えた店内には、今はもうCDのコーナーはなくなっていて、埃とプラスチックの混ざったあの匂いが、幽霊の足音のように転がっている。
当たり前のようだった風景は、当たり前のように変わっていく。国道沿いにたくさんあったレンタルビデオ屋さんは、ほとんど空き店舗になってしまった。色あせた映画のポスターの上から貼られたテナント募集の張り紙。そんな風景もすぐにあたらしくてきれいなものに変わってしまうだろう。この町は真っ白な影でいっぱいになってしまうだろう。
大きな国道をお父さんの運転でドライブする夕方、あたたかな西日と眠気のなかぼんやりとした頭で、僕は真っ白な影がある日、大きな工事用の車がやってきて取り壊されるところを想像する。VHSや日に焼けたDVD、埃をかぶった映画の幽霊たちの眠りは、急に差し込んだ光で突然終わりを迎える。壁のポスターは剥がされ、倒れた棚の下には粉々になったプラスチックのケースの破片が散らばる。レンタルビデオショップのあの匂いの正体は魔法でもなんでもなく、たまった埃とプラスチックの匂いだということを僕はもう知ってしまっている。その匂いも舞い上がるちりと一緒になって風のなかに消えてしまう。幽霊たちはもうどこにもいけないし、ここにいることもできない。手を振るものもいないだろう。だからせめて僕は覚えておこうと思う。
インターネットを開いて、僕が住んでいた町の名前と「アラスカ」を並べて検索しても、まともな情報は本当にひとつだって出てこない。あの坂の上の交差点にビデオ屋さんがあったことを覚えている人は、どれくらいいるのだろうか。あの町に暮らしていた、そして今も暮らしている人たちにとってあの場所はどんな存在だったのだろうか。そこにあった、ということすら、記号としてひとかけらも残っていないあのレンタルショップ。僕は2ヶ月に一度、文字を打ちながら隅々まであの小さな世界を思い出し、想像のなかで、棚を眺めている。ずらっと並んだ映画と映画の間にひっそりと隠れている記憶や匂いを掬い取って、ひとつの文章という形にする。そうやって僕は世界に「アラスカ」があった跡を残すことができた。忘れない、ということは「もうここにいない」ものに対して僕たちができる唯一の祈りのようなものだ。それは自分の大切なものや場所がこれ以上なくならないように、そして、今、これから、なくなっていこうとしているものがある、ということに気がつくためにできることでもあるのだ。
穏やかな坂を登った先に大きな交差点があって、その角には小さなレンタルビデオ屋さんがあった。レンタルショップ「アラスカ」、小さな町の小さなお店はたしかにそこにあった。
日に焼けたポスターに守られた暗闇のなか プラスチックのすみかで磁気が寝息をたてる 幽霊たちの国では ほこりの雨だけが音もなくふり続ける
突然それはやってくる 大きな音を立てて暗闇が折れる
暗闇は夜とは違うから 一秒だって耐えることはできない
一コマを送るその間に 光が差し込んできて 世界が結びついてしまう
さいごに 彼や彼女は ほこりのちりのすきまから あたらしい世界をひと目みるだろう そして自分たちがそこにはいられないことを知るだろう
16時のひかりのなかで 静かなその時間の間だけ 国道沿いの車も息をひそめるだろう それがどういう瞬間かよくわかっているから
ぼくはそれを午後のまどろみのなかでみた
流れていく砂のような時間のなか 鼻の奥だけがはっきりと最後のことばをうけとった
午後のまどろみのなかで 16時のひかりのなかで