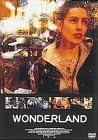目次

世界最大のファッションイベントの裏側
●『メットガラ ドレスをまとった美術館』(2016)
毎年5月の第1月曜日にニューヨークのメトロポリタン美術館(以下、MET)で行われる、世界最大のファッションイベント「メットガラ」(2020年は新型コロナウィルスの影響で中止、2021年は開催月を9月に変更し行われました)。参加したセレブ達の豪華絢爛なドレス姿をSNSなどで目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
そのメットガラを主催する、METの理事でありアメリカ版「VOGUE」誌の編集長でもあるアナ・ウィンターと、METの服飾部門キュレーターであり現在は同部門の責任者でもあるアンドリュー・ボルトンを中心に、メットガラを裏側で支える人々に迫る『メットガラ ドレスをまとった美術館』というドキュメンタリー映画があります。
私は本作を公開当時に映画館へ観に行きました。ファッションは人並みに好きですが、ファッション雑誌を熟読し、ブランドについて熟知しているほどではありません。そんな私が惹かれたわけは、METに所蔵されている、歴史的価値の高いドレスを鑑賞できるという「アート」の側面と、この巨大イベントをどんな人がどうやって成功させたのかという「お仕事ドキュメンタリー」としての側面に期待したからです。
本作では2015年のファッション・エキシビション「鏡の中の中国」を準備する過程が描かれているのですが、他国の文化や歴史などをセンシティブな面も理解し尊重しながら、自分たちが最高だと思える表現を追求し、実現させる粘り強さとプロ意識に圧倒されました。(アナ・ウィンターたちがメットガラの600席もあるパーティーの席順について何度も話し合っている姿が印象に残っています…。)
アンドリュー・ボルトンは「西欧のデザイナーは映画を通じて中国と出会う」と語っており、数々の中国や香港の映画、『ラストエンペラー』(1987)、『紅夢』(1991)、『さらば、わが愛/覇王別姫(はおうべっき)』(1993)、『花様年華(かようねんか)』(2000)などが紹介され、デザイナーが影響を受けた映画を知れるのも嬉しいポイントです。
エンドロールが終わり客席の照明が点くと、私の隣に座っていた女性がすぐにノートとペンを取り出し一生懸命何か書き留めていて、また他の客席でも、なにやら熱心に意見交換をしている姿が多く見かけられ、この作品が鑑賞した人たちに何かしらの刺激をもたらした瞬間を目にすることができました。
(鈴木隆子)
◯『メットガラ ドレスをまとった美術館』をAmazon Prime Videoで観る[30日間無料]
なんでもハンパはだめ
●『シング・ストリート 未来へのうた』(2015)
先日YouTubeを見ていると、見覚えのある猫背の男性の後ろ姿が目に留まりました。…まぎれもなく僕の背中です。それは友人バンドのミュージックビデオのメイキング映像で、大学時代に仲間たちと一緒に撮影したものだったのです。当時からこんなに丸い背中をしてたのかと思うと同時に、熱量だけで制作をしていたあの時間を懐かしく思い出しました。
ジョン・カーニー監督の『シング・ストリート 未来へのうた』にも、少年が学校のバンド仲間たちとミュージックビデオを撮影する場面がたくさん登場します。主人公・コナー(フェルディア・ウォルシュ=ピーロ)は、冴えない日々を送る高校生。想いを寄せるラフィーナ(ルーシー・ボイントン)を振り向かせるため「僕のバンドの PVに出ない?」と口走ってしまい、慌ててバンドを組むことに。無謀にもロンドンの音楽シーンを驚愕させるPVを撮ると決意し、練習、曲づくりの日々が始まります。そして、ようやくラフィーナの出演にこぎつけるのです。
彼らはストリートや海辺でPVの撮影を行うのですが、ある時、出演するラフィーナが撮影中、泳げないにも関わらず海に飛び込んでしまいます。追いかけるように飛び込んで助けたコナーが「なぜ海へ?」と問うと、ラフィーナは息を切らしてこう告げるのです。
「作品のためよ なんでもハンパはだめ 分かった?」
ミュージックビデオを撮影していた当時の僕らも、「ハンパなものにはしたくない」という想いが、撮影のイロハが分からないからこそ強くあったように思います。技術や経験がない分、あらゆる映画や映像作品を持ち寄って研究し、試行錯誤を繰り返しました。とにかく時間と熱量が僕たちにはありました。
ゴロゴロとYouTubeを見ていた自分の前に現れた、創造を楽しみ打ち込む自分の丸い背中。そして、久しぶりに観た本作の、ラフィーナの力強い眼差しとこのセリフに、思わずビンタを喰らったような心地になりました。
(鈴木健太)
◯『シング・ストリート 未来へのうた』をAmazon Prime Videoで観る[30日間無料]
◯『 シング・ストリート 未来へのうた』をU-NEXTで観る【31日間無料】
クリエイティブな人は「人たらし」
●『台風クラブ』(1985)
ある文化人の方が「最近、人に勧められたものしか観たり読んだりしなくなった」と言っているのを聴きました。“我が道を行くクリエイター”というイメージがあったので、意外な言葉で脳に焼きつきました。
それで思い出したのが、伝説の映画監督・相米慎二による『台風クラブ』です。台風の暴風雨で、学校に取り残された6人の中学生。気圧の影響か、彼らはやがて悲喜劇的な狂乱の世界に入っていきます。そんなユニークな物語自体は、監督のアイデアではなく、一般公募により選ばれた脚本(*)によるものです。
劇中、恐ろしくも妙に胸に迫るシーンがあります。真っ暗な校内で中学生の健が、歪んだ愛情を向けている同級生・美智子を追って、彼女が隠れた部屋のドアを蹴破っていく。実はこの蹴り、記録係が別のシーンで代役に入った時の何気ない仕草から、相米監督が膨らませたものだそうです。
この『シャイニング』ばりにホラーだけれど、かえって健の心の傷がヒリヒリと伝わってくる名シーンを、相米監督は現場でスタッフから着想を得て創り出したわけです。「クリエイティビティ」と聞くと、先天的な能力のように思えます。でも本当は、冒頭の文化人の話ではないですが、人と交わることこそ創造性の芽なのかもしれない。
そういえば『台風クラブ』で教師役を演じた三浦友和さんは当初、オファーを断るつもりで相米監督に会ったのに、帰り際には出演する気になっていたそうです。三浦さんは相米監督のことを「人たらし」と表現しています。なるほど、クリエイティブな人って別名、「人たらし」なのかもしれない、そう思いました。
(川口ミリ)
【参考図書】金原由佳、小林淳一 編『相米慎二という未来』(発行:東京ニュース通信社、発売:講談社)
*1982年、長谷川和彦、相米慎二、根岸吉太郎、黒沢清ら若手監督9人は“監督が撮りたい映画を撮り、利潤を得ること”を目標に、企画・制作会社「ディレクターズ・カンパニー」を設立した。同社では若い人材の発掘のため脚本を一般公募。その中から相米監督は、東京藝術大学に在籍中だった加藤祐司による応募作品を「すごい脚本だ」と絶賛して採用し、映画『台風クラブ』を生み出した。
◯『台風クラブ』をAmazon Prime Videoで観る[30日間無料]
仕事に追われる日々も照らしてくれる
●『ひかりのまち』(1999)
私たちの毎日には、映画のように刺激的なことなんてそうそう起こりません。家にこもって仕事をしていると、誰とも会わずに数日間が過ぎてしまった、ということもしょっちゅうあって、そんな時、自分だけが冴えない日々を過ごしているような、虚しい気分になることもあります。
マイケル・ウィンターボトム監督の『ひかりのまち』に登場する姉妹たちも、みんなどこか冴えない日々を過ごしています。恋人募集中で週末ごとにデートをするも、毎回うまくいかなかったり、出産を控えているのに孤独を感じていたり。映画に浮かび上がるのは、ロンドンという大都会の中で人々が抱える「自分だけがひとり」という感情です。
それでもこの映画が温かく感じられるのは、映像を照らすロンドンの街の光と、孤独に寄り添ってくれるような、マイケル・ナイマンの美しい音楽があるからでしょう。ラストで生まれる赤ちゃんにつけられた「アリス」という名前も、この不思議な国(映画の原題は『WANDERLAND』)に住む、すべての人の営みを祝福しているような優しさを感じるのです。
私たちのパッとしない毎日すら、優しく、美しく映し出してくれる。そんな表現が成せるのは、映画だけなんじゃないか。『ひかりのまち』を観る度に、「映画が好きで良かった」と思えるし、その喜びが、仕事に追われる日々をいつも照らしてくれます。
(安達友絵)
◯『ひかりのまち』をTSUTAYA DISACSで借りる[30日間無料]
可能性を魅せてくれる世界
●『アメリカン・ユートピア』(2021)
みなさんは、映画を観ていて、理由もわからず涙があふれてきた経験はありますか?
わたしは今年、涙があふれるほど胸を打たれたのに、それがなぜだかわからないという体験をしました。元トーキング・ヘッズのフロントマン、デヴィット・バーンのブロードウェイショーを映画化した『アメリカン・ユートピア』を観たときのことです。
舞台に立つのは、様々な国籍を持ったデヴィット・バーンを含む11人。彼らはケーブルやアンプがすべて排除された楽器を奏で、自由に踊り動き回ります。その姿は力強く、自由の可能性を目の当たりにせざるを得ませんでした。
デヴィットはこう語ります。
「僕たちがいるのはユートピアではないが、それを実現できる可能性についても伝えたかった。言葉で語るのではなくそれを観ることができる。そして、その心地いい手ごたえを感じることもできる」
わたしは日々のなかでどうしても自分の可能性を信じられず、「どうせ…」と卑下してしまいがちです。けれどこのステージの隅々に渡る表現の力強さを観てしまったら、そんなうじうじしている場合ではないと、パンチを食らった気がしてハッとしました。理想に近づくことは、できないことなんかではない。人間の持つ可能性に魅せられたからこそ、涙が止まらなかったのかもしれません。
(大槻菜奈)
◯『アメリカン・ユートピア』をTSUTAYA DISACSで借りる[30日間無料]
※2021年10月7日時点のVOD配信情報です。
- 「あの映画観た!?」気になるあの映画の“心に残る言葉”を語り合う! 時代劇映画『碁盤斬り』
- いまこそ、面白いドキュメンタリー映画を!
- 「最近、何観た?」編集部の休憩タイムをそのまま配信!
- 映画を普段観ない人と一緒に『ダークナイト』を観て語る!
- 映画を全く観ない人が、『タクシードライバー』を観たら…
- 企画会議をそのまま配信! 「映画がもっと楽しくなるグッズ」をみんなで考えよ?
- 映画を全く観ない人が、黒澤明監督の名作映画『生きる』を観たら…
- 2023年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10
- 映画の「倍速視聴」を考える! 話題の新書『映画を早送りで観る人たち』
- 2月の気になる「映画チラシ」!
- あなたの映画ライフを教えて!アンケート第1弾
- 新年のごあいさつ
- 2022年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10
- 11月の気になる「映画チラシ」!
- わたしの地元には映画館がない!
- 若者だって気になる!「名作映画」の世界
- 10月の気になる「映画チラシ」!
- ミニシアター、名画座に行ってみよう!
- 映画メディア編集って、どんな仕事?
- ブランドサイトをオープン! ロゴも一新しました
- ホラー映画沼へようこそ… (初心者も大丈夫!)
- 汗ばんだ肌、恋する予感。 夏こそ観たい! 爽やか名作映画
- GO VOTE! 政治を考える 今こそ観たい映画6選
- 連休なに観る!? 休日に落ち着いて観たい映画・ドラマ4選
- リラックスタイムにおすすめ! 心が落ち着く映画・ドラマ5選
- 新年のごあいさつ
- 2021年のPINTSCOPEを振り返って
- 2021年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10
- 切なくて、痛くて…胸が張り裂けそうになる! オススメ映画4選
- 心に一息を… 気分転換したい時のおすすめ映画
- 仕事にも人生にも創造力を! クリエイティビティが刺激されるおすすめ映画
- カンヌ国際映画祭 歴代ノミネート作品おすすめ4選!
- この連休どうする? 連休に観たいオススメ映画・ドラマ
- ちょっと空いたスキマ時間に映画はいかが?自分をリセットしてくれる映画を紹介
- こんな想いの伝え方が! おすすめ名作ロマンス映画
- 2020年のPINTSCOPEを振り返って
- 2020年に最も読まれたPINTSCOPE記事ベスト10
- 2020年10月のPINTSCOPE
- 映画好きの永遠の相棒 「ポップコーン」
- 部屋にある映画や本を通して、 「わたし」と再会する
- 「映画っていいね」を届けるためには? 新人編集者がみつけた、世界の広がる言葉たち
- 人の本質がまる見え!? 怖い…けど面白い! 「トラウマ映画」のススメ
- 疲れた時に観てほしい。 心がフッと軽くなる「映画の処方箋」
- 映画WEBマガジンを立ち上げ、PINTSCOPEが考えてきたこと