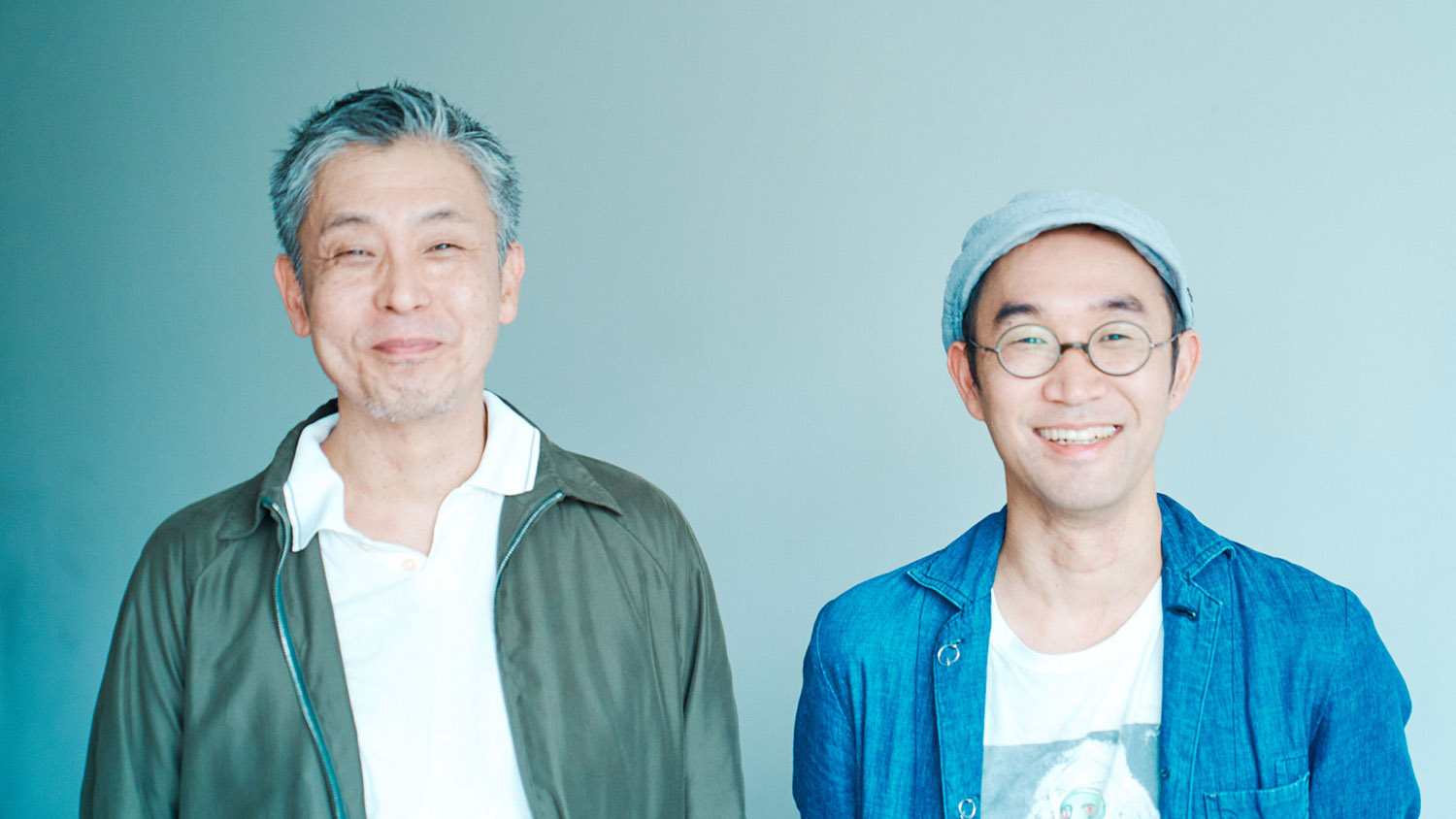目次

「笑い」は生き延びるための方法にもなる
― 映画『はるヲうるひと』は、「生きる手触りが掴めず、死んだように生きる人々が、それでも生き抜こうともがく壮絶な闘いのおはなし」です。今作のポスターに載っている「笑え、殺したいほど憎くても。」という言葉通り、お世辞にも幸せそうに見えない登場人物たちが、些細なことで笑い合うシーンが深く印象に残りました。
佐藤 : 人間って誰しもが大小さまざまな負を抱えているから、それが全くない人ってなかなかいないと思うんです。僕はそういう負を抱える人が、「何かをきっかけにしてフワーっとそれを乗り越える」のではなく、「負を抱えたまま『明日も生きていこう』と、ちょっとだけ、5mmでもいいから前を向く」物語にグッとくるんです。
― それは、なぜでしょう?
佐藤 : 自分でもわからないんですけど、理屈じゃないんですよね。自分が脚本を書くといつもそういう話になっちゃう。
― 今作は、佐藤さんが主宰する演劇ユニット「ちからわざ」で2009年に初演、2014年に再演された舞台を映画化した作品です。「ちからわざ」は、佐藤さんが27歳の時に旗揚げした劇団で、全公演で作・出演を務めていらっしゃいます。
佐藤 : 僕はよく20代を振り返る時に「暗黒の20代」と言っているんですけど、もしかしたら当時の経験が影響しているのかもしれません。話すと8時間くらいかかるんだけどね(笑)。

― (笑)。佐藤さんは大学卒業後、「役者になりたい」という気持ちを押し殺し、大手広告代理店に入社するも一日で辞めてしまい、再び役者の道を志したそうですね。そこから何度かの挫折を繰り返し、再び就職して、働きながら劇団「ちからわざ」を旗揚げされたと伺いました。
佐藤 : その経験って、影響あるかもね…。僕はずっと「役者になるために生まれてきたんだ」とバカみたいに信じてたけど、「役者をやりたい」「でも無理」「でもやっぱり役者をやりたい」「でも食えない」と繰り返していました。そういう時に、「今は全然ダメだけど、明日も頑張るか、俺」と何度も思っていたはずなんです。『memo』(2008)もそういう作品で。
― 佐藤さんの監督一作目となる『memo』は、ご自身の強迫障害の体験をもとに、紙にメモを取らずにはいられなくなる強迫性障害を持つ女子高生が、同じ病を抱える叔父との交流によって、少しずつ心が変化していく様子を描いた作品ですね。
佐藤 : 『はるヲうるひと』の脚本も、登場人物の“どこにも出口がないような売春婦たち”が、「どんなことがあれば『明日も生きていこう』って思えるのか」を考え、思い描きました。そして、その姿がうわっと浮かんできた時、自分も救われた気になるというか。それは、僕にとって「大きなきっかけ」ではない方がいいんです。
― 主人公の得太(山田孝之)と姉のいぶき(仲里依紗)は、貧困や複雑な家庭環境など、様々な抑圧のもと育ちます。その2人が幼少期にいじめられ落ち込む姿に、母親は「笑え。声出して笑え。試しに笑え。無理でも笑え。」という言葉で励ましますね。

佐藤 : それは、焼け石に水のような対策なんだけど、大人になった得太といぶきはその言葉を思い出して、ちょっと笑い合うんです。
実は、僕の母親がけっこう苦労したんですよ。父親が洋服屋を潰して借金を抱えちゃって。大変な苦労をして僕を育ててくれたんだと思う。でも、そんな姿を子どもには見せずに「二朗、そんなこと言っとっても、明日は明日の風が吹くで。悩んどってもしょうがないよ」って、よく言ってました。
― 「明日は明日の風が吹く」。
佐藤 : 「ケセラセラ」ってね。そのセリフも劇中に出てくるんです。
― 坂井真紀さん演じる桜井峯が、同僚の売春婦に向かって投げかける「何かになれても何にもなれんでも、そん時はそん時の風が吹きよろうぞ」というセリフですね。
佐藤 : 真紀ちゃんが素晴らしい演技を見せてくれて…。そう、僕の母親に伝えたんですよ、「お袋の口癖を映画のなかで使っているんだよ」って。
― お母様の返答は?
佐藤 : 「おっ、あ、あぁー!」って言ってた(笑)。「三重でも上映すんか?」って。今、三重に住んでるから。
― (笑)。
佐藤 : よく言うじゃない?「人は憎むより愛したり、信じたりする感情の方が強い」って。だから、笑うって大事なことですよね。何にも解決しないかもしれないけど、ちょっと無理してでも笑ってみたら、ほんの何ミクロンかもしれないけど「明日も生きるか」って気持ちになるかもしれない。そして、そこにこそドラマがあると思う。
僕はそういう姿を丁寧に捉えて描いていきたいし、凄く難しいことは承知で、僕だからこその表現があると思えるうちは、監督を続けたいですね。

佐藤二朗の「心の一本」の映画
― 佐藤さんのお話を伺い、以前インタビューした際に橋口亮輔監督がおっしゃっていた「映画は『絶望を描いてもいい』けれど、それを観た人を『絶望させてはいけない』と僕は思うんです。」という言葉を思い出しました。
佐藤 : 橋口監督の『恋人たち』(2015)という僕の大好きな映画があるんですけど、主演である3人の登場人物たちも、それぞれ劇的に置かれている状況が良くなるわけではないんですよね。でも、会社の先輩と話してふと笑顔になったり、パッと青空を見上げて「よし」ってつぶいたりする。そういうささやかな瞬間って、現実にもあると思うんです。やっぱり僕はそういう物語が、どうにも好きなんでしょうね。
― 『恋人たち』は、妻を通り魔殺人で亡くし、裁判を起こすために奔走する青年と、自分に関心を持たない夫と気が合わない義母と暮らしている女性、同性愛者であるエリート弁護士、それぞれが心に傷を抱えながらも懸命に生きている姿を描いた作品です。
佐藤 : 通り魔殺人事件によって妻を亡くしたアツシが、妻の遺影の前でじんわり泣きながら長ゼリフを話すシーンあるんですけど、それを観ながら「橋口さんのことだから撮影を朝まで続けたんじゃないかな…」とか想像したりしてね(笑)。

― 佐藤さんは、橋口監督の『ハッシュ!』(2001)や『ぐるりのこと。』(2008)にも出演されています。佐藤さんの著書『のれんをくぐると、』(山下書店)を読ませて頂いたんですが、こちらにも、お好きな映画で『ハッシュ!』と書かれていました。
佐藤 : 本当に大好きな映画です。僕が出演していることは別にして(笑)。
― (笑)。改めて、佐藤さんの「『明日も生きていこう』と、前を向く」気持ちになれた映画を教えてください。
佐藤 : この本にも挙げたけれど『幸福の黄色いハンカチ』(1977)と『クラッシュ』(2004)かな。
佐藤 : 『幸福の黄色いハンカチ』は、何回観ても泣いてしまう。それを恐れ多くも山田洋次監督に伝えたら、笑ってくださって。僕の妻には「アンタ何回観る気?」と驚かれるんですけど(笑)。
― 『幸福の黄色いハンカチ』、は北海道を舞台に刑務所帰りの中年・島勇作(高倉健)が、失恋のショックで仕事を辞めて旅に出た青年・欽也(武田鉄矢)と同じく失恋をして一人旅をする朱美(桃井かおり)と出会い、勇作の妻・光枝(倍賞千恵子)に会いに行くまでを描いたロードムービーですね。
佐藤 : 島は、夕張にいる光枝の気持ちを確かめたいけど、ためらう。その島の事情を知った欽也と朱美が、「行こうや、夕張!」と島を誘うんです。それで三人が乗った車が走り出した時に音楽が流れて…そこで涙がばーっと出て。…何回観てもそこで泣くんだよ。それも山田監督に伝えたんだけどね。

佐藤 : 島は人を殺めてしまった過去がある。けれど、彼が「どうして俺はやくざな性分に生まれついたのかな」とつぶやくシーンがあるように、人を殺めていい理由なんてないことを島自身がものすごくわかっているんです。
だから出所しても妻のもとには戻れない気持ちもわかるじゃないですか。それを汲んで、どうしようもない若者二人が「行こうや!」って言うのが……。泣けてくるわ! もう泣けてくる! 話してても涙が出そうになる!!
― 何度もご覧になられていると言うことですが、どんな時に観られるんですか。
佐藤 : ちょっと、ふさぎ込んでいる時に観るかな。どこか、この映画に背中を押してもらいたいって気持ちがあるかもしれないですね。
― もう一作に挙げて頂いた、ポール・ハギス監督の『クラッシュ』は、サンドラ・ブロックやドン・チードル、マット・ディロンなど豪華キャストが脚本に惚れ込み出演を決めた作品ですね。多民族国家で暮らすアメリカを舞台に、人種差別や階層、偏見や憎悪など人々の衝突がありながらも、愛や繋がりを求める人々の姿を描いています。
佐藤 : この『クラッシュ』は名作だよね。人は人と繋がらないと生きていけないから、心のどこかで接触したりぶつかったりすることを求めていると思うんです。人種差別など衝突を通して、それでも生きていくんだよってところにグッときたんでしょうね。
― 結局、人は人が必要だと。
佐藤 : 誰とも衝突することなく生きていくことの方が全然楽なんだけど、それだと人は発狂しちゃうんだろうね。
だから、人は人と繋がることを…って、なんか金八先生みたいになっちゃった(笑)。金八先生も「人という字は…」って言うけれど、人間はそうやって人と繋がらなきゃ生きていけない生き物だと思います。