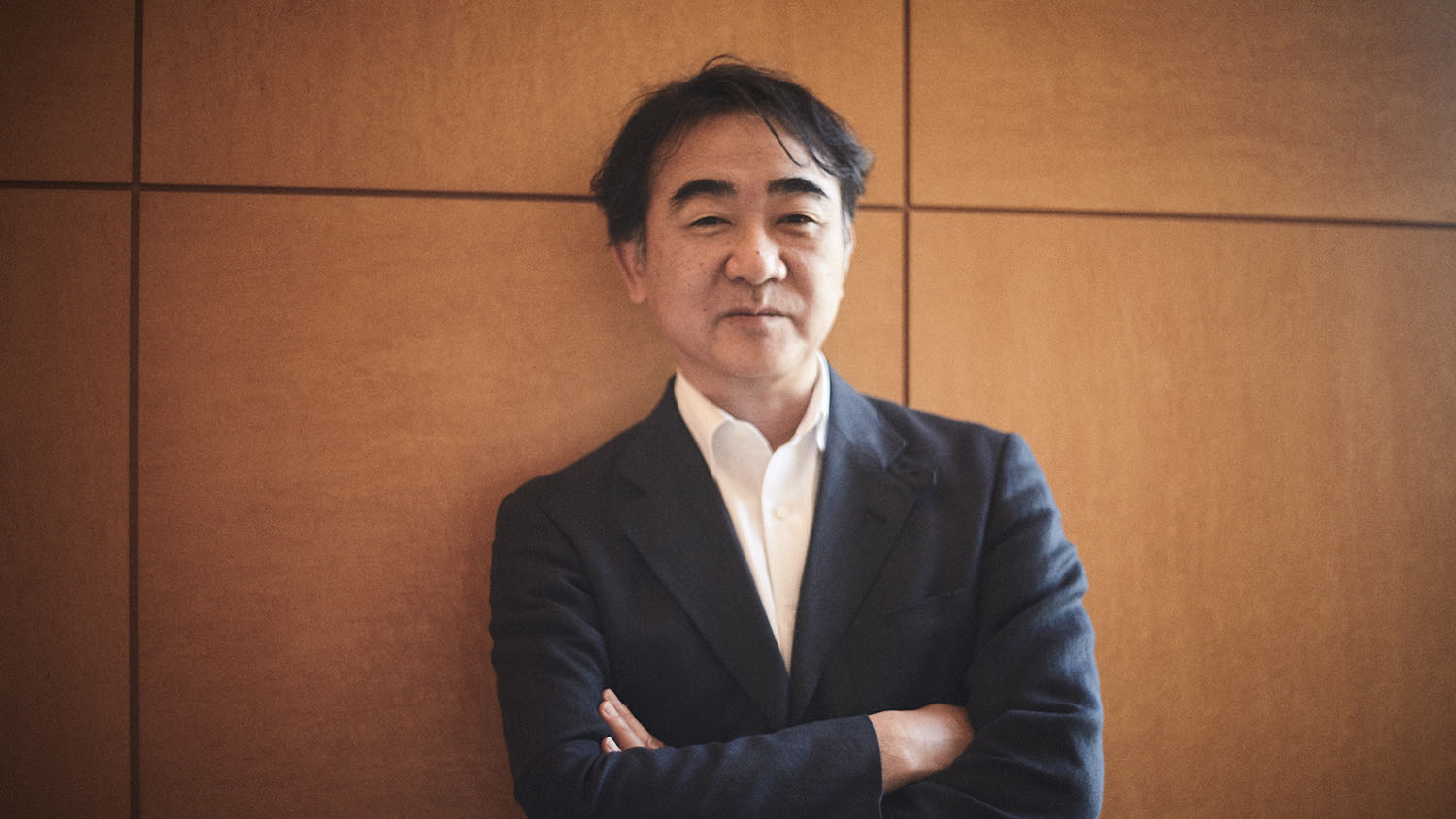目次

「もっと僕を褒めて!」
過去を捨てる生き方、を実践してきた
― 中井さんは2018年に三谷幸喜作品の『日本の歴史』でミュージカルに初挑戦されました。その挑戦について、中井さんは「恥をかくため」とおっしゃっていましたね。
中井 : 自分でも歳を重ねると、もっと守りに入るのかなと思っていたんだけれど、今になって思うとラッキーだったと感じることがあります。それは“大きい事務所”に所属せず俳優業をやってこれたということです。デビューは19歳。まだ大学生でしたが、事務所に所属すると学業が疎かになると思ったんです。卒業は必ずすると決めていたので、悩んだ末個人で事務所を立ち上げました。常に一人でやってきたからこそ、“守られている”と感じたことがなかったんです。
― なるほど、そういう状況にいたからこそ、挑戦することができたと。
中井 : だって誰も褒めてくれないんですよ(笑)。本当は「もっと褒めて」…ってずっと思ってました。でも、自分から「今の演技よかった?」って聞くのも気が引けるじゃないですか。相手は「うん」としか言えないもの。そういう過保護にされなかった状況の中で、“自分はどのように生きていくのか”を考え続けてきたんです。それで僕は「過去を捨てる」という生き方をしてきました。

― 「過去を捨てる」とは?
中井 : 映画やドラマを撮影している時は、撮影中がすべてなんです。そこで、どういうパフォーマンスを見せることができるかということに全神経を集中しています。そして、撮影が終わったらすべてを忘れて次に向かう、というように自分の中で切り替えるようにしています。意識して「挑戦をしよう!」と意気込んでいるわけではなく、そうやって「次しか見ない、見れない」とずっと歩んできたことが、もう習性になっているというのかな。
― “心がけて”やっていることではなく、“身に染み付いた”生き方になっているんですね。
中井 : 誰かが何とかしてくれるということが無かったっていうのが、大きいかもしれないですね。
― ちなみに、中井さんは今回演じられた役のように、記憶喪失になることがあれば、今の自分から変化させたいところはありますか?
中井 : もっと傲慢に生きてみたいです。自分勝手に(笑)。でも、残念ながら僕はそういうタイプではない…。そうなれるのは、才能を持ち、自信を持つことができる環境にいる人だと思います。先ほども申し上げましたが僕は、そういう環境下で育てられなかった。
どんなに興行成績があがった映画でも、賞を受賞しても褒められませんでした。いつも「父親には及ばない」「勉強が足りない」「それでは小津安二郎監督には使ってもらえない」…などとしか言われませんでしたから…。(※中井さんのお父様は、数多くの映画に出演された俳優の佐田啓二さん。中井さんは幼い頃にお父様を亡くされている) だから、傲慢な雰囲気を習得するなんてあり得なかったんです。

三谷幸喜と佐藤浩市と中井貴一。
三人は根っこで繋がっている!?
― 三谷幸喜さんと中井さんは同じ1961年生まれですね。お二人は親交も長く、中井さんは映画・ドラマ・舞台と数多くの三谷作品にも出演されています。三谷さんは今作について「この作品は僕の中ではある意味で“中井貴一ショー”」とおっしゃられていますが、三谷さんが中井さんをどのような人物だと捉えられていると感じますか?
中井 : 捉えられ方はわかりません…(笑)。ただ僕が三谷作品を演じる際、いつも思うことがあるんです。それは、私が出演した三谷監督作品で、もし三谷監督が俳優として演じるなら、多分僕の役だろうなと思うんです。
― なぜでしょうか?
中井 : 僕は学生時代に体育会系、三谷監督は文化系という違いもあるのだけれど、育ってきた頃から見聞きするものが一緒、つまりどこかで核となるところが共通していると思っているんです。だから、三谷作品を演じている時、「僕にアテガキをしているのか、それともご自身を投影しているのかどっちなんだろう?」と感じることがあります。
― 同世代というと、今作で中井さんと圧巻の長いシーンを演じられたフリーライター役の佐藤浩市さんも、1960年生まれですね。中井さんと佐藤さんが映画で長いシーンを演じられるのは、『壬生義士伝』(2002)以来かと。佐藤さんや三谷さんとはプライベートでも交流を持たれているのでしょうか?
中井 : プライベートでお食事に行ったり遊びに行ったりと、いわゆる仲良しごっこはしないですね。撮影現場で一緒になった時に、すぐに呼吸を合わせられる。そういう時に三人はそれぞれの価値観を持ちながらも、似たような境遇や同じ時代を生きてきたということを、いつも感じます。親友とかそうじゃないですか、会っていない時間が長くても、会った瞬間昔のような会話ができる。私達には、そういうところがあるような感じがしています(笑)。

― 中井さんは、これまで様々な方と出会われてきたと思うのですが、今作で演じられた役のように自身を大きく変えた出会いはありますか?
中井 : たくさんありますね…。けれど、この「俳優」という仕事と出会えたことが、僕にとって一番の出会いです。
僕は大学に入るまで、自分の進路に「俳優」という道は存在しなかったんです。親父が俳優だったけれども、芸能界との繋がりは、笠智衆さんと三井弘次さん(数多くの小津安二郎監督作品に出演した日本の名優)の二人だけでした。笠さんは、幼い頃の僕にとって、チャンバラごっこで切ったら、うまく死んでくれるおじさんだったんですよ(笑)。
― 幼い頃の中井さんにとって笠智衆さんは、一人のおじさんでしかなかったんですね。
中井 : とても失礼ですが、その当時はそうでしたね(笑)。芸能界というものに興味がなかったので、大学に入学しました。ただそこで自分の将来のことを考えたときに、「そういえば親父のことを何も知らない。親父がやってたことは何なんだろう?」と思いました。映画界というよりは親父の背中を知りたいと思ったんです。ちょうどそのタイミングで、映画出演のお話をいただきました。
― 中井さんは19歳の時、松林宗惠監督にスカウトされ、『連合艦隊』(1981)でデビューされます。
中井 : はい。その後すぐ小林桂樹さんから映画『父と子』(1983)の出演オファーをいただき、俳優の道を進もうと決心しました。それからは市川崑監督や相米慎二監督、それこそ三谷監督とも出会ったり…。小林さんに出会わなければ、その出会いもなかったわけなんです。

― 「俳優」という仕事は、ご自身にどういう変化をもたらしましたか?
中井 : 僕は赤面症で、人の前に立つのが嫌いだった人間です。学芸会でも、「やりたい!」と手をあげる子がいる中で、「あれ? お前、役決まったのか?」って周りから忘れられたいと思っているような子供でした(笑)。そんな自分が、初めての映画撮影の時、カメラの前で赤面しなかったんです。今まで思っていた自分とは違う“知らない自分”に出会ったのが、俳優という仕事でしたね。
― では、最後に「心の一本の映画」を教えてください。
中井 : 『サウンド・オブ・ミュージック』(1965)です。僕はいつも迷いなくこのタイトルを言います。小学校3年生(1970年)の時に、丸の内の映画館でリバイバル上映されているのを観たのが初めて。そこで、僕はジュリー・アンドリュースに恋をしました。
― 主人公の修道女・マリアを演じる女優ですね。どこに惚れたのでしょうか?
中井 : どこに、とかではなく心が震えたんですよ! 子供の頃に本当に好きになる映画って、理屈ではない。だから、当時、僕の理想の女性はジュリー・アンドリュースでした。サウンドトラックも擦り切れるくらい聞いて、初めて英語で覚えた歌が「ドレミのうた」でしたね。
― この映画を大人になってから再び観られましたか?
中井 : はい。でも、変わらないもんなんですよね。初めて観たときのワクワク感というか、とっても懐かしい故郷の小川を歩いている時のような気持ちになる。その川そのものが綺麗だと思うと同時に、自分がそこで幼い頃遊んだ姿を思い出すような。
こんなに純粋に映画を観たことはないと思うんです。親父が出ている映画は、子どもの頃から観ていたけれど、それは「僕の父親は、どんな人だったんだろう?」と“父親”を追いかけるためでした。でも『サウンド・オブ・ミュージック』は初めての洋画で、その世界に「ハ〜…」と陶酔できた作品なんです。大人になると小難しい映画も観るようになるけれど、誰にでもこういう原体験みたいな映画があると思う。照れ臭くってなかなか言えないんだけどね。