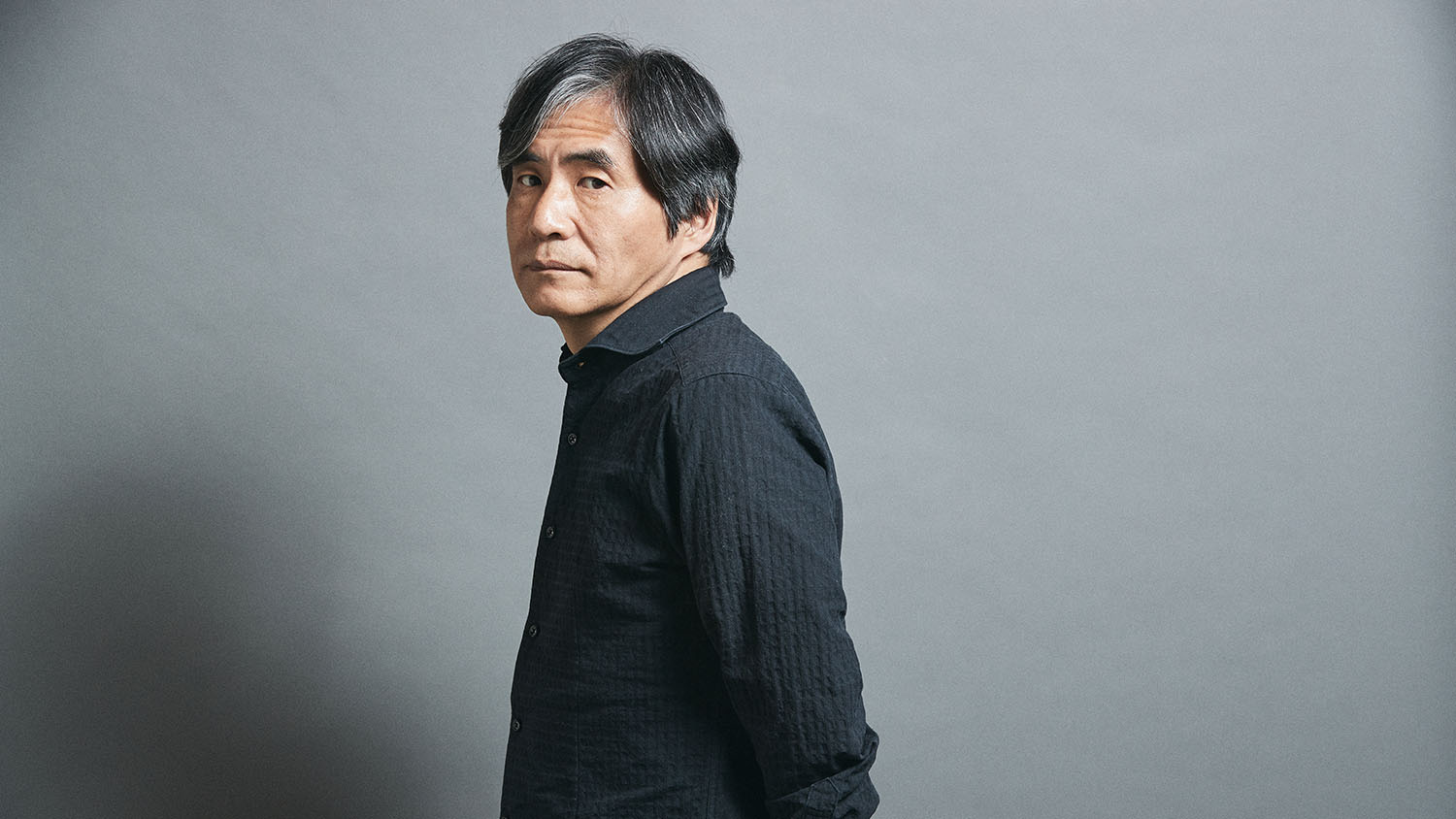目次

苦手だと思うことこそ踏み出す。
状況を動かすのは自分次第
― “金魚すくい”がモチーフでもある今作は、水槽を映し出す美しい光や幻想的な映像も相まって、主人公の香芝が、まるで不思議の国に迷い込んだ物語のようにも見えました。
松也 : 金魚すくいがあって、ミュージカルの要素もあって…僕自身も、脚本を読んでいて「これをどう映像化するのだろう?」と不思議でした。ですが、完成した作品を観たら、映像も演出も、これは新感覚の映画になったと思いました。普通はミュージカルでも歌わないような場面で、この映画では急に歌いだしたりしますからね(笑)。
― 冒頭で、東京本店から左遷されて田舎町にやってきた香芝が、その哀愁をラップで表現する場面には、意表をつかれました!
松也 : 「え、ここで歌うの?」となりますよね(笑)。演出としては、結構トリッキーな表現もたくさんあって、歌あり笑いありの、振り幅の広い映画だと思うんです。だからこそ、その軸にあるドラマや、僕が演じた香芝の人間性の部分は、ぶれないようにしようと意識していました。
香芝の想いや成長する姿というのが、最終的に映画をまとめると思っていたので。

― 元エリート銀行マンの香芝は、一度の左遷で人生に絶望してしまったり、新しい環境でも人に心を閉ざしてしまったりと、ネガティブな性格の持ち主です。そして、赴任してきた当初は、他人と距離をとっている人物でもありました。
松也 : 香芝は人との交流を避けて、自分のプライドだけで生きてきたような性格ですよね。考え方にも偏りがあって、東京から左遷されてやってきたこの町のことも、何もないつまらない場所だと思っている。
ですが、香芝の持つ偏見のように、形は違えど、気づかないうちに偏って物事を見ていることって、僕にもありますし、誰にでもあることだと思うんです。それが如実に現れている人物なので、僕はすごく人間的な男だなと思っていました。
― 歌舞伎の舞台を軸に、舞台や映画、テレビドラマやバラエティなど、新しい挑戦を続ける松也さんとは正反対のような印象を受けました。
松也 : 実は僕も香芝と同じく、人付き合いが得意な方ではなくて、コミュニケーション力というのはあまりない方なのです。だからこそ、心を閉ざしがちな香芝の気持ちも、わかるところはあります。
― 今回共演された柿澤勇人さんは、「松也さんが現場を盛り上げてくれた」とコメントされていたので、少し意外です。新しい環境や人間関係に向き合う時は、どうやってその苦手な部分を突破されているんですか?
松也 : プライベートでは、なかなか初対面の方と上手くコミュニケーションが取れないのですが、仕事では自分が“苦手”と思うことこそ、あえて踏み込んでいくことにしています。「自分から踏み越えないと、何も動き出さない」くらいの気持ちで。

― あえて踏み込む、とは例えばどのような?
松也 : 例えば、最近、少しずつ出させていただいていているバラエティ番組では、他の出演者の方との対話も含めて、その瞬間瞬間をどううまく反応し、返せるのかが問われると思うので、毎回挑戦する気持ちで向き合っています。
映画や舞台などに臨むような時は、まずスタッフのみなさんの名前を覚えることから始めます。長い時間をかけてのお付き合いになりますから。あとは、とにかく積極的に話しかける!
― どちらも松也さんにとって、“コミュニケーション”という意味での挑戦なんですね。
松也 : 普段なら僕が一番苦手なことですけど、そこは意識して取り組んでいます。
― 今作でも、他人と距離を取ってきた香芝が、相手と対話をすることで変化していく姿が描かれていました。
松也 : 見栄やプライドに縛られて、他人に心を閉ざしていた香芝が、新しい場所で出会った人たちを通して、仕事は人生を生きるためのツールに過ぎない、自分の人生を楽しむことの方が大切なんだ、と知っていく。人間関係の中で、自分にはなかった考え方に感化されて、成長していくことが、この映画の大きな枠としてあると思います。

エンターテイメントの力に救われたからこそ、
誰かのために舞台へ立ち続けたい
― 「出会いによって成長していく」香芝の姿が描かれているということでしたが、心を閉ざしてきた香芝が変わったのは、左遷先で出会った金魚すくい店を営む吉乃(百田夏菜子)を救ってあげようと行動をしたことがきっかけでした。松也さんも、そういう経験はありますか?
松也 : そうですね…歌舞伎は、伝統継承の文化でもあるので、先輩に教えていただいたことを後輩に伝えていくという、“恩返し”の繰り返しで成り立っているんです。そういう意味では、自分が若い人たちに伝えることが、「人のため」といえる行動になっているのかもしれません。
僕もまだまだ修行中ですので、自分から教えるということはあまりないのですが、歳を重ねてそういう機会が増えていったら、より誰かのために動いていると実感するでしょうね。でも、「誰かのため」は「自分のため」だと最近よく感じます。
― それは、どういうことでしょうか?

松也 : 今、このインタビューでもそうですが、人に伝える時って言葉や形にするため思考を頭の中で整理しますよね。相手からの質問に答えようとして、考えを整理するうちに、「自分はこんな風に感じていたんだ」と気づくこともある。人のために動くことって、最後には自分の成長につながってくるんだなと思います。
― 「人のため」は「自分のため」となぜ、最近感じるようになったのですか。
松也 : 昨年は、自粛で家にいる時間も長かったので、自分の仕事について、誰かのために舞台に立つことについて、よく考えていました。
舞台に立ったり映画に出たりするという僕の仕事は、観客のみなさんがいてこその表現ですよね。でも、こういう状況になるまでは、目の前の仕事にベストを尽くすことで精一杯になってしまい、「誰かに向かって表現をする」ということへ冷静に向き合う時間が少なかったように思います。
― それが、自粛期間を通して仕事から離れることで、改めて仕事に向き合う時間になったと。

松也 : そうなんです。家にいる間、何をして過ごしていたかと思い出すと、とにかくずっとテレビや映画を観ていました。でもそれは僕だけではなくて、多分あの時期は、世の中の多くの方が、家で同じように過ごしていたと思うんです。
― 動画配信サービスの利用者数も、あの時期から急伸し、書籍の売り上げも上がったそうですね。
松也 : 僕がそうであったように、きっとエンターテイメントがなかったら、あの期間を乗りこられなかった方が多くいたのではないかなと想像するんです。ですので、自分が携わっている仕事の意味、エンターテイメントの役割を再確認できたというか。自分に向き合う時間になりました。
― 松也さんご自身も、自粛期間中、エンターテイメントの力に救われたんですか。
松也 : 僕の場合は、海外のテレビドラマシリーズ『ゲーム・オブ・スローンズ』を観て、昨年の自粛期間を乗り越えたのですけど(笑)。あれは、世界中に人気のある作品で、本当に多くの方が観て元気をもらっていたと思います。
規模は違っても、僕が舞台や映画に出ることで、誰か一人でも、同じように感じてくださる方がいるかもしれない。そう思うと、自粛期間を乗り越える力にもなりましたし、自分の関わっている仕事も誇らしく、何か感慨深い気持ちになりました…。そういう時間でしたね、僕にとって自粛期間は。

尾上松也の「心の一本」の映画
― 自粛期間を経て、プライベートでの映画の楽しみ方で変わったところはありましたか?
松也 : 変わったところもあったと思うのですが、ある程度の時間を過ぎると、だんだん日常になってきて忘れてしまうんですよね。仕事も、映画や舞台の現場から離れていた時は、「早く戻りたい」と思っていましたし、久しぶりに現場に行った時は「うわ、芝居ができてる」と泣きそうになったのですが、人ってすぐ状況に慣れてしまうもので、数日後には「明日も早朝から撮影が始まるのか…」と思っている自分がいて(笑)。
でも、1回目の緊急事態宣言を経て、久しぶりに映画館に行った時のことはよく覚えています。
― 何をご覧になったんですか?
松也 : 『ドクター・ドリトル』(2020)ですね。ロバート・ダウニー・Jr主演の。劇場が暗くなって、映画館の大きなスクリーンに予告編が流れているだけで、もう泣きそうになりました。「こうやって映画館で観られていることは、普通ではないんだ」という特別感があって。最近では、コロナ禍であることが以前よりも日常になってきてしまいましたが、あの時に映画館で受けた特別な感動は、今でも印象深く残っています。
― では最後に、そんな映画好きの松也さんにとっての、「心の一本」となる作品を教えて下さい。
松也 : 僕が昔から好きなのは、『アンタッチャブル』(1987)ですね。いつ観ても、本当にかっこいいです!
― 『アンタッチャブル』は、禁酒法時代(※)のアメリカを舞台に、犯罪組織と捜査官チームの戦いの日々を描いた名作ですね。ケビン・コスナー、アンディ・ガルシア、ロバート・デ・ニーロ、ショーン・コネリーと名だたる名優が出演する作品でもあります。
松也 : あの時代のケビン・コスナーがかっこよくて、痺れますね。アンディ・ガルシアの、まだフレッシュな魅力もたまらないし。あとは、ロバート・デ・ニーロ! 彼が画面にいるだけで、観ている自分も一緒にその場にいるかのように緊張してしまいます。『ケープ・フィアー』(1991)で演じた犯罪者の役もそうですが、何をしでかすか予想がつかない怖さがあって。デ・ニーロは、佇まいだけでそれを見せるのが、まー本当に上手い! その最強のコラボレーションで文句なしに面白い!!

『ゴッドファーザー』(1972)なども好きなのですが、昔からギャング映画に描かれる、男たちの関係性が好きなんです。昨日の友は明日の敵、みたいなところがあるじゃないですか。手を組んだと思ったら裏切られ…という繰り返しで、誰も信用できない。戦国時代の武将みたいな、人間関係の駆け引きがあるんです。
― 死が隣り合わせにあるからこそ、ギャング映画には“緊張感ある駆け引き”が生まれるのでしょうか。
松也 : 多分そうですよね。自分の現実には、死が隣り合う人間関係なんて絶対ないですけど(笑)、だからこそ憧れます。特に、その中で生まれた男の絆の物語が好きで。死が身近に存在する中での信頼関係って、家族とも友人とも違う、特異なものがあると思います。そこに男のロマンを感じるんでしょうね。ギャング映画の「喧嘩してなんぼ」みたいな潔さも好きです。
― 禁酒法時代という、映画の背景も関係があるのかもしれません。密造や賭博などが横行し、ギャングが街を支配する中で、警察や政治も巻き込んで、正義とは何かということすら揺らいでいた時代が描かれています。
松也 : あんな時代がまた来たら大変ですが、あの時代設定だからこそ、あそこまでめちゃくちゃでかっこいい男たちが作品の中に生まれたんだろうな、とは思ってしまいますね。ルール無用で、法もかいくぐって、仲間が裏切られたらすぐに報復する、みたいな。
でも、別にギャングとかマフィアになりたいわけではないです(笑)。…が、自分の本能をストップするものが何もない、理性ではなくて野生のまま生きている。そこには、やっぱり憧れるものがありますね。

※禁酒法…1920年代から30年代初期まで、アメリカ合衆国憲法修正第18条下において施行され、消費のためのアルコールの製造、販売、輸送が全面的に禁止された法律。
↓『すくってごらん』原作本を読む!