目次
ロケ地に立つと、『男はつらいよ』の軌跡が
ARのように浮かんでくる
― 原野さんは「寅さん ロケ地ハンター」として、『男はつらいよ』シリーズのロケ地を巡り、そこで撮影した写真をSNSに投稿されていますね。
原野 : むしろ、ロケ地巡りを本業としています。
― 本業ですか!(笑) 最近の投稿では、吉永小百合さんがマドンナを務めた13作『寅次郎恋やつれ』(1974)のロケ地・島根県津和野町を訪れた際の写真をあげられていました。
原野 : 誰も見つけられなかったポイントを発見するのが嬉しいんですよ、日本初公開的な(笑)。でも、実は僕だけでなく、寅さんのロケ地を周ってその記録をブログで綴っている大先輩がたくさんいるんです。
― そうなんですね!
原野 : 『男はつらいよ』で撮影されたポイントを、ストリートビューなどで探し出し、最後は足で歩き回って検証していて、ものすごいんです、本当に。僕は、そういう先輩方の記録を参考にして巡っています。多分想像するに、発信されている方は、寅さんが好きで、すでに定年退職されて時間に余裕のある方などが多いのではないかな。
― 原野さんはロケ地を巡るだけでなく、具体的にどの角度から実際に撮影されたか、カメラの位置まで探求されていますよね。1〜49作『男はつらいよ』の撮影監督である高羽哲夫さんの名前から、「#_高羽アングル」と名付けていらっしゃいます。
原野 : 僕は、山田洋次監督と高羽哲夫さんを、ジョンとポール(ジョン・レノンとポール・マッカートニー)のように思っています。お二人が担当された『幸福の黄色いハンカチ』(1977)『遙かなる山の呼び声』(1980)なども大好きで。

― 高羽さんについて、山田監督は「この人を仕事の伴侶に得たぼくは、はかりしれぬ果報者だった」とおっしゃっていますね。
原野 : いい映画は「画集」のようなものなのです。『男はつらいよ』シリーズで映し出される風景の連続は、まさに画集。だから、作品の魅力の秘密は、画(映像)にも隠されているのではないかと思ったんです。やはり、僕はクリエイティブディレクターでもあるので、撮影された場所に実際に立って、感じ、その秘密を探ってみたくなりました。
ギターを始めると最初は好きなアーティストの楽曲をコピーするじゃないですか。まさにそんな感じで、映画をコピーするような感覚です。実際行って撮ってみると「あれ? なんか違うな…ここに柵が写っているはずなのに…(振り返って)あ、わざわざあの柵を入れるためにあそこから撮ったのか!」と、こだわりポイントのようなことがだんだんわかってくる。そんなふうに、山田監督や高羽さんがその場所で撮影した理由を考えるのが面白いんですよ。
― 自分がいいと思った作品を、自身でなぞってみることで取り入れてるんですか。
原野 : 僕は『男はつらいよ』をつくりあげてきた人たちを、すごく尊敬しています。「ロケ地ハンター」をしていると、山田監督や高羽さん、それから美術のチームなど出演者やスタッフが、その場所に集まって「ああでもない、こうでもない」と試行錯誤した軌跡を感じることができるんです。AR(拡張現実)みたいなものですよね。

― 自分の現実に、『男はつらいよ』の情景を重ね合わせていると。
原野 : 僕は1971年生まれなんですが、満男と世代が同じなんです。だから、映画を観ていると、満男を通して僕が見てきた風景を追体験しているような気にもなって。
― 満男は、博(前田吟)とさくら(倍賞千恵子)の息子で、27作から吉岡秀隆さんが演じられている役です。12月に公開される新作『男はつらいよ おかえり 寅さん』(2019年12月27日公開)にも物語の中心人物として登場しますね。
原野 : 満男の身につけている服とか、持っているおもちゃとか、テレビゲームとか、ワープロとか。そういう変遷が僕の人生のそれとシンクロしています。
― なるほど。『男はつらいよ』シリーズを、自身の記録のようにも感じている。
原野 : そう。フィクションなんだけれど、ドキュメンタリーを観ているようでもある。その感覚が、ロケ地ハンターの趣味にも繋がっている気がしますね。
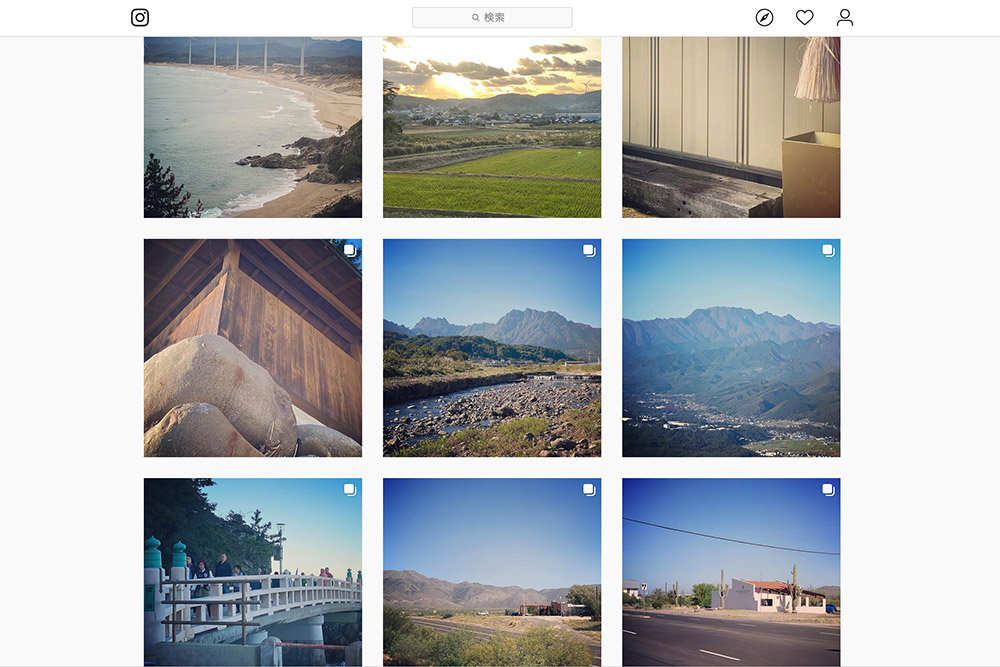
『男はつらいよ』は、
映画という枠組みを超えた「現象」である
― 原野さんが生まれた1971年は、『男はつらいよ』6・7・8作が公開された年ですが、子供の頃からご覧になっていましたか?
原野 : いや、僕が『男はつらいよ』を好きになったのは、大人になってからなんですよ。しかもつい最近です。
― そうなんですか!
原野 : 僕と『男はつらいよ』の出会いは、国際線の飛行機の中なんです。海外に出張することが多い時期に、機内ビデオで鑑賞しました。飛行機の中で観るといい映画っていうのがあるんです。
― 確かに、寅さんは「お尻のまわりはクソだらけ」などといった口上を語りますから(笑)。
原野 : 僕と『男はつらいよ』の出会いは、国際線の飛行機の中なんです。海外に出張することが多い時期に、機内ビデオで鑑賞しました。飛行機の中で観るといい映画っていうのがあるんです。

― どうしてですか?
原野 : 映画館もそうなんですが、誰かと映画を観る場合、みんなで「笑う」ことはできても「泣く」って意外と難しいんですよね、僕の場合。ちょっと恥ずかしいというか。でも、飛行機の中だと周りを気にしなくてもいい。しかも、日本を離れる・戻ってくるという状況で、日本の風景や風俗を感じられるというのも良くて。
― 機内だからこその映画体験があるんですね!
原野 : はい。それをきっかけに好きになり、動画配信でも観るようになりました。よく寝る前に観ていましたね。
― 安眠できるのでしょうか(笑)。
原野 : そう、2・3本観て。
― 2・3本も観ちゃうんですか!?(笑)
原野 : 夜、なかなか寝つけない人なんで(笑)。そうやって、シリーズを観ていくことでハマっていきました。「このフリがあるってことは、こういう展開になるな!」とお約束もわかって、より作品を楽しめるようになる。

原野 : だから、長く続く作品は、フレームワーク(枠組み)がはっきりしているところに秘訣があるのではないかと感じます。『スター・ウォーズ』もそうですし。偉大なるマンネリズム。
― 脚本の朝間義隆さんも「『寅さん』の物語にはいつも決まった形がある。決まった人物もたくさん登場する。だから、一つ一つ違う物語をこしらえるために、毎回新しい人物を作りださなければならない。それが、また、大いなる楽しみでもある」とおっしゃっています。
原野 : 一作一作よく観ていくと、同じ形の中にも新しい工夫というか挑戦を発見しますよね。
― 今回、シリーズ49作の4Kデジタル修復の指揮をとったプロデューサーの方も、同じことをおっしゃっていました。
原野 : これだけ長く、多くの人に愛され続けた作品の持つ力を、そこに感じます。『男はつらいよ』は、70〜80年代という“一番いいときの日本”で万人に愛されて、“一番売れた映画”です。つまり、日本映画の「top of the top」。そういうトップを駆け抜けたエンターテインメントというのは、その存在自体が「現象」となり人を惹きつけているところがあると思います。

原野 : ザ・ビートルズもその楽曲だけでなく、周りで「キャー!」と歓喜しているファンの姿をひっくるめて“ビートルズ現象”になっていますよね。偉大なエンターテインメントは、「現象」であり、「事件」なんです。
― 『男はつらいよ』は、もはや映画という枠組みを超えた存在になっていると。原野さんが、満男を通して自身が育ってきた風景を体験したように、『男はつらいよ』はシリーズ49作が公開された1969〜1997年、そして新作が公開された2019年までの、50年間の日本の記録でもあります。
原野 : その時代時代の空気が注意深く捉えられていると思います。あと、渥美清さんはじめ、倍賞千恵子さんや前田吟さんなど、その方たちの人生の記録でもある。
だから、『男はつらいよ』のシリーズを通して観るということは、その人にとって「体験」という意味合いが強いですよね。ノンフィクション性がある。僕は全作観てるだけでなく、ほとんどのロケ地にも訪れているので、新作『男はつらいよ おかえり 寅さん』(2019)を試写で観させていただいたとき、もうちょっと涙止まらない感じありました。1カット1カットに、溢れ出てくることがたくさんありすぎて(笑)。やはり、「ノンフィクション」というのは、より一層人を動かすんだと感じましたよ。

― 原野さんは、広告に現象や体験といった「ノンフィクション性」を取り入れてきた第一人者として知られています。2011年のカンヌ国際広告祭で金賞した『森の木琴』は、福岡県の古処山の樹間に間伐材で組み上げられた44mの木琴に玉が転がり、バッハの音楽が実際の森の中で奏でられます。その音と映像が心に響きました。
原野 : あの広告ではメイキング的なシーンをわざと冒頭にいれることで、木琴のアートを見せるだけでなく、それをつくった人々の物語も見せるということをしています。そうした実際の物語、ノンフィクションには「強さ」と「新しさ」が宿るということですね。
― 2014年に手がけられた、アメリカのロックバンドOK GOの「I Won’t Let You Down」のミュージッククリップも、室内から外、そして空までをワンカットで撮影されていて、「現象」を見ている気持ちになりました。
原野 : ワンカットで撮ることによって、その映像はノンフィクションになるんです。OK Goは世界で初めてそのことを発見したバンドで、ノンフィクション性が受けるインターネット時代の最初のヒーローになりました。去年大ヒットした『カメラを止めるな!』(2017)もワンカット撮影が事件になることを知っていて、巧みに利用している。
でも、「ロケ地ハンター」で得た『男はつらいよ』の画角などを、映像の広告に取り入れたりはしていますが、僕の『男はつらいよ』への愛と尊敬を反映したものは、僕はまだつくれていないように思います。

4Kデジタル修復された『男はつらいよ』は、 人類を豊かにするバトンである
― 最後に、『男はつらいよ』シリーズの中で、原野さんが一番好きなシリーズ作品「#推し寅」を教えてください。
原野 : 難しいですよね…。これまで『男はつらいよ』とザ・ビートルズを重ね合わせてきましたが、ビートルズを好きな人は、楽曲の中で一番どれがいいかを答えられないんです(笑)。
― 一番は決められない(笑)。
原野 : ビートルズの音楽は「前期」「中期」「後期」と分けられて語られることが多いのですが、「ちょっと前までは前期が好きだったんだけど、今は中期がぐっとくる」というように大好きな時期はしょっちゅう変化するんです。僕は『男はつらいよ』も「前期」「中期」「後期」という区分があるような気がしていて、「最初のころは、渥美清の脂がのりきった中期が好きだったけれど、今は満男が活躍する後期が好き」とか自分の状態によって変化します。
― その中でも、今の原野さんは…?
原野 : そうだな…あっ、7作の榊原るみさんがマドンナ・花子を演じる『奮闘篇』(1971)は、最後のシーンというか終わり方が好きな作品です。バスの中で寅さんが、青森まで迎えに来てくれたさくらに言う「死ぬわけねえよな」のセリフがぐっとくるんです。田中邦衛さん演じる、花子の身元引受人となる朴訥な教師の役もすごく良くて…。

― マドンナの花子が話す津軽弁や、ロケ地の青森の風景も印象的ですよね。
原野 : はい、行きました(笑)。
― やはり、行かれましたか(笑)。
原野 : 花子が、一連のマドンナとは違った役割を担った存在であるところも好きな理由です。竹下景子さんがマドンナを演じるシリーズを観たくなるときもあるし、松坂慶子さんの時もあるし…。
― そう思うと、時々の自分の状態によって選べるのは贅沢ですね(笑)。
原野 : 38作『知床慕情』(1987)、41作『寅次郎心の旅路』(1989)のマドンナ・竹下景子さんと淡路恵子さんの掛け合わせもいいんですよ。
原野 : あと、ほとんどのシリーズ作品に出演する、女優の谷よしのさん。行商の花売り、くるまやの客、旅館の女中とかちょっとした役で登場していて。『男はつらいよ』を愛する人の中では、谷さんファンが多いんです…と、ずっと語れるわけですが(笑)。

― 新作が出ることで、こうやってまた語り継がれていくんでしょうね。
原野 : だからこそ、残していきたい。そこが重要なのではないでしょうか。後世に残していかなければいけないものってあると思うんです。例えば絵画なども、そのために修復するわけです。ザ・ビートルズも最近、リミックスされた『アビー・ロード』50周年記念エディションが発売されましたよね。その時代のテクノロジーの進化に合わせてメンテナンスし、残していく。『男はつらいよ』もそうです。
― 50周年に合わせて、全49作が4Kデジタル修復されました。これも今の技術があったからこそ、できたことだそうです。
原野 : 制作した映画監督が作品の修復過程を監修するというのも奇跡的ですよね。そんな作品は、なかなかない。長生きしていただいたおかげですね。もっとも、高羽さんには見ていただけなかったわけですが…。
映画も広告もそうですが、新しい作品は、つねに過去の作品にインスパイアされて生み出されていきます。その積み重ねなんです。『男はつらいよ』の4Kデジタル修復にインスパイアされて、また新しい映画が生み出されることでしょう。人類の財産である数々の名作をお借りして新しいものが創り出され、それがまた人類の財産として「お返し」され蓄積していく。そうやって人類はだんだん豊かになっていくのではないでしょうか。




![男はつらいよ 寅次郎恋やつれ[DVD]](https://www.pintscope.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/540e950876a4088e0e193053d795d71b.jpg)
![幸福の黄色いハンカチ[Blu-ray]](https://www.pintscope.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/SHBR-1014_S.jpg)
![遙かなる山の呼び声[Blu-ray]](https://www.pintscope.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/SHBR-0311_S1.jpg)

![男はつらいよ 奮闘篇[DVD]](https://www.pintscope.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/d0258fe7a2752a814dd33cb74ee18abf.jpg)
![男はつらいよ 知床慕情[Blu-ray]](https://www.pintscope.com/wp/wp-content/uploads/2019/12/f7326225375d7e7110d749686ab59fbe.jpg)




