目次

「撮る覚悟」があらねば
― ドキュメンタリー作品に長年携わってこられた皆さんのーー信友さんは監督として、濱さんは製作として、大槻さんは劇場としてーーそれぞれの視点から、ドキュメンタリーの魅力に迫れればと思います。
信友 : 気持ち的な予習をあまりして来なかったので、ぶっつけ本番になっちゃうと思いますが、がんばります。
濱 : 信友さんは、ぶっつけ本番に強いので大丈夫です!
信友 : もし私が変なことを言ったら止めてね。……撮影されること考えて、服選んできた?
濱 : え!? これじゃダメ?
大槻 : マフラーは取った方がいい?
信友 : 色味があるといいから、つけといた方がいいわよ。
― (笑)。仲の良さを、先ほどからずっと感じております。皆さんが一緒に携わったのは、フジテレビの『Mr.サンデー』から企画が立ち上がり、2018年にポレポレ東中野で公開後、口コミで上映館を99館まで増やした『ぼけますから、よろしくお願いします。』(2018)です。
― 今作は、信友監督のご両親の老老介護をする日常が、離れて住む娘の葛藤を交えて描かれており、信友監督にとって初の映画作品となりますね。濱さんは『Mr.サンデー』と映画のプロデューサーとして、大槻さんはポレポレ東中野の代表として、この映画を届けられてきました。ドキュメンタリー映画では異例の大ヒットとなったわけですが、ご両親を撮り始めた時は、世に出すつもりはなかったそうですね?

信友 : 最初はあくまで「信友家」の記録として撮り始めたんです。ちょうどその頃、ディレクター一人で現場に行って撮るのが主流になってきたのもあって、2000年の年末に初めて自分で小型カメラを買いました。でも、人を撮るのってやっぱり難しいから、練習をしようと思って。
だからといって、テレビで放送する予定もないから、他人に頼むのは気を遣う。親を撮っている分には文句は言われないだろうと、2001年のお正月から「信友家」の日常を撮ることにしたんです。
― いわゆるホームビデオ的な、家族の記録だったと。
信友 : そうなんです。そうこうしてたら6年後、私が45歳で乳がんを罹って、闘病中の自分と、広島から上京して私の看病をしてくれた母を撮ることになりました。
― それは、2009年にフジテレビの『ザ・ノンフィクション』で放送されたドキュメンタリー『おっぱいと東京タワー ~私の乳がん日記〜』として発表されています。がんの摘出手術の前に信友監督が泣きながら自身の胸の記念写真を撮る様子や、治療で髪が抜けた信友監督にお母さまが「可愛い」と声をかける場面は印象的でした。

信友 : その後、母におかしな行動が目立ち始めた頃、私、家族を撮るのを一度やめているんです。母が自分の異変を一生懸命私に隠そうとしていることが分かったので。
― 「おかしな行動」とは、認知症の兆候ということですね。
信友 : もしその異変をカメラで記録してしまったら、母のことを傷つけてしまいそうで怖くなったんです。すると母が「あんた前はよくカメラでお母さんのこと撮りよったのに、最近撮らんようになったね。お母さんがおかしゅうなったけん、撮らんようになったん?」って言ってきて。母にとってはいままで通り、撮り続けた方が傷つかないんだと気づいて、「そんなことないよ、撮るよ」とまた撮影を再開しました。
― あくまで「母娘」という関係性の中で撮影をしていたと。
信友 : その矢先、母が突然「なんで私はこういう風になったんかね…」と言い始めたんです。認知症に関するドキュメンタリーを過去に何本か製作した立場から見ても、患者本人がここまで自発的に語る姿は見たことがなくて驚きました。
― 信友監督は、まだ認知症だと公言することが憚られていた時代の2006年に、フジテレビで『消えゆく記憶〜若年認知症と向き合って』というドキュメンタリーを発表されています。
信友 : 「こんな機会を撮り逃すわけにはいかない」という、ある種の使命感もあって。「ちょっと待って!」と慌ててカメラを取りに行って「なになに? お母さん、どうしたん?」って改めて聞き直したんです。
大槻 : え…!?
濱 : 普通はそこで撮れないですよ(笑)。ドキュメンタリーディレクターとしての血が騒ぎましたね。
信友 : これからどうなるか不安でたまらない患者の気持ちが、すごく伝わるなと思ったから。認知症になると、周りは大変だけど本人は何も分かっていないんだろうと思われがち。でも実は患者本人が自分の異変に一番怯え傷ついているんです。
我ながら「すごい映像が撮れた」という手ごたえもあったから、いつか発表したいという気持ちはあったんだけど、父と母のプライドもあるだろうし、その時点では「発表できるとしたら二人が亡くなった後になる」という気がしていました。
― それが、なぜ想定より早く、世に出ることになったのでしょうか?

濱 : 当時ぼくがプロデューサーをやっていた『Mr.サンデー』の企画会議で、あるADが「信友さんが、認知症に罹ったお母さんの様子をずっと撮影しているんです」と発言したんです。それで、その映像の存在を知ることとなって。
信友 : たまたま、別件でそのADに預けたテープの後ろに、両親を撮った映像が入っていて(笑)。それを目にしたADが、「これはすごい瞬間だ!」とすぐに企画会議に出したんです。私に事前確認したら絶対に「ちょっと待って」と止めるだろうなと思ったそうで。
― 「これを世に出さなくては」と、使命感を持たざるを得ない映像だったんですね。
濱 : 僕は、元気な頃の信友さんのお母さんにもお会いしたことがあったので、初めてその映像を見た時はショックを受けました。映画をご覧になったら分かるように、信友さんのお母さんはとても明るく朗らかで、すごく魅力的な人だったから。

― 信友さんが乳がんの手術を受けられた時でしょうか?
濱 : いや、それより前で、信友さんがインドで列車に轢かれた時ですね。信友さんはとにかくネタが豊富なんですよ(笑)。
― そのエピソードも気になります(笑)。
濱 : でも、それと同時にテレビ屋として「!」と思ったんです。信友さんはドキュメンタリーの最高の撮り屋であり、「撮る覚悟」を持っている人だから。
― 「撮る覚悟」ですか。
濱 : 例えば『消えゆく記憶』を撮った当時は、認知症に対して理解がほとんど浸透していなかったから、今よりも更に偏見があって、患者さんが顔を出してありのままの姿を伝える映像はほとんどなかったんです。その中で、信友さんはそれを実現させた。
信友 : そうね。まだ「認知症」という言葉が定着してなくて、「ボケ」とか「痴呆」と言っていた頃だったし。当時番組のMCを務めていた小島奈津子さんが「認知症という言葉で統一しましょう」と啓蒙していたのを覚えています。
濱 : あと、僕が「撮る覚悟」を感じたのは、信友さんが自身の乳がんの手術から1年後、再検査の結果を関係者に報告する際に「私、数値が悪くて、がんが再発したら死んじゃうかもしれないの!」ってわんわん泣きながらも、ふと後輩ディレクターを振り返って、「(カメラ)回してる?」って確認したというエピソードを聞いた時。

濱 : 自分の感情に向き合うのも本気だけど、撮って伝えることも同じくらい本気なんですよ。そうすることで常に自分の気持ちを保っていて、客観性に長けているんです。テレビに携わっている人間としては、そんなすごい人が撮った映像を、放っておくわけにはいかないじゃないですか。
― 信友監督は以前「家族も好きだけれど、ドキュメンタリーも大好き」と発言されていますね。
濱 : とはいえ、『Mr.サンデー』は日曜夜のプライムタイムに放送する番組なので、正直「認知症のドキュメンタリー」というだけでは、企画として成立しづらいんです。でも信友さんが撮ったものなら、とてつもなく質の良いものである可能性が極めて高い。
― 信友監督のつくるものへ信頼があったと。
濱 : 長い付き合いでしたから。信友さん自身がOKするのは間違いないと思ったけど、ご両親がどう判断するかはわからない。テレビに映るとなれば良いことばかりでなく、もしかすると悪い影響も出るかもしれない。「やるからには覚悟を決めてやりませんか?」と信友さんと話したのが、この企画のそもそものはじまりですね。

「届ける覚悟」もあらねば
― 信友監督のお母さまが認知症になり、お父さまが介護をする日常を撮った映像が、『Mr.サンデー』の企画として放送された後、その反響の大きさから第二弾が放送され、BSフジで一つの番組としても放送されることとなります。そこから映画として、ドキュメンタリーを中心に上映するポレポレ東中野で公開されることになったわけですが、映画館の代表である大槻さんは『ぼけますから〜』と、どう出会われたんですか?
大槻 : きっかけは、大島さんなんだよね。濱さんも来てたと思うんだけど。
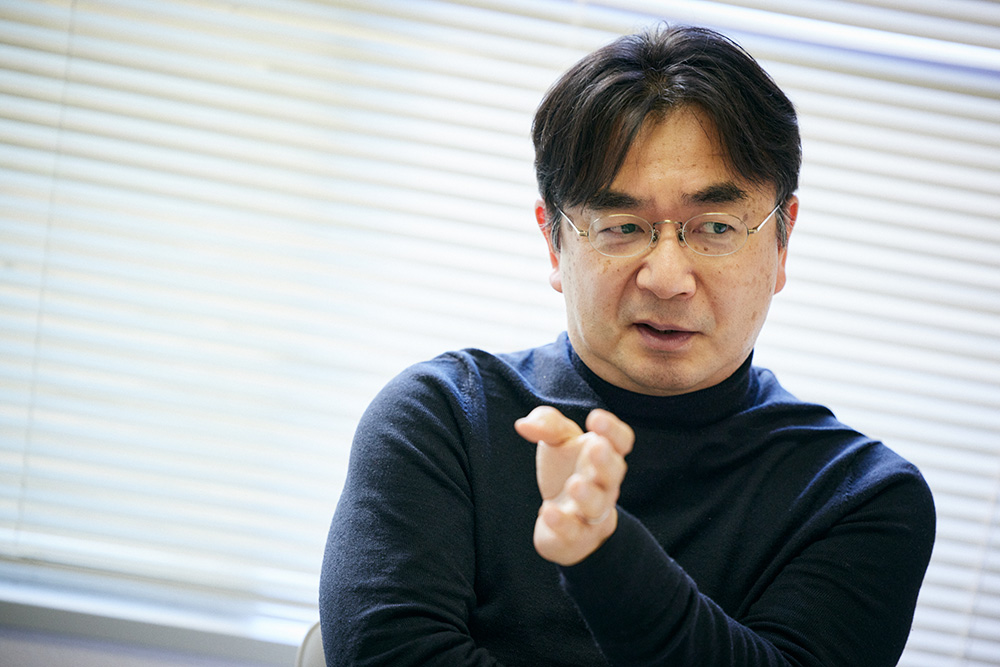
― 『なぜ君は総理大臣になれないのか』(2020)、『香川1区』(2021)の監督である大島新さんですね。フジテレビで『NONFIX』『ザ・ノンフィクション』などのディレクターを経て、独立後は様々なドキュメンタリー作品を撮られています。『ぼけますから〜』には、濱さんと一緒にプロデユーサーとして参加されています。
大槻 : 以前から付き合いのあった大島さんが、「これは絶対に当たります!」とBSフジで放送された素材を僕のところに持ってきたんです。
濱 : ちょうど大島さんと一緒に進めていた別企画が難航していたタイミングで、たまたま『Mr.サンデー』を観た彼が、しきりに信友さんの話をしていたんです。BSフジでも放送されるよと言ったら、それも観た上で「俺が全部リスクを取るから映画にしよう!」と言ってくれて。
信友さん自身も「いつか映画にしたいなぁ」と雑談レベルで話してはいたんですが、僕の中にはそこまで具体的なアイデアはなかった。もし大島さんが「やろうよ!」と言ってくれなかったら、映画にはならなかったと思いますね。
信友 : テレビディレクターの私にとって、映画は憧れではあるけれど夢のまた夢みたいな、手の届かない存在だったんです。映画製作には借金を抱えるイメージがあったし、ましてやドキュメンタリーなんてほとんど儲からない。自分のメシのタネは自分でなんとかしないとならない独身の私に、老後の資金まで全部つぎ込むギャンブルなんて到底できっこない。
だから、濱ちゃんにその話を聞いた時、「え!? 大島さんが全部払ってくれるなら絶対にやって!!」って、一気にテンションが上がったのは今でも鮮明に覚えてる(笑)。
大槻 : でも、それまで大島さんが僕のところに持ってきたドキュメンタリーはあまり動員数が伸びなかったんですよ(笑)。だから「当たる!」って言われても、その過去も知ってるからね…。
― 大島さんご自身も、それまでの作品は自信があったけれど、興行的に厳しく、自身の会社の経理を担当する妻から「頼むからもう映画はやらないで」と泣き怒りされたとおっしゃっていますね。
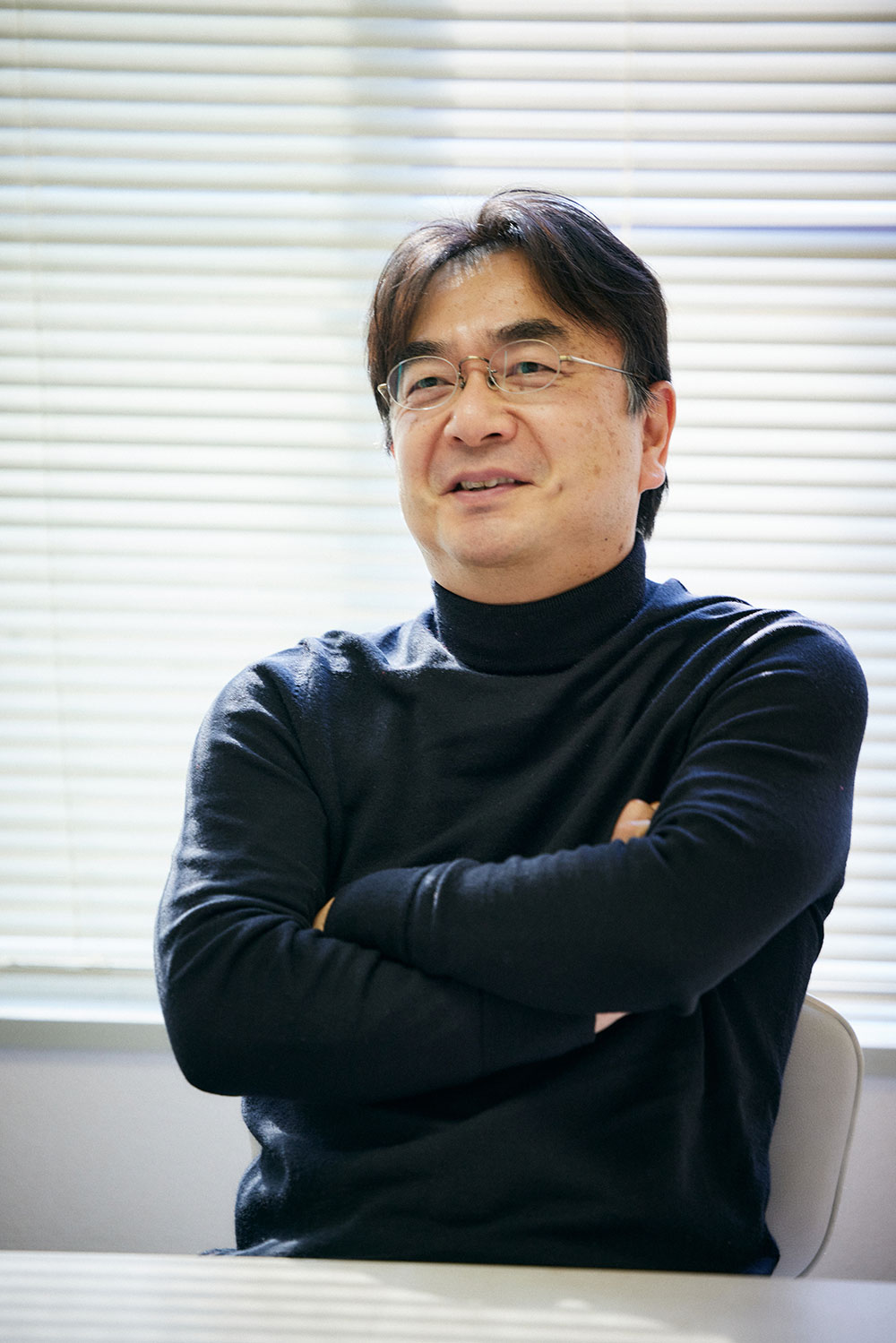
大槻 : …まあ思い出すと、それまでは「当たる」とは言ってなかったな、「上映お願いします」とかだった(笑)。
一同 : (笑)。
大槻 : でも、『ぼけますから、よろしくお願いします。』は「当たります!」って言ってきた。それが面白いと思って。その時、俺は「プロデューサーの役割は、監督とは違う。どこまで観てもらえるか、どこまで広げるかがプロデューサーの考えるところ」という話をして。
― プロデューサーとしての覚悟を問うたと。
大槻 : そんな偉そうに言ったわけじゃないけど。
信友 : いやいや、偉そうに言ったと思うなー(笑)。
大槻 : ……僕も偉そうにしたと思うわ(笑)。そういう話をしてもやると言ったので、こちらも具体的に動き出したんだと思う。
あと、「覚悟」というところで覚えているのは、当時はまだ『なぜ君は〜』がヒットする前だったので、「大島渚監督の息子としてではなく、大島新自身はいつブレイクするんだ?」と聞いたら、「まずはプロデューサーとして、この作品でブレイクしたい」と言ったこと。
― 大島新さんのご両親は、『愛のコリーダ』(1976)、『戦場のメリークリスマス』(1983)などを手がけた大島渚監督と俳優の小山明子さんですね。大島渚監督は『忘れられた皇軍』(1963)などを撮られたドキュメンタリストでもあります。
大槻 : それで「小山明子さんをトークショーのゲストに」という話が出たんだけれど、最初は「それは絶対に嫌だ」と言っていた。にもかかわらず、ある日「やっぱり呼ぶ」と言い出した。それを聞いて僕は「あ、彼もちゃんとプロデューサーとしてやる覚悟を決めたんだな」と感じたんです。
濱 : 確かにあれは、大島さんなりの覚悟だったと僕も思いました。
大槻 : だと思う。本当にそう思った。
信友 : そうね、普通は自分の親を舞台に上げたくないわよね。
濱 : 小山さんは長年にわたって自身の夫である大島監督を介護されていた経験もあるし、テーマ的にも極めて的確な人選であるとはいえ、親を引っ張りださなくてもいいわけです。でもたとえどんなに良い作品を作ったとしても、お客さんが入らなければ意味がない。
しかも普段ドキュメンタリー番組を手がけている僕らにとって「ポレポレ東中野」は聖地のような場所だから、一度テレビで放送したネタを映画館で上映してほしいと大槻さんに覚悟を迫るからには、プロデューサーとして大ヒットさせないわけにはいかないと、彼なりに腹を括ったんだと思います。それで、大槻さんが「やる!」と決めてくれた時には、皆で「ウォーッ」と盛り上がりました。
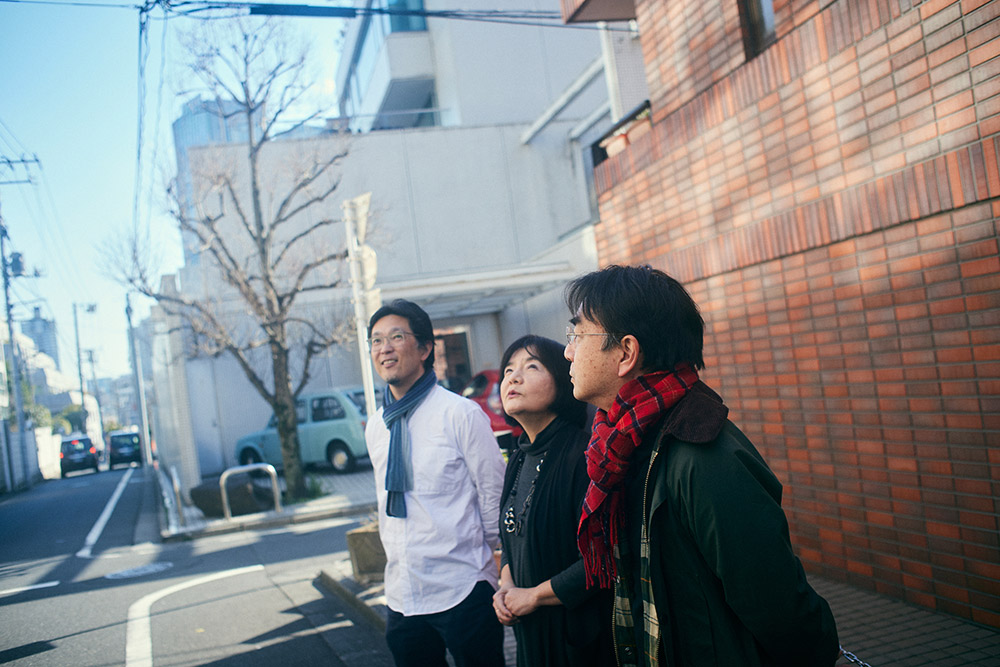
信友 : そう。本当に「ポレポレ東中野」にはずっと昔から憧れがあったから、今の我々を見ても信じてもらえないだろうけど、大槻さんと初めて会う日はすごく緊張してたんです。
大槻 : 今更何を言ってるの(笑)。それを言うならもちろん僕も信友さんと初めて会う日はすごく緊張してましたよ(笑)。
信友 : 嘘だー!!
一同 : (笑)。
信友 : でも、すごく相性がいいなと思って。こんなに仲良くなれることは、なかなかないから。何が違うんだろう?
大槻 : (笑)。僕の基本のスタンスとしては、相手が年下だろうが年上だろうが、面白いものは面白いし、面白くないものは面白くない、と正直に話す。でも、それを上映するかしないかはそれとはまた別の話で、もちろん商売のことも考える。そのあたりのバランス感覚が信友さんと似ているんだろうな。
そして、この作品の良い流れに関しては、大島さんが「絶対当たる!」と言いきったのが、僕の中ではやっぱり一番大きかった気がするな。
濱 : 大島さんは『ぼけますから〜』でプロデューサーに徹したから、『なぜ君は〜』では監督として自分の作品を世に出すモチベーションに繋がったのかもと、僕は勝手に想像しています。
巫女でもあり、観察者でもあり
― 「撮る側」「届ける側」がともに覚悟を持って携わった『ぼけますから〜』は、1館の公開から全国99館へ、上映会も合わせると20万人以上を動員というドキュメンタリー作品としては異例の大ヒットとなりました。
大槻 : 初日も2日目もほぼ満席で、上映後のサイン会が人生相談のようになったのには驚いた(笑)。
信友 : 「うちにも認知症の親がいるんですが、どうしたらいいでしょう?」と質問されて、「それはですね~」と、まるでカウンセラーみたいに返していたような感じでしたね(笑)。
大槻 : 正直期待はあったんですよ。誰が聞いても一発で覚えられるキャッチーなタイトルと、それに負けていない中身。あとは信友さんというキャラクター。巫女じゃないかと思うくらい何かが乗り移ったようにしゃべったり。
上映の後の挨拶で「今みんなの気持ちが入ってきた気がする…」と言ってて、何考えてるんだこの人は?と(笑)。

濱 : 今回は被写体がご両親だから、その類まれな能力を発揮する機会は少なかったかもしれないけど、信友さんの場合はいつでも目の前の取材対象者に憑依するというか、「みんな、なぜ信友さんの前だとこんなに無防備になれるの?」っていうくらい、相手の心を開かせることができるんです。
― 拉致被害者家族に寄り添って取材を続けた時は、信友監督だけが自宅取材を許されるなど、ドキュメンタリストとして才能を発揮したエピソードは数多くあるそうですね。
信友 : 相手の話を聞く時は、一対一で本人の中にダイブしていくような感覚があって、他のことが一切耳に入らなくなるんです。魔法にかけるようなイメージで、相手にすごく念を送ります(笑)。
― 念を送って、ダイブ…!
信友 : そういえば昔、ダイビングのライセンスを取るための講習を受けた時に、「あ、これはドキュメンタリーを撮っている時の感覚と似ている」と感じたことがありました。
― ドキュメンタリーを撮るのと、海へ潜るのが似ていると。
大槻 : なるほどねー。
信友 : 奥深く潜る。相手の口から食道を通って、体の中に入っていくような感覚と言ったらいいのかな。自分でも気づいていないような深層心理に一緒にたどり着けたら、お互い嬉しいじゃないですか。心理カウンセラーなら、知り得た事実は絶対秘密にする必要があるけど、ドキュメンタリーのディレクターなら、「こんな人がいるんですよ」って、広く伝えることができるんですよ。

濱 : そういう意味では、本当にこの仕事は信友さんにとって天職だと思いますね。相手にこれだけ深く感情移入することと、作品として「この画は必要ない」っていう判断をすることが、この人の中でどうやって両立してるんだろう?
― 「相手にダイブすること」と「客観的に取捨選択する視点」が信友監督の中で共存してるんですね。ご両親を「撮る覚悟」を決めてからは、撮り方に変化はあったのでしょうか。
信友 : テレビ番組にすることが決まった時点では、洗濯機の前で母が寝てしまう画や、スーパーに父が一人で買い物に出る画はまだなくて。
― どちらも娘という立場であれば撮ってはいられない、両親の「老いの現実」をうつした場面ですね。
信友 : ああいった画が撮れたのは、普段通りの、私がいない時の二人の姿を収めたいと思って、カメラを回すことに徹したからなんです。
濱 : 要は「観察者」になったということですよね。自分でカメラを回しているという点では同じセルフドキュメンタリーではあるけれど、企画が決まる前と後とでは、明らかに信友さんの視点が変わっている。娘としてではなく二人暮らしの老夫婦の日常を客観的に記録する作業をしているんです。

― 「娘」としてではなく、「観察者」として客観的に家族の日常を捉えたと。
濱 : でもテレビを映画にするにあたっては、大島が信友さんにお願いしたことが一つだけあって。「一人称で両親を撮影することに対しての自らのスタンスを、映画のどこかで必ず表明してほしい」と。テレビ番組の場合は常に情報としての客観性が担保される必要があるのですが、映画にするからには一貫して信友さんの主観だけで描いて欲しかったんです。
信友 : 実は、最初に『Mr.サンデー』で放送した際は、私は編集を担当していないんです。 この番組は男性の視聴者も多い時間帯の放送で、あくまでも情報番組として客観的な視点でつくってもらった方がいいと思ったから、素材だけお渡ししてお任せしたんです。2回放送してもらったんですが、映画版と比べてだいぶシリアスな仕上がりだったと思います。
映画はテレビと違って、暗闇の中で情報を全く遮断した状態で観るものだから、より感情移入しやすいじゃないですか。映画では、登場人物と一緒にたゆたえる体感ムービーのような感じにしたいなと思って、できるだけ余白を多めにゆったりつなぐようにしました。
― 確かに、「映画館で観る」のと「日常の中で観る」のでは、観る環境が大きく異なりますね。
信友 : たとえば、映画の中で買い物に行った父が一人でたくさんの荷物を運んでいる場面でも、「いやいや、普段は私が荷物を持ってるんですよ!」と言い訳の一つもしたくなったけど、そういうのはあえて入れないようにしたんです。その後、同名の本も出版したことで、撮影中に私が感じていたことも伝えられたし、メディアミックスとして完結できた部分もありますね。
ぼけますから、よろしくお願いします。 単行本(ソフトカバー)
濱 : 『Mr.サンデー』で流した3回分を、信友さん自身が2時間にまとめてBSフジで放送した際、視聴者から1000通以上のメッセージが番組宛に届いたんです。2時間枠のドキュメンタリーで当時一番反響が大きかったと聞きました。しかも単なる番組の感想ではなく、一つ一つがすごく気持ちのこもった内容だったことに驚いて。
― どんなメッセージだったんですか?
濱 : 「自分の親が〜」「自分の家族が〜」と、みんな自分自身のことに置き換えてましたね。
信友 : そうそう。うちもこうなんですって。
― テレビ版の時から、見たら自分のことを語りたくなる作品だったんですね。
濱 : 『ぼけますから~』には普遍性があるからこそ、僕もちゃんと記録に残したいと思ったんです。テレビってどうしても一過性なんですよね。今旬であることが必要ですし、視聴者に有用な情報も入れなければいけない。今はBSやCSもありますが、以前は再放送したとしても1回程度で、その後はテレビ局の倉庫にしまわれて誰にも見られることもない。でも映画にすれば数年後にリバイバル上映することもあるし、配信やDVDでも観てもらえる。

大槻 : 100席に満たない劇場で1日4回上映してもMAX400人のところ、テレビなら視聴率1%でも100万人以上に届くわけですよね。人数で考えると桁が違うけど、掛け算の熱量は一緒だったんじゃないかな。
濱 : テレビで観るのと映画館で観るのとでは、視聴体験も比較にならないくらい違うものなんだと、映画が公開されて改めて実感する出来事があったんです。うちの親父は80歳なんですが、テレビで放送された時からずっと観ていたはずなのに、映画館でこの作品を観てものすごく感激して、「信友さんのお父さんは、これから自分が余生を過ごすうえで手本となるような魅力的な人だから、感謝の気持ちを伝えたい」と、信友さんのお父さん宛てに手紙を書いた。普段は絶対にそんなことをする人じゃないんですけどね(笑)。
― 観客への刺さり方が、より一層深かったというわけですね。
信友 : 私が映画監督になって一番良かったなと感じたのは、観た人の反応がリアルに分かること。テレビのディレクターは、納品した時点で終わりなんですよ。どんな風に皆さんが観てくれて、どんな感想を抱くのか。
テレビの場合は局に届くメールや、身近な友だちから感想を聞くくらいしかできないけど、映画館に行けば、どこで泣いたり笑ったりするのか、観終わった後、どんな顔をして出てくるのか、観た人たち同士でどんな会話をしているのか、私を見つけたらどんなことを話しかけてくれるのか。そういったものを全て体感できるじゃないですか。それが味わえるのが、私が映画作りにハマった理由かもしれませんね。










