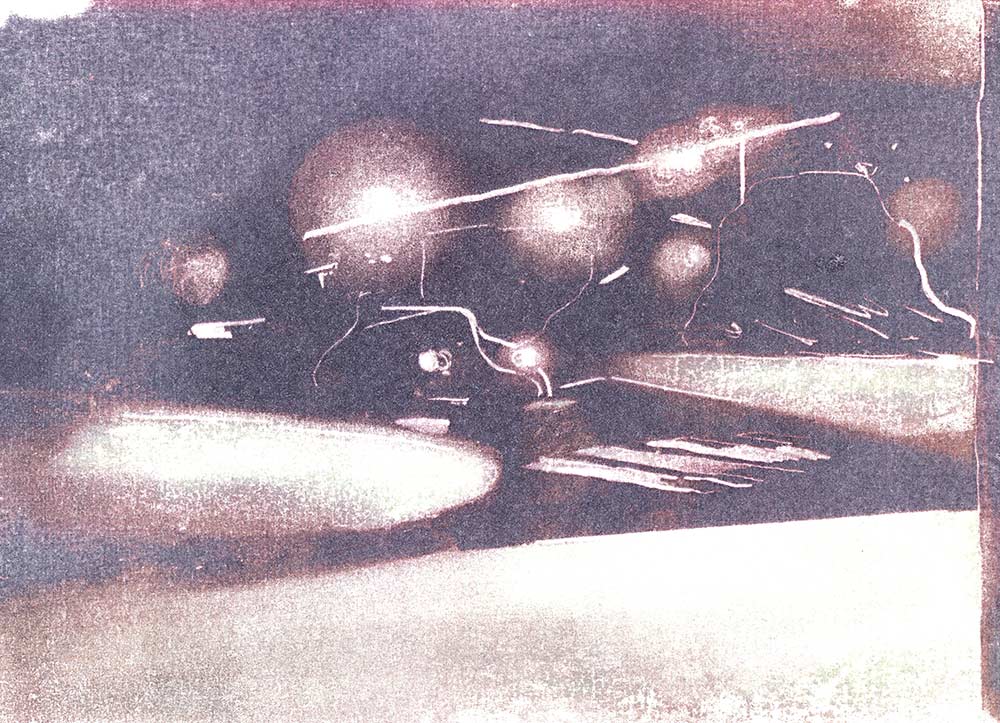目次

ユーモアは人生のスパイス。
悲しみも含めた、人生すべてがユーモアにつながっている
― シェルワン・ハジさんが主演を務める『希望のかなた』では、俳優オーディションが行われたそうですね。その応募条件の中に「ユーモアを理解できる人」とあったと伺いました。
ハジ : 実は、僕はカウリスマキ監督の映画だと知らずにオーディションを受けたんです。あるプロダクションから、“英語とアラビア語ができて、できればフィンランド語も喋れる中東出身の俳優”を探しているというメールをもらったのですが、その中に「ユーモアが理解できる人」とも書いてありました。僕は古いパスポートを確認して、鏡をのぞいて「オッケー。自分でもいける」と思いました。
― ユーモアについて自信があったんですね。
ハジ : ユーモアのセンスが自分にあるのかの確証はありませんでした。けれど、僕は生きるのが好きです。いかなる状況におかれても、僕は生きることへの愛を失くすつもりはないんです。そして、そのためによりよい場所を求めることも忘れていません。
― つまり…それは、どういうことでしょうか?
ハジ : 別の言い方をすれば…ユーモアは人生のスパイスだと思います。なくても生きていける。でも、味わいが変わります。ユーモアなしに生きるということは、刺身をわさびなしで食べるようなものです。わさびは絶対に必要なものでもないし、味覚を劇的によくしてくれる訳でもないけれど、より多くの味わいをもたらしてくれますよね。人生も同じだと思います。

― なるほど。ユーモアがあると人生をより味わうことができる。そして、それは「生きることへの愛」につながるということですね。
ハジ : ユーモアは、もともと皆が持っているものだと思うんです。ない人はいません。でもそれぞれが置かれた環境によって、維持するのが難しかったり、無理矢理ユーモアを表さないといけなかったり、実践する機会がなかったりすることもあるでしょう。僕はそうした状況も体験してきました。自分なりにですが、いろんな困難を経験してきたと思います。でも、一生懸命歯を食いしばってユーモアを残そうとしてきました。そうでないと、何か生きるための…種…のようなものを失ってしまう気がするんです。
― 生きるための種ですか…。悩んでしまうと、その悩みに集中してしまって、自分にユーモアが失くなってしまっていると感じるときがあります。
ハジ : そんなときがあるんですね! もし、ここにボールが3つあったら、ジャグリングしてあなたに見せてあげたいところです(笑)。人生にはいろいろなことがあります。残念ながら、悲しみも人生には多いです。でも、それはユーモアにつながることでもあると思うのです。悲しみを経験するということは、もちろん楽しいことではない。でも、それにどう対抗していくか、それをどう消化していくか、そのわたしたちがたどった道のりがユーモアにつながるのではないでしょうか。
― 悲しみも含めて、自分がたどってきた人生すべてがユーモアにつながっているということですね。
ハジ : 僕は悲しみも燃料にして人生を良くしていきたい。どの瞬間もできる限り楽しもうとしています。人生は矛盾に満ちている。白黒はっきりしている訳ではありません。だからこそ、人生は面白い場所になりえます。

“マスター・オブ・ユーモア”に教えられた、
「判断しすぎない」「ブロックしすぎない」ユーモアの源
― 『希望のかなた』の後半で、ハジさん演じる主人公を含めたレストランで働く5人が、だんだん親密になっていく時間はおかしみに溢れていました。店を繁盛させるために、寿司店を皆で準備して開業するところは特に。カウリスマキ監督は、主演俳優に「ユーモアの理解」を求めていましたが、撮影現場も映画同様ユーモアで溢れていたのでしょうか。
ハジ : この作品の主要出演者は僕以外、アキ(・カウリスマキ)と一緒に仕事をしたことがある人ばかりでした。だから、僕はこの現場に初めて入るときに緊張したけれど、アキは平等に接してくれたんです。一緒に座って、皆でシンプルな会話をしました。ただそこに自分らしくいて、そのまま話をすればいいんです。それが、とても美しいことに感じました。

― 撮影現場では、そのままのハジさんでいることができたんですね。
ハジ : そういう環境で一緒に時間を過ごすことで、安心感を共有することができました。そうすると、コミュニケーションを相手ととることができるようになるんです。そのことで、自分も自由になっていく。関係性ができれば、そこからジョークが生まれ始めます。そして、ユーモアという名の子どもを自由に解き放って、いろんなところを登らせることができるんです。
― 役者が自由に表現できる環境を、カウリスマキ監督が用意してくれたというわけですか。
ハジ : そういう意味で、アキは“マスター・オブ・ユーモア”です。この仕事をもらうまでは、ユーモアについて深く考えなかったのですが、この作品を通して理解できたことがあります。それは、“ユーモアとは、技術ではなく、能力なのではないか”ということです。つまり、相手をその人の人間性のままに受け入れられるかどうか、という「許容力」だと思うんです。

― ユーモアとは、技術ではなく「許容力」だと。
ハジ : 相手を受け入れるということは、クリエイティブな作業だと思います。それを自分にとって楽しいことに、変換できるかどうかではないでしょうか。しかし、自分の中に不安や恐怖があった状態で相手に接すると、クリエイティブの流れが止まってしまい、相手のあるがままを受け入れられません。例えば、あなたのことをそのまま受け入れられれば、会話はずっと続けられると思いませんか? でも、壁をつくってしまうと、達成できるものはあるかもしれませんが、特別なことが起きる期待はできません。“寛容さ”というのは、化学反応でもあると考えます。
― そう考えるようになったきっかけは、何かあったのでしょうか。
ハジ : アキは撮影の中盤まで、僕の演技に対してほとんど指示をしませんでした。自分ではそれがどうにも不安で、ある撮影日の休憩中、アキがお茶を入れてくれて飲んでいたときに、「どうして僕の演技に何も口出ししないのか」と聞いてみました。
彼は僕の目をじっと見て「マシンがちゃんと機能していると確認できたら、機能するがままに任せておけばいいんだよ」と答えました。つまり撮影がうまくいっているなら、無理に介入する必要はないわけです。でも、もしうまくいかなくなったら、何とかしなければならない。このように流れに身を任せ、どんな状況も受け入れようとする姿勢がクリエイティブな仕事につながっているんだと思ったんです。
― あまり計画を立てすぎず、現場での周りの状況に応じて創造を加える余白を残しているんですね。
ハジ : また別の日にランチを食べたあと、アキと音楽の話をしていたら、「何か楽器を弾けるか」と聞かれたんです。僕はシリア出身なのですが、サズというシリアの伝統楽器を子どもの頃から弾いていたと答えました。そこでアキはピンと閃いたようで、早速、僕がサズを演奏するシーンを脚本に書き加えていましたね。アキのように「判断しすぎない」「ブロックしすぎない」ということも、ユーモアの源だと思います。

シェルワン・ハジの「心の一本」の映画
― 今のハジさんのお話を伺って、「人が誰かを受け入れるとき、そこには希望が生まれる」という『希望のかなた』のキャッチフレーズに改めて感じ入りました。ハジさんの言うように、「ユーモアとは相手を受け入れる力」と考えると、カウリスマキ監督がこの映画の出演俳優に「ユーモア」を求めた理由がわかった気がします。
ハジ : 僕はこの映画の一番のメッセージは“人間性”だと思います。人間性を持ち続けることが大切なんです。
― ベルリン国際映画祭の記者会見でカウリスマキ監督は「友人に対する思いやりがなければ、誰も存在できない。人間性がなければ、一体、我々は何者なんだろう。」とおっしゃっていました。
ハジ : ひとつ心に残っているできごとがあります。僕は仕事でニューヨークに滞在していたあるとき、ホテルにいたら、70歳くらいのドアマンが仕事でくたびれた僕の顔を見てこう言いました。「君はなんでそんな顔をしているんだ。笑えよ」と。僕が「何で笑わなきゃいけないんだ。疲れているんだよ」と言い返したら、彼は「もう朝だよ。新しい1日がはじまっているんだ。楽しむべきだよ」と言ったんです。

― 映画のワンシーンのようです。
ハジ : デヴィッド・リンチ監督の映画みたいでしょう(笑)。ドアマンの彼の言葉はシンプルだけど、明瞭です。シンプルな状態が、ときに我々には必要なんです。
私たちが、住んでいる世界は天国であったことがありません。虹があって蝶々が飛んでいてユニコーンがいてという世界ではないんです。でも、そういう世界ではなかったとしても、そこから一歩先に進むために、自分に燃料をくべて人生に意味を与えようとしてきました。僕はシリアから来ました。僕の故郷があった街では、悪夢をさらに先にいったようなことが続いています。でも、僕には選択肢がある。そして、希望を持つことは大事だと考えます。僕にとって、その方法のひとつは、自分らしくあることです。そして、人をリスペクトすること。シンプルなことです。そうすれば、変化をもたらすことが可能であると思います。
― シンプルなことの積み上げが、希望につながっていくのですね。最後に、ハジさんがユーモアと聞いて、思い浮かぶ映画を教えてください。
ハジ : ちょっと考えさせてください…僕が観る映画は、観た後、落ち込むようなものが多いんです(笑)。そうですね、先ほど名前が出てきたデヴィッド・リンチ監督の作品も好きです。特に好きなのは『マルホランド・ドライブ』(2001)、『ロスト・ハイウェイ』(1997)、『イレイザーヘッド』(1976)です。彼の映画には、クレイジーで抽象的なタイプのユーモアを感じます。
― 以前リンチ監督が、カウリスマキ監督の『過去のない男』(2002)が好きだと言っていましたね。
ハジ : 『時計じかけのオレンジ』(1971)をはじめとするスタンリー・キューブリックの作品も、第六感的を働かせたような独自のユーモアがあるからお気に入りです。テリー・ギリアムの『未来世紀ブラジル』(1985)もおもしろい映画ですね。彼が元々いたコメディ集団「モンティ・パイソン」の作品もよく観ていました。
ハジ : たくさんありますよね…後から思い出して「あの映画のこと言わなかったなぁ」といやな気持ちになりそうだな…。今夜一晩、考えてみます……って、宿題を押し付けないでくださいよ(笑)。