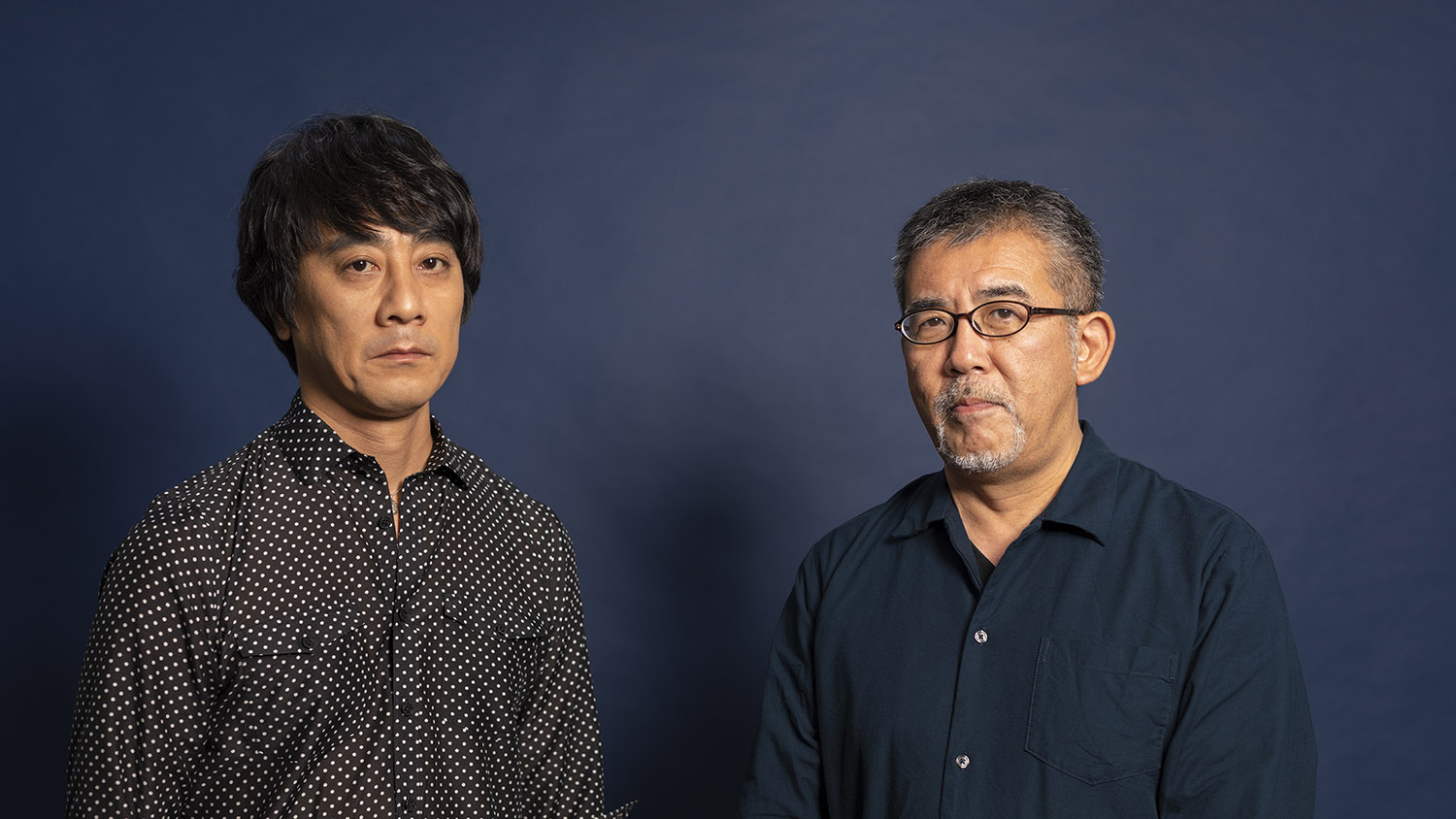目次

泥棒とミュージシャンは
通ずる生き方をしている
― 先ほどの写真撮影では、「見つめ合うのは初めてだ」とお互い照れくさそうにされていましたが、短い時間の中でも、おふたりの深い関係性がしっかり感じられました。
山崎 : 基本的にシノさん(篠原哲雄監督)は、『月とキャベツ』のときから変わってないですよね。白髪が増えたくらい(笑)。
篠原 : 山ちゃん(山崎まさよしさん)も少し太ったくらいで(笑)。あと、一重が二重になったよね。
山崎 : そうなんです。当時は一重でした(笑)。
― (笑)。23年の時が流れても、お互い変化したのはちょっとした外見ぐらいだと。
篠原 : あと、山ちゃんはどこか図太くなったんじゃないですかね。
山崎 : 確かにそうです。当時は演じること全てが初めてでしたから。

― 『月とキャベツ』で篠原監督は、俳優経験がないシンガーソングライターの山崎さんを主人公に抜擢されました。
篠原 : あの時はミュージシャンという役だったから、ありのままの自分を投影することが山ちゃんにとって役に近づく一番の近道だったと思う。でも、今作では泥棒を稼業にする「真壁修一」という、自分とは違う人間像をつくり上げなくてはいけない役柄だったんです。
山ちゃんがライブで観客に語りかける言葉って、ユーモアが含まれているんです。それに対して、観客から笑いという反応が起こる。僕はそういう姿を見てきたから。
― 写真撮影風景を拝見していただけでも、山崎さんのユーモア精神が存分に感じられました。
篠原 : でも、今回演じた真壁は、人に対して問いかけたり、さりげなく探っていたり、引き出したりする役でした。だから、山ちゃんは自分の中から、どちらかというと表には出していない「裏」の部分を引き出して、近づけていかなくてはいけなかったので大変だったと思います。
山崎 : やっとシノさんが俳優と認めてくれました……って、それは冗談ですが(笑)。
篠原 : でも、この役を演じきったという意味で、「俳優・山崎まさよし」が非常に大きく浮上した作品になったんじゃないかな。

― 山崎さんご自身は「真壁修一というこのキャラクターであれば自分にも合うんじゃないかなと。」とおっしゃっていますね。
山崎 : 刑事とか検察官の役を僕が演じるというのは、やっぱりリアリティがないと思うんです。でも、今作はシンプルに「官」ではなく「民」の主人公だから。そして、同じ「民」でも医者や弁護士の役は無理だけど、泥棒ならいけるんじゃないかと(笑)。
盗みのプロを生業にしている主人公の境遇を「自分の腕一本で生きてきた職人気質の男」と捉えるなら、僕もソロミュージシャンなので「個」の存在として通じ合う部分があるように感じられたんです、彼も「個」で活動しているわけだから。そういう想像ができたことが演じるうえで大きかったですね。
― 世間のルールから外れて「個」として生きる、アウトローの主人公・修一には、特有の生き辛さのようなものを感じました。
山崎 : それはあると思います。やっぱり一人で活動していると「これは正しいことなのか」「どこか道を踏み外していないか」「欲望のままにやっているだけじゃないか」と迷うことも多くて、なかなか決断ができなくなる。「個」として生きるというのは、そういう危うさをずっと持ちつつも、社会の流れを感じながら自分で決断を重ねて進んでいくことなんじゃないですかね。壁にぶち当たりながら、壁を掘り続けている感じと言えばいいのかな。
― 壁を掘り続けながら生きていると。
山崎 : よくわからないものに向かって、進んでいくことが「個」として生きていくことなんですかね…。

篠原 : 原作者の横山秀夫さんは「山崎さんを泥棒にしてしまってすみません」とおっしゃっていますが、僕は「山ちゃんは泥棒が似合っているかもしれない」とたまに言っていたんです(笑)。ミュージシャンの山ちゃんと泥棒の真壁は、どこか通底するものがあったと思います。
だから、真壁という役と山崎まさよしという自分を行ったり来たりする作業が、演じながらあったのではないでしょうか。
山崎 : 僕の少ない経験から考えるに、俳優は「主観と客観が入れ替わり続ける作業」をしているのだと思います。例えば、カメラが回ってないときは「この役だったら、こう動くんだろうな」と客観的視点から役について考え、カメラが回った瞬間から「それが自分だったら?」と主観的視点で役を演じる。
― 共演された尾野真千子さんや滝藤賢一さんが、スタートがかかった瞬間に大きく切り替わる姿を見て、俳優のすごさを実感されたそうですね。
山崎 : そうやって一瞬で、主観客観を切り替えられるのが、プロの俳優だと感じました…って、シノサンこれで合っていますかね?
篠原 : 正しいですよ。主観と客観を切り替えながら演じる態度は、俳優としてとても正しいと思います。まさか、ここまで山ちゃんが俳優を語れるようになるとは驚きです!
山崎 : …やっと俳優として認めてくれ……ウソです(笑)。

山崎まさよしと篠原哲雄の「心の一本」の映画
― 山崎さんが演じられた修一にとっての“盗み”は「心に内包する情念を吐き出すため」と感じたとおっしゃっています。山崎さんは「個」として生きるという意味で、自分と通じるところがあるということでしたが、そういった意味でも、音楽を奏で歌うご自身と共通するところがあったのでしょうか?
山崎 : 音楽という手段を使って心に内包するものをはき出すことは、ミュージシャンにとって普通のことですよね。修一は、自分のために盗みを働き、そうすることで自分が救われたかったのだと思います。弟の啓二(北村匠海)から修一に問いかけるセリフにも「(盗みを働くことが)気持ちいいんだろう?」とあります。
僕の場合は、もちろん情念を吐き出して「自分が救われる」という部分も少しはあるけれど、音楽それ自体がとても素晴らしいものだから、創作行為やそれを表現することで「達成感を得ている」という方が大きいかもしれない。

― 『月とキャベツ』で「One more time, One more chance」を山崎さんが創作し歌われたように、今回も主題歌「影踏み」を手がけられましたね。
山崎 : 役を演じることで得たアイデアも、音楽にいくつか入っているんです。ラッシュ映像を何度も観つつ音楽を付ける作業は、すごく楽しかったですね。
― 歌詞の中の「夢」や「影」という言葉がとても印象的でした。篠原監督は「この世から消えゆく存在を、映像的にどう伝えるか」が、前回同様今作も重要なテーマだとおっしゃっています。
篠原 : 僕にとって、「この世から消えゆく存在」を表現することは思い入れのあるテーマなのですが…それは、なぜなんでしょうね…。僕自身の人間関係で言えば、誰かが消えていくのではなく、維持していく関係性の方が多い。でも、なぜか僕はそういったファンタジー的な作品に携わることが多いんです。描くからには、そういう“間(あわい)の存在”にこだわりたい。そう思うと、実人生と映画って違うんだなと感じますね。
― では最後に、自分の人生に寄り添う存在のような映画を教えてください。
篠原 : 僕は『タクシードライバー』(1976)ですね。17歳の時に初めて観て衝撃を受けたことを覚えています。それからは数年に一度は観返すほど、大好きな作品なんです。

― ニューヨークを舞台にロバート・デ・ニーロ演じる元ベトナム帰還兵のタクシードライバーを軸に、社会に潜む激情を描き出したヒューマンドラマですね。現在、社会現象ともなっている『ジョーカー』を創作するにあたって影響を与えた作品としても話題です。
篠原 : ロバート・デ・ニーロの演技を観ると、その内包する狂気を自分でも実現しようと思ったり……というのは、ウソですけど(笑)。
山崎 : 限られた取材時間の中で、ウソ言ったらダメでしょ(笑)。
篠原 : でも、そういった狂気に感化されたものが、自分の表現に繋がっているところはあると思います。映画に興味を持った最初の作品でありますし、表現方法に困った時にも観返す大切な作品です。
山崎 : 僕は人生に寄り添うってわけはないけど、子どもの頃からブルース・リーが大好きなので、大人になった今でも彼の出演する作品を観ますね。特に『燃えよドラゴン』(1973)が好きで、僕の子どもにカンフー着を着させるくらい(笑)。
ブルース・リーは、悲しい顔がすごく似合うんです。それでいて、どこかチャーミングでもありますし。
篠原 : それなら山ちゃんもアクション映画に挑戦してみたら?
山崎 : いやいや(笑)。僕は、ブルース・リーがアクションするのを観るのが好きなだけで、自分がアクションシーンを演じるのは話が別です(笑)。
篠原 : でも、『影踏み』でも住居に侵入するシーンや、取っ組み合うシーンがいくつかあって、機敏に動けるように体づくりしてたじゃない? アクションに目覚める部分もあったとか!?
山崎 : じゃあ、次作は1カ月くらいアクションの訓練をしてから挑む映画にしましょう(笑)。
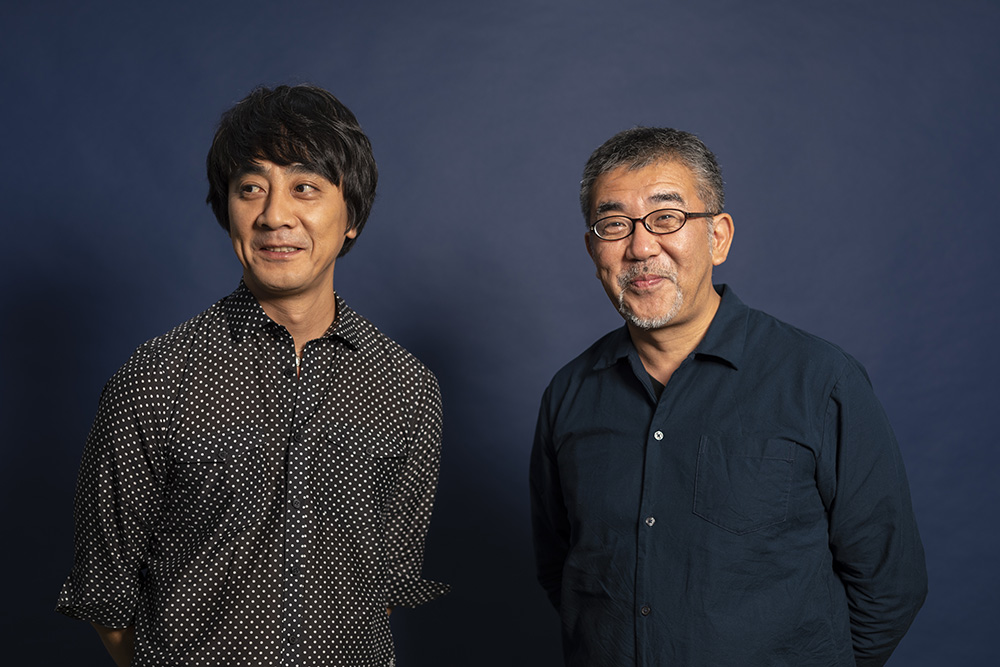
◎『影踏み』原案