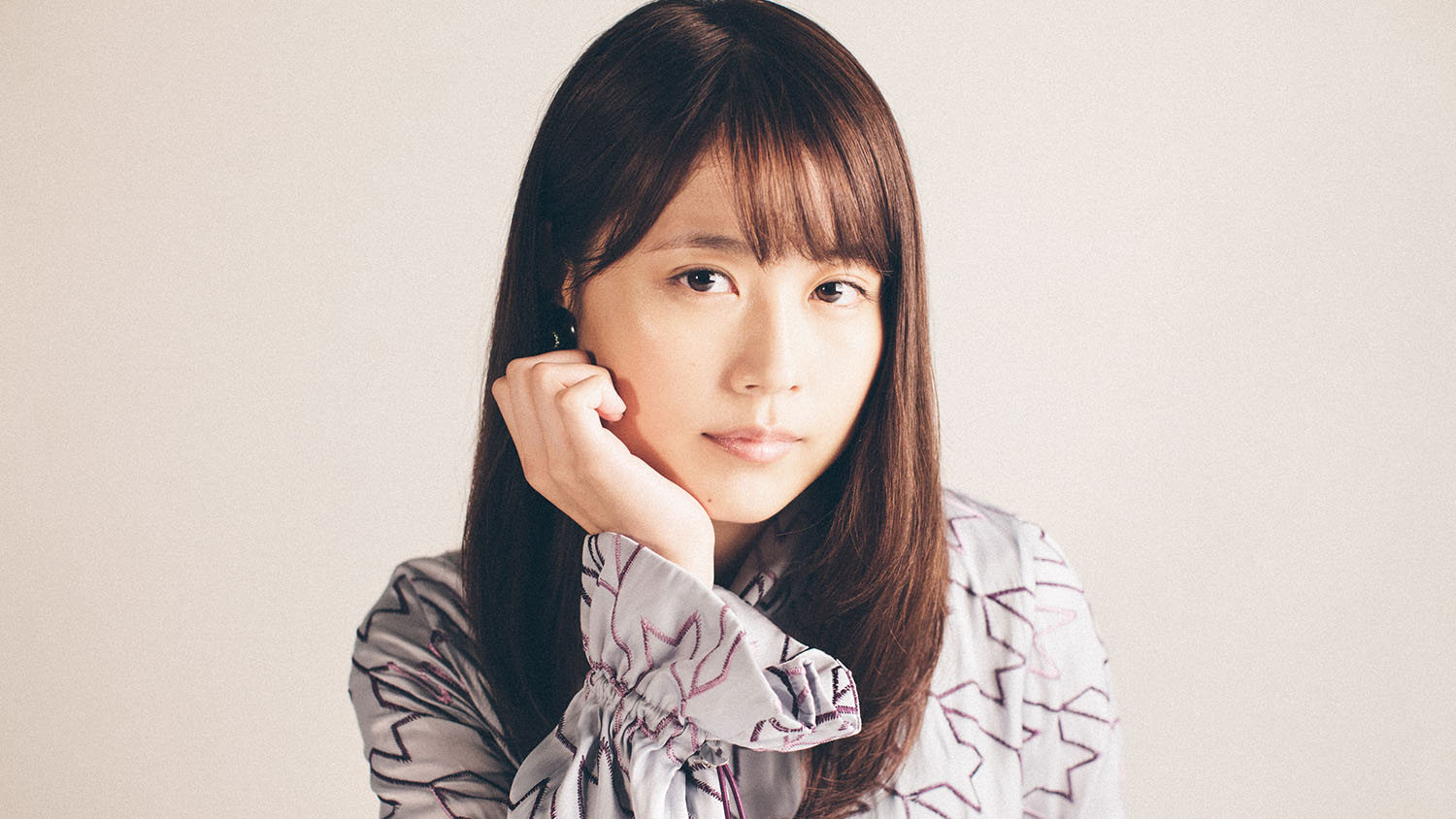目次

「やるなら今しかない。いつだって、今しかないんだよ。」
その言葉に動かされ、瀬々監督に猛アタック
― 山田さんと韓さんは、『菊とギロチン』に出演したいと直接、監督に直訴したとお伺いしました。
韓 : ある忘年会で瀬々監督とご一緒した時に、瀬々監督が『菊とギロチン』という作品の台本がある、とおっしゃっていて「ぜひ読ませてください」とお願いしたんです。後日台本をいただいて読んでいる最中、思わず泣いてしまって。読み終わった直後、いても立ってもいられなくなり、監督へ感想を送りました。瀬々監督の連絡先がわからなかったんですが、思い切ってTwitterのDM(ダイレクトメッセージ)経由で連絡しました(笑)。
山田 : 私は、マネージャーさんが“菊とギロチン出演者募集!!”と書かれたチラシを持ってきてくれて、「真歩ちゃん、こういうの好きでしょ」と勧めてくれたことがきっかけで、この映画のことを知りました。
韓 : 当時、Twitterなどでも大々的に募集していましたよね、私もよく覚えている。
山田 : そう、だから役者はみんな知っていたよね。その出演者募集のチラシも映画館だけじゃなくて料理屋さんとか「なんでこんなところに!?」というような場所にも置いてあって。しかもそこには“やるなら今しかない!”と綴られていて、そう言われると「そうか……今か!!」と、こちらも気持ちが高まってしまいました。「これは本当に、どんな役でもいいから出たい!」と、瀬々監督宛てに手紙を書いて渡してもらったんです。それまで私は、そんな風に監督宛てに直接何か書いて伝えたこととかなかったし、本当に初めてだったんだけど。
韓 : 私も普段、台本って「これはどういう風に撮るんだろうな」とか考えながら読みがちなんですけど、これはもう本を読むような感じで読めてしまったんです。
山田 : 誰もがこの大正時代の女相撲やアナキストのことを詳しく知っているわけではないだろうけれど、オーディションも700人くらいが受けたらしいですから、この映画のパワーを感じた人が多かったんでしょうね。役者の友達にはみんな「あれは出たかったんだ」と羨ましがられます。私も女力士のことはよくわかっていなかったけど、この作品には、とにかく関わりたいと思いました。

本気で笑って本気で喧嘩した、
サーカス小屋みたいな撮影現場
― お二人が演じた女相撲の一団は、撮影期間中、大部屋で雑魚寝の合宿状態だったそうですね。
山田 : 撮影に入る1〜2か月前から、日大の相撲部に通って稽古をさせてもらったんだよね?
韓 : そう。一番初めに、7月に会ったメンバーがいて、そこからも続々と出演者が決まっていきました。本当に相撲部屋というか、部活が始まる時のようだったのが印象的で。
山田 : 12人くらいで女相撲部屋を結成したような状態でしたから。みんな、髪に鬢(びん)付け油をベタベタに塗った状態でターバンみたいなのを巻いて、ファミレスにごはん食べに行ったこともあったね(笑)。

― 韓さんが今作の公式サイトに寄せたコメントでは「腹がよじれる程本気で笑って、本気で喧嘩した日もあった。」とありましたね。
韓 : 喧嘩もしましたね…。まああれだけ女子が集まると、みんな獣みたいな感じなんで…珍獣かな?(笑)。
山田 : というか、サーカス小屋みたいな(笑)? 合宿所の隣の空き地で朝練をしたり、街の公園で四股踏んだり。そういう意味では、本当にみんなでともに生活しながらつくっていった感じがありました。一度、盛大に喧嘩して、韓ちゃんの部屋に集まって話して全員で泣く、みたいなことがあったよね。

韓 : そう、それを今話していて思い出しちゃって、「ああ、ほんとにみんなでつくったんだなあ」って改めて思った。その相撲部屋全員で泣いて語り合った時の真歩さんの名言が……
山田 : 「ねえ…芝居好き?」…でしょ。言ったよねえ(笑)。だってみんな、ちゃんとオーディションで受かってきているのに「私は必要じゃないかもしれない」とかって泣き出したりして! 映画が初めての人もいたから、自分じゃないほうをカメラが向いてしまったって落ち込んじゃっている子とかもいて。そうやって、あの現場にはたくさんの「いろんな人」がいたんです。だからこそみんなで集まって話そうってよくなったね。
韓 : 「ここはもう部屋に集まって飲もう!」ってね。「いい組だねえ。こんなこと今までなかったわあ」とか言いながら勝虎役の大西礼芳ちゃんが泣き始めたりしてね(笑)。みんな疲れていることもあって、いい感じに酔っ払ってきて、誰かが泣いている一方で誰かが歌いだす、みたいな夜もありました。
山田 : なかなか、そんなことないもんねえ。
韓 : そういえば、撮影のロケ地までのバスの中で、真歩さんと私でコアな政治とか文化の話とかもしましたよね。今の日本のこととか、世界のこととか。みんないびきかいて寝ている中だったけど。あんな地球の片隅のバスの中で、そういう話を二人だけで話した時間もいい思い出です。

デコボコだっていい、堂々と自分らしく生きよう
― 「いろんな人」が集まった女相撲一座は、映画の中でも様々な過去を背負ってその場所に辿りついた女性たちでした。その中でも、お二人が演じた役は、同性愛者だと噂される“小桜”と、朝鮮半島から渡ってきた元遊女の“十勝川”という、「女」というだけでも困難な人生を生きざるを得なかった時代に、さらに生きづらさを負った人物でした。
韓 : 私は自分の役を考えるときに、ルーツとか国籍は関係なく、十勝川は人として東出昌大さん演じる中濱鐡が好きなんだろうなと思ったんです。私の母と父も韓国と日本で、生まれ育った場所は離れていたけれど、そういうのは関係なく愛していたから結婚したと思うので。十勝川も鐡さんの情熱や人間愛が滲み出ているところを愛したいと思ったんだろうな、と。あとは、この時代のことを知るために、浅草凌雲閣(明治時代に浅草に建てられた眺望用の建築物で、地下に私娼街があった。関東大震災により上部が崩壊し、そのまま解体)のことや関東大震災の本や資料を読みましたね。
山田 : 私はこの映画の現場に入るために、『菊とギロチン』にも登場する“大杉栄”というアナキストの内縁の妻だった婦人解放運動家・伊藤野枝という人の伝記を読みました。彼女は、結婚制度に反対した論文などを書いていた人だったのですが、彼女の言葉が今作の台本にいっぱい引用されていることがわかって。やっぱり、瀬々さんはあの時代に体当たりで生きた女の人たちのことを、この物語に込めたんだなあと思います。それは、「堂々と自分らしく生きろ」ということだと思うんですけどね。
韓 : この役を演じることで、自身としても “もっと力強く、自分らしく”生きたくなりました。この映画が、「強くなりたい」という願いを相撲で叶えようとした女力士たちのような生き方も「それでいいんだ」と肯定してくれているからかもしれないです。

山田 : 瀬々さんの作品って、いろんな人の視線に立ってくれるじゃないですか。例えば、今作でもあれだけいろんな人が登場しますが、主役にみんなが迎合することなく、それぞれがそれぞれの人生を生きながら交差している、ということを描いている。いろんな人の価値観に寄り添ってくれるから、観客としても演者としてもすごく居心地のよさを感じられるんです。
私ね“生物多様性”という言葉が好きで。いろいろな人が勝手に生きていて、どれかの価値観に刈られないことが大事というか……いつでも「その人の目線から見たらそう見えるかもしれない」ということが、ちょっとでもそこにあると嬉しいんです。社会の流れも映画も、一方向の見方だけを強要するのではない、窮屈な感じになりすぎないことが重要だと思います。「もっといろんな見方があっていいんじゃないか」って、いつも思っているかな。
― 山田さんがそういう考えを持つようになったきっかけって、何かあったのでしょうか?
山田 : たぶん…私の場合は、テレビをほとんど観ることができない家だったことが大きく影響しているかな。当時、観てもいいテレビ番組は『クイズダービー』(1976年〜1992年まで続いたTBSチャンネルの人気クイズ番組)とアニメの『世界名作劇場』(『アルプスの少女ハイジ』や『フランダースの犬』などの名作アニメを多数輩出したフジテレビのアニメ放送枠)だけだったので。『北の国から』ですら観たことがなかったから、学校で誰かが田中邦衛さんのモノマネをしていてもわからなくて。今になって「ドリフ、おもしろいじゃん」とかってものすごい後追いで観ているんですけど(笑)。でも、それで友達がいなかったわけでもなかったから。他のことで話していたし。それが大きいかもしれないですね。だからみんなと違う部分があることを、別に悪いことだとは思っていなかったのかな。
― 周りと自分を比べていなかったんですね。
山田 : 20代後半で芸能界に入るまでは、全く比較しなかったんです。この仕事を始めてオーディションなどで「落ちる」という経験をして、初めて周りと自分を比較する視点ができたかな。それまでは、小学校からずっとみんな違うって思って生きてきたから、この『菊とギロチン』で一緒に過ごしたみんなの、デコボコした人たちがたくさんいる状況というのはすごく自然だし、いいなって思います。
韓 : 現場でも、真歩さんはみんなの輪の真ん中に自然にいてくれるっていうか……さっき話に出た喧嘩みたいなときも、輪を壊さないようにしてくれていましたから。
山田 : 小桜がそういう役だったから自然とそういう立ち位置になったっていうのもあるけどね。
韓 : うん。だから本当にもうあの役は、瀬々監督のあてがきだったはず。たとえば現場で演者同士の喧嘩があっても、「もうそんなの気にしなくていいじゃん」て真歩さんが言ってくれると整う、みたいな。だから本当に、小桜がいてくれてよかったなあ、って。あの現場にいたみんなが、そこに空気みたいに存在していて、一人でも欠けたら成立していなかったと思います。
山田 : 仕方なくやっている人が一人もいなかったよね。スタッフも演者も映画に関わる人全員が燃えていた。そういう現場って、なかなか巡り会えないよね。

「明日もう一日、生きてみよう」
そう思ってもらえるような映画を届けたい
― 韓さんは4月にご自身のTwitterで「わたしはただ、日々に疲れてもう死にたいと思ってしまった人に、明日もう一日、生きてみよう。と思ってもらえるような映画に一本でも多く携わりたい。」と発信していましたね。
韓 : 社会のしがらみや人間関係、セクハラとかいろいろな問題がありますが……、そんなことに日々悩んでしまって、命を絶とうかと思い詰めている人がいたとして、私が女優としてできることがあるとすれば、そういう人たちがなにかその映画から感じて救われていく作品に携わっていくことだと思ったので。私自身にも自分のアイデンティティーについて悩んでいた時期はあるから、決して他人事だとは思えないんですよね。
山田 : 私も仕事をする上で、誰かの役に立たなければ自分の存在意義はないと思います。作品を観る人を「笑わせる」とか何でもいいんですけどね。観る人の励みになる作品に一本でも多く関われたらいいなと思います。
― お二人が役者として関わることで「力強く、自分らしく生きよう」と思った今作のように、観た後、励みになったり救われたりした映画があれば教えてください。
山田 : 私はなんといってもフェデリコ・フェリーニ監督の『カビリアの夜』(1957年)です。大学生の頃に本当に何度も繰り返して観ていた作品で。貧しくも明るい娼婦のカビリアは、男性に何度突き放されて傷つこうと疑わず、相手を信じようとし続けます。特にラスト、男性にひどく騙された衝撃の後で、林の中の道を歩いていくカビリアの、それでも生きる希望に満ちた表情は忘れられません。私にとって、人生で大事なテーマが詰まった作品です。
韓 : 私は『グレイテスト・ショーマン』(2017年)です。最近公開されて日本でも大ヒットした映画なので、私が勧めるまでもないかもしれないですが……、作品を観るまでは「ハリウッドの新作ミュージカル映画だから見よーっと」くらいに思っていたんですよ。でも実際に観たらすごくグッと心打たれてしまって。
社会に居場所がないアウトサイダーな人々がサーカスの一座に加わり、居場所を見つけていくという話なんですけど、「私は、私。誰に何を言われようとも自分がいいと思うように生きる」というメッセージが込められた“This Is Me”という歌が素晴らしいんです。真歩さんにもぜひ観てほしい!
山田 : うん、観てみる。