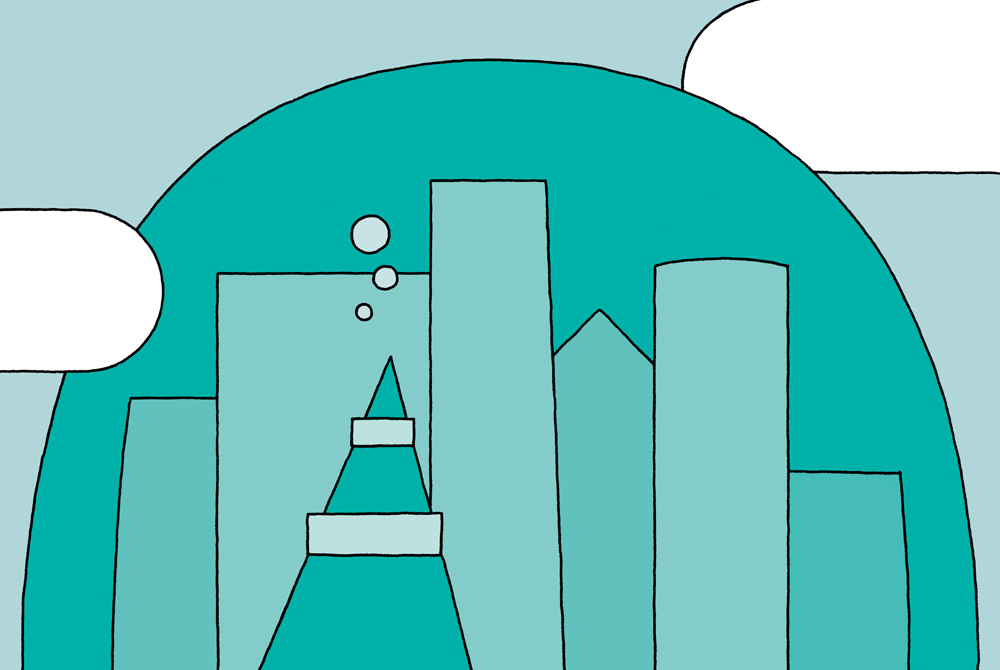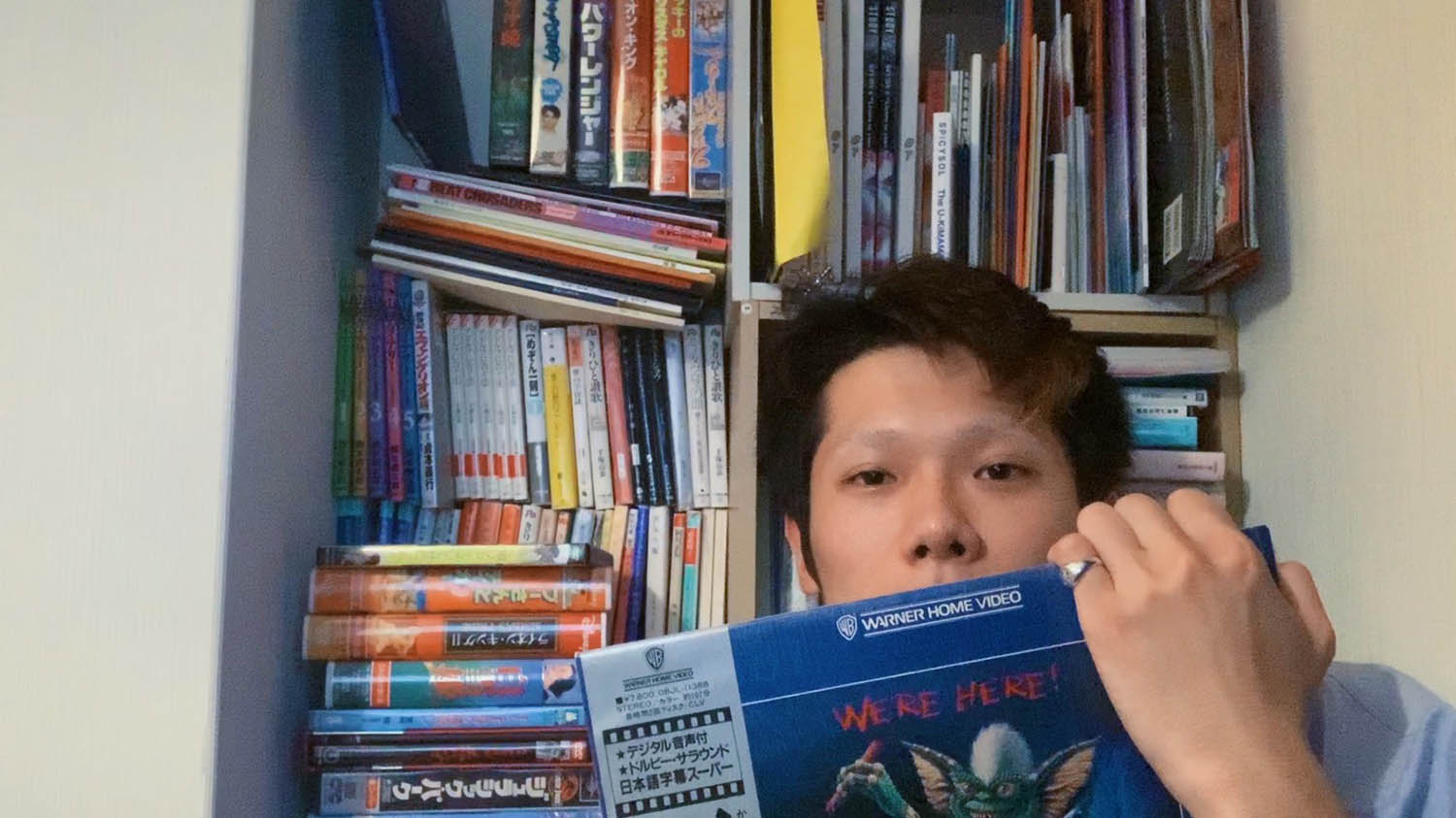目次

車の中から見える風景
前作の『ドライブ・マイ・カー』が記憶に新しい濱口竜介監督の最新作『悪は存在しない』。 自然が豊かで水の美味しい長野県、水挽町に暮らす父娘の生活とその周辺の人々の暮らしを美しい映像と巧みな言葉で綴ります。しかしある日、東京にある芸能事務所が、彼らの住む場所のすぐ近くにグランピング場をつくる計画を打ち出したことによって、それまであった穏やかな暮らしは大きく揺さぶられていくのです。

ところで、「車のある生活」が劇中に描かれると、そこが地方都市だと読み取る人は多いでしょう。本作でも車での時間が多々描かれます。つまり、車なしでは生活できない“不便な”場所であると「車」が語るのですが、それは、自然とともに生きているように見える人も、便利さをすべて手放して自然と共存することはできないという矛盾を伝えるようにも感じます。
本作での車は多くを語ります。『ドライブ・マイ・カー』のように、車の外観が入る少し離れた視点でのシーンはほとんど描かれませんが、車の中から見える風景がゆったりと映されます。それは、車に後ろ向きに座ったときに見える風景、横にある窓に顔を近づけると見える風景、天を仰ぐように頭を後ろに倒すと見える風景といった、車中からの人の目を通したような風景ばかり。あらゆる視点で映される風景は、少し不安定に、車や人の頭が小さくゆらゆらと動いているように切り取られているものだから、「誰かが見ている」ことを感じて不気味さを醸し出します。木の葉を透かす朝の光、木々の間から覗く雪原や、遠く山の端に薄づく太陽に美しさを感じながらも、あきらかな人の気配から、あとに何か事件が起きることを予見させるのが本作の妙でしょう。

風景を切りとりゆく車がこの映画の中で答えを語ることはありません。ただただ問いかけ続ける役目を車が担います。答えの用意された映画は多いですが、『悪は存在しない』は、車という新しい視点を持って、観る者に「問い」を与えます。
映画において、車という道具はよく使われます。それはおおむね、「悪」や「恐怖」の代弁者としてですが、本作での車はそのどちらにも寄らず、人と自然の仲介者として存在する。その曖昧な存在こそが、この映画における「答え」なのかもしれません。
映画の始まりとともに一台の車に乗車する。どこで降りたらいいかはずっと分からないまま、心地よさにもつながる揺れを片手に、少しずつ問いを集めていく感覚。気がついたら車から放り出されているのだけれども、またあの車に乗りたい、問いかけを浴びたい。そう願いながら映画を観終えるでしょう。
それを知らないということは恐ろしいこと、でも答えはここにはない。本作でも濱口監督がそう語るように感じたのは私だけではないはずです。