目次

「ここまでこだわりを貫いていいんだ!」
いまの創作につながる2つの運命の映画
リビングの床に座ると目線が合うほどの高さに置かれた、2段ほどの棚。その上の段には、隅から隅までぎっしりとDVDが並んでいます。タイトルを眺めてみると、『ビートたけしのつくり方』や『ピタゴラ装置DVDブック』などのテレビ番組、そしていくつかの日本映画のタイトルが目に入ってきます。その間に、同じ雰囲気の佇まいでずらりと揃っているのは、劇団・ヨーロッパ企画の公演のDVDです。
今回ご紹介するDVD棚の持ち主は、毎年の本公演で1万5千人を動員する、人気劇団ヨーロッパ企画の代表・上田誠さんです。大学在学中に旗揚げ後、全本公演の脚本と演出を担当している上田さんは、ヨーロッパ企画の人気作で映画化もされた『サマータイムマシン・ブルース』(2005)をはじめ、『夜は短し歩けよ乙女』(2017)『ペンギン・ハイウェイ』(2018)『前田建設ファンタジー営業部』(2020)など数多くの映画の脚本や、テレビアニメーションのシリーズ構成などを手掛けています。

代表の上田さんだけではなく、劇団員それぞれが、ドラマや映画、ラジオやバラエティ番組など、多方面にわたって映像作品の制作に関わっているヨーロッパ企画。今年の6月には、劇団初のヨーロッパ企画によるオリジナル長編映画『ドロステのはてで僕ら』が公開。ここでも上田さんは原案と脚本を担当しました。
時間やSFをテーマに、前例のない仕掛けやトリックを盛り込んだ作品を次々と制作してきた上田さん。“まだ誰も観たことのないもの”を常に目指し、『ドロステのはてで僕ら』でも、パズルのような物語の構造、長回しの群像劇など、予想を超えた新たな映画の可能性に挑戦しています。そんな上田さんのDVD棚には、どんな映画が並んでいるのでしょうか? オンラインで伺いました。

「映画に詳しそうとか、SF映画ばかり観ていそうとか、よく言われるんですけど、僕はそんなに映画に詳しい方ではなくて…普段はコメディが好きで、お笑い番組ばっかり見てるんです(笑)。だから持っている映画のDVDも少ないんですけど、でもそのかわり、好きになった映画は何十回も繰り返し観ます」
映画でも音楽でも、予算を多くかけたスケールの大きな作品より、創作の手触りが見えるような作品に惹かれると、上田さんは言います。

「僕は、映画監督やミュージシャン、お笑いとか、分野は関係なく、ものづくりに関わる人が好きなんです。その人が、どういう手つきや心持ちで制作をしているのかというところに興味があるので、映画も“何か身になる、創作のヒントがあるんじゃないか”という、作り手の視点で観ることが多いですね。小規模でも、作り手のアイデアや工夫、こだわりが滲み出ているような映画に出会うと嬉しくなるし、それだけでなく、自分でその作品を引き寄せた必然性みたいなものも感じます」
家族や友人と、映画の話題を日常的にすることはあまりなかったという高校時代。その中でも、必然のように出会えた映画が2本ありました。テレビの深夜放送で偶然見かけた三谷幸喜さん脚本の『12人の優しい日本人』(1991)と、“めずらしく友人が映画を勧めてくれた”という記憶とともに思い出す、SABU監督の『ポストマン・ブルース』(1997)です。
『12人の優しい日本人』は、陪審員たちが密室で白熱の議論を交わす名作『十二人の怒れる男』(1957)をパロディ化した“密室劇”のコメディ映画、一方、『ポストマン・ブルース』は、運び屋と勘違いされ、警察から追われることになってしまう郵便局員の、友情や恋愛を描いた映画です。当時、衝撃を受け、そして今でも一番観返しているというこの2作品には、上田さんの創作につながる、ある共通点がありました。
「『12人の優しい日本人』は、密室というシチュエーションが物語にうまく活かされているし、『ポストマン・ブルース』には“自転車で疾走する人間を撮る”というこだわりが軸にあって、2つとも作品全体をコンセプトがしっかり貫いているんです。確固たるコンセプトがあって、そこから物語が派生していく。僕も作品をつくる際、ひとつの視点に執拗にこだわる、という作り方をいつもするんですけど、この2つの映画を観ると、“ここまでこだわりを貫いていいんだ”と勇気をもらいます」

他にも、監督の視点や斬新なコンセプトに惹き込まれた映画として、刑務所内の生活を食事という視点から描いた『刑務所の中』(2002)や、地球上のシーンを挟まないことにより、宇宙空間の美しさと恐怖を徹底して見せた『ゼロ・グラビティ』(2013)が好きだと上田さんは語ります。
自らも“企画性コメディ”と名付けている上田さんの創り出す演劇たち。その、ルールや舞台設定などの“企画性=コンセプト”を軸に、ストーリーを創作していくという方法は、前例のない新しい表現を生み続けています。
「コンセプトを先に決めることによる“不自由さ”も確かにあります。でも、その縛りを突き抜けることによって、半端な覚悟では到達できなかった場所にたどり着けるんです。コンセプトをはっきりしておかないと、漠然と過去の作品をなぞってしまいそうだし、“何か物足りないから、この要素を足しておこう”という応急処置が重なって、ふわっとした曖昧な作品になるんじゃないかな、と。作品全体を一本の軸が貫いていれば、自然と物語もブレなくなるので、実は遊びの要素も入れやすいんです」

上田さんの作品は、斬新なコンセプトや演出でも、見ている人を突き放したり、置き去りにしたりすることなく、現代的なポップさと、どこかカラッとした明るさで最後まで引き込んでいきます。テンポの良い会話や群像劇の中で描かれる、決して器用ではない人たちのどこか可笑しみのある人間模様も、魅力のひとつです。
「例えば、立方体の部屋に閉じ込められる『キューブ』(1997)という映画が僕は好きで。あれは、密室サスペンスですけど、見知らぬ人間同士が脱出を試みる群像的として観るのも、すごく面白いんです。恐ろしい出来事も、感情に寄り添えば“悲劇”に見えるけど、俯瞰して状況を捉えると“コメディ”に見えてくる。僕は大学で理系を専攻していたのですが、そのこともあって、物事をわりと観察するように引いて観ていることが多いんです。だから、どんなことも、あまりネガティブな感情にならずに、ちょっとコミカルに捉える習性があるので、今作のようにルールやシステムの中で右往左往する人間模様を、水槽の外から観察するように描く群像劇が好きなのかもしれません」

前例のない表現に挑戦したい!
「未知」と「既知」の絶妙なバランスとは?
上田さんが原案・脚本を手掛け、ヨーロッパ企画初の長編映画作品となった『ドロステのはてで僕ら』は、部屋で無くしものを探していた主人公が、2分後の自分からモニター越しに話しかけられる…という奇妙な場面から幕を開けます。絵の中の人物が自分を描いた絵を持ち、その絵の中の自分も自分の描かれた絵を持ち…という、入れ子のような構造が無限に続く“ドロステ効果”をコンセプトにしたこの映画。上田さんの真骨頂“時間”をテーマにしたパズル的な構造と、群像による長回し映像という挑戦的な撮影を、劇団ならではのチームワークで実現させています。

「映画の方法論を知らない、演劇のチームがつくった初めての映画なので、映画の作法として至らないところはあるのかもしれません。でも、今回は“知らない”ということを逆に強みと捉えて、ヨーロッパ企画だからこそつくれる映画に挑戦しようと思いました。観てくれた人から“こんなに脳内がクラクラするような映画、よく撮ったね”とよく言われますが、本当に劇団のチーム力がないと撮れなかったと思います(笑)。でも、せっかくつくるなら、世の中にまだないやり方をしたいし、それが業界全体の多様性になるんじゃないかなと思っているんです」
演劇でのキャリアは20年以上、さらに映画やアニメーションの脚本も多く手掛けてきた上田さんが目指しているものは、昔も今も変わりません。それは、“誰も観たことのないものを作る”ということ。その想いが、上田さんのものづくりの初期衝動を支えています。
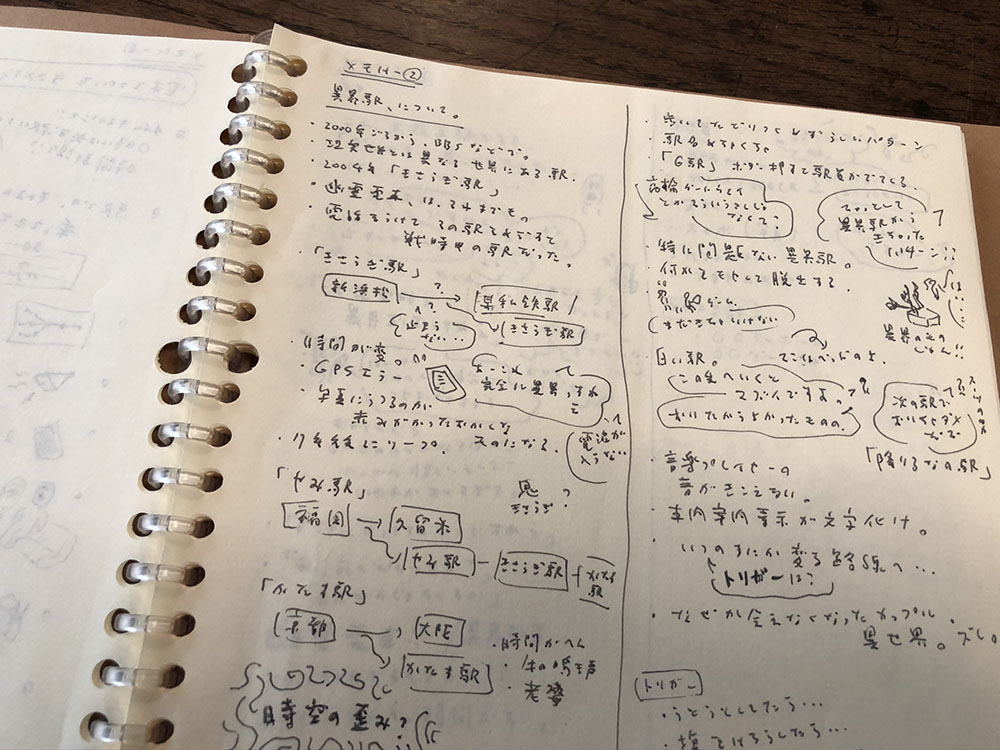
前例のないコンセプトの企画を通すためには、プロトタイプを一度制作して説明するなど、困難も多いため、「同じ方向に走っている人が他に誰もいない」という感覚になってしまうこともあるそうです。
そんな時に上田さんが思い出す、ひとりの映画監督がいました。『インセプション』(2010)『インターステラー』(2014)など、“時間”をモチーフにした映画を多く制作しているクリストファー・ノーラン監督です。本物のビルを実際に崩す、ミニチュアを使うなど、極力CGでの撮影を避けることでも知られ、アナログな手触りを残しながらも、革新的なアイデアと物語の構造で作品を撮り続けています。
「僕は、“時間”をテーマにした作品を書くことが多いのですが、そうすると、“SF”というジャンルにおさめられることが多いんです。でも、クリストファー・ノーラン監督の『メメント』(2000)は、時系列が逆向きに進行するという構造を使うことで、“時間”をテーマにしながらもSFではなく、それでいて既視感のない映画を生み出しましたよね。あの作品はすごく好きで、僕も、タイムマシンなどのモチーフを使わずに、時間の構造を使って面白いことができないかなというのは、いつも考えていることです」
ヨーロッパ企画 第36回公演の『出てこようとしてるトロンプルイユ』では、「騙し絵」を使い、額縁の中の絵と、それを観ている側の関係性や時間軸が揺らいでいく、という奇妙な物語を演劇で、『ドロステのはてで僕ら』では、入れ子構造を使って、時間が行き来するような仕掛けを映像で表現しました。

今後も、映画という分野で、新しい表現や物語の構造にチャレンジしていきたいと話す上田さん。一方、その時に大事にしたいのが、既視感とのバランスだと言います。
「つい“世の中にない映画だから観てください!”と言いたくなってしまうんですけど、人はどこかで既視感のあるものを観たかったりもするし、未知のものに触れるのって、体力がいるんですよね…。僕がひとりで考えるものは、凝りすぎるというかソリッドになってしまうところがあるので、劇団のみんなからも“これを実現させるのはしんどいわ”とよく言われるんです(笑)。そこから、マイルドさとか可愛げみたいなものを入れたり、みんなの演技が加味されたりすることで、親しみやすい作品になっていく…。そのバランス感覚は、演劇や映画という集団でつくる創作の中では、いつも意識しています」
上田さんの作品を観た後にいつも心に残るのは、“新しいジャンルを目撃した”という興奮と、個性的な登場人物が行き交う人間模様です。『ドロステのはてで僕ら』も、人が集まるからこそ生まれる人間の振る舞いが、じんわりと胸に残り、そして、人と対面することに距離ができてしまった今の時代だからこそ、響いてくるものがあります。

「ある種のコミュニティ映画だと思っているし、人が集まる良さ、というのは意識した映画です。ヨーロッパ企画のメンバーもまさに、集団だから広がる可能性があるんだ、ということを感じられるチームでもあるので。今回の映画は、物語の構造上、役者もスタッフも大変だったと思います。でもヨーロッパ企画のメンバーなら、これくらいの芝居できるよね、という気持ちもありました(笑)。次の映画ではもっと無茶な構造で脚本を書くかもしれないし、それを実現できるチームだと思うので、 “これまでにない”ものに挑戦し続けたいです」
作り手のアイデアや創作の手触りが滲み出るような映画に惹かれ、その徹底した姿勢に勇気をもらっていたという上田さん。これから上田さんが挑戦していく作品も、きっと同じように私たちを驚かせ、“ここまでやっていいんだ!”という衝撃が、作り手たちの背中を押していくのでしょう。
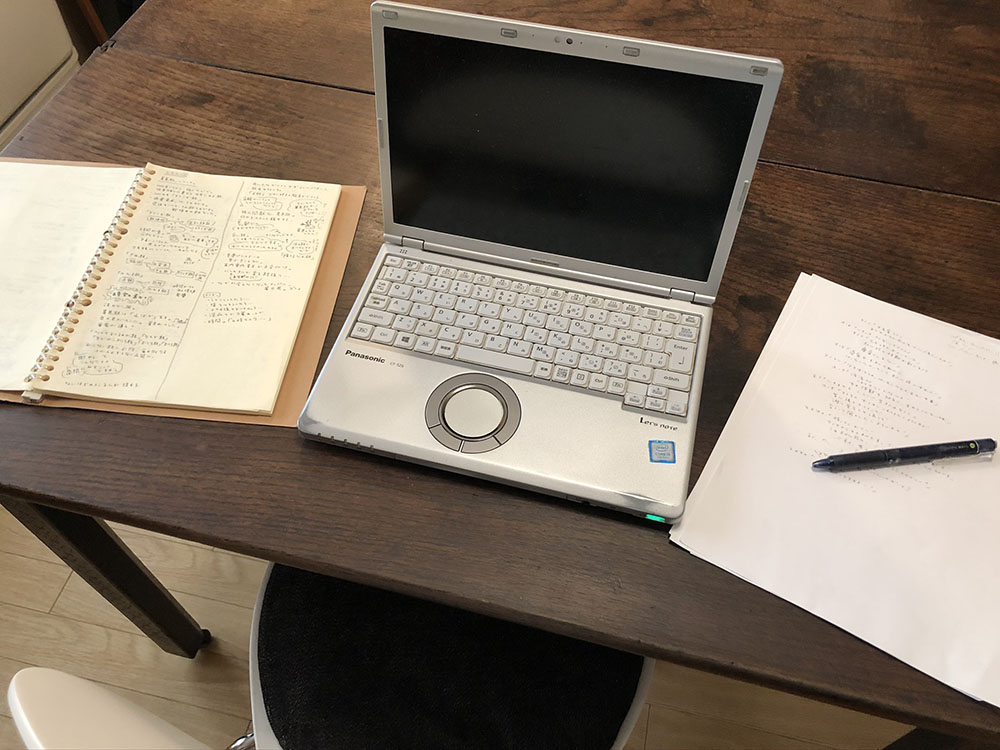
- 映画に込められた愛情と熱量が 自分の「好き」を貫く力になる
- 「好き」が詰まった部屋はアイディアの引出し
- 映画を作るように、料理を作りたい。働き方の理想は、いつも映画の中に
- 最新技術と共に歩んできた映画の歴史から、“前例のない表現”に挑む勇気をもらう
- 映画は仕事への熱量を高めてくれる存在。写真家のそばにあるDVD棚
- “これまでにない”へ挑みつづける!劇団ヨーロッパ企画・上田誠が勇気と覚悟をもらう映画
- “好き”が深いからこそ見える世界がある!鉄道ファンの漫画家が楽しむ映画とは?
- 一人で完結せず、仲間と楽しむ映画のススメ
- おうち時間は、アジア映画で異国情緒に浸る
- 漫画家・山田玲司の表現者としての炎に、火をくべる映画たち
- 時代の感覚を、いつでも取り出せるように。僕が仕事場にDVDを置く理由
- 「この時代に生まれたかった!」 平成生まれの役者がのめりこむ、昭和の映画たち
- 好きな映画から広がる想像力が 「既視感がバグる」表現のヒントになる
- 好きな映画の話を相手にすると 深いところで一気につながる感覚がある
- 勉強ができなくても、図書館や映画館に通っていれば一人前になれる。
- ナンセンスな発想を現実に! 明和電機とSF映画の共通点とは?
- 22歳にして大病で死にかけた僕。「支えは映画だった」 絵本作家の仕事部屋にあるDVD棚
- 映画は家族を知るための扉。 保育園を営む夫婦のDVD棚
- 「映画を観続けてきた自分の人生を、誰かに見せたい」 映画ファンが集う空間をつくった、飲食店オーナーのDVD棚
- “すべての人を肯定する服作り”をするファッションデザイナーのDVD棚
- 「データは信用していない」映像制作プロデューサーが、映画を集める理由
- 写真家としてテーマを明確にした映画。自分の歩む道を決めてきた、過去が並ぶDVD棚。
- DVD棚は“卒アル”。 わたしの辿ってきた道筋だから、ちょっと恥ずかしい
- 映画を通して「念い(おもい)を刻む」方法を知る
- 家にいながらにして、多くの人生に出会える映画は、私の大切なインスピレーション源。
- オフィスのミーティングスペースにDVD棚を。発想の種が、そこから生まれる
- 映画の閃きを“少女”の版画に閉じ込める
- 映画の中に、いつでも音楽を探している
- 映画から、もうひとつの物語が生まれる
- 探求精神があふれる、宝の山へようこそ。
- 無限の会話が生まれる場所。 ここから、創作の閃きが生まれる。
- 夢をスタートさせる場所。 このDVD棚が初めの一歩となる。
- 本や映画という存在を側に置いて、想像を絶やさないようにしたい。









