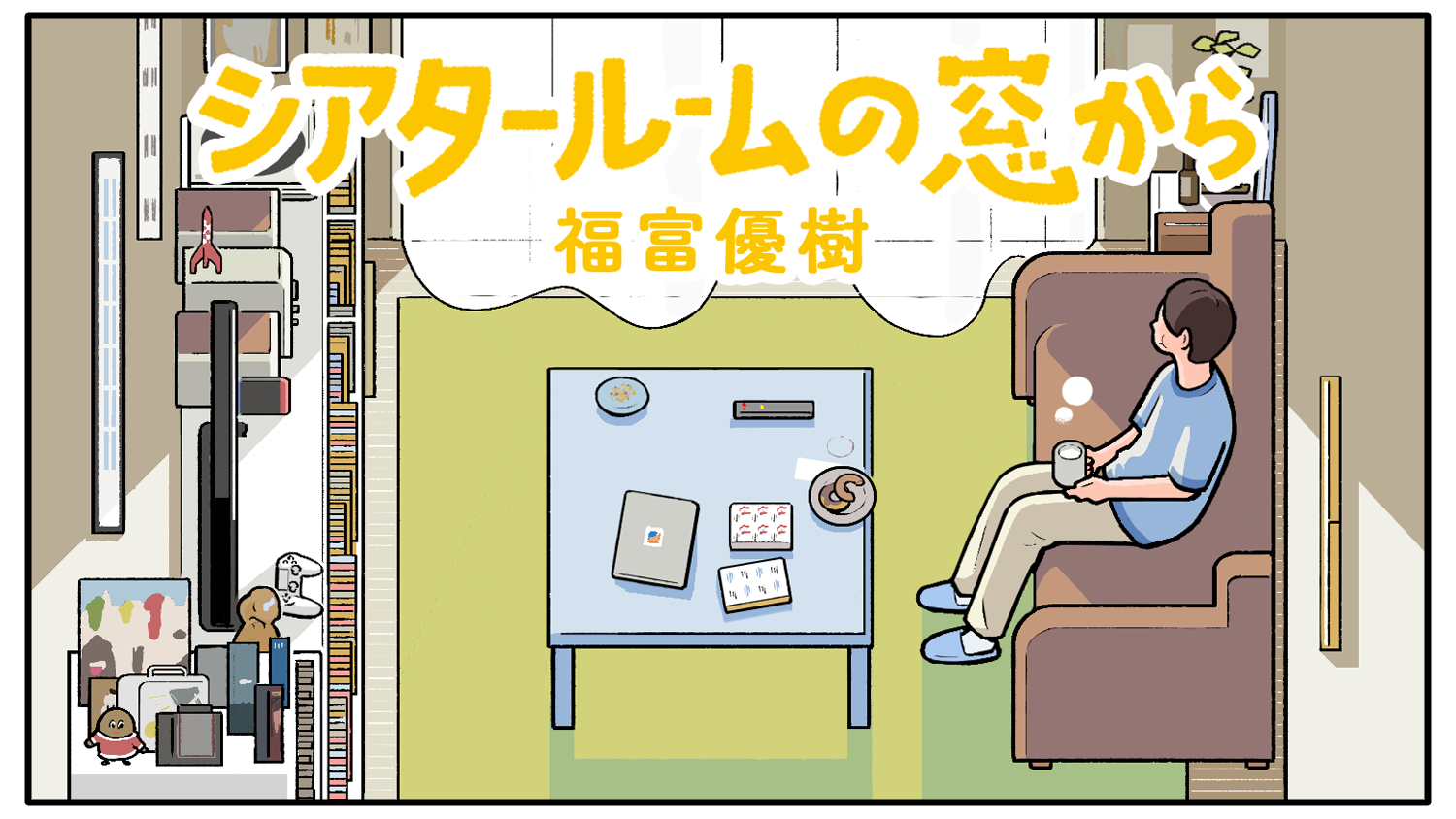
ついこの間、車の免許を取るために教習所に通いはじめたという友達との会話のなかで、『ウォールフラワー』のことをふいに思い出した。劇中で2度登場する最高のドライブシーンとそのときにかかるデヴィッド・ボウイの「Heroes」。観たら絶対運転したくなるから!とおすすめしておきながら(同時に事故のシーンもあるのでもしかしたら気が重くなってしまうかもしれないけれど)僕自身も長らく観直してないことに気がついて、久しぶりにDVDを棚から引っ張り出した。冬の寒さが顔を出してきた11月の夜、小さな明かりだけを点けた部屋でタオルケットにくるまりながら、隅から隅まで好きなものが詰まったこの映画にまた夢中になった。
『ウォールフラワー』は1999年に出版されたヤングアダルト小説を原作とした映画で、原作者のスティーブン・チョボスキー自らが監督を務めている。彼はこの映画を撮ったのちに『ワンダー 君は太陽』や『ディア・エヴァン・ハンセン』といった作品も手掛けている。ちなみに原題は『The Perks of Being a Wallflower』といい、直訳すると「壁の花でいることの特典」。このタイトルが僕が大好きなThe Pains of Being Pure at Heartというバンドの名前とどこなく響きが似ていることがこの作品を知るきっかけだったこともあって(バンド名の由来はチャールズ・オーガスタス・スティーン3世の同名小説から)、彼らのようなきらきらしたインディーポップのサウンドとこの映画は自分のなかで強く結びついている。
物語は高校生になる主人公のチャーリーが“君”と呼ぶ友達へ宛てた手紙という形をもって始まる。“君”は「人の話を聞く人」で「パーティーでも あの人と寝なかった」らしい。“君”は直接的に物語を受け取る「こちら」のことであるように思えるし、チャーリーが作り出した「イマジナリーフレンド」、もしくは「彼自身」でもあるように思える。最後まで“君”が実際の姿かたちで登場することはないのだけれど、チャーリーにとってその存在は大きな救いとなっている。彼は“君”を通してこちらに少しずつ自分のことを話す(書き連ねる)。まるでホールデン・コールフィールド(※)のように。そしてチャーリーもまたこんがらがっている。
チャーリーは高校生活という新しい世界で居場所を見つけられないでいる。パーティーの隅で壁にもたれる姿はまさに“壁の花/ウォールフラワー”だ。そんな彼の手をとるのはパトリックとサムという上級生のふたりだ。「はみだしものの島へようこそ」と歌うように差し伸べる彼や彼女の手ひらにも隠された傷あとがみえる。チャーリーを導き、力強く飄々と生きているようにみえるパトリックは、生きづらさを押し付ける社会と戦うために過剰に明るく振る舞っている。
パーティーで彼と関係をもった男の子は「親父に殺される」とこぼし、関係が明るみにでることを恐れている。物語の時代設定は90年代のはじめ頃、現代に比べてその時代の10代が自分たちのセクシュアリティをオープンにすることの障害は大きかったのだろう(まだまだ多様な価値観を受け入れているとはいえないのだけれど)。サラもまた、自らの価値をはっきりと見出だせないでいる。男性との関係に悩み、自分が選択する答えに自信が持てないがゆえ、さらにその間違った答えに依存していく。物語のなかでパトリックやサラたちが演じるミュージカル『ロッキー・ホラー・ショー』にはそんな「はみだしてしまう/はじきだされてしまう」ものたちへの開放の祈りが込められている。力強い歌とダンスは誰かに決められた「普通」の価値観から逸脱することそのものを描き、祝福しているように映る。小さな社会と大きな社会の間のような歳月、高速道路を走る車窓のように目まぐるしい季節のなかで、誰もが自らと周囲の傷に向き合い、誰かと連帯していく。それは実際に手をとれる友達の場合もあれば、“君”のように手紙を送る相手との間で生まれるものでもある。
日本で『ウォールフラワー』が公開されたのは、2013年の終わり頃、ちょうどこの原稿書いている今と同じ、11月のことだった。僕はまだ大学生で、バンドが軌道にのっていく期待感と周りとは違う道を選ぼうとしていることへの不安感がないまぜになっている季節だった。バンドの状況は良くなっていくものの、自分たちがどんな音楽をやっていきたいのかいまいち測りかねていた。大学の小さな部室から始まった僕たちの旅は、なによりもその行き先を求めていた。そんなときに出会ったこの映画は僕にひとつ大きな指針をくれた。はっきりと、この映画のような音楽がやりたい、と思ったのだ。大学の近くのよく冷える小さな町で、静かに灯火が点いたような、そんな気にすらなったことを覚えている。チャーリーのように“君”へと音楽を届け、“君”のように誰かの遠くて近い友達のように思える存在になりたい。物語を彩るような音楽を作りたい。カセットテープから流れるThe Smithの「Asleep」、パーティー会場のNew Orderの「Temptation」と、ダンスシーンの「Come On Eileen」。リビングでうっすらとかかるPavementの「Here」、そして夜のトンネルに響く黄金色にもみえる「Heroes」。そんなきらめくような音楽を。
今もその灯りは消えることなく残り続けている。ロマンチックで切なくてきらきらしたインディーロックというある意味記号的な側面、物語を彩るサウンドトラック的な部分は少し変化したかもしれないけれど、10年近くたった今観返してみて感じるのは、手紙を送り合うような存在として音楽やその周縁の活動を通して誰かと手を取り合いたいという思いはむしろ強くなっているということだ。
今年もあと少しで終わり、クリスマスや大晦日やお正月というなんだか心がざわざわしてしまいそうなイベントごとも近づいてきた。色々な理由や状況があるけれど、街やSNSがきらきらと輝く日や、周りの友達が揃って久しぶりに家族と過ごしているような日々では、たとえ普段はそこまで気にならなくても、1人でぽつんといることについて嫌でも考えてしまいがちだ。綺麗な雪や好きなはずの凛とした寒さもときに僕たちを必要以上に寂しくさせる。そんなときにはこんな映画を手にとってみるのもいいかもしれない。チャーリーが仰向けに倒れ込む雪はときに彼に引き出しの奥のとげとげしい思い出をフラッシュバックさせるけれど、彼が地面に打ち付けられないように受け止める存在でもある。こぼれおちるそのぎりぎりにそっと受け止めるような存在。僕たちの音楽もそんなときにそばにおいてもらえると嬉しい。チャーリーが“君”へ手紙を出したように僕たちは音楽を作りたいし、僕たちにも手紙を書くようにあなたのことも教えてもらえると嬉しいと思う。返事はできなくても、彼らや彼女たちのように実際に手をとることはできなくても、僕たちはここにいて、手紙は届くのだから。

※小説『ライ麦畑でつかまえて』の主人公の名前
- two sea, your color 物語の終わりはハッピーエンドがいい
- moon shaped river life
- 『ゴーストワールド』にまつわる3篇
- won’t you be my neighbor? 『幸せへのまわり道』
- 自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に 『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』
- “君”のように遠くて近い友達 『ウォールフラワー』
- あの街のレコード店がなくなった日 『アザー・ミュージック』
- 君の手がきらめく 『コーダ あいのうた』
- Sorry We Missed You 『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』
- 変化し続ける煙をつかまえて 『スモーク』
- 僕や君が世界とつながるのは、いつか、今なのかもしれない。『チョコレートドーナツ』と『Herge』
- この世界は“カラフル”だ。緑のネイルと『ブックスマート』
- 僕だけの明るい場所 『最高に素晴らしいこと』
- 僕たちはいつだって世界を旅することができる。タンタンと僕と『タンタンと私』
- 川むかいにある部屋の窓から 君に手紙を投げるように







