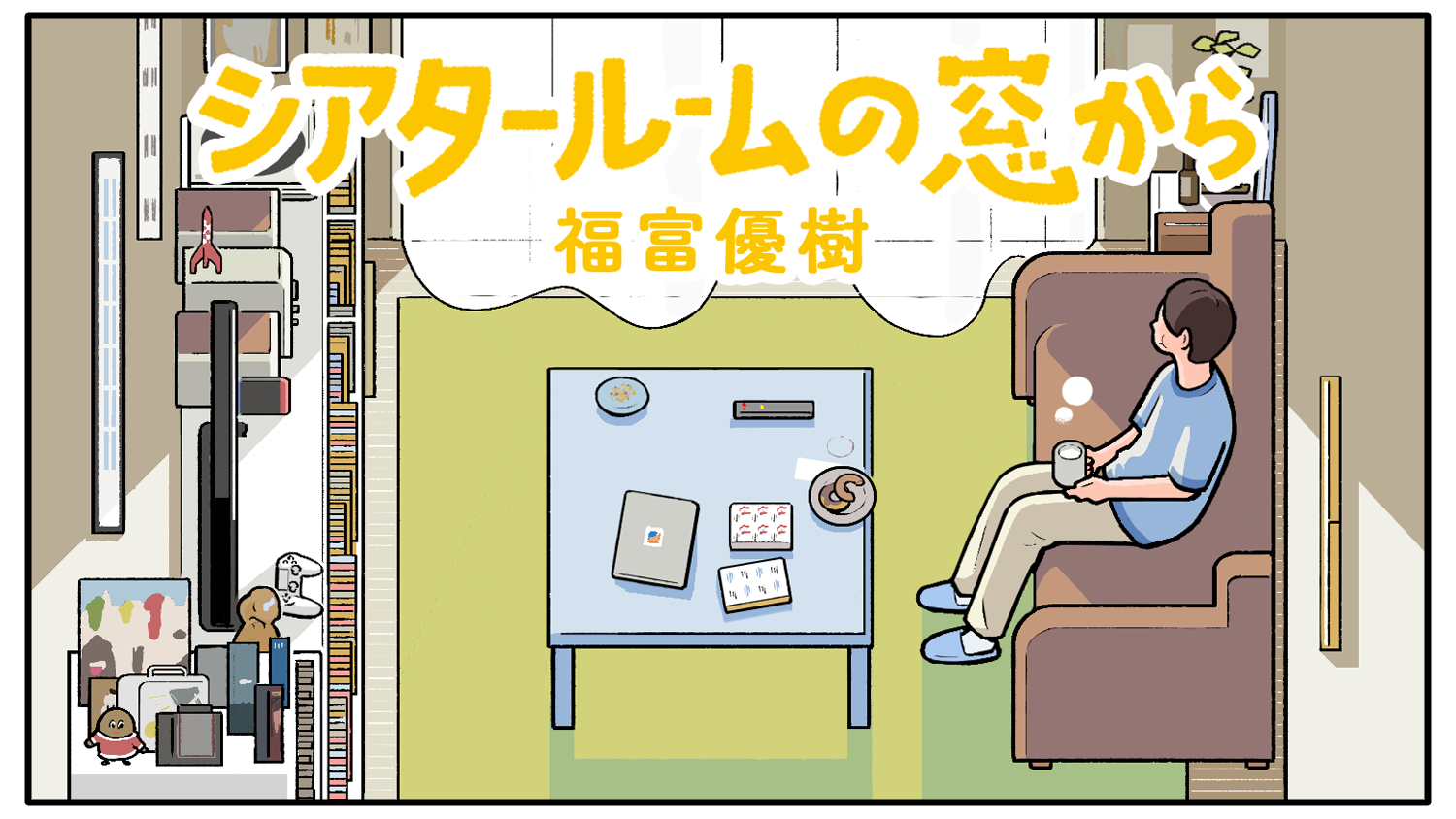
僕が生まれ育った町には小さくてさみしくて、それでもここではないどこかにつながっている海岸がある。海水浴はできなくもないけれど、泳いでいる人はほとんどいないその海岸で、僕は放課後の時間の多くを過ごした。砂浜と海沿いの細い道をつなぐ低く広い階段に座り、イヤホンからは音楽が小さく流れ、手には図書館から借りてきた小説。陽が落ちてきて文字を追えなくなると、そっと階段から立ち上がり自転車にまたがって家に帰る。電車で片道40分かけて登校するようになった高校生の3年間。部活に入ることが義務付けられていた中学生の頃とは違い、まだ空が明るい時間に自由になれることはどこか寂しいことでもあって、そのなんとなくの寂しさとの上手な付き合い方が、海岸で音楽や文学に触れることだった。あの頃はまだ今みたいにiPhoneやサブスクが当たり前になる前だったからNetflixやU-NEXTで映画を観ることはできなかったけど、目の前の風景やそこにいる自分、という状況からなんとなく気分だけは映画にも触れているような気になっていた。
あの海岸は『ジョゼと虎と魚たち』で二人が本来の旅路を逸れてたどり着く、恒夫が今も写真のなかに収めたままにしている海辺や、『花とアリス』の物語の中盤、トランプが舞い、過去の大切なものが砂の中から掘り起こされる砂浜とどこか似ていて、だからこそこの2本は僕にとって特別な映画になっているように思う。どちらもどこか噛み合っていない人たちの、なにかの終わりのはじまりの舞台で、あの町と同じように晴れきっていない空がそんな予感を写しているようだ。あの頃の僕は、静かな地味だけどずっと心に残るような、そんな映画のなかの主人公になったような気分でもあったのかもしれない。今振り返るとあまりにも青くて恥ずかしい時間だけど、あの時間、あの場所が今の僕にとってもとても大切なのだ。
海辺の町にはもうひとつの海がある。あたり一面の稲穂の海。季節ごとに色や形を変えながら、どこまでもどこまでも続いていくような海の中に浮かぶような町で僕は小学生から高校を卒業するまでの12年間を過ごした。あまりにも広く続く稲穂の景色に、カゴ付きのママチャリではそんなに遠くまでは海を渡れないような気にさせられた。車がないとどこへも行けない、ということは、大人になるまで自分の力ではどこにも行けないということで、自分の使えるお金では1時間に1本しか来ない電車でどこまで行けるか分からなかった。町のはずれの小さな公園からは、遠くに遊園地の観覧車が観える。それはきらきらした場所というよりも、なにかこの風景に張り付いたハリボテのようにもおもえた。そんな風景のせいなのか、音楽でも映画でも文学でも。寂しさの匂いがする作品に惹かれるようになった。僕はおそらく、あの景色のなかで僕というものを形成していったのだと思う。
音楽が映画や小説に触れることでここじゃないどこかとつながっているような気持ちになれたし、ときにはそんな自分の状況が画面に映し出されることもあった。『リリィ・シュシュのすべて』のあの稲穂の海とそのなかで佇みながらヘッドフォンで音楽と、世界とつながる物語はあまりにも自分の近くにありすぎて、その悲しい結末たちも相まって、しばらく観直すことができない作品だったりもした。2000年代と2010年代を経て、巡る巡って“今” の社会の空気感を含んでいる、不思議な魅力がある映画だと思う。最近になって何度も観返しているのだけど、そのたびにズキズキと胸の奥から音がするような感覚になる。町を離れて何年も経ってようやくあの稲穂の景色を綺麗だと思えるようになったけれど、それはなにかを忘れてしまっただけなのか、自分のなにが変わったのか、そんなことを観るたびに問われているような気がするのだった。もしもあのままどこへも行けなかったら(これはあくまでどこかに行きたかった僕だけの話であってあの町自体やそこで暮らすみんなを否定するわけでは全然なくて)、僕はあの景色を綺麗だと思えただろうか、好きになることができたのだろうか。インターネットはあるけれど、インターネットで誰かと繋がったり、なにかを作ったりすることにはまだ距離がある時代だった。少なくともあの頃僕が手にしていた物だけではここからなにかを世界に投げ込むことは難しそうに思えた。「掲示板」というものをつかって繋がることはできたかもしれないけれど、それがどんなことになるのか、『リリィ・シュシュのすべて』の結末はあの頃の僕にとってもリアルなものであり、なんとなく“少し前のこと”という感覚でもあった。リーマンショックもあって世界は大変だったけれど、TVやエンターテイメントの世界は底が抜けたように明るくて単純明快で、感動の涙で溢れていた。なんとなく2000年代中頃から2010年代に入るまではそんな時代だったように思う。ふたつの海の存在は、そんな時代でもちゃんと僕を寂しくさせてくれた。そんなふたつの海や寂しさと向き合うことで手にした様々な感触は、今も自分が物を作るうえで手放すことのできないものだ。
『see you, frail angel. sea adore you』というHomecomingsの新しいアルバムは、そんな海のことを、そんな海で触れた音楽や文学や映画の匂いをかたちにすることからはじまった作品だ。きっかけは年始にあった震災で、警報で沿岸が真っ赤に染まる地図が映し出される画面をただただ祈るような気持ちで見つめるしかなかったあの日、海の新しい表情を見た。はっきりと自分の町のことになってようやく、僕は海の怖さをしっかりと感じた。それからの日々はあの町や海のことばかりを考えて過ごした。時間が経っても怖さは薄れはしないけれどそれでも僕はあの海のことを、あの海で想ったことをしっかりと自分のことばで、詩と音楽にしたかった。僕はあの海を漕ぎ出した。漕ぎ出すことができて、その背中を押してくれる存在がいた。あの頃の僕のなかには、そう遠くない未来、どこかへと漕ぎ出していく自分がいて、今の自分のなかにはまだあの頃の海にいる自分もいる。小さなボートに大切なものをいくつも積み込んで漕ぎ出した自分の背中にはあの稲穂があの海辺が、その場所で触れた音楽や物語が、傷つきやすく寂しがり屋なあの頃の自分が灯台のように存在し続けている。それは実際に手に取れるものでも、無形のものでも、イマジナリーなものでもよくて、最近なかなか連絡できていないけれど大切な人だったり、お守りのような音楽であったりする。それは天使のような存在で、いつでもうっすらと側に寄り添っている。
何ヶ月もかかって『see you, frail angel. sea adore you』というタイトルをつけたあと、山田尚子監督の新作『きみの色』を観た。あの頃の自分が感じていたこともそこにあったし、なにより山田さんがよく話してくれていたジョン・カーニー監督の作品、とりわけ『シング・ストリート』への愛やオマージュが様々な場面で弾けていて、その悦びが作り手の温度感が、物語を前へ前へと進めているように思えた。自分の目で見る「他人」のことはわかりやすく理解できるのに、自分のことは、自分の色を見ることはなかなか難しい。僕たちは身の回りの人々や物事に自分を反射させて、自分自身を探っていく。自分の色も見つけられない僕たちや誰かも、他の誰かにとっての灯台であって天使であったりする。漕ぎ出す人を漕ぎ出そうとしている誰かを見守ること、手を降ること。漕ぎ出すこと。そのときに口にすること。エンドロール後に一瞬だけ浮かび上がるあることばに、あまりにもはっとさせられてしまい背中が座席にぴったりとくっついたまま動けなくなってしまうくらい胸がドキドキした。
変えられないものと変えるべきものを選ぶことは大人になったいまでも難しい。子ども大人もその選択は自分の責任で、それを繰り返すことで少しは上手になったかもしれないけれど、それでもいつでも僕たちは迷っている。ただ、漕ぎ出す勇気は確かにこの手にある。変えられないことを受け入れることは僕はまだ少しむずかしいけれど、あの海はいつでもそんな僕を受け入れてくれるだろう。たとえ僕があの海から漕ぎ出さないことを選んだとしても、それは間違いでもなんでもないはずだ。
海はどこかへとつながっていながらその対岸を映すことはない。晴れた日はうっすらとその対岸が見えるという『シング・ストリート』でもその航海の先は描かれないまま物語は一旦の幕を下ろす。『きみの色』の3人はこれからどんな航路を行くのだろうか。踏み出すまでと踏み出したその一歩、そこから先にはどんな出来事が待っているのだろか。大丈夫、心配ないよ、とそっとエンドロールが語り、またね、とひとことだけが綴れる。物語の終わりはハッピーエンドがいい。でもそれはなにもかもがうまくいって、すべての困難が消しされた世界よりもこれから先、なにがあるかはわからないけれど、それでもきっと大丈夫、と言ってくれる、そう思わせてくれるようなものがいい。現実も希望もひとしく、ただ幾分かの希望のメモリが大きい、そんななにかのはじまりのうたを僕はいつまでも大切に思いたいのだ。

- two sea, your color 物語の終わりはハッピーエンドがいい
- moon shaped river life
- 『ゴーストワールド』にまつわる3篇
- won’t you be my neighbor? 『幸せへのまわり道』
- 自分のことも世界のことも嫌いになってしまう前に 『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』
- “君”のように遠くて近い友達 『ウォールフラワー』
- あの街のレコード店がなくなった日 『アザー・ミュージック』
- 君の手がきらめく 『コーダ あいのうた』
- Sorry We Missed You 『わたしは、ダニエル・ブレイク』『家族を想うとき』
- 変化し続ける煙をつかまえて 『スモーク』
- 僕や君が世界とつながるのは、いつか、今なのかもしれない。『チョコレートドーナツ』と『Herge』
- この世界は“カラフル”だ。緑のネイルと『ブックスマート』
- 僕だけの明るい場所 『最高に素晴らしいこと』
- 僕たちはいつだって世界を旅することができる。タンタンと僕と『タンタンと私』
- 川むかいにある部屋の窓から 君に手紙を投げるように







