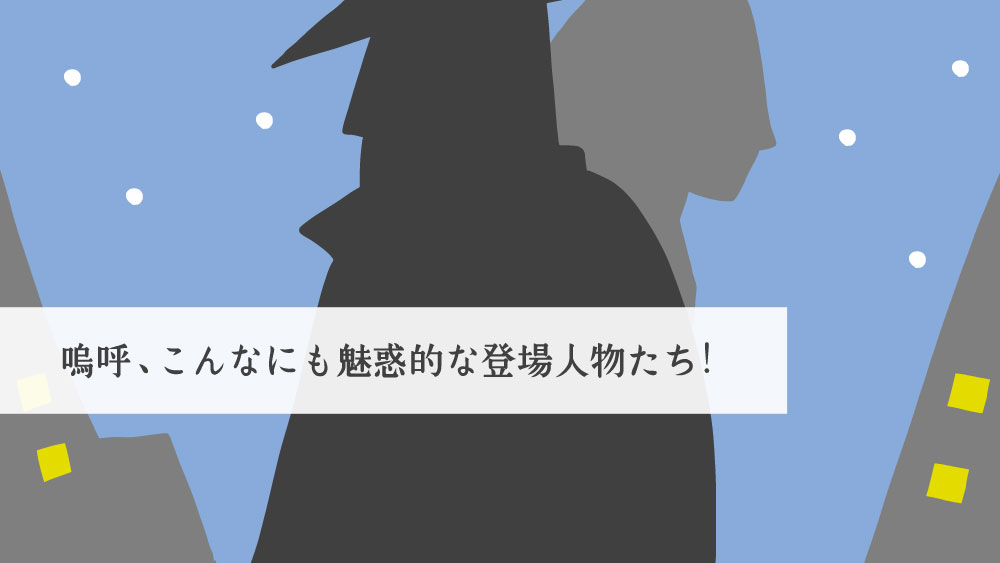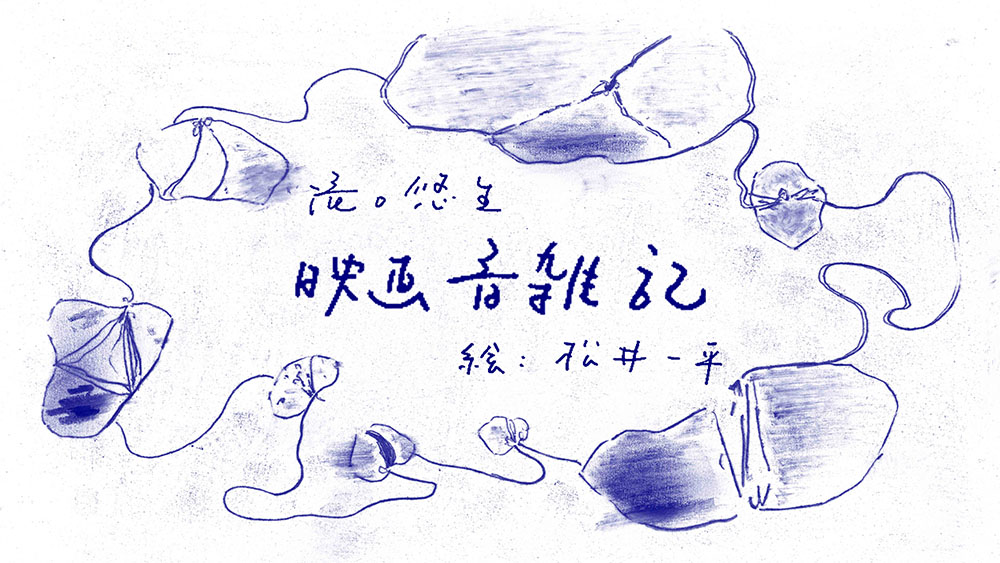
登場人物たちはいつも静かな場所にいて、あまりしゃべらない。だから、この映画の物音は小さな音でもよく響く。そして聞こえる音の多くは、なにかを打つように短く響いてはすぐに消える。
たとえば映画の冒頭で、初老の男が妻に別れを告げて家を出る場面。別れを告げるといっても、妻も、夫も、ひと言も発さない。時計の秒針のような音が微かに聞こえるなか、頭にカーラーをつけて煙草を吸っている妻の前に、夫は黙って鍵と結婚指輪を置く。聞こえるのはその音だけ。硬く冷ややかなその音たちが、夫婦の関係の終わりをどんな言葉よりも残酷に示す。その後に続く地下駐車場の場面では、男が自動車のドアを閉める音が彼の意志や決断に力を与えるかのように大きく響く。
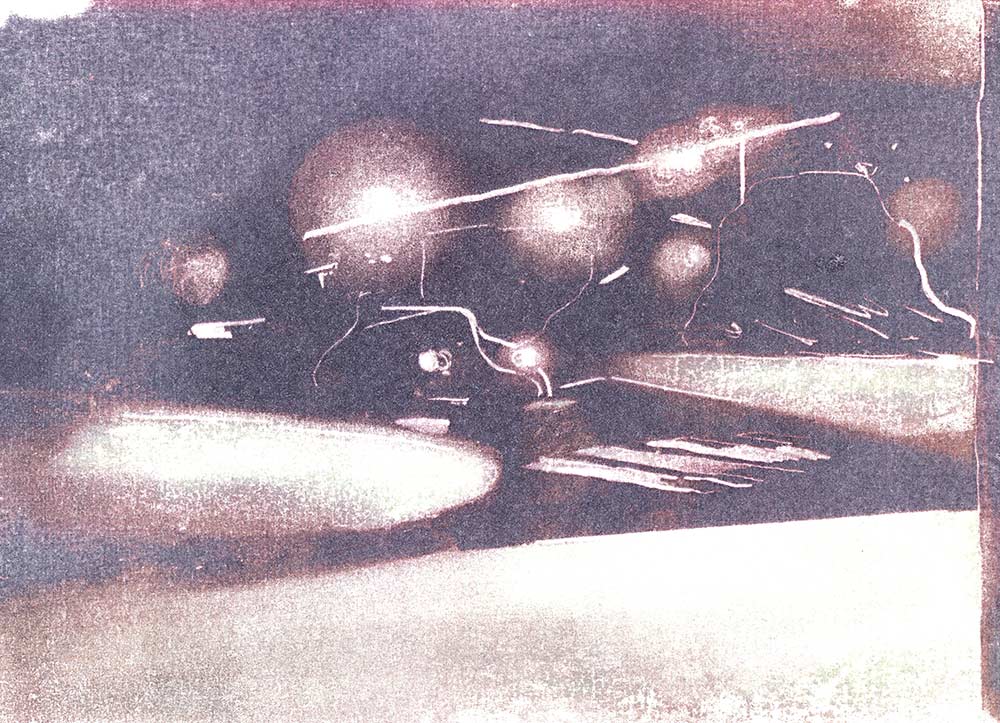
この映画では、しばしば、登場人物のたてる音が、言葉に代わって彼らの意志を表す。ヘルシンキを舞台にした物語の中心にはふたりの男がいる。
ひとりは、シリアの内戦で家族を失った青年カーリド。生き別れた妹を探して各国を巡りながら貨物船で偶然ヘルシンキにたどり着き、難民申請をする。
もうひとりは、先の通り妻と別れて、老年にして新たな生活をはじめることになったヴィクストロム。元はシャツの卸をやっていたようだが、在庫整理してポーカーで儲けた金でレストランを買い、オーナーになる。
難民申請が通らず、強制送還を逃れるため収容所から脱走したカーリドは行き場がなくなり、レストランのゴミ置き場で寝ていたところをヴィクストロムに見つかる。ふたりはそうして出会うわけだが、その場面でもやはり言葉は少ない。出て行け。出て行かない。簡単な応答のあと互いに一発ずつ殴り合って鼻血を出したところで場面は切り替わる。ことの経緯はまったくわからないまま、どうやらふたりは和解して、カーリドがヴィクストロムの店でスープをふるまわれている。そしてそのままカーリドが店で働くことになる。

なにかとなにかがぶつかれば音が鳴る。この映画はそういう音を丹念に拾い上げ、そこに潜む意志を表出させる。誰かの小さな声、声にならない声に耳をすませるように。そして音が鳴ると、言葉を超えて物語が進む。
そうやって物音にひかれてこの映画を観ていると、言葉少なな登場人物たちのセリフも、まるで音のように聞こえてくる。カーリドが難民申請のための面接に臨んでいる場面は、この映画のなかで最も多くの言葉が発される場面だ。しかし、故郷を追われ偶然たどり着いた異国で、知らない言語で問われる問いに答えるカーリドの声は、ぎこちなく強ばっている。まっすぐ面接官の顔を見て淡々と語られる彼とその家族の苦境は、面接官の、あるいはフィンランドという国のドアを、ノックしている音のようだ。そのドアが正しいのか、そのドアの向こうになにがあるのかもわからないが、そうするほかに手段がない。諦めと祈りを打ちつけるみたいな、ノックの音。
あるいは冷たい悪意も打ちつけられる。フィンランドのネオナチのグループが、カーリドを殴る音。バスの窓に投げつけられた酒瓶が割れる音は、彼らの言葉以上に救いのない憎悪を示し、絶望的に響く。
この映画にはたくさんの絶望が刻まれている。『希望のかなた』というタイトルには、「希望」という言葉が入っているけれどそれは遠い彼方にある。カーリドの難民申請は通らず、彼は名前を捨て偽のIDをつくって生きる。けれども映画の終盤で、ほんのわずかだけれどいくつかのドアが開く。希望はまだまだ彼方のものかもしれないが、ノックの音を聞いているひとはいたということだ。